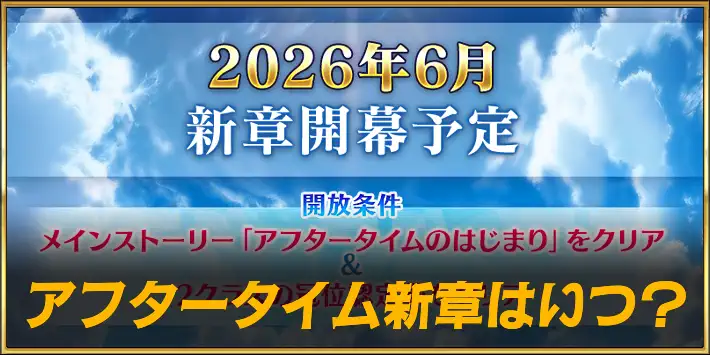Anker、モバイルバッテリーなど52万台リコール 交換や返金対応はどうなる?

モバイルバッテリー大手のアンカー・ジャパン(Anker)が、10月21日、商品の不具合を理由として大規模リコールを発表し、経済産業省に届け出を行いました。 アンカーの発表によると、今回のリコール対象となるのは、モバイルバッテリー(リチウム電池内蔵充電器)やモバイルスピーカーなど合計約52万台です。 アンカーは2019年以降、モバイルバッテリーなどの自主回収を度々行っており、その累計は約100万台にのぼっています。また、これまでに41件、発火があった重大事故が報告されています。 経済産業省は、これを受けて10月21日付でアンカー・ジャパンに対し、製造体制やリコールの状況について報告を求める行政指導を行っています。 原因は、製品で使用されているリチウムイオン電池の製造工程において、サプライヤー側で異物が混入し、使用に伴い電池セルの内部短絡(ショート)が起こり、発火・発煙の危険があるというものです。 今回の事例は、有名メーカーの製品であっても、製造過程におけるリスクを排除することは難しい現実を示しています。 本記事では、今回の事例を材料に、リチウムイオン電池製品全般の安全性確保のあり方について、企業と消費者双方の視点から解説します。
製造物責任法3条は、製造物の「欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したとき」は、製造業者等が損害賠償責任を負うと定めています。この法律における「欠陥」とは、製造物が通常有すべき安全性を欠いていることを指します。 本件のリコールの原因は、サプライヤーの製造工程における異物混入による「電池セルの内部短絡の可能性」とされています。これは、製造工程に不備があったことによる「製造上の欠陥」に該当する可能性が高いといえます。 製造物責任法が適用される場合、被害者がメーカーの「過失」を立証する必要がなくなります。 一般的な民法の規定による場合には、製品に欠陥があって、消費者が損害を受けた場合、その欠陥が「過失」(メーカー側の不注意)に基づくものであることを消費者側が立証する必要があります。 しかし、製造物責任法では、この「過失」の立証は不要となり、「製造物」であることと、「欠陥」と「損害」、およびその「因果関係」を立証すれば足りることとされています。 つまり、「メーカー側の不注意」を証明しなくても、「製品に欠陥があって、それが原因で被害が出た」ことを証明できれば、メーカーに賠償を求めることができます。 なお、「欠陥」の立証は大変そうに思えますが、実務上は製造物の具体的な欠陥や機序などの特定までは必要とされておらず、その製造物の通常の用法に従って使用しているときに異常が発生した事情を主張立証することで足りると考えられています(東京地判平成30年2月27日参照)。