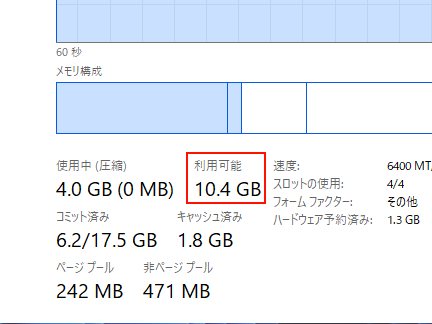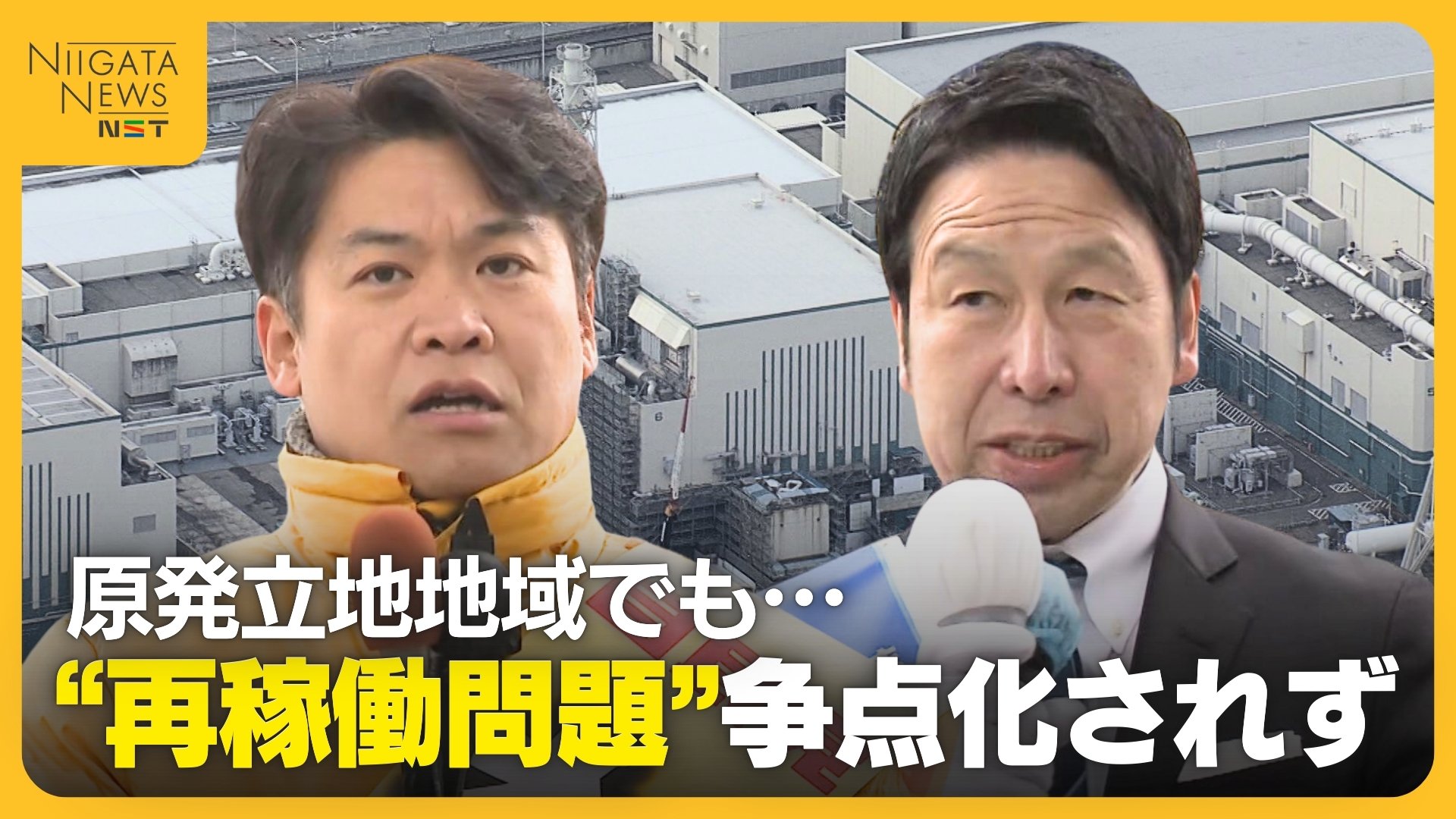AIに置換されるのは若者たち? 「若手を採用し、育成するコストが大きすぎる!」と考えはじめた企業

「もう若手の採用は、控えてくれ」
総務部長にこう言われ、ある人事担当者が衝撃を受けた。
「これまでインターンや新卒が担っていた業務はAIがこなしている」
「経験豊富で、AIを使える人を雇ってくれれば、それで十分だ」
育成コストも下がるし、「パワハラだ」と言われることにビクビクすることもなくなる、と言う。
このように若手の採用を控える流れは、徐々に広まりつつある。実際に、求人の経験年数要件を引き上げる企業も出てきた。「5年以上の実務経験」を採用条件とするテック企業もある。
そこで今回はAI時代における若手採用の現状について解説する。ご興味がある方は、ぜひ最後まで読んでもらいたい。
■デジタルはボトムアップ、AIはトップアップ
私は、デジタルは「ボトムアップ」につながり、AIは「トップアップ」につながると考えている。
「ボトムアップ」とは、スキルが低い人、経験の浅い人たちが効率よく成果を出せることだ。いっぽう「トップアップ」とは、すでに経験を積んでいる人が、さらに効率的に成果を上げられること。
デジタルで「ボトムアップ」の例を紹介しよう。
私の知人に看板屋を営む人がいる。かつてその社長は、一枚一枚の看板をすべて手作業で描いていた。文字の太さや筆の勢い、配色のバランスは職人の長年の経験によって支えられていた。若手が同じレベルに達するには長い修業が必要だった。
ところがデジタル技術が進化すると、作業は様変わりした。デザインソフトやカッティングマシン、インクジェットプリンターの導入で、経験の浅い若手でも、短期間で「それなりの品質」を出せるようになったのだ。
これがデジタルによる「ボトムアップ」の好例だ。
■AIが若手の仕事を奪う理由
いっぽうAIはどうか?
先ほどの看板であれば、AIなど使わなくてもデジタル技術で完成する。しかし、どんな看板を作るのかというアイデアは人間が考える分野だ。これを経験が浅い人ができるかというと、難しい。
お客様とのコミュニケーションを通じて、どのような意図で看板を作るのか、トーン&マナーをどう揃えるべきか、それなりの知識や経験がないとデザインできない。上手に「字」や「絵」を描き、うまいこと配置できたらいい、ということではないのだ。
しかしながらAIに任せたら、いろいろなアイデアを出してくれる。どんなに経験が浅い人がやっても、そなりに見栄えのいい看板を瞬時に生成してくれる。だが、本当にその看板でいいのか? その評価は誰がするのか?
もし、経験の浅い人でもお客様が望むデザインができるのであれば、お客様自身がAIで作ればいい、ということになる。年賀状を自分で作るように、だ。
AIに任せられない価値があるから、人間に頼むのである。
■AIの成果物を誰が検証するのか?
私は青年海外協力隊としてグアテマラに滞在していたとき、よくセビーチェという中南米料理を食べた。
このセビーチェという料理を、AIに「作って」と依頼し、美味しい料理ができたとしよう。それを食べた誰もが「美味しい」と賞賛してくれたとしよう。しかし、それでいいのか? それが「正真正銘のセビーチェ」かどうか、誰が評価するのか?
食べたことがない人なら「これがセビーチェか」、と思い込むだろう。しかしもし間違ったものが生成されていた場合はどうなる? 私のように経験がある人なら、
「美味しいけれど、こんなものはセビーチェとは呼べない」
と判断するはずだ。現地の料理人が口にしたら、
「まったく違う! これはセビーチェじゃない」
と言うだろう。つまり、AIに依頼すれば、瞬時にそのテーマに沿った「それらしいもの」を作ってくれる。しかし、それを検証できる人は、それなりの知識と経験が求められるのだ。
レベルの高い成果物を求められる場合は、より一層、経験豊かな人の力が必要になる。
■AIを正しく使うには経験が必要
実際に、ある若手社員から見せられたプレゼン資料に、私はかなりガッカリした。一発で、生成AIで作られたプレゼン資料だと分かったからだ。
「AIで生成したらダメなんですか?」
と言われたが、そうではない。プレゼン資料の基本を知らないのに、AIに任せたことが問題なのだ。
このプレゼンの目的は何か? 何を訴求したいのか? 目的に合ったフレームワークを使っているか? 他資料とのトーン&マナーは合っているか? これらを理解し、AIに指示したら、もっとクオリティの高いプレゼン資料になっただろう。
ただ、経験がある人ならわかるだろうが、そこまで指示しても、こちらの意図通りにAIは生成してくれない。微妙に伝わらないのだ。経験があればあるほど細部にこだわる。うまく言葉で表現できない「小さなズレ」が許せない。
だから、結局はAIに任せず「自分でやったほうが早い」となる。
経験の浅い人、そもそもプレゼンとは何か? について知識がない人は、洗練されたビジュアルのスライドを見せられたら「凄いものができた」「もう人間は要らない」などと思い込むが、そうではないのだ。
先述のセビーチェでもそうだ。「本物のセビーチェとは違うかもしれないが、これはこれで美味しいからいいじゃないか」と、基本を知らない人は評価してしまう。
しかしこれが寿司だったらどうか? 肉じゃがのような料理を出されて、「本物の寿司とは違うかもしれないが、これはこれで美味しいからいいじゃないか」と言われたら納得するだろうか?
正しい知識や経験を身につけていないと、AIが生成した成果物を自分でクリティカルに検証することができない。
■まとめ
AI時代に求められるのは「AIを使う前に、そのテーマにおいて自分の腕を磨くこと」だ。基本を押さえ、経験を積んで初めてAIを正しく活用できるのだ。
企業が若手の採用を控える流れは、今後も加速していくかもしれない。採用と育成コストがかかるだけでなく、過剰に「気を遣う」ことでベテラン社員の生産性が落ちることも考えると、なおさらである。