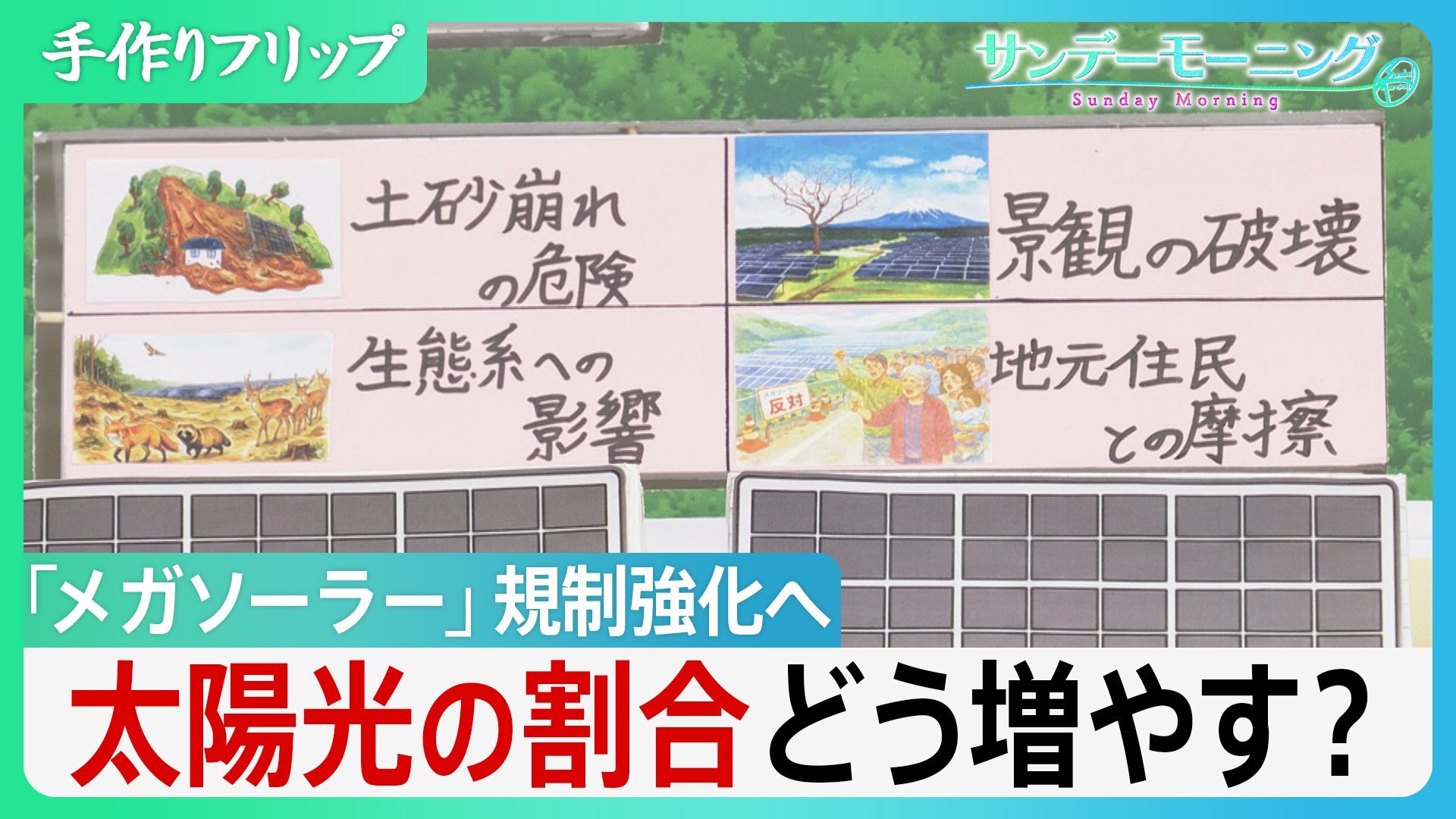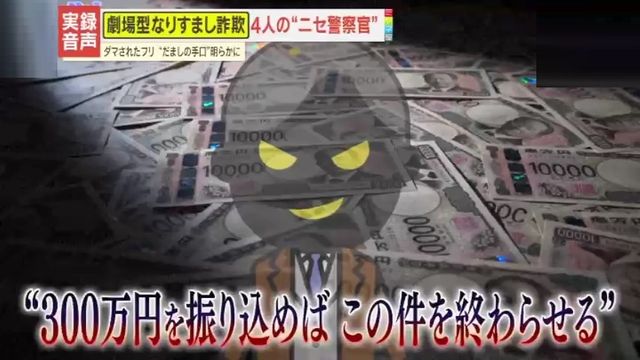核融合発電の中核研究3施設、100億円かけ増強…企業に利用促し国際的な開発競争で優位に

政府は、次世代エネルギーとして期待される核融合発電の実現に向け、国内に3か所ある中核研究機関を大幅に拡充する方針を固めた。発電設備の耐久性を調べる装置など、技術実証に必要な設備を約100億円かけて整備する。企業にも積極的な利用を促し、商用化を見据えて激化する国際的な開発競争で優位に立つ。
文部科学省核融合は太陽内部で起きている反応で、原子核同士の融合によって膨大なエネルギーを生み出す。燃料1グラムから石油8トンを燃やした時と同じエネルギーを得られるとされる。
核分裂の連鎖反応を伴う原子力発電と違って制御不能になるリスクが少なく、安全性は高いといわれる。発電時に二酸化炭素が出ない脱炭素電源でもあり、世界で開発競争が活発化する。
政府が行う核融合開発支援策のイメージ核融合発電は、反応の方法によって主に3方式ある。国内では量子科学技術研究開発機構、自然科学研究機構核融合科学研究所、大阪大レーザー科学研究所の3機関が各方式の開発の中核を担うが、実験段階で実用化のメドは立っていない。
そこで文部科学省と内閣府は、今年度中に約100億円かけて量研機構の六ヶ所フュージョンエネルギー研究所など3機関の設備を拡充。各方式の技術実証を加速し、早期実用化を目指す。具体的には、発生したエネルギーを熱に変換する装置の耐久性を調べる設備などを整備する。燃料を加熱するレーザー照射装置も改良する計画だ。
核融合発電は近年、商用化を目指すスタートアップ(新興企業)が国内外で誕生し、政府主導だった研究開発に民間資金が流れている。特に米国では、巨額の投資を集める有力企業が開発を加速させている。
政府は産業育成のため、拡充した中核機関を民間にも有償で開放し、企業単独では難しい大規模な設備を使った実験や核融合反応の長時間維持に必要な技術実証などに活用してもらう。
核融合発電を巡って政府は、国内での実用化を目指す国家戦略を近く改定し、「2050年頃」としていた実現の目標時期を「30年代」に前倒しする方針を盛り込む。それには民間の力が必要なため、中核機関を産官学連携の拠点とする。
世界の開発競争、新興企業の存在感高まる
核融合発電の開発では近年、世界的に新興企業の存在感が高まっており、国内でも設立が相次ぐ。民間も利用できる中核研究機関の拡充は、国際競争を勝ち抜くため、核融合を新産業として育成する狙いがある。
核融合発電は、高度な技術の集合体だ。核融合反応を制御する機器には誤差1万分の1以下の工作精度が必要で、一部の部品には数千度の耐熱性が求められる。
開発には、大規模な設備投資が欠かせない。米国では、2030年代初頭の商用発電を目指す新興企業の一つが20億ドル(約2900億円)超の資金を集めた。一方、日本では投資規模が小さく、自前で大がかりな実験設備をそろえられない。
日本の核融合開発の中心は従来、日米欧などがフランスに建設中の国際熱核融合実験炉「 ITER(イーター) 」だった。だが、不具合が見つかるなどして計画は遅れ、運転開始は34年を予定する。
ITERにも参画する中国は、独自に実験炉の建設を進め、開発に本腰を入れる。日本は蓄積した技術を活用するためにも、官民を挙げた開発体制を早期に構築するべきだ。(科学部 大山博之)
◆核融合発電= 燃料となる重水素や三重水素を1億度以上に加熱して核融合反応を起こし、発生したエネルギーを熱に変えて発電する。超高温のプラズマを閉じ込めて反応を起こす「トカマク型」と「ヘリカル型」、燃料をレーザーで加熱する「レーザー型」がある。