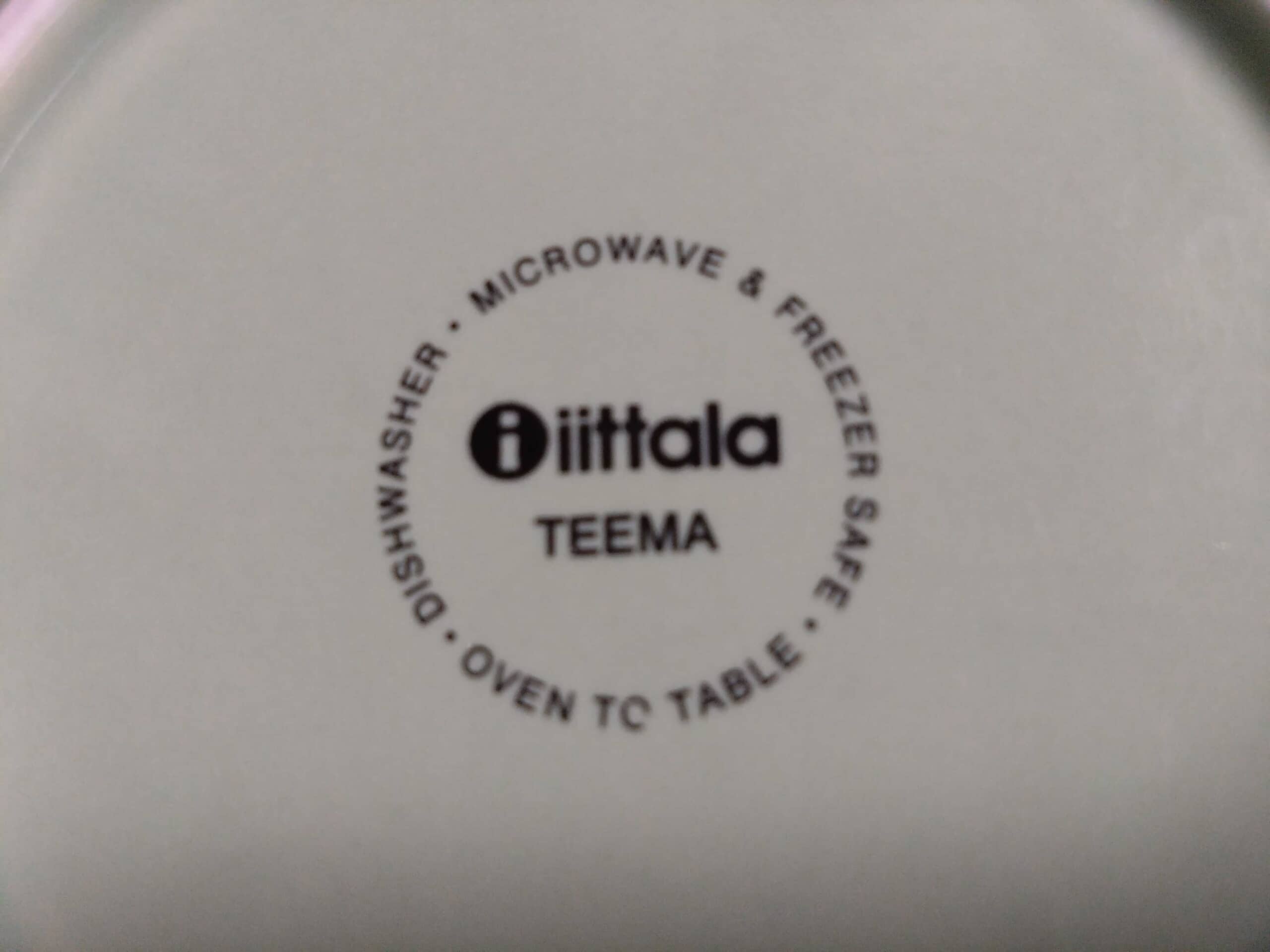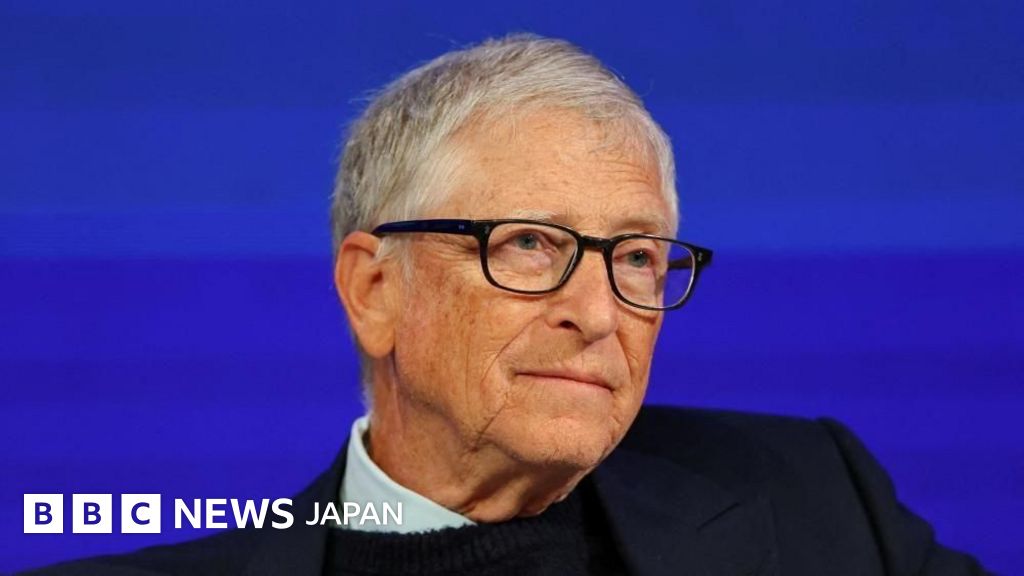朝起きるのがツラい理由、脳のスキャンで解明

誰だって朝、スッキリ目覚めたいものです。
気持ちよく目覚めるためにやった方がいいと言われる夜のルーティンや早寝、寝る前にデバイスを使わないなどといった方法でも、どうも変化がないという人もいるんじゃないかとお思います。
その理由のひとつとして、眠りにつく時と翌朝目覚める時の脳の働き方が、実は違っているということが新しい研究でわかりました。
20人の目覚めを1000回以上記録
オランダ神経科学研究所の神経科学者チームが、20人の被験者の脳活動を観察し、被験者たちが自然に、あるいはアラームによって目覚める様子を1000回以上記録しました。その結果、目覚めを示す特有の脳活動パターンがあることがわかりましたが、それは脳が活発に動いている浅い眠りのレム睡眠の最中に起こされた人と、脳も体も休まる深い眠りのノンレム睡眠中の人とでは異なっていたのです。そして、レム睡眠中に目覚めた人の方が「目覚めたときに疲れている」と感じる傾向が強いことも判明しました。
「驚いたのは、このパターンがすべての目覚めで非常に一貫して見られたこと、そしてそれが主観的な眠気の感じ方と関連していたことです」
と、オランダ神経科学研究所の神経科学者でこの研究の責任著者であるFrancesca Siclari氏は、Nature誌に語っています。 今回のこの研究結果は『Current Biology』誌に掲載されています。
「覚醒の波」が来るまでには時間がかかる
実験では被験者の頭に256個のセンサーが取り付けられ、脳活動を1秒単位で追跡しました。これにより、研究チームは各被験者の脳の活動を視覚的にマッピングし、目覚めたときの眠気の自己評価と比較できたのです。
その結果、レム睡眠中に目覚めた場合、脳内では「活性化の波」が前頭部から後頭部へと移動していることがわかりました。まず実行機能や意思決定を担う前頭前野が活動を始め、それに続いて「覚醒の波」が視覚を司る後部領域までゆっくりと広がっていきました。ノンレム睡眠中の目覚めでは、この波は脳の中央部の「ホットスポット」から始まり、同様に前から後ろへと進んでいきました。
この発見は、睡眠に問題がある人がなぜすっきり目覚められないのか、その原因を明らかにする手がかりになるかもしれません。ただし、睡眠中の体の動きなど、他の要因についても今後さらに研究が必要となってくるとのこと。主観的な眠気だけでなく、より客観的な覚醒度の測定も、今後の研究の精度を高める可能性があります。
「通常の目覚めのときに脳がどのように活動しているかが正確にわかれば、異常な目覚めとの比較がしやすくなります」
と、Siclari氏は説明しています。