ひろゆき×進化生態学者・鈴木紀之のシン・進化論④「動物のオスは、違う種類のメスにも求愛するって本当?」【この件について】(週プレNEWS)
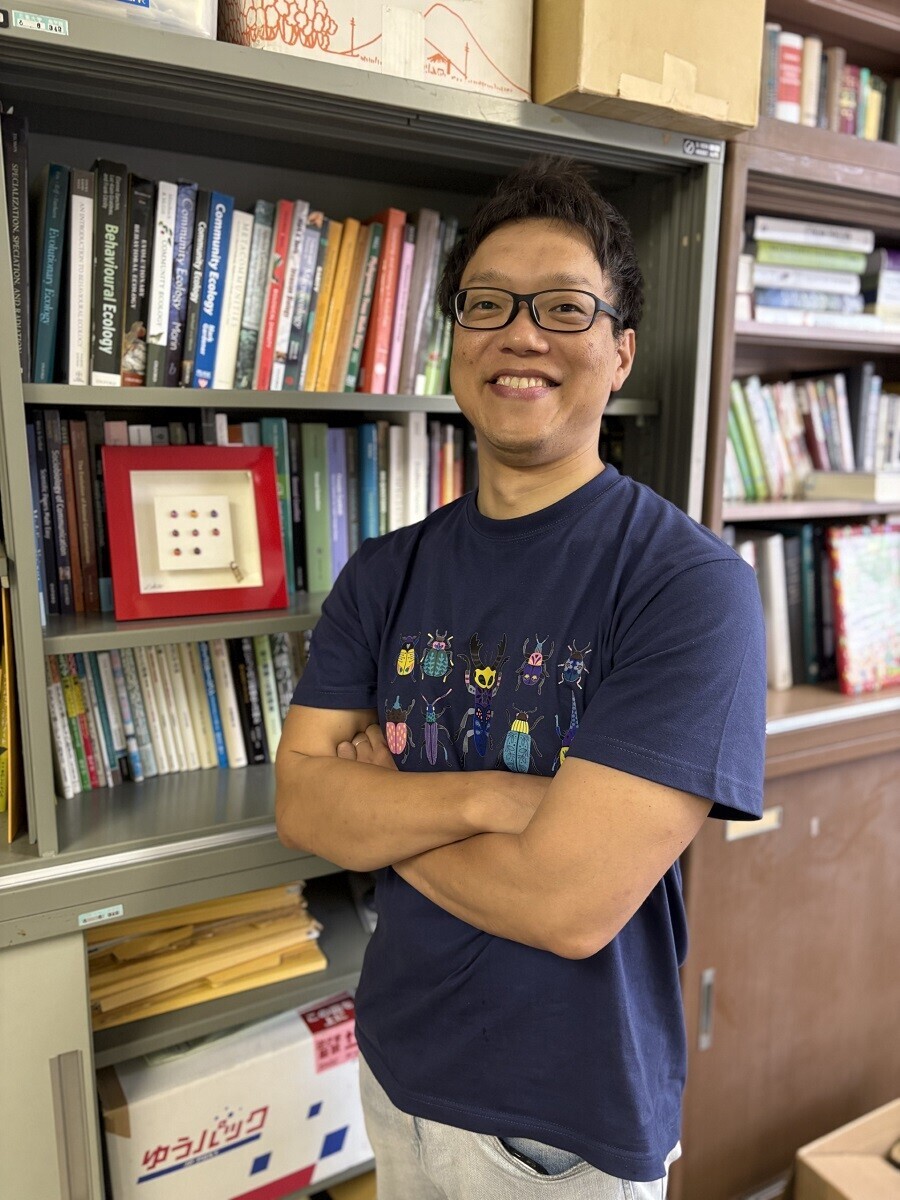
ひろゆきがゲストとディープ討論する『週刊プレイボーイ』の連載「この件について」。進化生態学者の鈴木紀之先生をゲストに迎えた4回目です。 動物のオスは自分と同じ種類のメスだけでなく、違う種類のメスにも求愛するらしいんです。男性読者なら、その気持ちがなんとなくわかりますか? ということで、鈴木先生に理由を教えてもらいました。 *** ひろゆき(以下、ひろ) 昆虫とかって、違う種類のメスにオスが求愛しちゃうことあるんですか? 鈴木紀之(以下、鈴木) ありますよ。昆虫に限らず、動物でもオスが違う種類のメスにアプローチすることはあります。そして、メスのほうもそれを受け入れてしまう場合があるんです。 ひろ へえ、相手が違う種類でも交尾しちゃうんだ。 鈴木 ただ、仮に子供が生まれても体が弱かったり、子孫が残せなかったりします。 ひろ でも、なんでそんなことが起きるんですか? 子孫が残せないのに......。 鈴木 ですから、生物学的には「エラー」とされてきたんです。進化生物学の基本的な考えは「生物の行動は長い時間をかけて最適化されている」はずなので、こうした「不利益なエラーは淘汰されて、起こらない」と考えるのが自然です。でも研究が進むと、これが「ごくまれな例外ではない」ことがわかってきたんです。 ひろ ということは、頻繁に起きてるんですか? 鈴木 はい。昆虫や魚類、哺乳類でも種をまたいだ交尾は見られます。つまり、例外どころか無視できない頻度で起きている。じゃあ、なぜそんなエラーが起きるのか。それは、むしろ「最適化されたがゆえに起きるエラー」だと考えられてるんです。 ひろ どういうことですか? 鈴木 例えば、自然界の中で自分と似た種を見分けるのは、けっこうなコストがかかるんです。自分と同じ種の相手を100%正確に見分けるのが理想ですが、識別するためにはエネルギーも時間も必要になる。それなら「多少間違えてもいいや」と割り切ったほうが生存戦略として合理的だと考えることもできる。 ひろ 「間違えたって死ぬわけじゃないし、手当たり次第にアタックしたほうが効率いいんじゃね?」みたいな感じですかね(笑)。 鈴木 そうです。そして、その戦略が成り立つかどうかは、間違えることのデメリットの大きさによります。例えば、多くの動物のオスの場合、求愛をメスに断られたり相手が違う種だったりしても、また次のメスを探せばいい。つまり、求愛が失敗に終わってもデメリットは小さいんです。 ひろ 確かに。オスは失うものが少ない。 鈴木 となると「正確に見分けるコスト」と「間違えるコスト」を天秤にかけた結果、「取りあえず手当たり次第にアタックする」という戦略のほうが、子孫を残す確率が高まって有利になる。だからこそ「一見、不合理に見えるエラーが進化の過程で淘汰されずに残っている」と解釈できるわけです。 ひろ じゃあ、違う種同士で交尾して、たまたま受精卵ができちゃうパターンもあるんですか? 鈴木 はい、雑種ができることはあります。特に遺伝的に近い種同士だと交尾して子供が生まれることがあります。ただ、先ほども触れたように、うまく成長できなかったり、生殖能力がなかったり、次の世代につながらないケースがほとんどです。 ひろ ちなみに、その種はどのくらい離れててもいいんですか? 例えば、人間はどの人種同士で子供をつくっても、特に生存に不利にならないじゃないですか。そう考えると「人間は種が分かれていない」ということですか? 鈴木 そのとおりです。肌や目の色、体格など、いわゆる〝人種〟による特徴はさまざまですが、生物学的には紛れもなくひとつの種です。 ひろ 見た目はけっこう違うのに。 鈴木 その理由は、人類の歴史の浅さにあります。現生人類はアフリカで誕生し、その後、世界中に広がっていきましたが、この拡散が起こったのは、わずか数万年の間です。これは進化の歴史でいうとごく最近の出来事で、遺伝的な分化はそれほど進んでいません。 ひろ じゃあほかの昆虫や動物の種の違いに比べたら、人間の見た目の差なんて、微々たるものだと。 鈴木 今では遺伝学的な研究も進み、人種という区分は生物学的な根拠に基づくものではなく、社会的、文化的につくられたカテゴリーだと考えられています。



