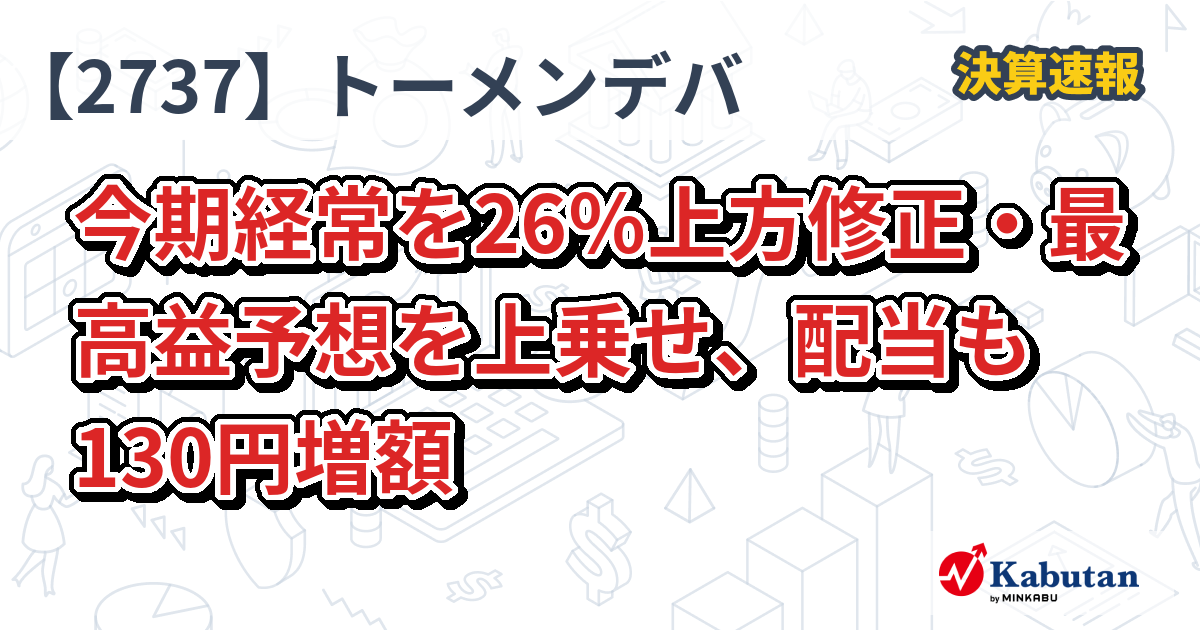【為替】通貨安誘導封じを確認した日米共同声明

日米の財務省が9月12日発表した共同声明の中では、「国際収支の実効的な調整を妨げたり不公正な競争上の優位性を得るために為替レートや国際通貨システムを操作することを、両者は避けてきたことを再確認した」と述べた上で、以下のように「競争上の目的のために為替レートを目標としない」という指摘が何度も繰り返された。
・財政・金融政策は、国内の手段を用いてそれぞれの国内目的を達成することに向けられ、競争上の目的のために為替レートを目標とはしないとの G7のコミットメントについての認識を再確認した。
・いかなるマクロプルーデンス措置又は資本フロー措置も、競争上の目的のために為替レートを目標とはしない。
・年金基金等その他の政府の投資主体による海外への投資は、引き続きリスク調整後のリターンや分散化の目的で行われ、競争上の目的のために為替レートを目標とはしない。
「競争上の目的のために為替レートを目標とする」、その分かりやすい具体例は輸出競争力を向上させるための通貨安誘導だ。その意味では、今回の共同声明の主な目的は、通貨安誘導封じということになるだろう。そして日本の円安誘導とともに米国の米ドル安誘導も公平にけん制した内容になっている。
米財務省為替報告書、ベッセント・コメントとの類似
ただし、このテーマへのこだわりは米国サイドが主導したのではないか。というのは、6月に米財務省が為替報告書を公表した際に出されたベッセント財務長官のコメントの中の以下のような一節に類似しているからだ。「トランプ政権は、米国との不均衡な貿易関係を助長するマクロ経済政策はもはや容認しないと貿易相手国・地域に警告してきた」。
今回の共同声明にあった、「国際収支の実効的な調整を妨げたり不公正な競争上の優位性を得るために為替レートや国際通貨システムを操作すること」を米国サイドから見ると、「米国との不均衡な貿易関係を助長するマクロ経済政策」とほぼ同じ意味になるだろう。
その上で、今回の共同声明の中にあった、為替介入や財政・金融政策、さらに年金基金など政府の他の投資主体まで広げて通貨安誘導を容認しないといった独特とも言えそうな論法は、まさに6月の為替報告書およびベッセント・コメントの中で展開されていたものだった。
ベッセント主導の円安誘導封じ=アベノミクス再来へのけん制も
以上のように見ると、米国、特にベッセント財務長官主導の通貨安誘導封じの考え方を、日米合意の形にしたのが今回の共同声明ということだったのではないか。そうであれば、米ドル安以上に、円安への過度な誘導を行わないことを日本政府も確認したという意味が大きかったようにも感じられる。
近年の為替相場の歴史の中で、このような「競争上の目的のために為替レートを目標とはしない」、別の言い方をすると「過度な通貨安への誘導を行わない」という考え方への「違反」が疑われたのが安倍政権2期目の経済政策、「アベノミクス」ではなかったか。アベノミクスの中核こそは、日銀による大胆な金融緩和と、それを受けた円安を容認することでデフレからの脱却を目指すというものだったからだ。
1年前の自民党総裁選挙で、高市・前経済安全保障担当相はアベノミクスの継承者を自認した。うがった見方をすれば、共同声明がこのタイミングで出されたのは、自民党総裁選でのアベノミクス再来に対するけん制といった狙いもあったかもしれない。