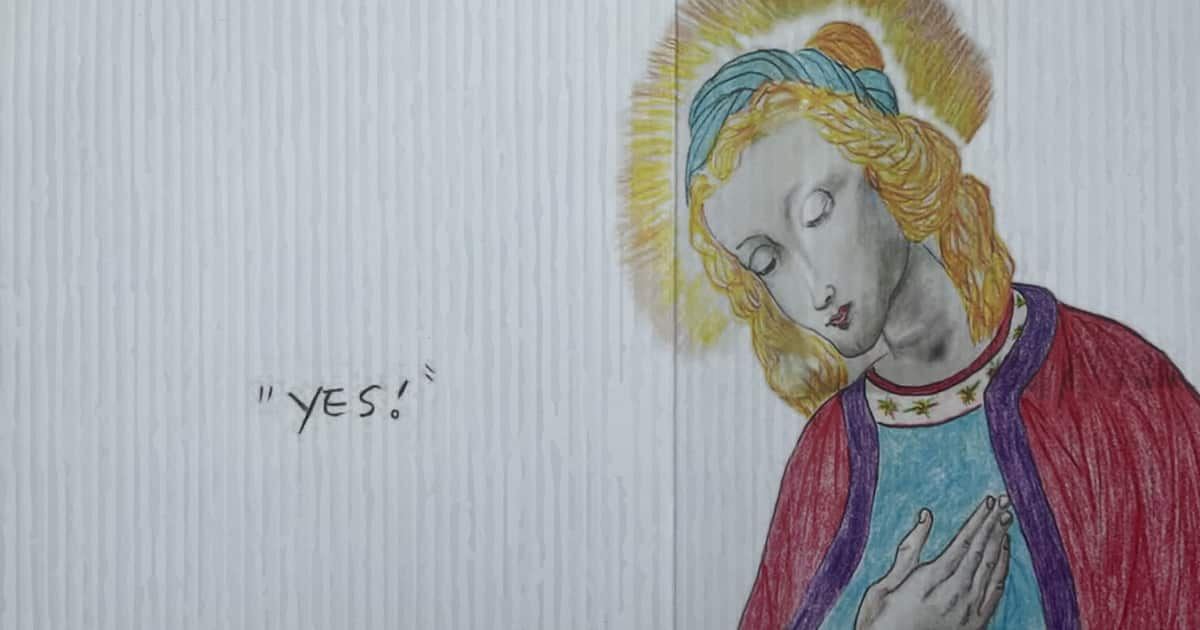超低金利時代に幕、1450兆円の債務下で日本企業へのストレス顕在化も

日本の超低金利時代が終わりを迎え、借り換え需要が高まる中で、企業や金融機関に新たな打撃が及びつつある。
円建ての借り入れコストは、2000年代後半以来の高水準に達し、財務基盤の弱い企業では、リファイナンスを迫られる中で資金繰りのストレスが表面化している。
国際通貨基金(IMF)によれば、日本の政府債務は今年1450兆円に達し、国内総生産(GDP)比で230%と先進国で最も高い水準が見込まれる。
日産自動車は今期2750億円の営業赤字を見込み、20年以上ぶりの深刻な財務危機に直面している。
危機は連鎖し、主要取引先の部品メーカー、マレリホールディングスは最近、米国で連邦破産法11条(日本の民事再生法に相当)の適用申請の手続きを実施。原因の一つとして関税を挙げた。
イベントのお知らせ:グローバル・クレジット・フォーラム東京
11月5日(水)午後4時より、ブルームバーグ主催「グローバル・クレジット・フォーラム東京」を開催します。三村淳財務官や伊藤豊金融庁長官のほか、金融業界のリーダーらがクレジット市場の課題や展望について議論します。端末でのご視聴はこちら、オンラインからはこちらでご覧ください。
企業倒産も増加しており、24年度の件数は1万70件と前年度比で13%増え、14年以来の高水準となった。
高市早苗新首相にとって、こうした状況は大きな試練となる。財政出動に関する主張はややトーンダウンさせているものの、かつて積極的な拡張策を訴えていた経緯から、市場を動揺させた英国のトラス元首相のような事態を招きかねないとの懸念も一部にある。
ニッセイ基礎研究所の福本勇樹金融調査室長は、日本の政府債務の水準の高さに加え、国債の格下げリスクもあることから、金融不安が広がった場合に政府が企業支援に動ける余地は限られる可能性があると指摘する。
福本氏は、金利が上昇することで出現するのは「ウィナー(勝者)とルーザー(敗者)」だとし、その結果、二極化現象が生じるとの見方を示した。さらに、「国債が格下げになると、全体的に調達コストが上昇し、勝者の数が減り、敗者の数が増える」と語った。
日本のクレジット市場は相対的に見れば依然として安定さが目立つ。
それでも警戒を促す動きは増えつつある。ブルームバーグ・インテリジェンス(BI)のクレジットアナリスト、リサ・チョウ氏は最近のリポートで、自動車セクターは関税措置による不確実性に直面していると指摘している。
10月24日時点で、自動車メーカーの海外子会社を含む7社が格下げリスクに直面しており、債券発行残高は総額750億ドル(約11兆5200億円)に達している。
顕在化していないリスク
世界の市場は顕在化していない債務リスクに神経質になっており、日本企業の経営悪化が広がれば問題視されやすい状況だ。
JPモルガン・チェースのジェイミー・ダイモン最高経営責任者(CEO)は最近、こうしたリスクを巡って「ゴキブリを1匹見たら、恐らく他にもいる」と発言し、市場で注目を浴びた。
日本の金融機関もそうした市場の異変の影響と無縁ではない。
自動車部品メーカー、ファースト・ブランズ・グループの破綻に関連して、農林中央金庫と三井物産が大株主であるJA三井リースが多額の債権を抱えていることが明らかになっている。
別のリスク要因もある。M&A(企業の合併・買収)取引の増加だ。
日本企業による成立済みまたは進行中のM&A取引は今年これまでに129%増の2620億ドルに達し、世界で最も活発な市場の一つとなっている。人工知能(AI)や半導体、データセンターといったセクターで買収価格が急上昇し、企業は負債を積み上げている状況だ。
これに伴い、一部の企業は管理可能な範囲を超えた債務を抱え先行きに不確実性が生じる可能性もある。
野村証券の荻野和馬シニア・クレジット・アナリストは、M&Aブームにより、財務レバレッジが悪化する企業が出てくる可能性があると指摘。「企業がM&Aをすればするほど、利益が増えるより、借金が増えるスピードが速くなる」リスクがあるとの見解を示した。
原題:Japan’s $9.4 Trillion of Debt Looms as Corporate Strains Appear(抜粋)
— 取材協力 Libby Cherry, Giulia Morpurgo, Trista Xinyi Luo, Pearl Liu, Macarena Munoz Montijano, Tasos Vossos and Luca Casiraghi