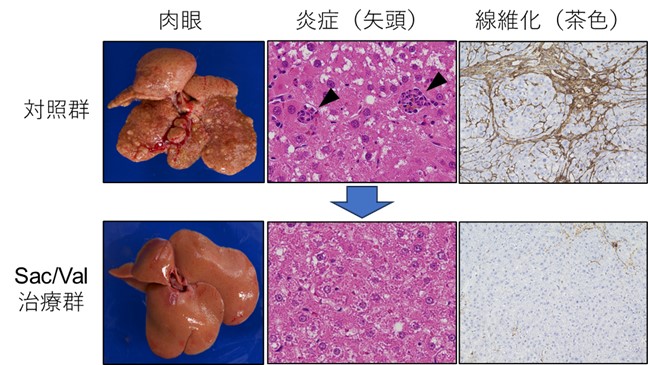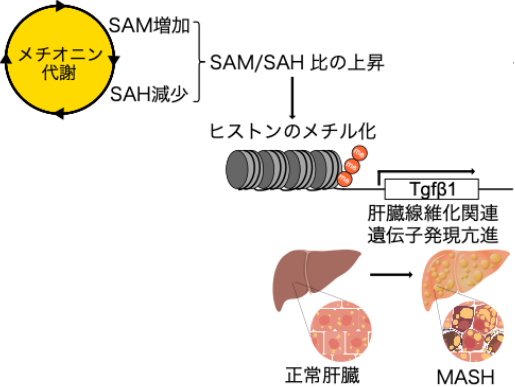「押し入れに頭をぶつけて…」「くしゃみで…」高齢者に潜む“予期せぬ死” “知っていれば避けられる”対策を法医学の第一人者が指南

「超高齢社会になり、独居のかたも増える中、高齢者のご遺体を解剖する機会が増えています。今後も増え続けると思います」 そう語るのは法医学者の高木徹也さん。これまで5000件以上の遺体を解剖する一方、高齢者に特徴的な「異状死」や浴槽内死亡事例等を研究している。 「医療技術の発達で、日本人は長生きになりました。本人も家族も『長生きなのは元気だから』と思い込んでいますが、細胞の老化は確実に進み、臓器や血管、神経は衰えます。そのため、若い頃にはありえないことで命を落とすことがあるのです」(高木さん・以下同) 法医学の現場では、どのような遺体が解剖されるのだろうか。 「事故や突然死で亡くなった『異状死』と呼ばれるご遺体です。まず警察の依頼を受けた『検案医』が遺体の外表を観察し、死因を特定(外表検査)しますが、検案医が死因を特定できない場合や事件性が疑われる場合にご遺体の解剖を依頼されます。 異状死は全死亡者の10〜15%。その中で解剖が必要となるのは約10%です」 高木さんの現在の勤務地である宮城県の年間異状死件数は約4000件。そのうちおおよそ400件が解剖を要する計算だ。 今回紹介する30の例は、高木さんが実際に解剖した、あるいは耳にした“意外な死因”のほんの一例だ。 「その中には事前に原因を知っていれば防げた事態がたくさんあります」と言う。 たとえば、頭をぶつけたり、つまずいたりと、うっかりやりがちな行動で亡くなる事例。どうやって防いだらいいのだろうか。 「高齢になると血管が硬くなり、筋肉や臓器の機能も落ちるため、弱い外力を受けただけでダメージがある。当初は症状がなく、数日かけてじわじわと脳や臓器から出血し、死に至ることが多いのです。もし頭をぶつけたら注意深く体調を観察し、気になる場合は脳神経外科医などの専門医を受診してください。 また、骨密度が低下するため、転倒して容易に骨折し、寝たきりになるリスクも高まります。つま先を上げ、足の筋肉の動きを意識して歩きましょう」 入浴中に意識を失い溺死する事例も昨今よく聞くが、これには高齢者特有の体の変化が関連している。 「65才を境に自律神経の反射が遅れるのです。私たちは、自律神経(交感神経と副交感神経)の働きを切り替えることで、活動的になったり、リラックスしたりするのですが、年を取るとその切り替えが鈍くなる」 入浴中にウトウトするのは眠気ではなく、脳への血流が低下し、“気絶状態”になっているから。若いうちは交感神経がすぐ働いて目覚めるのに、65才を過ぎると切り替えが遅くなり、溺れてしまうのだ。 「臨床現場においても、65才以上の患者さんの中には手術中に出血してもしばらくは血圧が下がらず、突然ガクンと下がって慌てて輸血することがある。これも反射の遅延によるもので、決して珍しいケースではありません」 車道への飛び出し、運転中の操作ミスなども反射神経の衰えが大きい。「とっさの判断には時間がかかる」と肝に銘じておこう。