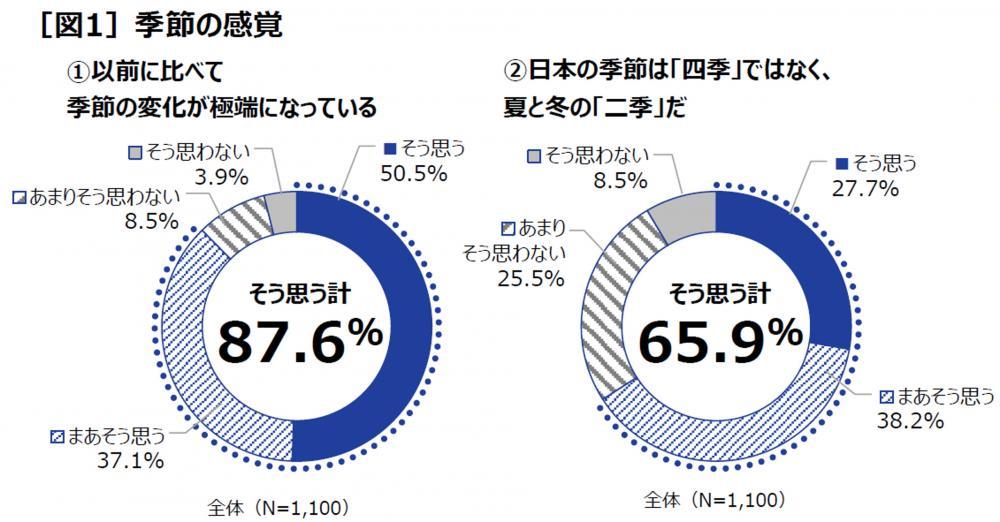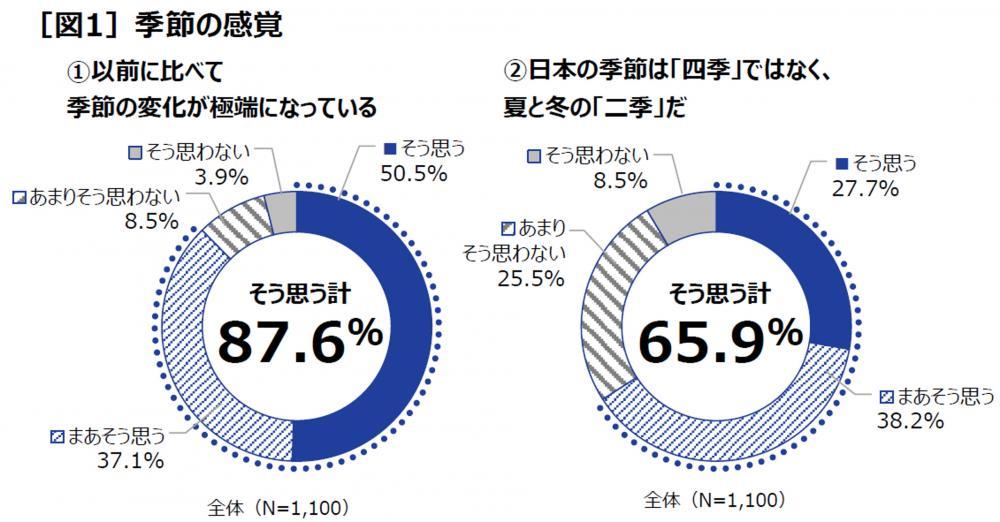アプリでお酒を減らす? 保険適用の“減酒アプリ”登場

葉石かおり=エッセイスト・酒ジャーナリスト
アルコールの飲み過ぎによる弊害は多岐にわたる。お酒に依存気味で「減らすべきだ」と分かっているが、自力で減らすことはできないという人もいるだろう。そんな人は減酒に向けた治療を検討したい。実は今年9月、アルコール依存症の患者を対象にした減酒アプリが登場した。このアプリ、医師の診断のもと、保険適用で処方されるもので、その効果も治験で明らかになっている。いったいどんなアプリなのだろうか。精神科医でアプリ開発に携わった宋龍平氏に詳しく話を聞いた。
酒をこよなく愛する者にとって、「断酒」という選択は人生のトロの部分をもぎ取られるようなもの。医師から断酒を言い渡されぬよう、日々酒量をコントロールしている人も多いだろう。筆者もその1人である。
しかし、一口に「酒量をコントロールする」といっても、自分自身でコントロールをするのは非常に難しい。なぜなら、酒好きの多くは何かと理由をこじつけ、飲む機会を自ら作っているからだ。目標を成し遂げればご褒美に酒、さらには忘年会に新年会、そして歓送迎会と、年間を通して飲酒機会を見つけ、せっせと酒を飲んでいる。
なかには、「酒にかなり依存気味で、何とかして酒量を減らしたい。だが、セルフでは難しい」という人もいるかもしれない。アルコール依存症の「治療」は医療機関で行っているが、なかでも「減酒」については医師と一緒に取り組むアプリ治療という方法があるという。
(写真はイメージ:PIXTA)
アルコール依存症の患者を対象にした減酒アプリが、2025年9月に沢井製薬(開発はCureApp)から発売された。その名は「HAUDY(ハウディ)」。依存症対策の1つである「減酒」を支援する。
HAUDYは医師の診断のもと、保険適用で処方される減酒治療補助アプリなのだ。日本初となる減酒治療補助アプリとは、いったいどのようなものなのだろうか? 精神科医で、本アプリ プロジェクトリーダーの宋龍平氏に話を伺った。
もう少し早く治療に来てくれたら…
先生、減酒治療補助アプリを作ろうと思ったのはなぜですか?
「父が神戸でアルコール依存症の専門クリニックを開業しており、私は高校の頃からその建物の中で暮らしていました。なので、アルコール依存症の患者さんは、私にとって特別な存在ではなく、身近な人だったんです。クリニックに来る人は、なんとかしたいという意志を持っているので、良くなっていく人が多い。その様子を見ていたので、“依存症は治らない病気ではない”という感覚を持っていました」(宋氏)
そうした若き頃の経験に加え、精神科医となりアルコール依存症治療の診療現場で働くようになった宋氏は患者の現状を目の当たりにする。
「“もう少し早く来てくれたら”と思う患者さんが多かったんです。お酒をやめても、既に肝臓がんを発症していたり、体がボロボロになっていたりする。そういう人を何人も見てきたこともあり、“もっと早い段階で支援できる仕組みを作りたい”と思うようになりました。それがアプリ開発のきっかけの1つでした」(宋氏)
こうした現場感覚の背景には、日本の現実がある。久里浜医療センターによる2024年の調査によると、国内のアルコール使用障害(Alcohol Use Disorder=AUD)患者は約304万人と推計されている。AUDとは、酒量を自らコントロールすることが難しくなり、心身や社会生活にさまざまな影響を及ぼす疾患を指す。
-
- 新国民病の「逆流性食道炎」、気づきにくい「食道がん」
-
「逆流性食道炎」は近年、患者数が急増しており、今や「新国民病」と呼ばれるほど、年齢を問わず多くの人を悩ませている。自覚症状がなく気づきにくい「食道がん」は、進行すると手術の難易度が高くなり、患者への負担も高くなる。今回は身近なようで実は知らない「食道」の病気について解説していく。
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 2
ビジネスでも、プライベートでも、「酒」が同席する機会は少なくない。ましてや日本の文化に「酒」はなくてはならないもの。祝い酒、嬉し酒、やけ酒、涙酒…。「アルコールはガソリン!」という“超・左党”たちから、「アルコールとは時々仲良し」という“準・左党”たちまで、皆に役立つ酒と健康の最新科学を贈る! (タイトル題字:葉石かおり)
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- 新国民病の「逆流性食道炎」、気づきにくい「食道がん」
-
「逆流性食道炎」は近年、患者数が急増しており、今や「新国民病」と呼ばれるほど、年齢を問わず多くの人を悩ませている。自覚症状がなく気づきにくい「食道がん」は、進行すると手術の難易度が高くなり、患者への負担も高くなる。今回は身近なようで実は知らない「食道」の病気について解説していく。
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 3
ビジネスでも、プライベートでも、「酒」が同席する機会は少なくない。ましてや日本の文化に「酒」はなくてはならないもの。祝い酒、嬉し酒、やけ酒、涙酒…。「アルコールはガソリン!」という“超・左党”たちから、「アルコールとは時々仲良し」という“準・左党”たちまで、皆に役立つ酒と健康の最新科学を贈る! (タイトル題字:葉石かおり)
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- 新国民病の「逆流性食道炎」、気づきにくい「食道がん」
-
「逆流性食道炎」は近年、患者数が急増しており、今や「新国民病」と呼ばれるほど、年齢を問わず多くの人を悩ませている。自覚症状がなく気づきにくい「食道がん」は、進行すると手術の難易度が高くなり、患者への負担も高くなる。今回は身近なようで実は知らない「食道」の病気について解説していく。
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 4
健康・医療に関するホット・トピックスをお伝えします。
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- 新国民病の「逆流性食道炎」、気づきにくい「食道がん」
-
「逆流性食道炎」は近年、患者数が急増しており、今や「新国民病」と呼ばれるほど、年齢を問わず多くの人を悩ませている。自覚症状がなく気づきにくい「食道がん」は、進行すると手術の難易度が高くなり、患者への負担も高くなる。今回は身近なようで実は知らない「食道」の病気について解説していく。
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 5
働く女性にとって、自分の体調管理は仕事と同じくらい大切です。日経ヘルスにて好評連載中の「女性のお悩み相談室」から、女性特有の病気について、予防法や対処法を学びましょう。今日も輝くあなたの「転ばぬ先の杖」になること請け合いです!
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- 新国民病の「逆流性食道炎」、気づきにくい「食道がん」
-
「逆流性食道炎」は近年、患者数が急増しており、今や「新国民病」と呼ばれるほど、年齢を問わず多くの人を悩ませている。自覚症状がなく気づきにくい「食道がん」は、進行すると手術の難易度が高くなり、患者への負担も高くなる。今回は身近なようで実は知らない「食道」の病気について解説していく。
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 6
日経Goodayでは日々、新しい健康・医療情報をお届けしています。その中で、読者のみなさまが今、最も気になっているテーマ、例えば、「大腸がん」「脂肪肝」「痛風・尿酸値」「男性ホルモン」などに関する多数の記事の“エッセンス”をすばやく知りたい――。そんなニーズにお答えする新サービスを開始します。
それが「テーマ別特集」です。毎月、読者のみなさまの関心が高かったテーマをチョイスし、特に好評だった記事のポイントを編集部でピックアップしてお届けします。そのテーマ、ジャンルについて知っておくべきことが、この記事を読むだけですべて把握できます。さらに、そのテーマに関する記事一覧もご用意しました。ご活用ください。
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- 新国民病の「逆流性食道炎」、気づきにくい「食道がん」
-
「逆流性食道炎」は近年、患者数が急増しており、今や「新国民病」と呼ばれるほど、年齢を問わず多くの人を悩ませている。自覚症状がなく気づきにくい「食道がん」は、進行すると手術の難易度が高くなり、患者への負担も高くなる。今回は身近なようで実は知らない「食道」の病気について解説していく。
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 7
「逆流性食道炎」は近年、患者数が急増しており、今や「新国民病」と呼ばれるほど、年齢を問わず多くの人を悩ませている。自覚症状がなく気づきにくい「食道がん」は、進行すると手術の難易度が高くなり、患者への負担も高くなる。今回は身近なようで実は知らない「食道」の病気について解説していく。
テーマ別特集「食道」この記事の主な内容 逆流性食道炎 つらい胸やけ、みぞおちの不快感などはある? 日本人患者における重症度別の割合は? 胃酸を抑える薬を使って、症状の経過を見ていく 「ゆるみ・胃酸・腹圧」を改善し、逆流を防ぐ バレット食道の人はどんなことに注意すべき? 発見が遅れると手術の難易度が高くなる「食道がん」 食道がんの2大リスク要因は、「お酒」と「たばこ」 3人に1人、飲酒で顔が赤くなる「フラッシャー」は要注意 食道がんが見つかったら、どんな治療をする?(写真:PIXTA)
逆流性食道炎 つらい胸やけ、みぞおちの不快感などはある?
食道の病気には、症状を感じやすいものがある。それが、逆流性食道炎だ。逆流性食道炎は近年急増しており、今や「新国民病」と呼ばれるほど、ポピュラーな病気になっている。あなたはどうだろうか。以下のチェックリストの項目に当てはまる人は、逆流性食道炎の可能性が高い。
逆流性食道炎チェック
Q1 こんな症状がありますか?
- 胸やけのような、みぞおち付近の不快感がある
- すっぱいものなど、何かがのどに込み上げてくる(呑酸;どんさん)
- のどがつかえたような感じがある
↓ ↓ ↓
Q2 どんな場面でその症状を感じますか?
- 食べ過ぎたとき
- 脂っこい料理を食べた後
- 香辛料の効いた料理を食べた後
- 前かがみの姿勢や、横になったとき
- 重い物を持ち上げるなど、力んだとき
(島田英昭『逆流性食道炎は自分で防ぐ!』(池田書店)を参考に作成)
胸やけ、すっぱいものが込み上げてくるような感覚(呑酸;どんさん)、のどがつかえる感じは、いずれも逆流性食道炎の代表的な症状だ。「もしかしたら私も?」と思った人も多いのではないだろうか?
胸やけ、すっぱいものが込み上げる、のどのつかえなどが気になれば、逆流性食道炎の可能性がある。(写真:eddows/stock.adobe.com)
「食道がん」へ進展するケースもある
逆流性食道炎は、長い間、不快な症状に悩む人が多い病気だ。だが、怖いのはそれだけではない。逆流性食道炎は、長い時間を経て食道がんへと進展するケースがある。「逆流性食道炎からくる食道がんは、腺がんというタイプのがんです。日本では今のところまだ少数派ですが、その数は増え続けています」と東邦大学医学部外科学講座教授の島田英昭氏は指摘する。
胃の内容物には、強酸性(pH1~2)である胃酸が含まれている。一方、食道は中性(pH6~7)に保たれているので、胃酸が食道に逆流すると、食道の粘膜はダメージを受けてしまう。食道が胃酸にさらされ続けると、やがて胃に近い食道下部の粘膜は性質が変わり、別のタイプの細胞に置き換わっていく(バレット食道という)。これが、食道がんの発生母地になると考えられているのだ。
「逆流性食道炎があって、バレット食道も指摘されたことがある人は、食道がんにつながる階段を1段上がっていると考えられ、警戒が必要です」(島田氏)
【 ピックアップ記事 】 急増する逆流性食道炎 つらい胸やけを解決する3つのアプローチ日本人患者における重症度別の割合は?
逆流性食道炎と呼ばれるものは、医学的には胃酸が逆流することを「胃食道逆流症(GERD)」といい、食道に炎症があるものを逆流性食道炎、炎症がないものを非びらん性胃食道逆流症(NERD)という。
「炎症が起こっていないのに痛みや胸やけを感じるのは、知覚過敏が原因です。歯の知覚過敏と同じようなことが、食道でも起こっているわけです。胃食道逆流症患者の中で、逆流性食道炎と非びらん性胃食道逆流症の比率は半々くらいになります」と、国立国際医療研究センター病院消化器内科診療科長の秋山純一氏は話す。
炎症がある逆流性食道炎にも軽症と重症があり、グレードA、Bが軽症。複数の赤みが融合して広がっているC、Dが重症となる。日本では、軽症のグレードA(54.6%)、B(32.4%)の患者の割合が高い。
逆流性食道炎の重症度(グレード)と患者の割合
日本では、軽症のグレードA、Bの患者の割合が高い。(右の円グラフの出典:J Gastroenterol. 2009;44(6):518-534.)
「逆流性食道炎は非びらん性胃食道逆流症に比べて逆流する胃酸の量が多いが、その原因は胃と食道の間にある括約筋が緩むことです。したがって括約筋が緩まず、胃酸が逆流しにくくなるように生活習慣を改善することが大切になります」(秋山氏)
グレードA程度の逆流性食道炎なら、簡単なセルフケアだけで治ることもあるという。「例えば、高脂肪食、食べ過ぎ、アルコール、喫煙、炭酸飲料、チョコレート、コーヒー、これらは括約筋を緩める作用があるので、控えめにしてください」(秋山氏)
非びらん性胃食道逆流症については、「知覚過敏で起こるもので、実際にはそれほど逆流があるわけではありません。したがって、セルフケアをしてもあまり良くならないことが多いです。知覚過敏の原因はストレスが一番なので、ストレスへの対処が大切になります」(秋山氏)
【 ピックアップ記事 】 「老化した胃を若返らせたい」「逆流性食道炎はがんになる?」名医が回答
-
- 新国民病の「逆流性食道炎」、気づきにくい「食道がん」
-
「逆流性食道炎」は近年、患者数が急増しており、今や「新国民病」と呼ばれるほど、年齢を問わず多くの人を悩ませている。自覚症状がなく気づきにくい「食道がん」は、進行すると手術の難易度が高くなり、患者への負担も高くなる。今回は身近なようで実は知らない「食道」の病気について解説していく。
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 8
日経Goodayでは日々、新しい健康・医療情報をお届けしています。その中で、読者のみなさまが今、最も気になっているテーマ、例えば、「大腸がん」「脂肪肝」「痛風・尿酸値」「男性ホルモン」などに関する多数の記事の“エッセンス”をすばやく知りたい――。そんなニーズにお答えする新サービスを開始します。
それが「テーマ別特集」です。毎月、読者のみなさまの関心が高かったテーマをチョイスし、特に好評だった記事のポイントを編集部でピックアップしてお届けします。そのテーマ、ジャンルについて知っておくべきことが、この記事を読むだけですべて把握できます。さらに、そのテーマに関する記事一覧もご用意しました。ご活用ください。
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- 新国民病の「逆流性食道炎」、気づきにくい「食道がん」
-
「逆流性食道炎」は近年、患者数が急増しており、今や「新国民病」と呼ばれるほど、年齢を問わず多くの人を悩ませている。自覚症状がなく気づきにくい「食道がん」は、進行すると手術の難易度が高くなり、患者への負担も高くなる。今回は身近なようで実は知らない「食道」の病気について解説していく。
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 9
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつある。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていない。一体、どのように摂取するとよいのだろうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていこう。
テーマ別特集「たんぱく質」この記事の主な内容 シニアになると、若いころより筋肉がつきにくい! 60代は若い頃に比べて筋肉が約30%も減る たんぱく質は認知機能や寿命にも影響 筋肉を増やすために必要なたんぱく質の量は? 中高年以降は朝のたんぱく質摂取が大事 昼食はたんぱく質摂取量がばらつきやすい シニアが優先的に選びたい食材は? たくさん食べられない人はプロテインで補完、注意点は 慢性腎臓病の人は、たんぱく質のとり過ぎに注意シニアになると、若いころより筋肉がつきにくい!
いくつになっても十分な筋肉量を保ち続けることができれば、丈夫な足腰を維持し、そして、さまざまな病気を予防することが期待できる。筋肉づくりのためには、筋トレなどの運動をすることはもちろん、食事にも気を使うことが大切だ。筋肉を増やすために重要な栄養素が「たんぱく質」。たんぱく質は筋肉の材料であり、筋合成のスイッチを押す役割もある。
特にたんぱく質をとる上で気を付けたいのがシニア世代だ。この世代で筋肉量やたんぱく質摂取量が少ない人は、より積極的にとっていきたい。というのも、高齢になると若いころより筋肉がつきにくくなるからだ。筋肉がつかないわけではないが、シニアは若い人と同じ量のたんぱく質を摂取しても、同じだけの筋肉を合成することができない。筋肉不足になると、フレイル(虚弱)が進行してしまう。そうした事態はなんとしても避けたい。
60代は若い頃に比べて筋肉が約30%も減る
そもそも、シニアになると若いときと同じようには筋肉がつくれなくなるのはなぜなのか。
ポイントは、必須アミノ酸の一つである「ロイシン」にある。ロイシンは、必須アミノ酸の中でも特に強く筋合成のスイッチを押してくれる。しかし、高齢者はロイシンに対する抵抗性を持っているため、若い人と同じ量のたんぱく質を摂取しても筋合成を高めにくい。立命館大学スポーツ健康科学部教授の藤田聡氏は「高齢者はより多くのたんぱく質を摂取しないと食後の筋合成を最大化できないことになります」と話す。
筋肉量は、年齢を重ねるとともに低下していく。筋肉量は20~30代ごろをピークに、10年ごとに約8~10%ずつ減少し、40代ではピーク時と比べて約10%、50代では約20%、60代では約30%も減ってしまう。
「筋肉量が低下すると、歩行や階段の上り下りといった日常生活の動作に困難をきたしやすくなります。それにより活動範囲が狭くなり、1日の運動量が少なくなる。すると、さらに筋肉量が少なくなる…といった悪循環が生まれます」と藤田氏は話す。
さらに転倒や寝たきりのリスクも出てくる。「歩行速度が遅くなることによって転倒のリスクが高くなります。筋肉はクッション材の役割もしているので、筋肉量が低下すると骨折する可能性も高くなり、骨折すると寝たきりのリスクも高まるのが怖いところです」(藤田氏)
図1 筋肉量低下の悪循環
加齢による筋肉量の減少は避けられないものではあるが、減少の程度はなるべく最小限にとどめたいもの。筋肉量が減少していき、かつ筋肉がつきにくいシニアは、より意識的にたんぱく質摂取や筋トレをしたい。
本記事では、筋肉をつけるためのたんぱく質のとり方のコツを、過去の人気記事を基に紹介しよう。
-
- 新国民病の「逆流性食道炎」、気づきにくい「食道がん」
-
「逆流性食道炎」は近年、患者数が急増しており、今や「新国民病」と呼ばれるほど、年齢を問わず多くの人を悩ませている。自覚症状がなく気づきにくい「食道がん」は、進行すると手術の難易度が高くなり、患者への負担も高くなる。今回は身近なようで実は知らない「食道」の病気について解説していく。
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 10
葉石かおり=エッセイスト・酒ジャーナリスト
アルコールの飲み過ぎによる弊害は多岐にわたる。お酒に依存気味で「減らすべきだ」と分かっているが、自力で減らすことはできないという人もいるだろう。そんな人は減酒に向けた治療を検討したい。実は今年9月、アルコール依存症の患者を対象にした減酒アプリが登場した。このアプリ、医師の診断のもと、保険適用で処方されるもので、その効果も治験で明らかになっている。いったいどんなアプリなのだろうか。精神科医でアプリ開発に携わった宋龍平氏に詳しく話を聞いた。
酒をこよなく愛する者にとって、「断酒」という選択は人生のトロの部分をもぎ取られるようなもの。医師から断酒を言い渡されぬよう、日々酒量をコントロールしている人も多いだろう。筆者もその1人である。
しかし、一口に「酒量をコントロールする」といっても、自分自身でコントロールをするのは非常に難しい。なぜなら、酒好きの多くは何かと理由をこじつけ、飲む機会を自ら作っているからだ。目標を成し遂げればご褒美に酒、さらには忘年会に新年会、そして歓送迎会と、年間を通して飲酒機会を見つけ、せっせと酒を飲んでいる。
なかには、「酒にかなり依存気味で、何とかして酒量を減らしたい。だが、セルフでは難しい」という人もいるかもしれない。アルコール依存症の「治療」は医療機関で行っているが、なかでも「減酒」については医師と一緒に取り組むアプリ治療という方法があるという。
(写真はイメージ:PIXTA)
アルコール依存症の患者を対象にした減酒アプリが、2025年9月に沢井製薬(開発はCureApp)から発売された。その名は「HAUDY(ハウディ)」。依存症対策の1つである「減酒」を支援する。
HAUDYは医師の診断のもと、保険適用で処方される減酒治療補助アプリなのだ。日本初となる減酒治療補助アプリとは、いったいどのようなものなのだろうか? 精神科医で、本アプリ プロジェクトリーダーの宋龍平氏に話を伺った。
もう少し早く治療に来てくれたら…
先生、減酒治療補助アプリを作ろうと思ったのはなぜですか?
「父が神戸でアルコール依存症の専門クリニックを開業しており、私は高校の頃からその建物の中で暮らしていました。なので、アルコール依存症の患者さんは、私にとって特別な存在ではなく、身近な人だったんです。クリニックに来る人は、なんとかしたいという意志を持っているので、良くなっていく人が多い。その様子を見ていたので、“依存症は治らない病気ではない”という感覚を持っていました」(宋氏)
そうした若き頃の経験に加え、精神科医となりアルコール依存症治療の診療現場で働くようになった宋氏は患者の現状を目の当たりにする。
「“もう少し早く来てくれたら”と思う患者さんが多かったんです。お酒をやめても、既に肝臓がんを発症していたり、体がボロボロになっていたりする。そういう人を何人も見てきたこともあり、“もっと早い段階で支援できる仕組みを作りたい”と思うようになりました。それがアプリ開発のきっかけの1つでした」(宋氏)
こうした現場感覚の背景には、日本の現実がある。久里浜医療センターによる2024年の調査によると、国内のアルコール使用障害(Alcohol Use Disorder=AUD)患者は約304万人と推計されている。AUDとは、酒量を自らコントロールすることが難しくなり、心身や社会生活にさまざまな影響を及ぼす疾患を指す。
-
- 新国民病の「逆流性食道炎」、気づきにくい「食道がん」
-
「逆流性食道炎」は近年、患者数が急増しており、今や「新国民病」と呼ばれるほど、年齢を問わず多くの人を悩ませている。自覚症状がなく気づきにくい「食道がん」は、進行すると手術の難易度が高くなり、患者への負担も高くなる。今回は身近なようで実は知らない「食道」の病気について解説していく。
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 11
ラーメン王国・山形で、ラーメンを食べる頻度と死亡リスクを調べる研究が行われた。対象は「山形コホート研究」に参加した40歳以上の6725人。塩分や脂質、糖質が多いラーメンの食べすぎは、健康に悪影響を及ぼすことは分かっているが、死亡リスクとの関係はどうなのか。主任研究者を務めた山形県立米沢栄養大学健康栄養学部講師の鈴木美穂氏に聞いた。
(写真:PIXTA)
世界的に人気だが、ヘルシーな食事とはいえない
総務省が発表した2024年(令和6年)家計調査によると、都道府県庁所在市と政令指定都市の中で、「外食・中華そば(ラーメン)」の支出額が最も多かったのは、山形市の2万2389円。3年連続で1位だ。
ラーメンの支出額は全国で山形市がトップ
2024年における外食・中華そば(ラーメン)の1世帯(2人以上)当たりの支出額(都道府県庁所在市と政令指定都市別)。1位は山形市の2万2389円で3年連続トップ。2位は新潟市(1万6292円)、3位は仙台市(1万5534円)だった。(出所:総務省 2024年家計調査、イラストPIXTA)
そんなラーメン王国・山形で、ユニークな研究が行われた。山形大学および山形県立米沢栄養大学の共同研究チームが、6725人の山形県民を対象に「ラーメンの摂取頻度と死亡リスクの関係」を調べたのだ(*1)。
今やラーメンといえば、寿司や天ぷらと並ぶ人気と知名度を誇る“21世紀を代表する日本食”。実に多彩なバリエーションがあり、世界中の人々に愛されている。ただし、ラーメンを「健康的な食品」と思って食べている人は少ないだろう。糖質や脂質が多い上に、特に気になるのが塩分だ。
「日本人の食事摂取基準(2025年版)」では、1日に摂取する食塩の目標量は男性7.5g未満、女性6.5g未満とされている。ところが一般的なラーメン1杯に含まれる塩分は6~8gだ。それだけで、ほぼ1日分の食塩をとってしまうことになる。ご存じの通り、塩分のとりすぎは血圧を上げて心筋梗塞や脳卒中を引き起こし、胃がんのリスクも高くする。ラーメンは「体に悪いけどおいしい」食品の代表格といってもいいだろう。
主任研究者となった山形県立米沢栄養大学健康栄養学部講師の鈴木美穂氏は、次のように研究のきっかけを話す。
「山形県といえばラーメンですし、私自身も好きで、週1回は食べています。だけど健康面のリスクはどうなのか、スープは全部飲んでも大丈夫なのか、と心配する人も少なくありません。一度きちんと調べて、データを取ったほうが安心して食べられるようになると思いました」
*1 J Nutr Health Aging. 2025 Oct;29(19):100643.
-
- 新国民病の「逆流性食道炎」、気づきにくい「食道がん」
-
「逆流性食道炎」は近年、患者数が急増しており、今や「新国民病」と呼ばれるほど、年齢を問わず多くの人を悩ませている。自覚症状がなく気づきにくい「食道がん」は、進行すると手術の難易度が高くなり、患者への負担も高くなる。今回は身近なようで実は知らない「食道」の病気について解説していく。
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 12
健康・医療に関するホット・トピックスをお伝えします。
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- 新国民病の「逆流性食道炎」、気づきにくい「食道がん」
-
「逆流性食道炎」は近年、患者数が急増しており、今や「新国民病」と呼ばれるほど、年齢を問わず多くの人を悩ませている。自覚症状がなく気づきにくい「食道がん」は、進行すると手術の難易度が高くなり、患者への負担も高くなる。今回は身近なようで実は知らない「食道」の病気について解説していく。
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 13
「人の名前が出てこない」「判断力が鈍った」──年齢を重ねるにつれ、こうした「脳の老化」を感じる人は多いだろう。実は、脳の老化スピードは個人差が大きいとされている。年を重ねてもはつらつと活動的な人もいる。その差を生み出すものは何なのか。本特集では、脳の発達や加齢のメカニズムを研究する東北大学加齢医学研究所教授の瀧靖之氏への取材を基に、脳を若く維持する秘訣を紹介していく。
瀧靖之(たき やすゆき)氏 東北大学加齢医学研究所臨床加齢医学研究分野教授、東北大学スマート・エイジング学際重点研究センター長
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- 新国民病の「逆流性食道炎」、気づきにくい「食道がん」
-
「逆流性食道炎」は近年、患者数が急増しており、今や「新国民病」と呼ばれるほど、年齢を問わず多くの人を悩ませている。自覚症状がなく気づきにくい「食道がん」は、進行すると手術の難易度が高くなり、患者への負担も高くなる。今回は身近なようで実は知らない「食道」の病気について解説していく。
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 14
ひざの痛みを放置すると、悪化していくばかりか、将来的な介護リスクにもつながります。年齢とともにひざへの負担が蓄積され、変形性膝関節症以外のひざの疾患も生じやすくなります。どのようなセルフケア、治療を選ぶのが正解なのか。最新の「変形性膝関節症診療ガイドライン」をもとに、日常生活のコツや気になる最新治療について紹介します。
内尾祐司(うちお ゆうじ)氏 島根大学医学部 整形外科学講座教授
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- 新国民病の「逆流性食道炎」、気づきにくい「食道がん」
-
「逆流性食道炎」は近年、患者数が急増しており、今や「新国民病」と呼ばれるほど、年齢を問わず多くの人を悩ませている。自覚症状がなく気づきにくい「食道がん」は、進行すると手術の難易度が高くなり、患者への負担も高くなる。今回は身近なようで実は知らない「食道」の病気について解説していく。
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 15
「最近、肩が上がりにくい」「腕を上げるとズキッと痛みが走る」──これらの症状を、単なる肩こりや「五十肩」だとあきらめていませんか。肩の痛みの原因はさまざまで、放置すると症状が悪化し、日常生活に支障を来すこともあります。しかし、適切な治療や日々のケア次第で軽減させることは可能です。本特集では、五十肩とよく似た病気の見分け方から、それぞれの治療法、悪化を防ぐセルフケアを紹介します。肩の専門医のアドバイスに沿って、一生モノの肩の守り方を見ていきましょう。
今井晋二(いまい しんじ)氏 滋賀医科大学整形外科学講座 教授
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- 新国民病の「逆流性食道炎」、気づきにくい「食道がん」
-
「逆流性食道炎」は近年、患者数が急増しており、今や「新国民病」と呼ばれるほど、年齢を問わず多くの人を悩ませている。自覚症状がなく気づきにくい「食道がん」は、進行すると手術の難易度が高くなり、患者への負担も高くなる。今回は身近なようで実は知らない「食道」の病気について解説していく。
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 16
順風満帆に過ごしているつもりでも、職場やプライベートの悩みがむくむくと膨らんでくる。強がってみたり、困りごとに向き合わずに放置したりと一瞬悩みから解放されたように振る舞っても、ふと立ち戻ると何も解決していないことに気が付き、一人で考え込んでしまう……そんなあなたは悩みで心がコリ固まっています。
職場での人間関係、恋愛、健康や病気、加齢、キャリア、家庭……人の悩みはさまざまな場面で存在します。でもその多くは、「こうあるべき」という自分の思い込みによるものかもしれません。決めつけや先入観、一つひとつ、はがしていきませんか。
この連載では、「こうあるべき」の思い込みを解いて心のコリを軽くするような言葉を、精神科医のTomy先生が発信していきます。きっとパッと視界が広がるでしょう。
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- 新国民病の「逆流性食道炎」、気づきにくい「食道がん」
-
「逆流性食道炎」は近年、患者数が急増しており、今や「新国民病」と呼ばれるほど、年齢を問わず多くの人を悩ませている。自覚症状がなく気づきにくい「食道がん」は、進行すると手術の難易度が高くなり、患者への負担も高くなる。今回は身近なようで実は知らない「食道」の病気について解説していく。
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 17
食事はカラダを作る源。健康で長生きするには、カラダに必要な栄養成分をきちんと摂取するのが大切です。しかし、どの成分をどれだけとる必要があるのか、どうやってとるべきなのか、不足するとなぜ良くないのかーーそんな基本的なことがわからないという人も多いでしょう。
栄養と健康に関する研究は日々世界中で進められており、情報は常にアップデートされています。数年前には「常識」だったことが否定されることも珍しくありません。この連載では、私たちの体に不可欠な栄養成分の最新知見を専門家に聞き、日々の食生活にどう反映していけばいいかを明らかにしていきます。
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- 新国民病の「逆流性食道炎」、気づきにくい「食道がん」
-
「逆流性食道炎」は近年、患者数が急増しており、今や「新国民病」と呼ばれるほど、年齢を問わず多くの人を悩ませている。自覚症状がなく気づきにくい「食道がん」は、進行すると手術の難易度が高くなり、患者への負担も高くなる。今回は身近なようで実は知らない「食道」の病気について解説していく。
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 18
ビタミンB群の中でも特に妊婦に必要なビタミンとしてよく知られる「葉酸」。でも実は血管や骨の老化が気になる中高年においても葉酸は重要な役割を担っています。ところが、日本人の半数以上は実は葉酸がうまく使えていない可能性があるとのこと。葉酸がどのように老化予防に役立つのか、なぜ葉酸がうまく使えない人がいるのでしょう。栄養の専門家に聞いてみました。
(写真:PIXTA)
中高年の健康維持にも不可欠な葉酸
葉酸は貧血予防因子として1944年に発見されたビタミンB群の一種。ビタミンM、ビタミンB9と呼ばれることもあるが、一般的には葉酸(英語でFolic Acid)と呼ばれることが多い。「葉っぱの酸」と呼ばれる由来は発見時のホウレン草の葉から抽出されたからだ。
長年、葉酸に関する調査研究を行ってきた千葉県立保健医療大学教授の平岡真実氏は、「ビタミンB群とは体の中でエネルギー産生など代謝における補酵素として働くビタミンの中で水溶性のものの総称です。葉酸はその中で9番目に発見されたため、ビタミンB9とも呼ばれます」と説明する。ビタミンMと呼ばれたのは、最初にサル(Monkey)の抗貧血物質として見いだされたことに由来するという。
葉酸は「妊婦に不可欠なビタミン」としてよく知られるが、その理由は胎児の成長に関わるからだ。「葉酸は細胞分裂やDNA合成に不可欠な成分で、主に酵素反応を助ける補酵素として働きます。葉酸が十分にないと細胞増殖がスムーズに行われなくなってしまい、神経管閉鎖障害の発生につながるということが明らかになっています」(平岡氏)
だが、葉酸が重要なのは妊婦だけではない。中高年にとっても葉酸は非常に重要だ。例えば、葉酸は正常な赤血球の生成をサポートし、欠乏するとめまいや立ちくらみ、息切れ、動悸などを伴う巨赤芽球性貧血が起きやすくなるという。「赤血球の寿命は約4カ月で常に新しい赤血球が作られています。赤血球も細胞の一つで、その前駆細胞である正常な赤芽球を作るのに葉酸やビタミンB12が関与しているのですが、葉酸が欠乏すると骨髄内で正常な赤芽球を作ることができず巨大で機能不全な赤芽球が増えてしまいます。この異常な巨大赤芽球の多くは骨髄内で成熟しきる前に破壊されてしまうため、血流内に赤血球が不足する貧血が起きてしまうのです」と平岡氏は説明する。
さらに、中高年が気になる動脈硬化や骨粗しょう症、認知症などの進行にも葉酸不足は深く関連するという。
-
- 新国民病の「逆流性食道炎」、気づきにくい「食道がん」
-
「逆流性食道炎」は近年、患者数が急増しており、今や「新国民病」と呼ばれるほど、年齢を問わず多くの人を悩ませている。自覚症状がなく気づきにくい「食道がん」は、進行すると手術の難易度が高くなり、患者への負担も高くなる。今回は身近なようで実は知らない「食道」の病気について解説していく。
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 19
食事はカラダを作る源。健康で長生きするには、カラダに必要な栄養成分をきちんと摂取するのが大切です。しかし、どの成分をどれだけとる必要があるのか、どうやってとるべきなのか、不足するとなぜ良くないのかーーそんな基本的なことがわからないという人も多いでしょう。
栄養と健康に関する研究は日々世界中で進められており、情報は常にアップデートされています。数年前には「常識」だったことが否定されることも珍しくありません。この連載では、私たちの体に不可欠な栄養成分の最新知見を専門家に聞き、日々の食生活にどう反映していけばいいかを明らかにしていきます。
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- 新国民病の「逆流性食道炎」、気づきにくい「食道がん」
-
「逆流性食道炎」は近年、患者数が急増しており、今や「新国民病」と呼ばれるほど、年齢を問わず多くの人を悩ませている。自覚症状がなく気づきにくい「食道がん」は、進行すると手術の難易度が高くなり、患者への負担も高くなる。今回は身近なようで実は知らない「食道」の病気について解説していく。
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 20
記憶、判断などの脳の機能が低下していく「認知症」。15年後の2040年には認知症とその前段階のMCIを合計すると患者数は1200万人近くになると推計される。実は近年、科学的に正しい認知症予防に関するエビデンスが蓄積され、「認知症リスクは45%減らせる」という時代が到来している。認知症予防学の第一人者である日本認知症予防学会前代表理事で鳥取大学医学部教授の浦上克哉氏に、認知症予防に役立つ、認知症発症リスク因子に関する最新研究について詳しく聞いていく。
浦上克哉(うらかみ かつや)氏 日本認知症予防学会 前代表理事、鳥取大学医学部保健学科認知症予防学講座(寄附講座)教授
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- 新国民病の「逆流性食道炎」、気づきにくい「食道がん」
-
「逆流性食道炎」は近年、患者数が急増しており、今や「新国民病」と呼ばれるほど、年齢を問わず多くの人を悩ませている。自覚症状がなく気づきにくい「食道がん」は、進行すると手術の難易度が高くなり、患者への負担も高くなる。今回は身近なようで実は知らない「食道」の病気について解説していく。
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 21
健康診断や人間ドックは、病気を早期に見つける大切な機会。だが「なんとなく受けているだけ」で、その価値に気づいていない人も多い。加えて、人間ドックではどのオプション検査を受けたらいいか分からないという人もいる。本特集では、健診や人間ドックをより賢く活用するためのポイントを解説していく。
安田聖栄 (やすだ せいえい)氏 医療法人社団あんしん会 四谷メディカルキューブ 理事長、東海大学医学部 客員教授、医学博士
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- 新国民病の「逆流性食道炎」、気づきにくい「食道がん」
-
「逆流性食道炎」は近年、患者数が急増しており、今や「新国民病」と呼ばれるほど、年齢を問わず多くの人を悩ませている。自覚症状がなく気づきにくい「食道がん」は、進行すると手術の難易度が高くなり、患者への負担も高くなる。今回は身近なようで実は知らない「食道」の病気について解説していく。
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 22
健診や人間ドックは、病気を早期に見つける大切な機会。だが「なんとなく受けているだけ」で、その価値に気づいていない人も多い。人間ドックでは、検査項目を「選ぶ力」が健康寿命を延ばすことにつながる。そこで特集の2回目は、人間ドックの賢い利用法を見ていく。
(写真:PIXTA)
「人間ドック」という言葉は日本特有のものだ。船が定期的にドックに入り、時間をかけて綿密に修理や点検を行うことに例えている。第1回で紹介した一般的な健診(職場健診、住民健診、医療保険組合の健診)が、“病気の義務教育”だとすると、人間ドックは“高等教育”と呼べるだろう。人間ドックは基本の検査項目が健診より多く、さらに任意に選択できるオプション検査では、より多様で詳細な検査が可能になっている。
健診は生活習慣病の早期リスクを見つけるために大切だ。対策型がん検診(対象は大腸がん、肺がん、胃がん、乳がん、子宮頸がん)のように、各市区町村で対象として特定された年齢の住民が、無料か少額の自己負担で受けられる検診もある(がん検診については第3回で詳しく紹介する)。
健診や対策型がん検診は手軽に受けられる利点がある一方、自分が不安視する病気のリスクを、自分の意思とタイミングで受けられない欠点もある。その点、人間ドックは、自分が必要だと思った検査を、自分のタイミングで好きに選んで受けることができる。
健診では見つからなかった、がんなどの重篤な病気を早期発見できることもメリットとしては大きい。例えば肺がんの場合、健診で行う胸部X線検査では、小さな腫瘍や異常を見落とすことがある。だが肺CT検査を受ければ、そうした見落としのリスクを避けられる。
- 健診(健康診断) 全般的な健康状態を調べるもの。英語では「ヘルスチェックアップ」
- 検診 がん検診や糖尿病検診など、特定の疾患を調べるもの。英語では「スクリーニング」
- 人間ドック 日本独自の用語。入院して詳しく調べる検査を、船が「ドック入り」して点検することに例えて呼ばれたが、日帰りもある。
(※四谷メディカルキューブの理事長・安田聖栄氏による分類解説を編集部で編集)
悩ましいのは、数ある検査内容の理解と選択
人間ドックは、病気を予防するために任意で2日ないし1日で受けることが多い。検査項目は、「基本コース」や「スタンダードコース」などと呼ばれる「基本検査」に、必要に応じて選べる「オプション検査」がある。基本検査やオプション検査のメニューは、医療施設によってさまざま。多くの施設がオプション検査として扱う検査を、基本検査に加えているところもあるため、選ぶコースや選ぶオプション検査により、総費用も数万円から数十万円と異なる。このため、費用については、検査する医療施設のホームページで確認してほしい。
人間ドックは、公的医療保険(健康保険)の適用対象外となり、基本的に費用は全額自己負担だが、会社が福利厚生の1つとして費用補助をしているケースもある。そういった費用補助があるなら、ぜひ活用したいところだ。
そんな人間ドックだが、悩ましいのが数ある検査内容の理解と選択だ。「この検査は自分に必要か。いや、念のため、調べておいたほうがいいかもしれない。でも、気になる検査を加えて行ったらどんどん料金が高くなる…」――。このように複雑に感じる人も少なくない。だからこそ、人間ドックは賢い選択を踏まえた利用が必要になる。
人間ドックの施設として、医師も数多く受診する四谷メディカルキューブの理事長、安田聖栄氏は、「人間ドックで重要なのは基本検査の内容をよく理解すること。どんなオプション検査を受けるかもしっかり検討しましょう」と話す。そこで本特集の第2回は、人間ドックの検査内容や受診する際の押さえておきたいポイントを解説していく。
-
- 新国民病の「逆流性食道炎」、気づきにくい「食道がん」
-
「逆流性食道炎」は近年、患者数が急増しており、今や「新国民病」と呼ばれるほど、年齢を問わず多くの人を悩ませている。自覚症状がなく気づきにくい「食道がん」は、進行すると手術の難易度が高くなり、患者への負担も高くなる。今回は身近なようで実は知らない「食道」の病気について解説していく。
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 23
健康診断や人間ドックは、病気を早期に見つける大切な機会。だが「なんとなく受けているだけ」で、その価値に気づいていない人も多い。加えて、人間ドックではどのオプション検査を受けたらいいか分からないという人もいる。本特集では、健診や人間ドックをより賢く活用するためのポイントを解説していく。
安田聖栄 (やすだ せいえい)氏 医療法人社団あんしん会 四谷メディカルキューブ 理事長、東海大学医学部 客員教授、医学博士
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- 新国民病の「逆流性食道炎」、気づきにくい「食道がん」
-
「逆流性食道炎」は近年、患者数が急増しており、今や「新国民病」と呼ばれるほど、年齢を問わず多くの人を悩ませている。自覚症状がなく気づきにくい「食道がん」は、進行すると手術の難易度が高くなり、患者への負担も高くなる。今回は身近なようで実は知らない「食道」の病気について解説していく。
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 24
日本人が一生のうちに「がん」と診断される確率は、男女ともに2人の1人の割合に達する。がんは何より早期発見、早期治療が重要だ。そして、そのために必要になってくるのは、「がんの疑いがあるかどうか」を調べるがん検診である。そこで本特集の3回目はがん検診について詳しく見ていく。
(写真:PIXTA)
かつては不治の病と恐れられた、がん。今では、医療技術の目覚ましい進歩によって完治・寛解の可能性が高まり、がんサバイバーとして社会復帰する人も増えてきた。そこで大切なのは早期発見である。検診によって早期の状態でがんが発見できれば、それだけ体に負担のない治療が可能になる。
自治体から、「がん検診のお知らせ」という郵送物を受け取ることがあるだろう。きちんと中身を見ているだろうか。国の指針のもと、胃がん、肺がん、大腸がん、女性には子宮頸(けい)がんと乳がんの検診も、年齢に応じて届くようになっている。
しかし、今でも、がん検診を避けたがる人は少なくない。「忙しくて時間がない」「面倒だ」「がんと診断されるのが怖い」などが主な理由だ。
果たして、がん検診はどこまで有効なのか。受診すべきなのか。
人間ドックの施設として、医師も数多く受診する四谷メディカルキューブ理事長の安田聖栄氏は、がん検診を受けるべき理由として以下の3つを挙げる。
- 日本人が一生のうちでがんと診断される確率は、男女とも2人に1人の割合に達する(*1)
- がんは死因の第1位となっており、男性は4人に1人、女性は6人に1人ががんで死亡する(*2)
- 治療の技術も日進月歩で、がんはもはや不治の病ではなくなった
①と②は、がんは多くの人にとって「ひとごとではない」ということだ。その上で、③について、安田氏は次のように説明する。
「現在は治療技術が進み、がん検診の重要性が高くなっています。もし治療が困難ならば、いくら検査をしても意味がありません。しかし、今は内視鏡治療の進化に加え、ロボット手術の導入、がん治療の新薬の登場などで、より体に負担が少なく、効果的な治療法が開発されています。その恩恵を十分得られるのも、早期に発見できればこそ、です」
これは逆に言えば、いくら治療技術が進歩しても発見が遅れれば、肉体的にも経済的にも負担のかかる治療が必要になってくるということ。早期発見によって負担の少ない治療で済めば、その後の人生も元気に生きられる可能性が高まる。
*1 国立がん研究センターがん情報サービス 最新がん統計より(2021年のデータ) *2 厚生労働省「令和5年(2023年)人口動態統計」より
ひと口にがん検診といっても、さまざまな種類がある。どのような検診を受ければよいのだろうか。
「年齢や生活習慣、家族歴などを考慮に入れて、検診効果の高い検査を、適切な頻度で受けることが大切です。国が推奨しているがん検診は、大腸、肺、胃、乳、子宮頸(けい)がんの5つ。少なくともこの5つには検査の有効性に科学的根拠があり、早期発見の効果が証明されています」と安田氏は語る。
「検査の有効性」というのは、検査することによって命が助かる可能性が高まるかどうかを指している。
「科学的に有効であると示されたがん検診ですが、残念ながら日本の受診率は依然として低い水準にあります。大腸がん、乳がん、子宮頸がんに限ってみても、欧米では6〜7割の人が受診しているのですが、日本では4割程度にとどまっています」と安田氏は話す。
-
- 新国民病の「逆流性食道炎」、気づきにくい「食道がん」
-
「逆流性食道炎」は近年、患者数が急増しており、今や「新国民病」と呼ばれるほど、年齢を問わず多くの人を悩ませている。自覚症状がなく気づきにくい「食道がん」は、進行すると手術の難易度が高くなり、患者への負担も高くなる。今回は身近なようで実は知らない「食道」の病気について解説していく。
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 25
「認知症を予防したい」「認知機能が落ちてきたように思うので何とか改善したい」――。そんなとき何をすればいいのだろうか。今回紹介するのが「とっとり方式認知症予防プログラム」。日本認知症予防学会の初代理事長で、鳥取大学医学部教授の浦上克哉氏が開発したプログラムで、軽度認知障害(MCI)の人たちを対象に実施して、認知機能と身体機能が高まることを実証している。もちろんMCIになっていない人も、認知症予防としてぜひ実践してほしい。「認知症予防対策に手をつけるのは、早ければ早いほどいい」と話す浦上氏に、“脳のお掃除力”を高める具体的なプログラム内容を聞く。
人は突然認知症にはならない、MCIの段階の発見が大事
認知症は誰もがかかる可能性のある病気で、年を重ねるほどリスクが増えていく。しかし、「年を重ねると認知症になることは避けられないのか」と悲観する必要はない。第1回では、認知症予防の研究が世界で進行していて、現在では「認知症の45%は予防可能である」という最新知見を紹介した。
認知症に至る脳の変化は、発症の20~30年ほど前、つまり中年期から徐々に始まっている。この中年期から対策に着手することが認知症予防の第一歩となる。認知症予防の第一人者で鳥取大学医学部教授の浦上克哉氏は、「健康な中年期からしっかりと予防対策を継続することが重要です」と強調する。
浦上氏が監修した『1日10分から始めよう! 認知症予防学の第一人者が教える 脳のおそうじ体操』(中央公論新社)
高齢になるにつれ、認知症のリスクは高まっていくが、認知症になる段階について理解しておきたいポイントが2つある。1つは「健常な人が突然、認知症になってしまうわけではない」ということ。認知症と診断される前段階として、軽度の認知障害が認められる「MCI(軽度認知障害)」と呼ばれるフェーズがあり、その後、症状が悪化し、認知症へと進行していく。浦上氏は、認知症の1歩手前のMCIの状態で早期発見し、いち早く対策を行うことが極めて重要だと指摘する。なお、最新の調査では、2025年段階で高齢者の15.4%がMCIと推定されている(*1)。
もう1つのポイントは、「MCIの人が必ず認知症になるわけではない」ということだ。MCIとは、認知症でもなく、健常な状態でもない、ちょうど間にある、脳に何らかの病的な変化が生じている状態のことを言う(図1)。「医療機関でMCIと診断された人が認知症に移行するのは1年でおよそ5~15%です。その他の人は、MCIのレベルにとどまる人、そして正常レベルに回復する人もおよそ16~41%いることが分かっています。このため、MCIは認知症の“最終防衛ライン”といえます」(浦上氏)
図1 MCIでの早めの対策が認知症予防のカギを握る
MCIでの認知症予防が重要(国立研究開発法人国立長寿医療研究センター「あたまとからだを元気にするMCIハンドブック」より)
図2 軽度認知障害(MCI)なら元の状態に戻れる可能性がある
浦上氏が作成した図を基に作成。図中のデータは日本神経学会監修『認知症疾患診療ガイドライン2017』 CQ4B-2より
*1 「認知症及び軽度認知障害の有病率調査並びに将来推計に関する研究」(令和5年度老人保健事業推進費等補助金、厚生労働省より) PDFを開く
-
- 新国民病の「逆流性食道炎」、気づきにくい「食道がん」
-
「逆流性食道炎」は近年、患者数が急増しており、今や「新国民病」と呼ばれるほど、年齢を問わず多くの人を悩ませている。自覚症状がなく気づきにくい「食道がん」は、進行すると手術の難易度が高くなり、患者への負担も高くなる。今回は身近なようで実は知らない「食道」の病気について解説していく。
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 26
記憶、判断などの脳の機能が低下していく「認知症」。15年後の2040年には認知症とその前段階のMCIを合計すると患者数は1200万人近くになると推計される。実は近年、科学的に正しい認知症予防に関するエビデンスが蓄積され、「認知症リスクは45%減らせる」という時代が到来している。認知症予防学の第一人者である日本認知症予防学会前代表理事で鳥取大学医学部教授の浦上克哉氏に、認知症予防に役立つ、認知症発症リスク因子に関する最新研究について詳しく聞いていく。
浦上克哉(うらかみ かつや)氏 日本認知症予防学会 前代表理事、鳥取大学医学部保健学科認知症予防学講座(寄附講座)教授
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- 新国民病の「逆流性食道炎」、気づきにくい「食道がん」
-
「逆流性食道炎」は近年、患者数が急増しており、今や「新国民病」と呼ばれるほど、年齢を問わず多くの人を悩ませている。自覚症状がなく気づきにくい「食道がん」は、進行すると手術の難易度が高くなり、患者への負担も高くなる。今回は身近なようで実は知らない「食道」の病気について解説していく。
-
- シニアこそ「たんぱく質」で筋肉づくり 健康長寿をかなえる摂取術
-
シニア世代が特に意識したい栄養素が「たんぱく質」。近年、健康的に長生きするにはたんぱく質が重要だという認識が広がりつつあります。しかし、実際に何を、どのくらいとればいいのかについては、まだ十分に知られていません。一体、どのように摂取するとよいのでしょうか。過去の人気記事を基に、たんぱく質のとり方を見ていきましょう。
-
- 体のサビ防ぎ、老化を遠ざける! 「抗酸化生活」の極意
-
老化を進めるさまざまな要因が明らかになっている中で、大きく注目されているのが「酸化」だ。酸化によって細胞が傷つき、細胞や組織の機能を低下させ、老化を進行させてしまう。できるだけ老化を遅らせ、健康に過ごすためには、活性酸素を除去する力「抗酸化能」を高めることが肝要だ。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定