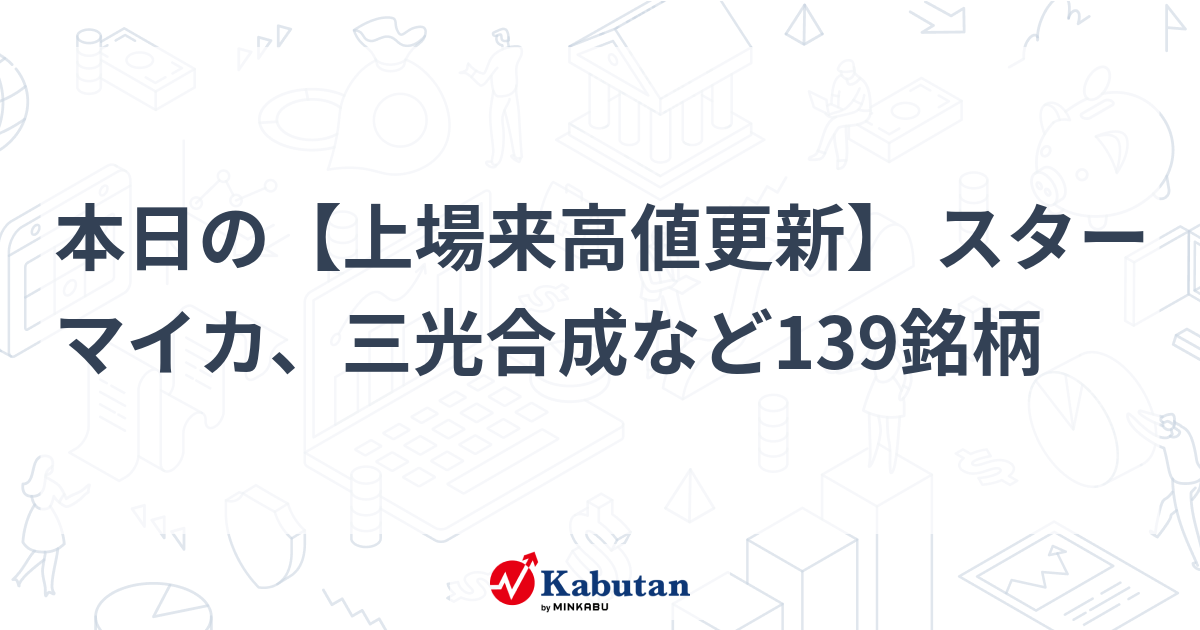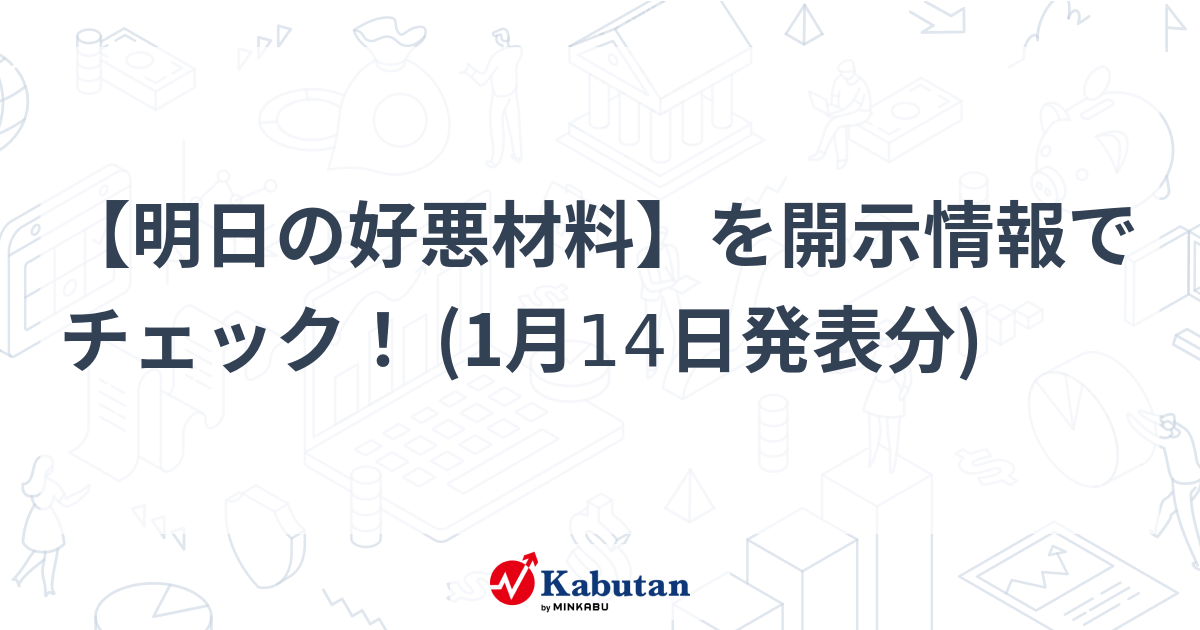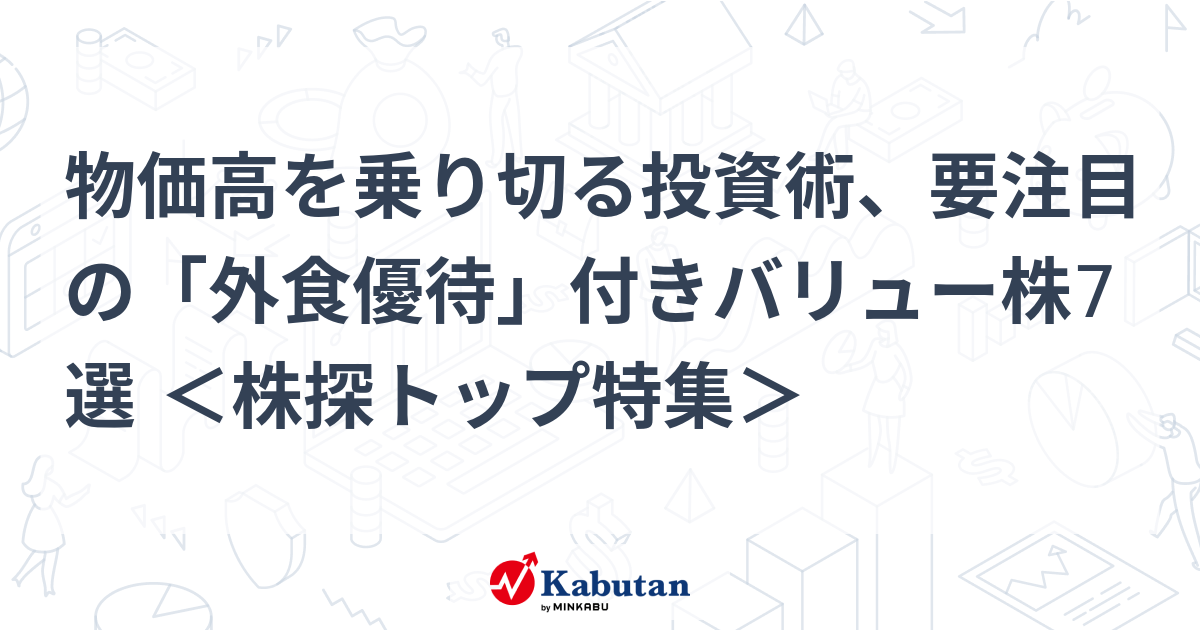小泉農水相に読んでほしい「コメ高騰の真犯人」 農家・政府と消費者感覚のずれ 花田紀凱 花田紀凱の週刊誌ウォッチング(1032)

コメコメコメコメうるさい。
日頃、コメなんかとんと関心もないくせに、新聞、テレビ、週刊誌、連日、コメコメコメコメ…。
小泉大臣がどうした、JAがどうした、中間業者がどうした…。が、本質的なところがわからない。
そう思っていたところに『ニューズウィーク日本版』(6・24)が10ページの大特集で「コメ高騰の真犯人」。
なかでも、加谷珪一氏(経済評論家)の「日本を揺るがす『コメ高騰』を構造分析する」は<金融システムとしてコメ本位性が採用されていたと見なすことも可能>という江戸時代の石高制から始まって、なぜ、今、コメの価格が上がったのか、どうすればいいかを、丁寧かつ、実にわかりやすく分析。
今週の週刊誌、この加谷氏のリポートを読めば十分だ。
<日本国内のコメ消費量は昭和の時代と比較すると約半分>
<市場が縮小した最大の原因は、私たち日本人がコメを食べなくなったからにほかならない。この根本原因から目をそらしてコメの問題を議論することはナンセンス>
<随意契約による放出を実施するまで、政府は価格引き下げに消極的だったが、最大の理由は、従来価格ですらコメ農家の存続が難しいからである>
<インフレであらゆるコストが上がるなか、コメの店頭価格が2000円レベルでは農家が事業を継続することは不可能である。ちなみに勤労世帯に換算した農家の平均年収は100万円を切っている。従事者の多くが高齢者で年金を受給しており、これで何とか生計を保っているのが現実だ>
だから、<農家や政府はコメの価格は下げたくないと考えており、これが一般的な消費者との感覚の乖離(かいり)を招いている。コメに対するこの認識の乖離こそが、一連の問題の本質>。
もう一本の山下一仁氏(キヤノングローバル戦略研究所研究主幹)の「コメ輸出にこそ活路あり」に同感。
この特集、小泉進次郎農林水産相にもぜひ読んでほしい。
『週刊ポスト』(6・27/7・4)のトップは「衝撃予測 まさかまさか! 党内調査で空気が一変-『小泉農政解散』で衆参W自民劇勝!」
じゃあ、石破続投? うんざり。
(月刊『Hanada』編集長)