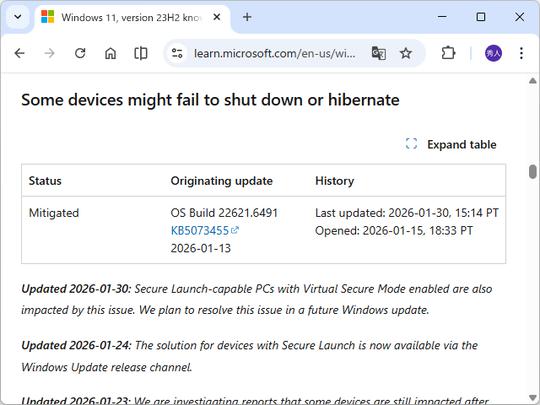【万博】「空飛ぶクルマ」機内に入ってわかったこと──JALが明かす“次の計画”(ビジネス+IT)

空飛ぶクルマ関連の施設は、万博会場内に2カ所設けられている。1つは会場北西端、夢洲西方に位置する専用離着陸場「EXPOバーティポート」と、もう1つは大屋根リング内に設置されたパビリオン「空飛ぶクルマ ステーション」だ。 次世代のモビリティとして期待される空飛ぶクルマには、安全性と効率性を確保するための運用インフラが不可欠である。その一環として整備されたのが「EXPOバーティポート」だ。そしてもう1つの関連施設「空飛ぶクルマ ステーション」では、このEXPOバーティポートの構造や今後の活用可能性について紹介する映像が上映されており、インフラ整備の重要性がわかりやすく解説されている。 このEXPOバーティポートを活用し、未来社会ショーケース事業「スマートモビリティ万博 空飛ぶクルマ」のお披露目イベントが開かれた。 登壇したのは、主催代表として2025年日本国際博覧会協会企画局長の河本健一氏、EXPOバーティポート運営協賛者のオリックス執行役員 グループ関西副代表の馬殿太郎氏のほか、運航協賛企業の代表としてスカイドライブ代表取締役CEOの福澤知浩氏、丸紅常務執行役員CSOの水野博通氏、リフトエアクラフト(以下リフト)CEOのマット・チェイスン氏がそろった。 次のページでは、待ちに待った空飛ぶクルマのお披露目と、筆者が実際に機内に入って感じたことを写真とともにお伝えする。
このEXPOバーティポートの協賛企業であるオリックスの馬殿氏は「本バーティポートは日本初の複数機種、複数機運航に対応可能な施設です」とその先進性を強調。 スカイドライブの福澤氏は、「民間航空機は日本製がほぼない中、電動化および高度な制御技術の開発を進めてきました。10人から始まったチームは今や400人に拡大し、“空飛ぶ絵”が着実に実現に向かっています」と話した。 続いて丸紅の水野氏は、「2021年からバーティカル・エアロスペースと提携を開始し、その後、今回機体を持ち込んでくれたリフトとも協業しています。『ヘクサ機』はすでに2023年に大阪城でデモフライトを実施済みで、当社のスローガンである『できないことをみんなでやろう』を体現する取り組みです」と紹介。 リフトのマット・チェイスン氏は、「当社の機体は2023年から米国で商用飛行を始めており、すでに数百人が搭乗を体験しています。本日午後にはデモフライトを予定しているので、ご期待いただきたい」と述べた。 その後、格納庫の扉が開き、スカイドライブ2機、ヘクサ2機の計4機を披露。うちヘクサの1機は万博仕様に赤と青で塗装され、庫内の雰囲気を明るくしていた。 機体内部も公開され、実際にコックピットや乗客用シートに座ることもできた。リフトのヘクサ機は1人乗り仕様で開放感があり、風を感じながら飛行するシーンを想像させる構造が印象的である。 一方、スカイドライブ機は、大型の液晶ディスプレイがコックピットに搭載されており、夢洲周辺の地図と予定航路が表示されていた。無人操縦の場合にも、航路の可視化が行われる設計とみられる。座席は機体上部の高い位置に配置されており、快適な座り心地とともに、視界の広さも特長の1つとなっている。
Page 2
冒頭でも少し紹介した、大屋根リング内のパビリオン「空飛ぶクルマ ステーション」は、空飛ぶクルマが社会に浸透した未来の姿を体感できる施設である。その中でも、JALが提供するイマーシブシアター「そらクルーズ」が注目を集めている。 本シアターでは、専用ゴーグルを必要とせず、リアルな映像や立体音響、振動によって、まるで空飛ぶクルマに搭乗し大阪上空を巡るかのような没入体験が可能となっている。 実際に会場に入ると、空飛ぶクルマの「デジタルお絵描き体験」も提供されており、子どもから大人まで楽しめる工夫が施されている。また、JALの職員が案内役としてデザインのやり方も教えてくれるという。デジタルお絵描きを完成させると、次のシアターでのクルーズ開始前に、自身のデザイン機が飛んでいく姿をディスプレイで見ることができる。 シアターでのクルーズは、55年前の大阪万博会場である千里丘陵を飛び立ち、大阪市内を通り関西空港へ向かう。また、紀伊半島へ飛行するルートも体験することができた。床の振動を感じると実際に飛行している気分になれるのが良い。 万博開幕日はJALのこのシアターのみであったが、会期中にはスカイドライブ、丸紅、ANAも各種イベントを予定しているそうだ。 空飛ぶクルマの社会実装には、機体の開発のみならず、バーティポートや航路の整備、運航管理といった関連インフラの構築が不可欠である。大阪・関西万博の開幕初日に取材した「空飛ぶクルマ ステーション」およびEXPOバーティポートでのデモフライトは、近未来のモビリティ社会の実現が目前に迫っていることを強く印象づけるものであった。今後、技術開発やインフラ整備、法規制の整備が進むことで、空飛ぶクルマが実用化される日もそう遠くはないであろう。 大阪・関西万博は、空飛ぶクルマの開発の通過点でしかない。この先は公共交通機関として社会実装が進むことを楽しみにしたい。
執筆:航空ジャーナリスト 北島 幸司