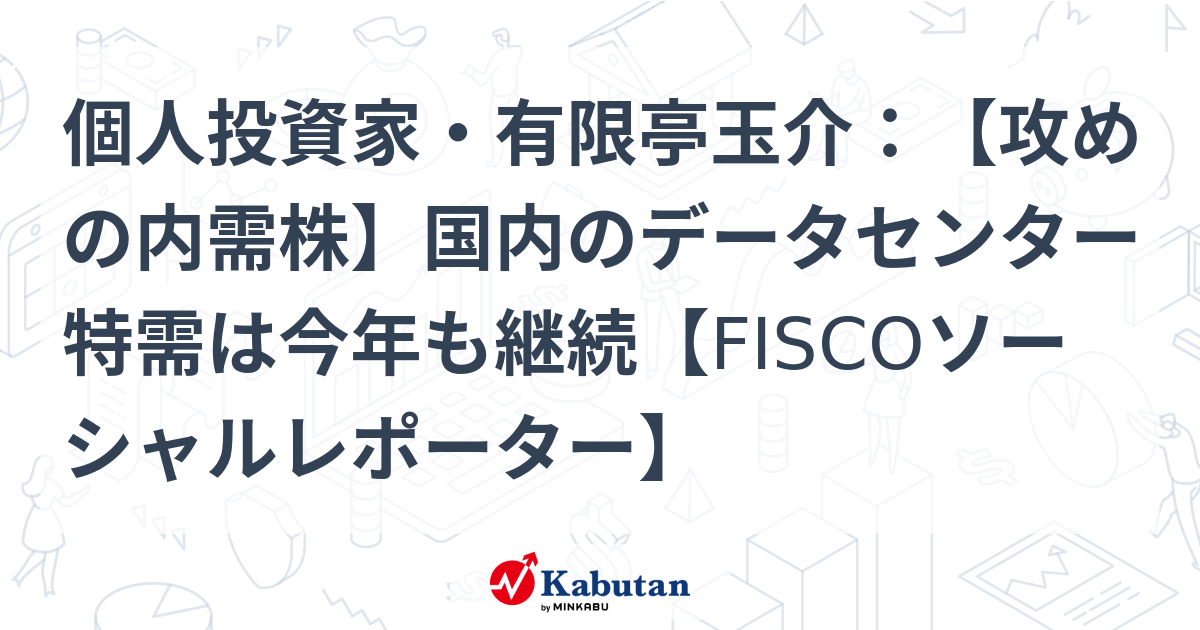日本からGAFAが生まれなかったのは教育のせい? AIを活用して成果を出す子どもの育て方、“データサイエンス力”の磨き方【大学教授・渡辺美智子先生が提言】

立正大学データサイエンス学部教授で、『こどもデータサイエンス なぜデータサイエンスが必要なのかがわかる本』を監修した渡辺美智子先生に、親が知っておくべきことや家庭でできることを聞きました。 『こどもデータサイエンス なぜデータサイエンスが必要なのかがわかる本』から一部抜粋 なんとなく不安の多いAI時代。でも渡辺先生は、「今の子どもたちは、チャンスの時代に生きているんですよ」と話します。 「今は第4次産業革命といわれ、生活や社会のあり方、働き方が一気に変わっていく時代です。こういう時代は、ローハンギングフルーツ(low-hanging fruit)といって、木の低い位置にたくさんおいしい実がなっている状態。誰でも手を伸ばせば、新しい技術の恩恵を受けられます。でも気付いた人と気付かない人で大きな差がつく。どこに目を向けるかで将来が変わってきます。 昔、馬車が自動車に変わったときも、最初は気付かない人がたくさんいました。でも気付いた人から先に、新しい世界で活躍できた。今も同じことが起きているんです」 すでに始まっている変化に意識を向け、どこに学びの軸を置くか。それが子どもたちの将来を左右するといいます。 ■子どもたちはAIネイティブ これからの子どもたちは単純なデジタルネイティブではなく、生まれたときからAIがある世界で育つAIネイティブ。これは強みになります。 「通販サイトでおすすめ商品が表示されたり、タブレット学習で一人ひとり違う問題が出たりするのが当たり前になりました。『なぜおすすめが当たるの?』『どうして隣の子と問題が違うの?』など、疑問を自然に持ちやすい環境。なぜ? という疑問から仕組みを考えたり確かめたりすることが、AIの基盤技術であるデータサイエンスを学ぶきっかけになります」(渡辺先生) 日本のデータサイエンス教育は海外に比べると長らく後れをとっていましたが、2024年12月には文部科学省が「初等中等教育段階における 生成AIの利活用に関するガイドライン」を改定。小学校でも生成AIを現場の判断で活用していく方向になるなど、ようやく変わり始めています。