PC 4億台超がゴミに…Windows 10サポート終了の裏にある、マイクロソフト「真の狙い」
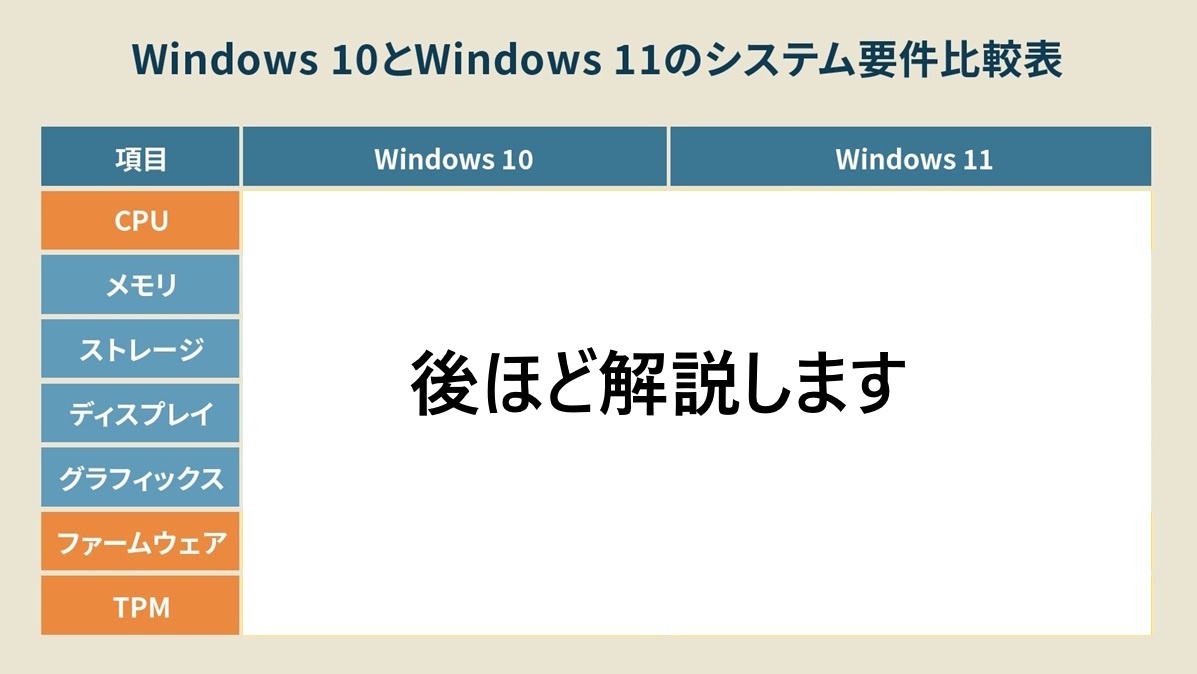
Windows 11は、基本的にWindows 10と同じカーネルを基盤に構築されており、カーネル部分はほとんど変更されていない。このため、ユーザーインターフェース(UI)が大きく変わったにもかかわらず、Windows 10で動作していた多くのアプリケーションやハードウェアはWindows 11でもそのまま動作し、高い互換性が維持されている。 UIを除く大きな変更点としては、メモリやストレージ、グラフィックスカードなどのシステム要件がいくぶん厳格化されている。とはいえWindows 10のPCにおいてアップグレードを考えるユーザーの多くは、メモリやストレージ、グラフィックスカードやディスプレイだけを見るならば、Windows 11への移行はほぼ問題ないはずだ。 しかし実際には、多数のユーザーが要件面で重大な壁を越えることができない。 最大の理由は、Windows 11においてデバイスの暗号化の回復キーを管理するなど、認証セキュリティ関連の機能を提供するマイクロチップのTPM 2.0が、マザーボードに搭載されている必要があるからだ。 インテルのCPUを例に挙げるならば、最低でも2017年製造の第8世代が搭載されている必要がある。しかも、第8世代でさえ要件を満たさない製品があり、すべてのCPUが完全にWindows 11にアップグレードできるのは、2021年製造の第11世代からとなる。 この敷居の高さから、一説によれば4億台以上のWindows 10のPCがセキュリティアップデートを受けられない、リスクの高い状態に置かれることになる。 そもそもTPM 2.0は、顔や指紋によるユーザー認証のWindows Helloを機能させ、ディスク暗号化のBitLockerの回復キーを収納するなど、デバイスのセキュリティを高めるために導入されたものだ。しかし、それを欠くために4億台以上のWindows 10のPCがWindows 11に移行できず、セキュリティ上のリスクにさらされるのは、一見矛盾している。 なぜマイクロソフトは、4億台以上のWindows 10のPCをサポートが受けられない状態に放置してまで、Windows 11のシステム要件を高める必要があったのだろうか。



