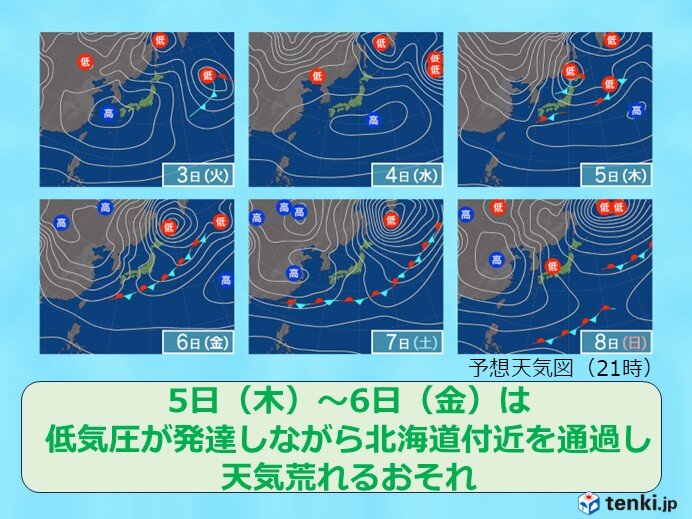南海トラフの確率併記に現れた地震学の限界 なぜややこしい発表に?

南海トラフ地震の新たな発生確率を政府の地震調査委員会が発表した。
30年以内に起こる確率は「60~90%程度以上」と「20~50%」の2通り。数字だけみれば高いとも低いとも受け取れるが、どちらも「最も高いランク」というのが、地震調査委の見解だ。
改定前は「80%程度」だった。
なぜこんなにややこしく、わかりにくい発表になったのか。
一言でいえば、地震学の限界だ。さらに言えば、学問の実力以上に「背伸び」をし、数字で情報を出そうとした結果といえる。
まず大前提として強調しておきたいのが、今回の確率改定は、計算方法を変えただけに過ぎないことだ。
あくまで見かけ上の数字をいじっただけで、実際の地震が近づいたわけでも、遠ざかったわけでもない。90%程度以上という高い数字だけをとらえて過度におびえても、20%だからといって安心してもいけない。
そして、南海トラフ地震はいつか必ず起きる。わかっている最短の間隔は90年。前回からすでに80年が過ぎようとしている。
地震調査委も、確率以前に「いつ起きても不思議はない」と強調している。
静岡県から宮崎県の沖合にかけて広がる南海トラフは、東日本大震災の巨大地震が起きた日本海溝と同じく、プレートが沈み込む場所だ。もし巨大地震が起これば、西日本を中心に広範囲が被災し、影響は全国に及ぶ。だからこそ、国を挙げた対策が求められてきた。
そもそも日本はどこでも地震のリスクがある。予知もできない。確率に振り回されることなく、着実に備えていくほかない。
では、なぜこんなに幅が生じたのか。
南海トラフ地震の発生確率の見直しをめぐる地震調査委員会の記者会見=東京・霞が関「今持っている知識を全部使って、科学としては最善の方法で示した」
「不確実であることをきちんと示すことが、この情報が確実であることにつながる」
「30年経っても起きないか…
この記事を書いた人
- 佐々木英輔
- 編集委員
- 専門・関心分野
- 災害、環境、リスク、自然と社会
南海トラフ地震の想定震源域は東海から九州の太平洋沖とされ、100年から200年ほどの間隔で、繰り返し巨大地震が起きてきました。もし起きれば被害は広い範囲に及び、いつ発生してもおかしくないと切迫性が指摘されています。最新のニュースや解説をお届けします。[もっと見る]