長引くせき、だるさ、体重減など中高年女性は気をつけて 「肺NTM症」結核上回る死者数 沖縄は重症化菌が他県の10倍
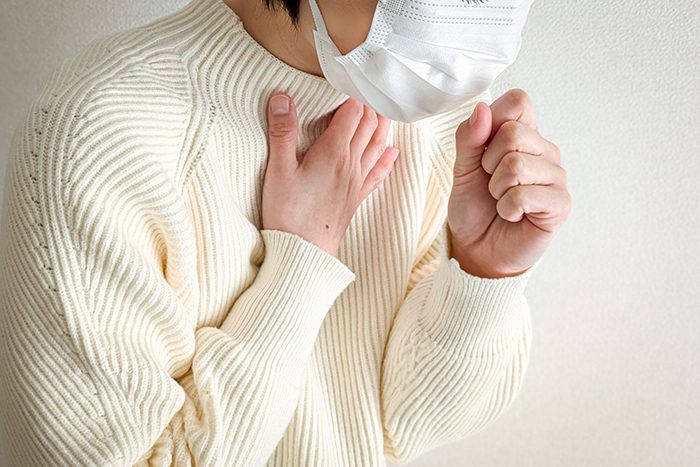
肺非結核性抗酸菌症(肺NTM症)という呼吸器疾患が近年、中高年の女性を中心に増えている。「せきが長引く」「だるくて体重が減った」―。そんな症状のときに感染が疑われ、死亡者数は結核を上回るようになった。沖縄は重症化しやすいアブセッサス菌が原因となる率が他県に比べて極端に高く、いっそうの注意が必要という。
非結核性抗酸菌(NTM)は結核菌と同じ抗酸菌の一種。土や水回りに潜み、日常的に吸い込んでいるが、多くの人は発病しない。免疫を抑える薬の服用者や免疫が低下する病気の人がかかりやすいという。
原因ははっきりしないが、男性より女性が発病し、40歳以降に急増する。人から人へは感染しないのも特徴だ。土いじりをするときにマスクをするなどが予防法だが、完全に防ぐのは難しい。
症状は、長引くせき、血が混じったたん、体のだるさ、体重減少など。症状がなく、健康診断の胸部エックス線検査で見つかることもある。
製薬会社インスメッド合同会社が約千人に実施した2023年の調査で「肺NTM症を知っている」との回答は9・3%だった。知名度の低さから、これまで専門の医療機関につながりにくかった面もあるとみられる。
患者数は増えており、肺NTM症の2017年の全国の罹患(りかん)率は10万人当たり19・2人。10年前の約3・4倍だ。死者数も20年からは肺結核を上回った。23年は2298人で、3年ぶりに減ったものの増加傾向にある。
山本和子 琉球大教授結核は薬により約半年で治ることが多いが、肺NTM症は薬が効きにくいという。呼吸器感染症が専門の山本和子・琉球大学教授は「平均2年の治療でやっと菌を抑えられる。点滴だけでなく吸入薬もできて自宅で治療する選択肢が増えたが、長期間の継続が必要になる」と説明する。
原因となるNTM菌にはたくさんの種類があるが、国内ではMAC菌が大半を占める。ところが沖縄では、治療が難しいアブセッサス菌の割合が非常に高い。17年の琉大と県立中部病院の共同研究では、アブセッサス菌が原因の肺NTM症は沖縄以外の国内では3・0%なのに、沖縄では30・5%を占めたという。
山本教授は「アブセッサス菌は薬が効きにくいし、悪化しやすい」と指摘。早期発見の重要性を強調し、「症状がある人の受診はもちろん、定期検診をきちんと受け、異常を指摘された場合の2次検診にも必ず行ってほしい」とアドバイスする。
(宮沢之祐)



