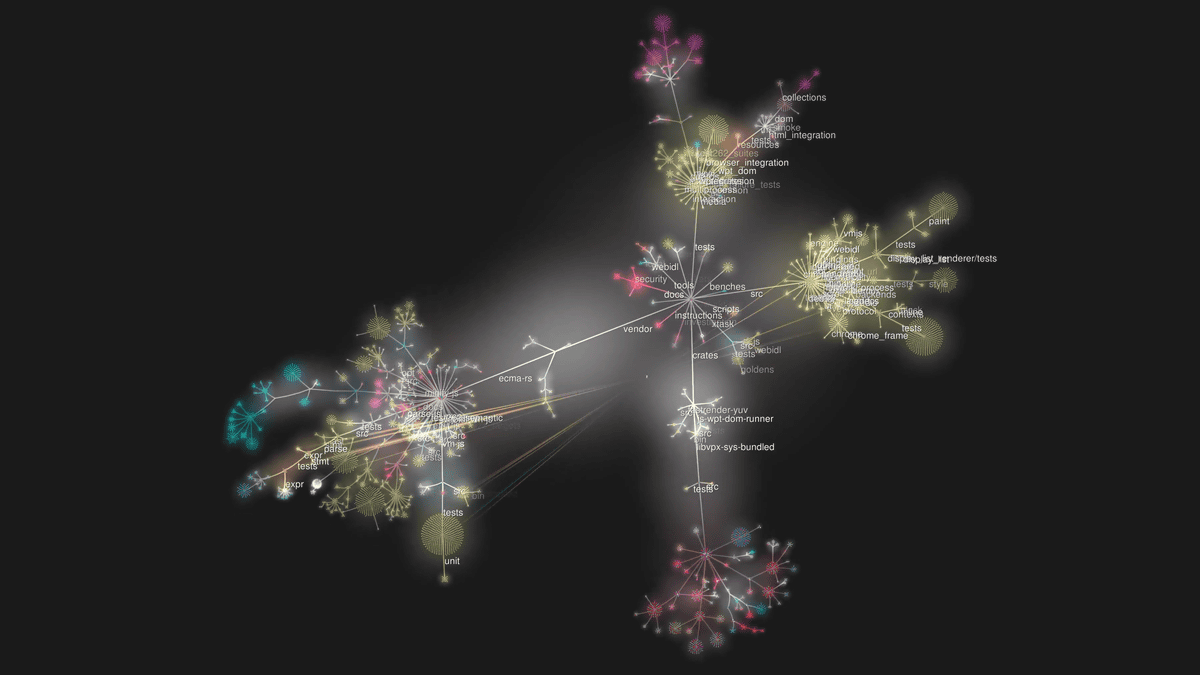メモリ64GBも選べるし結構安い!Ryzen AIのモバイルノート「ExpertBook P3」

アクセスランキング
Special Site
PC Watch をフォローする
最新記事
Impress Watchシリーズ 人気記事
おすすめ記事
ASUSのビジネスノートシリーズ「ExpertBook」に新モデルが登場した。4製品9モデルが発表されているが、ここではExpertBook P3(PM3406CKA)を取り上げよう。直販価格は14万9,800円(記事掲載時点では2万円オフ)からで11月中に発売予定だ。
ExpertBookシリーズにはP1、P3、P5、B1、B5……などがある。多少ややこしいかもしれないが、P3には16型モデル、14型モデルがある。ほかP1なども同様だ。その上でP3の14型と絞り込んでもRyzenモデルとCore iモデルがある。こうした理由から、ExpertBookシリーズを語るときは「ExpertBook P3(PM3406CKA)」とP3に続くカッコ内も指定しないとどの製品か判別できない。ちょっとした注意点だ。
そんなわけで今回は「ExpertBook P3(PM3406CKA)」だ。ExpertBook P3は14型のビジネスモバイルノートであり、CPUはRyzen AI 7 350を搭載している。ハイエンドかつAI対応CPUを採用するモバイルノートとなると、社外に出ても性能面で快適に働きたい人、外でもAIを活用したい人が主な対象になるだろう。
ExpertBook P3(PM3406CKA)には、型番が「PM3406CKA-LY0502X」と「PM3406CKA-LY0326X」という2モデルで展開されている。両者の違いはメモリ搭載量だけだ。前者は64GB、後者は32GBとなっている。ASUSは積極的に大容量メモリを搭載する傾向にあるメーカーだ。比較的早い段階で32GB搭載モバイルノートをリリースしていたし、今回は最大64GBだ。マルチタスクにおける快適さもあるし、AIアプリケーションを想定したものでもあるだろう。
こうしたハイエンド寄りスペックだと価格を心配される方も多いだろう。ところが前者で17万9,800円、後者にいたっては15万円を切る14万9,800円となっている。ビジネスモバイルの中心価格帯が10万円とするとそれよりは若干上だが、このスペックにしては意外と安いように感じられるのではないだろうか。15万円でメモリを32GB搭載するRyzen AIビジネスノートである。プラス3万円で64GBに増量でき、より大規模なLLMも動かせるわけである。
AIノートということで、標準インストールされるユーティリティ「ASUS Expert Panel」からもビジネスシーンでAIを活用する機能が呼び出せる。「AIミーティング議事録」「AI翻訳字幕」「動画の透かし」「画像の透かし」といった主にWeb会議でよく使うだろう機能だ。
また、ASUS Expert Panelの非AI部分でもWeb会議を円滑に進められるような構成になっている。「マイクのオン/オフ」「画面の録画」といった具合だ。そして最下段に「システムブースト」とある。これはメモリ解放機能だった。なぜか少し動作が重い……といった時によくあるのがメモリ不足。ホーム用途ではメモリを解放するアプリを導入している方も多いと思われるが、社内ルールに縛られるビジネスPCでは難しい。メーカー標準のユーティリティにこうした機能が備わっていれば、使い勝手が向上するかもしれない。
ボディカラーはミスティグレイ。ExpertBookシリーズでは定番色で、ワークシーンにもなじむ。
14型ディスプレイは、昨今のビジネスモバイルの定番16:10アスペクト比で解像度は1,920×1,200ドットとなっている。パネルは非光沢の液晶だ。もちろん左右ベゼルについては狭め、上側はWebカメラを搭載、下側は若干サイズがあるものの、閉じた際のサイズは359.5×232.2×19.9mmとなっている。なお、古い16:9時代の14型モバイルノート(当時の狭額縁)と並べてみたところ、幅が1cmほど短くコンパクトになっていた。比較的小さめのカバンにも収まりがよさそうだ。
質量は約1.468kg。1kg前後のものが増えていることもあり、1.5kg近い本製品は持ち比べてみて実際にやや重く感じた。ただし、より軽いものと持ち比べての話であり、1.5kg前後のモバイルノートもまだまだ多いので「モバイルの範疇」ではある。
インターフェイスを見てみよう。左側面には2基のUSB 3.2 Gen 2 Type-C、1基のUSB 3.2 Gen 1 Type-A、そしてHDMI、マイク/ヘッドフォンコンボジャックを、右側面にはUSB 3.2 Gen 1 Type-Aおよび有線LAN、セキュリティロックスロットを備えている。有線LAN非搭載が主流のモバイルノートにあって、貴重な有線LAN搭載モデルと言えるだろう。速度は1000BASE-Tだ。また、無線LANはWi-Fi 6E、Bluetooth 5.4にも対応している。
キーボードは日本語配列。キーピッチは実測で19mm程度と一般的なノートPCのサイズ感だ。Copilotキーもある。F1~F4キー部分は(デフォルトで)スピーカーのミュートや音量調節、マイクのオン/オフ機能に割り振られている。リモート会議時に判別しやすいよう青のラインも添えられている。ビジネスでの使い勝手をよく考慮されたキーボードだ。
なお、電源ボタンはキーボード右上にある。ただ、ここだけやや硬くプチッとした押下感としている。ほかのキーにそのまま並ぶ格好なので間違えて触れることは多いかもしれないが、感触が異なるので誤爆は防げそうだ。マークにある通り指紋認証も備えている。
メモリについては先に説明した通り今回試したモデルは64GB、もう1つのモデルは32GBだ。どちらがよいかというのは、予算もあるしAIをどの程度活用するのかにもよる。ただ、スペックを見ていてそこにSO-DIMMとあることに気づいた。
CPU-Zから確認してもDDR5-5600でSO-DIMM、32GB×2枚とのことだった。昨今のモバイルノートでは基板実装タイプで交換、増設不可のオンボードメモリが増えていた。そんな中、SO-DIMMスロットを採用するモデルは希少だ。また、サポートがどうなるかは要確認事項として、32GBモデルを64GBに増量できるかもしれない。
DDR5-5600のデュアルチャネルとメモリ速度的には普通なので、AI性能にフォーカスしたものではないと思われる。ただし、いずれにせよメモリが最低限の8GB、ちょっと増やした程度の16GBで交換不可のオンボード実装としたら、すぐに時代に取り残されてしまう可能性もある。ExpertBook P3(PM3406CKA)はSO-DIMMを採用していることで比較的長く現役でいられるビジネスノートPCと言えるかもしれない。
ストレージは1TB。PCI Express 4.0 x4接続のM.2 NVMe SSDとされている。ビジネスノートPCとして見れば大容量だろう。速度的に見てもスタンダードかビジネスノートPC用としては速い部類に入ると思われる。
バッテリについては容量70Whrで4セルリチウムイオンとされている。公称ではJEITA測定法3.0で18.5時間駆動とのことだ。ACアダプタは定格90WのUSB PDタイプが付属している。
パフォーマンスについては代表的なベンチマークの結果をいくつか提示しておこう。性能比較の参考となれば幸いだ。
Cinebench 2024のスコアはMulti Coreが813pts、Single Coreが117pts。マルチコア側は8コア16スレッドCPUなりで、十分に高いスコアだ。ただしモバイル向けRyzenの中でも非AIの8000シリーズの同数コアモデルよりは若干低い。8コアでも、4コアがZen5コア、残り4コアが同じアーキテクチャでも省電力のZen5cであるためこうしたスコアになったのだろう。一方、シングルスレッド性能は最新アーキテクチャとあって同クラスでは十分に高いスコアと言える。
GPUを活用するビジネスアプリケーションもあるが、そのGPU性能をファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー ベンチマークで測ってみた。1,920×1,200ドット、標準品質(ノートPC)で実行した結果はスコアが6,598ポイント、平均フレームレートが45.3fpsだった。統合GPU(Radeon 860M)利用モデルとしてはまずまず高いスコアと言えるだろう。
PCMark 10のOverallは7,378ポイント。ホーム用途のEssentials、ビジネス用途のProductivity、コンテンツ制作のDigital Content Creationという3つのシナリオそれぞれおおむね10,000ポイント前後を記録している。本製品でポイントになるだろうWeb会議テストはEssentialsに含まれているが、そのスコアも十分だ。ディスクリートGPUを搭載しているわけではないのでコンテンツ制作向きとは言えないが、統合GPU機能でもできる範囲、あるいはNPUを利用できる範囲では十分に通じる。
最後にバッテリ駆動時間をPCMark 10のModern Officeバッテリベンチマークで計測した。ビジネスアプリケーションを動かしながらテストをするものなので、動画再生で計測するテスト等と比べると実際の体感に近い結果になると思われる。電力設定を「最適な電力効率」、ディスプレイ輝度を50%といった条件で計測した結果は駆動時間13時間49分、スコアは4,895ポイントだった。ビジネスにおける営業時間は余裕を持ってカバーできる結果だ。
ExpertBook P3(PM3406CKA)を試した中で感じたポイントをまとめよう。まず非常によいと感じたのがコスパ面だ。このスペックにしてこの価格。Ryzen AI 7 350に大容量メモリ、SSDも十分といったスペックで10万円台半ばという価格は魅力的だ。
メモリに関してはSO-DIMM採用という点も推したい。そして有線LAN搭載も挙げられるだろう。デザインについてはオーソドックスかつシルバー系カラーでビジネスシーンに合う。
また、特に「Web会議」向け機能が充実しており、使いやすそうだ。Web会議で使う機能をキーボードでは青ラインで示し、ユーティリティでは一発で呼び出し切り替えできる。全体的に見てビジネスモバイルノートとしての完成度は高く、10万円台半ばという価格も投資した分の快適さ、そしてビジネスとしての結果を得られる製品と言えるのではないだろうか。