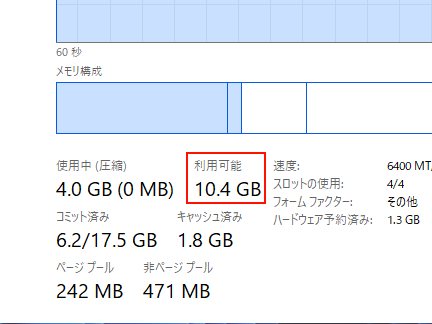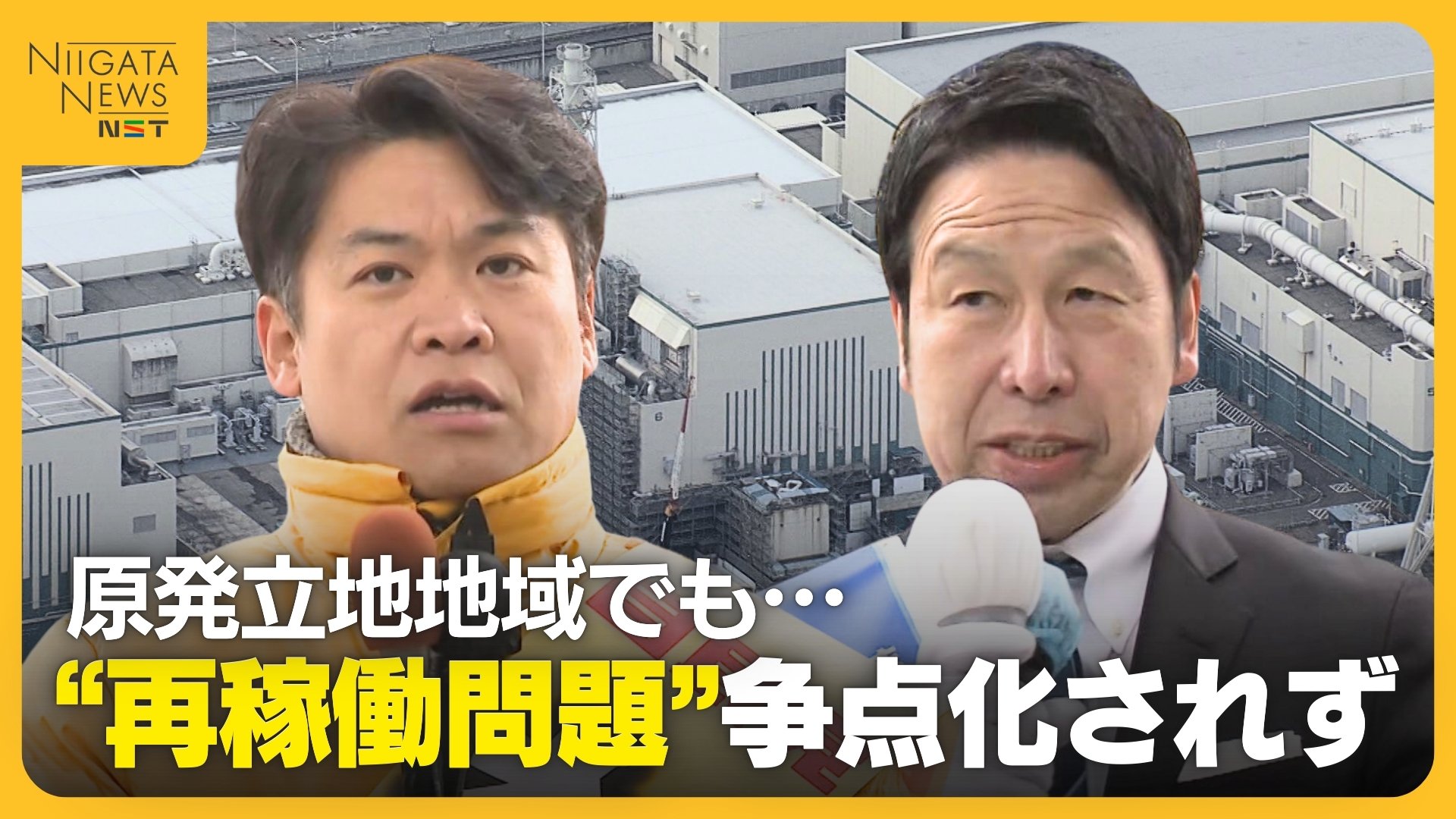「やりたかった恋愛シミュレーション、AIで作れた」 AIゲームの進化と課題

ChatGPTやGemini、Grokで遊べる最新のTRPG風ゲームや恋愛ゲーム、さらにビジネス化を試みる最新LLMゲームの動きや難しさを紹介します。 【もっと写真を見る】
LLMをリアルタイムで利用したゲームが次々に登場しつつあります。特に最近はLLMとゲーム要素を組み合わせてストーリーを展開させていくタイプが数多く登場しています。製品やサービスとしてパッケージ化されたゲームはまだ限定的ですが、新しい可能性が明確に見え始めています。ChatGPTやGemini、Grokで遊べる最新のテーブルトークRPG風ゲームや恋愛ゲーム、さらにビジネス化を試みる最新LLMゲームの動きや難しさを紹介します。 TRPGをAIで再現するテンプレート 筆者が、実際にプレイしてみて面白かったのが、ぶんきちさんがnoteで公開中の「AI用汎用TRPGゲームマスター・テンプレート」。8月に公開後、アップデートが続いています。内容はChatGPTやGeminiに読み込ませて、ストーリーを楽しむタイプのゲームです。テーブルトークRPG(TRPG)を名乗っていますので、プレイヤーには能力値であるパラメーターが存在し、アイテムを所持する概念があります。そして、ゲームを進めるうえの重要なタイミングで、行動決定に対して状況の難易度に応じて成功確率が決まり、ダイス(サイコロ)を振り、その結果によってゲーム展開が変わるという仕組みになっています。 ChatGPTでロールプレイをするというプロンプトは、これまでいくつも登場していますが、約1万5000字に及ぶプロンプトは作り込みが厚く、本格的なTRPGをプレイしているような気持ちにさせてくれます。 Geminiではカスタマイズ機能の「Gems」を使うことが強く推奨されており、筆者もその環境でプレイしています。テンプレートを読み込ませ、開始するだけでゲームはすぐに始まります。サイバーパンクシナリオを選択してプレイしたところ、まずはキャラクターの初期設定です。名前や能力値を設定し、特殊能力としてハッキングを選択。さらに、初期所有アイテムを選択します。後で、20の能力値を均等に配分したのは失敗したなと思うことになるのですが。 ゲームを開始すると、仲間との接触地点に向かっているのに、追われている可能性が出てきました。そこで、さっそくステルススーツを着込んで、やり過ごすことにしました。すると、ダイス判定になり、結果は成功。不審者は筆者を見つけることができませんでした。 ところが、その後がうまくいきません。不審者連中が何を目的としているのかを知るために、聞き耳を立てたのですが、その行動の成功には出目が14以上必要と提示されました。精神を5持っているので、出目9以上で成功なのですが、出目は2で合計すると7なので、失敗に終わり、不審者たちが何を追いかけていたのかがわからない結果に終わりました。 こうした形で、結果に対し、要所要所でダイスの結果による偶然の要素が絡みます。展開が単純ではなく、なかなか思ったように単純に展開しないため、知恵を絞って、緊張感をもってゲームを進めていくことができます。 この後は、ある情報チップを回収のために工場に侵入するという展開になります。ステルススーツを着てうまく管理室にいる3人組に気が付かれずに侵入し、彼らの話を盗み聞きすることで、地下室にチップに関連する人物がいることまでわかったのですが、地下室のルートは鍵がかけられており、そのハッキングを通じた解錠に失敗。銃で強引に鍵を破壊したら、その音で3人組に見つかり、やばいのでステルススーツを使って逃げようとしました。そのダイスの判定では、なんと出目1と最低数が出て、右足まで撃ち抜かれて動けなくなってしまいました。哀れみを乞うてみたのですが、そこでゲームオーバーとなりました。 ところが、ゲームはここで終わりではありません。 直後に、セーブデータが生成されるのですが、それが続きをプレイするためのプロンプトにもなっていて、ゲームを継続できるのです。ゲームは、命乞いをしているシーンから再開され、筆者は、敵に重要な情報を教えると言って、なんとか生き残ることに成功し、敵の医者によって、情報を抜き出すために脳ハッキングを受けるも、逆にハッキングを仕掛け返すことに成功。窮地を脱出することができました。自分の持つハッキング能力を使っての補正があるので、成功確率は50%まで高めることができていたのですが、ダイスを振るところは緊張するシーンでした。 ところが成功後に、気がついたら、病室の一室にいて、そこには巨大IT企業アラサカの施設でした。アラサカにより救助され治療を受けていた筆者は、協力員になり活動するか、この場で死ぬかを選べと言われ、さらに次の展開が始まるのです。 Grokで広がる恋愛アドベンチャーの世界 X上にも様々なGrokの仕組みを利用した選択式のテキストアドベンチャーが登場しています。sara(鳩)さんが開発した「アズライトの記憶」は、高校2年生の主人公が、夏休みに8年ぶりに故郷の港町に戻り、従姉妹と昔の記憶を思い出しながら、様々なところを訪ねるというゲームです。期間は3日間に限られ、昼夕夜と3ターンに分かれており、その選択によってだんだんとお互いの心の距離が変化していくというものです。よくある恋愛アドベンチャー風のゲームです。 ストーリーは基本的に決められているものの、AIが自動生成している文章も少なくありません。微妙に変わる関係性などが織り込まれつつ展開していきます。そして、選択肢を選ぶだけでゲームが進み、積み重ねによって3日目最後の別れの際に、3種類のエンディングから、結末が決まってきます。 【Grok利用アドベンチャーゲーム】 『アズライトの記憶』 キーワード:高校生、夏休み、港町、海、自転車 プレイはこちらからhttps://t.co/SR6cMU4iIBpic.twitter.com/0sdOww5FRg — sara(鳩) (@sara_sara0307) July 13, 2025 △sara(鳩)さんのXでの告知 Grokを使ったアドベンチャーゲームは、カガミカミ水鏡さんが、2月に「【オープンβ開始】X(Grok3)で動くっぽいチャットゲームの作り方をネチョネチョ分析」 という記事(一部アダルト寄りの内容)を公開して、パラメーター管理をしつつ、テキストゲームをプレイする仕組みを容易に作れることを紹介しました。その後、6月にシトラス(柑橘系)さんが「新人冒険者と7日間のダンジョン」など複数のゲームを発表しています。 どちらもプロンプトが公開されているので、それを改造したり、構造を真似して設定を変更することによって、オリジナルのゲームが開発できるのです。 実は、sara(鳩)さんは筆者の大学院ゼミに所属する学生で、これらの発表されたGrokゲームを参考にして、生成AIを使ったアドベンチャーゲームの研究の一環として開発しました。学部生時代には恋愛アドベンチャーゲームの研究をしていたのですが、「これまで自分ではゲームを作れなかったが、Grokがあることで作れるようになった」と話していました。 課題は「地味さ」とマネタイズの壁 ChatGPT、GeminiやGrokを使ったゲームの弱点は、テキストだけで地味であるという点、さらには、マネタイズの方法がほとんどないという点です。 すめらぎ店さんが開発している「エターナルハンド」は、LLMとパラメーター、さらには画像生成に音声合成まで組み合わせて生成AIでのゲーム体験を形作ろうとする意欲的な内容です。すでにBOOTHにて1000円の有料販売を始めています。ゲームでは4つのモードが選べるのですが、バトルモードやストーリーモードでは、自分が作成したキャラクターや最初から用意されたキャラクターを使って、ゲームを進めることができるのですが、基本シナリオ以外は、LLM生成による展開です。画像も生成され、雰囲気を盛り上げます。出てきたシナリオに対して、こちらがどのような行動をすべきかが入力し、パラメーターの影響を受けながらゲームが進んでいくという仕組みです。 ただし、プレイにはGoogle AI StudioのAPIキーの入力が必須で、また、入力から反応が戻ってくるまでには数十秒待たされ、それがなかなかのストレスです。まだUIがこなれていないこともあり、初心者には操作もわかりにくいと感じられます。またオンライン機能を使うには、2ヵ月目以降には月500円ほどかかるため継続のハードルは高そうに思えます。 LLMゲームはそれほど本格的なゲームはまだ登場していないのが実情です。ビジネスモデルの確立が難しいためです。現状はゲームユーザーのプレイ環境にローカルLLMまで組み込むことは現実的ではありません。そのため、クラウドサービスのLLMを呼び出せるように外部APIを使うのが普通です。しかし、それがSteamといったゲームプラットフォームにLLMゲームを登場させることを難しくしています。 Steamは公式ドキュメントで「あらゆるゲーム内購入はSteam Wallet(マイクロトランザクションAPI)を使用」と定め、外部決済へ誘導する設計は原則NGとしています。そのため外部API利用料を「別の月額(外部)で必須化する構造」は審査と衝突しやすいと理解するのが安全と考えられています。つまり、何かのLLMを月額課金で利用しているユーザーがその個人のAPIキーを使ってゲームをプレイすることを必須とすることが認められにくいということです。やるなら、Steamの継続課金、または、Steam内課金で構成する必要があります。 ゲーム会社側でAIの推論コストを負担することが、シンプルな仕組みにできるのですが、定額販売の買い切り型のゲームでは、プレイ時間が長くなるほどAI利用による推論コストが利益を圧迫し、赤字化リスクも生じます。月額でLLM利用ポイントを配布する方式も考えられますが、サービスの設計、利用枠管理や不正対策など運用ハードルがかなり上がります。 その結果、設計の可能性は広がっているものの、収益化の目処が立ちにくいため、現時点ではタイトル数は限定的でニッチにとどまる傾向があります。なお、ストア本文で外部サイトへ誘導するリンクは2024年以降さらに制限されており、表現面でも配慮が必要になっています。 Runwayが示す次世代AIゲームの姿 一方で、8月に動画生成AIサービスを提供してきた米Runwayが8月テキストアドベンチャーゲームを作れる新サービス「Runway Game Worlds」を開始しました。ゲームで使われるシナリオと画像をAIが作り、プレイできるというものです。現状の多くのLLMゲームが目標としているゲームの姿を垣間見ることができます。 サービス上にはあらかじめゲームブックのようなシナリオが用意されていて、ユーザーも自分でシナリオを作ることができます。たとえば、あらかじめ用意されているシナリオ「ガリアの嵐」では、ローマ軍に所属している主人公が、ユリウス・カエサルの遠征でともに戦い結果を出していながら、生き残ることを目指すシナリオです。もちろん、毎回展開は生成され結果が変わります。 AIがベースとなるゲームのシナリオを作っていて、それに合わせて漫画風のストーリーが展開され、一定進むと選択肢が現れるという形式になっています。それらの画像が自動生成されるのが、ゲームを楽しくします。もちろんパラメーターも存在しており、ローマ軍との戦いでは、残っている兵力が生命(Vitality)としてカウントされていきます。 そして、ゲームは「ダウンロード」を選ぶと、プレイしたゲームをビジュアルノベルとして保存して読めるようにもできます。すでにユーザー作成のシナリオも含め数十種類のゲームが登録されており、様々なゲームを楽しむことができます。 Runwayの主軸は動画ですが、計算コストが比較的安いテキストと画像を使ったサービスを提供してきたということでしょう。当然、自前でサーバーも課金システムも持っているために可能な展開とも言えます。 現状は無料で提供していますが、将来的には有償化して、生み出した物語から1本の映画のような動画も作れるようにするといった展開を考えているのではないかと思います。まだ英語でしかサービスが行われていないので、日本からは少しとっつきにくいのですが、いずれ多言語対応も進めてくることでしょう。 可能性は広がるが、普及には試練も LLMゲームは、その新しいゲーム体験の可能性の萌芽が見えているものの、多くのユーザーが手軽に楽しめる環境を開発者も用意できないため、様々な制限を抱えているという状況にはあります。しかし、その潜在的な可能性を十分に感じ取れる段階にあり、Runwayが可能性を示しているような、新しいビジネスモデルによるブレイクスルーが次々に登場するのは時間の問題ではないでしょうか。 筆者紹介:新清士(しんきよし) 1970年生まれ。株式会社AI Frog Interactive代表。デジタルハリウッド大学大学院教授。慶應義塾大学商学部及び環境情報学部卒。ゲームジャーナリストとして活躍後、VRマルチプレイ剣戟アクションゲーム「ソード・オブ・ガルガンチュア」の開発を主導。現在は、新作のインディゲームの開発をしている。著書に『メタバースビジネス覇権戦争』(NHK出版新書)がある。 文● 新清士