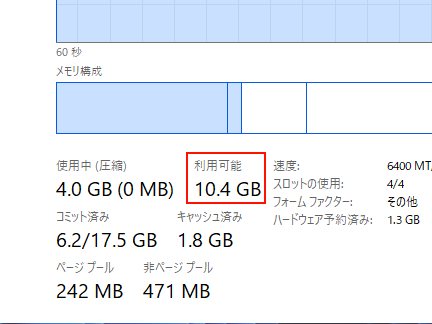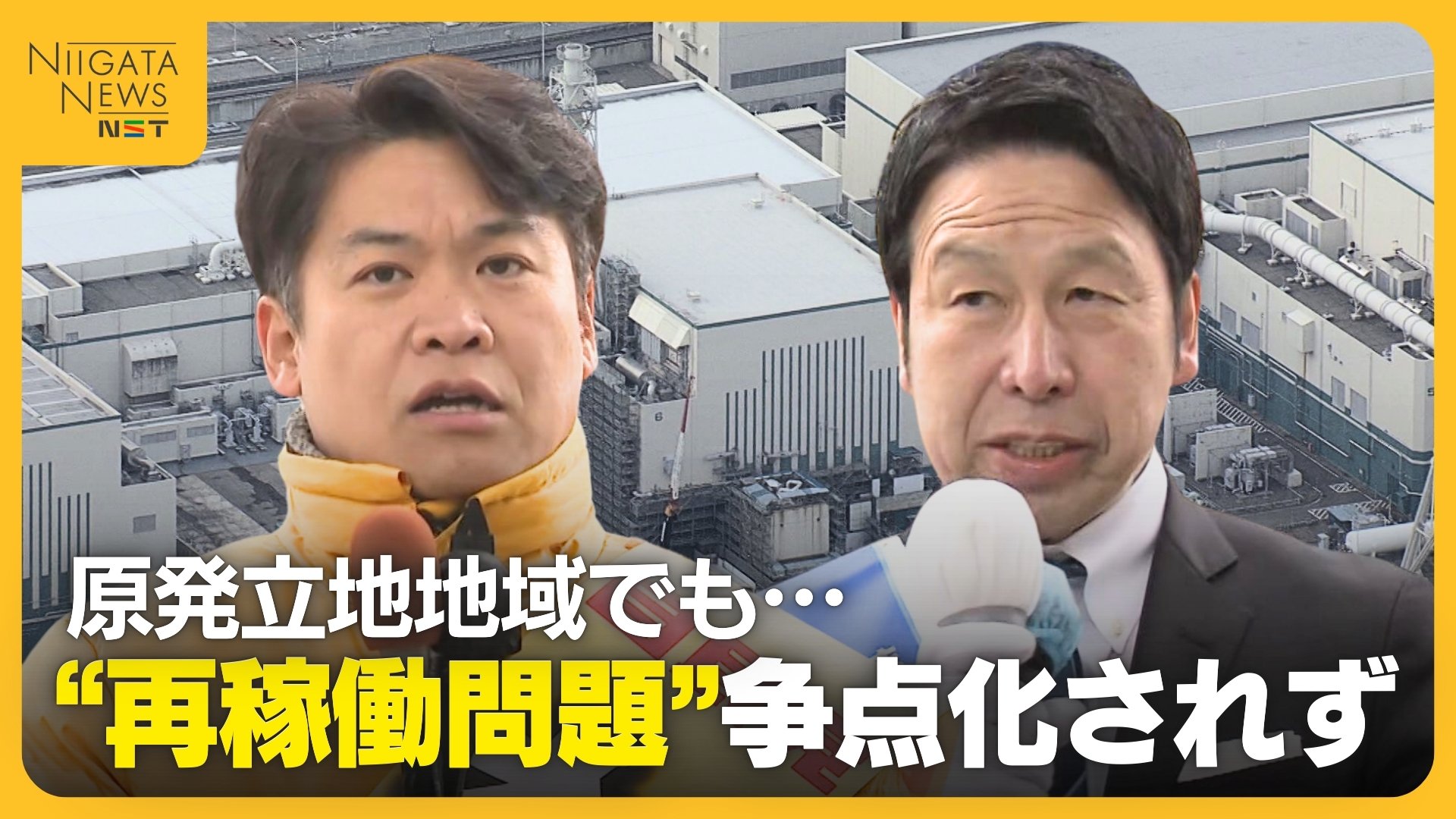社員発の“カスタムGPT”は2000個以上 MIXIの「ChatGPT Enterprise」全社導入で起きた2つの変化

MIXIでは、OpenAIとの二人三脚で、わずか1.5か月でChatGPT Enterpriseの全社導入に漕ぎつけ、さらには定着化のための施策を展開。アクティブユーザー率は3か月も経たずして80%に達し、「想定外だった2つの変化」が生まれたという。 【もっと写真を見る】
「全員で使って試す」という方針で、生成AIツールの利活用を推進するMIXI。2025年3月に「ChatGPT Enterprise」を全社導入してから数か月が経過した。 MIXIでは、OpenAIとの二人三脚で、わずか1.5か月でChatGPT Enterpriseの実装に漕ぎつけ、さらには定着化のための施策を展開。3か月も経たずにアクティブユーザー率が80%に達すると、「想定外だった2つの変化」が生まれたという。MIXIの執行役員 CTO 開発本部長である吉野純平氏に話を聞いた。 “全社員が変わるために”全社で導入、業務データを活用した本格活用を狙う スマホゲーム「モンスターストライク」や、子どもの写真・動画共有アプリ「家族アルバム みてね」、短文テキストSNS「mixi2」など、コミュニケーションを軸とした事業を展開するMIXI。同社は生成AIによる全社員の「シフトチェンジ」を進めている最中だ。 MIXIが生成AI活用で目指すのは、言うまでもなく「生産性の向上」である。ただし、単なる業務効率化にとどまらず、「AIが働きやすいように」ワークフローを見直している。AIとの共生を前提とした働き方を構築し、生まれた余力を活かして「MIXIらしい発明をAIと共創すること」が、最終的なゴールである。 このシフトチェンジのために、2024年12月、取締役を委員長とする「AI推進委員会」を発足。これは全部門の主体的なAI活用を加速させるための組織であり、トレーニングの展開や相談窓口の運営などを担う。加えて、各部署には「AIアンバサダー」を配置。社内外への情報発信や他部署との連携を担うAI活用の“ハブ”として、生成AI活用の現状や課題も取りまとめる。 こうした社内環境の整備に加えて、重要なのが生成AIツールの選定だ。MIXIでは、様々なツールが日々登場する中で、現状のフェーズでは「全員で使って試す」(吉野氏)方針を採る。そして、最初の全従業員向けツールとして2025年3月に導入したのが「ChatGPT Enterprise」である。同社の正社員は1717名(2025年3月末時点)だが、業務委託スタッフや一部のグループ会社社員も対象に含めて2000シート(シート=利用可能なアカウント数)を契約しており、OpenAI APIも利用している。 もともとMIXIでは、ChatGPTの有料プラン「ChatGPT Plus」の利用料を補助する制度を設けており、数百名規模で活用されていた。しかし、法人向けプランではなかったため、企業データを活用した本格的な業務利用には至らなかった。Azure OpenAIで自社開発した生成AIツールも展開していたが、使い勝手や機能面ではChatGPTに及ばない。「“全社員に変わって欲しい”というメッセージも込めて、ChatGPT Enterpriseの全社員利用を決めた」(吉野氏) OpenAIと二人三脚で進めた短期実装と定着策の展開 ChatGPT Enterpriseは、OpenAIの協力のもと、わずか1.5か月で短期導入された。監査ログの実装などに苦労したものの、IDaaSであるOktaとも連携して、快適かつ安心して全社活用できる基盤を構築できたという。 これと同時に、情報のレベルに応じて、適切な入力や外部へのアウトプットを徹底する社内ガイドラインも作成。ルールの範囲内であれば承認プロセスを簡略化できる、活用を妨げない体制も築いている。 さらに導入後には、ChatGPT EnterpriseやOenAI APIを社内に定着させる施策も、OpenAIと共に展開。ChatGPTを業務活用するためのベストプラクティスを学ぶ「ChatGPT 101トレーニング」には、500名規模の参加があった。加えて、2025年度の新卒社員向けワークショップ、OpenAI Agents SDKによるプロダクト開発ハッカソンの実施でも、OpenAIの協力を得ている。 MIXI独自の施策としても、全社研修ツールとして「生成AI教育コンテンツ」を作成。同社が注力する新卒エンジニア向けの技術研修においても、生成AIを含むAI全般の科目も設けている。 また、効果的な施策が打てるよう、部署や役職、職能、雇用形態単位での利用状況が可視化できる仕組みも構築している。これにより、「部署内で極端に利用が少ない社員をフォローしたり、属性ごとのリーチ率などを算出できる」と吉野氏は語る。 月間約1万7600時間の業務削減、さらに「想定外だった2つの成果」 こうした積極的な活用促進の結果、全社導入から3か月未満で、ChatGPT Enterpriseの1週間あたりのアクティブユーザー率(WAU)は80%に到達し、その後も高い利用率を維持しているという。 3か月経過時点での社内アンケートでは、99%が「生産性の向上」を実感しており、90%以上が「時間を節約できた」と回答。さらに、全社で月間約1万7600時間の業務削減効果が見込まれるという。 これに加えて吉野氏は、「当初の想定を超えた2つの変化が生じた」と語る。 ひとつは、目的に応じた独自のChatGPTである「カスタムGPT」を自発的に作る社員が急増したことだ。2025年7月末までに作られたカスタムGPTの数は2322個にも上り、アクティブなものも654個と、実に社員の約3分の1がカスタムGPTを活用している状況だ。最も利用が多いのは「法務との相談の論点をまとめるGPT」だという。 部署独自のカスタムGPT作りも活発で、例えば「家族アルバム みてね」のチームでは、特に広告クリエイティブの制作で活用が進んでいるという。コピーライティングがサービスの世界感に合っているかをレビューする「文言チェッカーGPT」、サービスバリューやユーザー属性を踏まえたマーケティングコピーを多言語で生成する「Creative Planning GPT」などのカスタムGPTが生まれている。 なぜ、ここまで大量のカスタムGPTが作られたのか。一番のきっかけは“研修”だという。カスタムGPTについての研修を全社規模で開催した結果、カスタムGPTの数は約3倍に増えた。「カスタムGPTを作ることまでは推奨していなかったので、ここまで増えたのは予想外」と吉野氏。すっかり定着化したことで、何か困ったことがあっても、現場内で力を合わせて解決する好循環も生まれているという。 そして、吉野氏がもうひとつ驚いたというのが、「非エンジニア職もプログラミングを始めたこと」だ。これまでエンジニアに依頼していた業務支援ツールなどの開発を、ChatGPTのコーディング支援を受けながら自ら構築するケースが増えてきており、「働き方そのものが変わりつつある」という。 こうしてMIXIは、ChatGPT Enterpriseの導入により、「社員の余力をつくり、生まれた時間で新たな価値を作る」という目標の達成に、着実に近づいている。吉野氏は、ここまで順調な理由は「全社導入」だと分析する。「業務委託の人なども含めて、使えない人がいないという状況を作ることで、会話が生まれ、サポートし合う環境が築けた」。 今後期待するのは“データに対する意識変革”だ。AI活用を繰り返すことで、「データの管理・運用の重要さ」が社員に浸透していくという。吉野氏は、「これからは非エンジニアでも、生成AIを使ってデータの応用までが完結できるようになっていく。それにより、より価値を生むデータドリブンな取り組みが増えることを期待したい」と展望を語った。 文● 福澤陽介/TECH.ASCII.jp