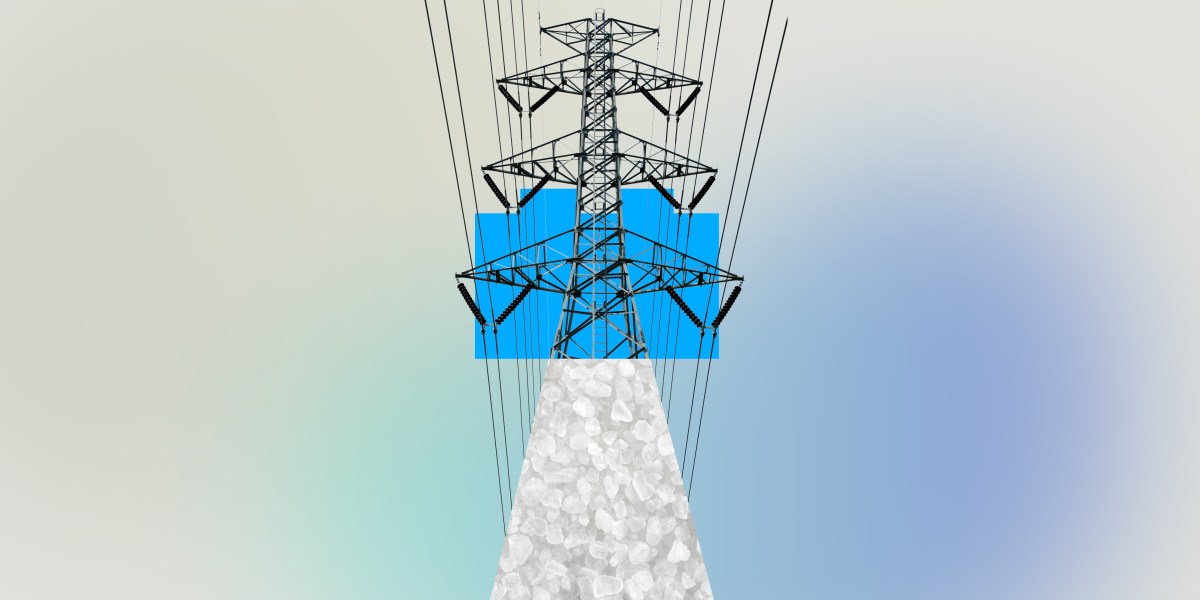「分子の輪」が守る!微小パラジウム触媒を開発 ――リング状の金属酸化物でつくる、選択性と安定性に優れたナノ触媒――

国立大学法人 東京大学東京都公立大学法人 東京都立大学
国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)
発表のポイント
◆高効率・高安定性に加え、特異な反応選択性を示すパラジウムナノクラスター触媒を開発。◆リング状の金属酸化物分子の内部に閉じ込めることで、表面が露出した微小サイズのパラジウムナノクラスターを安定的に保持。
◆多様なナノクラスター材料の開発により、資源循環に貢献する物質・エネルギー変換触媒や、光学材料、センシング、エレクトロニクスなどへの幅広い応用先への展開が可能。
本研究の概要
概要
東京大学大学院新領域創成科学研究科の鈴木 康介 教授、米里 健太郎 助教、同大学大学院工学系研究科の郗 睿 大学院生、谷田部 孝文 講師、小泉 慶洋 大学院生(研究当時)、山口 和也 教授らの研究グループは、東京都立大学大学院理学研究科の吉川 聡一 助教、山添 誠司 教授、物質・材料研究機構 原野 幸治 主幹研究員らと共同で、リング状の金属酸化物分子(注1)の中に閉じ込められた、微小サイズのパラジウムナノクラスター(注2)触媒の開発に成功しました。このナノクラスターは金属表面が露出しており、化学原料を効率的かつ安定に変換する触媒として機能するだけでなく、従来のパラジウム触媒とは異なる反応選択性(注3)を示す物質変換が可能であることが明らかになりました。本成果により、触媒として有用な微小金属ナノクラスターを精密に合成し安定的に利用できるようになるため、資源循環やエネルギー変換を担う触媒材料としての活用に加え、光機能材料、センサー、分子エレクトロニクスなど、さまざまな分野への応用が期待されます。
本研究成果は、7月28日付で学術誌「Advanced Science」誌のオンライン版に掲載されました。
発表内容
パラジウムは、石油化学製品や医薬品といった有用な化学品を、さまざまな化学原料から合成するための触媒や、自動車の排ガス浄化のための触媒として、重要な役割を果たしています。特に、パラジウムは水素化反応の触媒として広く利用されています。しかしながら、従来のパラジウム触媒は、反応中に分解したり、大きな粒子へと変化したりするため、反応効率や選択率の低下が起きてしまうという問題を抱えていました。
研究チームはこれまでに、直径約1ナノメートルの空間を持つリング状の金属酸化物分子を利用して、銀や銅のナノクラスターを内部に安定的に閉じ込める手法を開発してきました(関連情報)。今回の研究では、この技術を用いて、選択性と安定性に優れたパラジウムナノクラスター触媒を開発しました。まず、リング状の金属酸化物分子に酢酸パラジウムを反応させることで、8個のパラジウムイオンがリング状分子の内部に取り込まれることを、単結晶X線構造解析(注4)によって明らかにしました(図1a、b)。さらに、X線吸収微細構造法(注5)や走査型透過電子顕微鏡(注6)を用いて解析した結果、水素ガス中でパラジウムイオンが水素と反応しながら集合し、分子内部で直径1ナノメートル以下の微小なパラジウムナノクラスターが形成されることが分かりました(図1c、d)。
図1:本研究で開発した微小なパラジウムナノクラスター触媒の構造と形成過程
(a) 合成法の概要図。オレンジ色の球はパラジウムイオン (酸化状態)、黒色の球はパラジウム原子 (還元状態) を表す。(b) 単結晶X線構造解析によって明らかにされた、パラジウムイオンを導入したリング状金属酸化物分子の構造。緑色の八面体は、中心にタングステン (W) 原子、頂点に酸素 (O) 原子を持つWO6構造を示す。オレンジ色の球はパラジウムが存在し得る位置を示し、パラジウムはこのうち8箇所を占める。(c) パラジウムのX線吸収微細構造解析。水素ガス処理前 (上部青線) ではPd−O結合が主であるのに対し、水素ガス処理後 (下部赤線) にはPd−Pd結合が現れ、パラジウム原子が集合していることが分かる。(d) 走査型透過電子顕微鏡による観察像。白く明るい部分が金属原子の存在位置を示しており、金属酸化物分子のリング状構造の内部にパラジウムナノクラスターが形成している様子が確認できる。
このパラジウムナノクラスターは、金属酸化物分子の輪の内部に閉じ込められることで、微小なサイズを保ったまま安定的に存在することが可能となり、同時にクラスター表面が分子の開口部から露出しているという特徴があります。このような構造により、本触媒は高い反応性と選択性に加え、優れた安定性を兼ね備えています。例えば、シンナムアルデヒド(炭素-炭素二重結合および炭素-酸素二重結合、注7)や1-エチニル-4-ニトロベンゼン(炭素-炭素三重結合およびニトロ基(NO2))のような複数の反応点を持つ化合物に対し、従来のパラジウム触媒では両方の反応点が水素化された生成物が多く得られてしまいますが、本研究で開発したパラジウムナノクラスター触媒では、これらの化合物の水素化反応に対して高い活性を示すとともに、炭素-炭素二重結合や炭素-炭素三重結合の優先的な水素化を実現しました(図2a、b)。さらに、このパラジウムナノクラスター触媒は、複数回使用しても触媒性能がほとんど劣化しないことも明らかとなりました(図2c)。
図2:本研究で開発した微小なパラジウムナノクラスター触媒の特性
(a) 開発したナノクラスターを用いた水素化反応の例。基質としてシンナムアルデヒドおよび1-エチニル-4-ニトロベンゼンを用い、選択的かつ効率的な物質変換を実現した。(b) シンナムアルデヒドの反応における、従来のパラジウム触媒と本研究で開発したパラジウムナノクラスター触媒の比較。シンナムアルデヒドは、炭素-炭素二重結合(A、赤色部分)と炭素-酸素二重結合(B、青色部分)の2つの反応点を有するが、開発したパラジウムナノクラスターではBが選択的に反応し、従来触媒とは異なる生成物選択性を示す。(c) シンナムアルデヒドの水素化反応における触媒の再使用性評価。同一触媒を用いて繰り返し反応を行っても、シンナムアルデヒドの消費量(転化率)や、目的生成物の割合(選択率)に顕著な変化は見られず、高い触媒安定性が確認された。
本研究成果は、微小なパラジウムナノクラスターを精密に合成し、安定的に利用するための新たな道を切り拓くものであり、資源循環やエネルギー変換を担う高性能触媒としての応用に加えて、光機能材料、センサー、分子エレクトロニクスなど多岐にわたる分野への展開が期待されます。今後は、本研究で開発した合成手法を基盤として、さまざまな機能性ナノクラスター材料の開発とその応用技術の開発を進めます。
〇関連情報:プレスリリース「露出した金属表面を持つハイブリッド分子触媒を開発 ―安定性と高い触媒活性を両立―」(2023/6/9)https://www.t.u-tokyo.ac.jp/press/pr2023-06-09-001
発表者・研究者等情報
東京大学大学院新領域創成科学研究科 物質系専攻 米里 健太郎 助教 鈴木 康介 教授大学院工学系研究科 応用化学専攻 郗 睿 博士課程 小泉 慶洋 研究当時:博士課程 谷田部 孝文 講師
山口 和也 教授
東京都立大学 大学院理学研究科 化学専攻 吉川 聡一 助教
山添 誠司 教授
物質・材料研究機構 マテリアル基盤研究センター 原野 幸治 主幹研究員
論文情報
雑誌名:Advanced Science題 名:Surface-Exposed Pd Nanocluster Confined within a Ring-Shaped Polyoxometalate for Selective Hydrogenation著者名:Rui Xi, Kentaro Yonesato, Takafumi Yatabe, Yoshihiro Koizumi, Soichi Kikkawa, Seiji Yamazoe, Koji Harano, Kazuya Yamaguchi, Kosuke Suzuki*DOI: 10.1002/advs.202509418URL: https://doi.org/10.1002/advs.202509418
研究助成
本研究は、科学技術振興機構(JST) 創発的研究支援事業(課題番号:JPMJFR213M)、同 戦略的創造研究推進事業 CREST(課題番号:JPMJCR20B2)、日本学術振興会(JSPS) 科学研究費補助金(課題番号:24K01448、24H02210、24H02217、24K01279、23K13812、22H04971)の支援により実施されました。
用語解説
(注1) リング状の金属酸化物分子原子番号74のタングステン原子が、酸素原子を介して結合した分子状の化合物であり、1ナノメートル径の内部空間を持つ。本研究では、パラジウムナノクラスターを合成し、安定的に利用するための反応場として機能する。
(注2) パラジウムナノクラスター数個から数百個程度のパラジウム原子から構成される、数ナノメートル以下の大きさの化合物。水素化反応などの触媒への利用が見込まれている。本研究では、リング状の金属酸化物分子に8個のパラジウムイオンを導入して還元することにより、微小なパラジウムクラスターを精密に合成することを可能にした。
(注3) 反応選択性特定の反応が優先的に起こる性質。
(注4) 単結晶X線構造解析単結晶材料にX線を照射すると、特定の方向に強くX線が散乱される(回折)。X線の回折点を収集、解析することで分子や結晶性材料の構造を決定する方法。
(注5) X線吸収微細構造法目的の元素に適したエネルギーのX線を照射することで、物質中に含まれている目的の元素の周辺に存在する原子の情報を得る分析手法。共存する元素の影響を受けにくく、パラジウムナノクラスターの構造や電子状態の分析に強力な手法である。
(注6) 走査型透過電子顕微鏡観察したい分析試料に、細く絞った電子ビームを照射し透過する電子や散乱された電子を検出することで、粒子の形や、分子中の原子の種類と並び方が分かる像が得られる手法。
(注7) シンナムアルデヒド分子式C8H9Oで表される有機化合物で、シナモンの香気成分として含まれる。分子構造中に、水素分子が反応し得る炭素-炭素二重結合(ビニル基)と炭素-酸素二重結合(カルボニル基)を持つ。