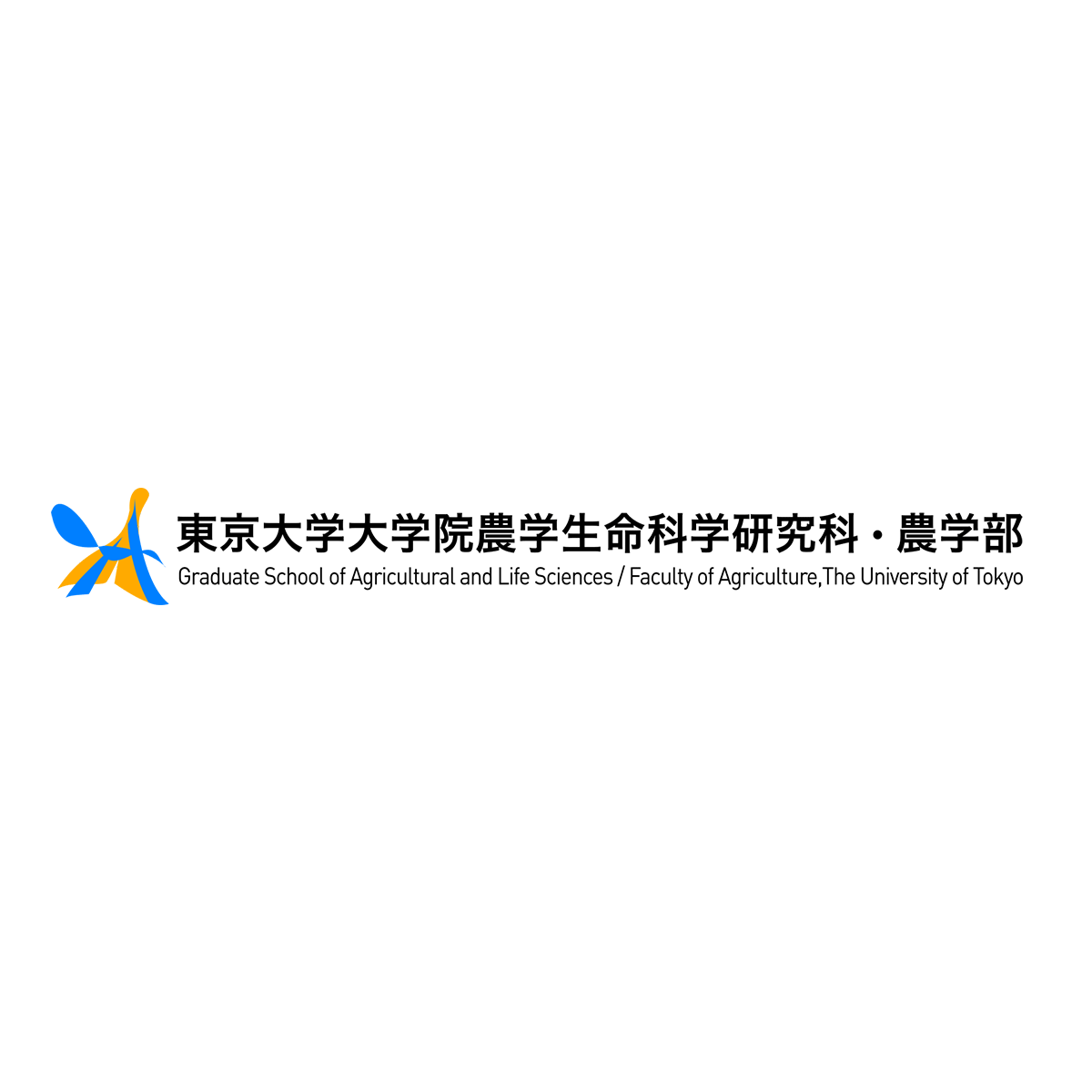知らないうちに腸にダメージを与え続けている…ほとんどの人がもつ「慢性型アレルギー」が引き起こす症状(プレジデントオンライン)

16:01 配信
腸が体に及ぼす影響は何か。医師の和田秀樹さんは「人の免疫細胞の80%が集中している腸の状態が悪いと、全身に悪影響を及ぼす。腸の健康を作る上では、ほとんどの人が何らかの食品に持つ、自覚症状に乏しい慢性型アレルギーに注意が必要だ。『この食べ物を食べると、体がだるくなることがある』『食べたあとに、なんとなく胸がムカムカする』という食材については、避けたほうがいい」という――。 ※本稿は、和田秀樹『75歳からやめて幸せになること 一気に老ける人、日ごとに若々しくなる人の差』(大和書房)の一部を再編集したものです。■「美容医療」に抵抗を持つ必要はない 日本では、若返りのために白髪染めや、シワ取りクリームを容認しているのに、美容皮膚科でシワを伸ばしたり、シミを取ったり、カツラをつけて薄毛を改善したりすることには抵抗感を持つ人が多いようです。 私にしてみれば、老化を食い止め若返りを追求する意味では、大差がないと思うのですが、美容医療に頼っていることを公言する人はまだまだ少数派です。 美容医療の分野は一昔前と比べてもかなり進化しています。ほうれい線を消す技術も、シワを伸ばす技術も向上しています。 一方で、世の中に流通しているシワ取りクリームには、効用が疑わしいものもあります。そうした商品にお金をかけるよりも、美容皮膚科でシワを伸ばしたほうが安全だし、確実な効果も得られます。
費用対効果で考えても、むしろリーズナブルな方法といえます。私だったら、美容医療に頼るほうを選びます。
■見た目が若返れば心も若返る 例えば、ヒアルロン酸注射やボトックス注射を打つと、気になる肌のシワやほうれい線をピンポイントで改善できます。一度試して自分に合わないと思ったら、次から施術を受けなければいいだけのことです。 若返った見た目を鏡で見れば、確実に気分は高揚します。人と会うとか、外に出かけようとするモチベーションも向上するはずです。結果的に免疫機能が高まる可能性も大いにあります。 美容医療というと、女性だけの話であり、自分には無関係だと考える男性が多いようですが、男性が若返りの努力をしていけない理屈はありません。 私が強調したいのは、人間には自分が好きなように生きる自由があるということです。老いるに任せて生きるのが一つの選択肢であるように、生きている以上は若々しい見た目でいたいという選択も尊重されるべきです。 年をとったからという理由で、当たり前の自己決定を手放してはいけません。■心のあり方は外側から規定される ホルモンや前頭葉は、心のあり方と密接に関係しています。心がウキウキしているときにはホルモンや前頭葉も活性化します。逆に、気分が落ちこんでいるときにはホルモンや前頭葉の働きも低下してしまうのです。 心のあり方については、心理学の知見では内側から出てくるものではなく、外側から規定されるという考え方が主流になっています。 例えば、パイロットが制服を着れば「乗客を安全に運ぶ」という意識になりやすく、医者が白衣を着れば「患者の命を助ける」という使命感にスイッチが入る、といった具合です。 この原理にならえば、心がウキウキするような行動をとれば、自ずとホルモンや前頭葉の働きも活性化することになります。 心をウキウキさせる一つの方法は、見た目をよくすることです。いつもよりお洒落な格好をして外出すると、心が高揚するものです。明るい色づかいの若々しい服装をするだけでも、気分が若返ります。 高齢者だからといって地味な格好をしていると、心のあり方まで年寄りっぽくなってきます。不思議なことに肌がたるんできたり、猫背になったり、足取りが重くなったりするのです。 「もう若くないし」というのはやめて、若々しい服装にチャレンジしましょう。人は、そこまで他人を見ていないのですから、まわりの目を気にしなくても大丈夫。「ちょっと若作りしすぎかな」と思うくらいで、ちょうどよいです。 色でいえば、赤やピンク、イエローやオレンジなどの暖色系を選ぶと気分が明るくなり、若返ります。 暖色系の色は男性ホルモンの分泌を促す効果もあるようです。
シックな色づかいが好きで、どうしても明るい色の服装に抵抗がある人は、ネクタイやスカーフ、マフラーなどに明るい色を取り入れるだけでもOKです。
■肌の調子は腸の状態とつながっている ここから少し、食生活についてお話ししたいと思います。 老化に歯止めをかけるには、腸の健康が重要です。 腸は食物を消化・吸収する大切な器官であるとともに、人の免疫細胞の80%が集中しているからです。 腸が健康であれば、細胞に栄養素を行き届かせることができます。また、免疫力があれば、細胞を傷つける異物を排除し、修復してくれます。 逆に腸の状態が悪いと、全身に悪影響が及びます。例えば、便秘になって腸が毒素を排出し切れず、血液によって全身に運ばれると、肌がくすみがちになったり吹き出物ができたりします。 つまり肌は、腸の状態のバロメーター。肌ツヤがいいときは腸も元気である証拠。逆に肌荒れしているときは腸の状態が悪化していると考えられるのです。 腸の健康を作る上では、アレルギーに注意する必要があります。アレルギーというと花粉症や卵などのアレルギーや鼻炎、喘息(ぜんそく)などが思い浮かびますが、それだけではありません。実は、自覚症状に乏しく長期化しやすいアレルギーもあるのです。 自覚症状がなくても、ほとんどの人は何らかの食品に、このタイプの慢性型アレルギーを持っています。症状が軽いので、気づかないうちに腸にダメージを与えていることがあります。 「この食べ物を食べると、体がだるくなることがある」「食べたあとに、なんとなく胸がムカムカする」という食材については、避けるようにしましょう。 意外にも、自分が好む食べ物がアレルギーを引き起こすケースがよくあります。心当たりがある食べ物は、控えたほうが賢明です。 慢性型アレルギーを正確に調べたい場合は、専門の医療機関で検査を受けましょう。日本では検査できる場所が限られているので、よく調べてから受診してください。■よく噛むことは、脳機能を活性化させる あなたは普段、「噛(か)む」ことをどれだけ意識しているでしょうか。よく噛むことは、健康上のさまざまな効果をもたらします。 最大のメリットは、なんといっても脳機能を活性化する効果です。 ものを噛むとき、あごの筋肉である「咬筋(こうきん)」が働きます。咬筋は、三叉神経(さんさしんけい)(顔の感覚を脳に伝える末梢神経の一つ)を通じて脳とつながっています。つまり、ものを噛むと脳が刺激されるということです。 また、上の歯と下の歯をしっかり合わせて噛むと、歯根膜(しこんまく)(歯の根っこと骨を連結させている薄い膜)が刺激され、これも脳を刺激します。 刺激された脳内では海馬の血流量が増え、活動的になります。よく知られているように、海馬は記憶形成と深くかかわっている器官にほかなりません。 これが「よく噛むと、脳機能が活性化する」のメカニズムです。
実際に、高齢になって歯が残っていない人ほど認知症になりやすいことがデータ上からもわかっています。
■ガムを一日10粒ほど食べる よく噛む行為は消化を助け、胃腸の働きをよくする効果もあります。 また、唾液がたくさん出ることで殺菌効果が働き、虫歯や歯周病、誤嚥性(ごえんせい)肺炎や感染症の予防効果も期待できます。さらに唾液中に含まれるペルオキシダーゼとカタラーゼという酵素が、発がん性物質の毒性を消してくれるだけでなく、活性酸素を除去する働きをしてくれます。 噛むことは、お金をかけずにすぐできる健康法です。やらない手はありません。まずは一口30回、30秒かけて食べる習慣を身につけましょう。 ほかにはガムの活用も有効です。私自身はガムを一日10粒ほど食べ、噛む力をトレーニングしています。 歯に不安を抱える人は、義歯やインプラントなど、しっかり治療をしておくことも大切です。■アルコールとうつ病の恐ろしい関係性 コロナ禍で外飲みの機会が減少して以来、逆に家飲みをする機会が増え、酒量も増加したという人が多いのではないでしょうか。 自宅で一人で飲む場合、ついつい歯止めがきかなくなります。酒量が増えると睡眠の質は低下し、中途覚醒(ちゅうとかくせい)も増えます。不眠症や睡眠障害のリスクも高まります。 眠れないからといって深酒をしていると、ますます眠れなくなる悪循環を招きます。お酒に頼る習慣が続くと、アルコール依存症に陥る危険性もあります。 アルコールには、脳内のセロトニンを減少させる作用があるとされています。 アルコール依存症からうつ症状につながる場合もあれば、逆にうつ病がきっかけでアルコール依存症になるパターンもあります。 アルコールは自殺とも関係しており、厚生労働省によると自殺者の3分の1からアルコールが検出されているといいます。
また、アルコール依存症の人は、そうでない人と比較して自殺の危険性が約6倍高いとされています。
■アルコールの危険性は軽視されがち 「自分は依存症なんてレベルではない」と思う人が多いでしょうが、診断基準のうえでは「毎日、お酒を口にしたくなる人はアルコール依存症」とされます。 日本は世界的に見れば、アルコールに寛容な国です。テレビでは缶ビールや缶チューハイの飲酒シーンのCMがこれでもかというくらい放映されています。どれだけ依存症に苦しむ人がいても、テレビ番組は絶対にアルコールの害を報じません。CMを出してくれるスポンサーに忖度しているからです。 そういった背景もあり、アルコールの危険性は軽視されがちですが、実は麻薬などと同じように怖い物だと知っておく必要があります。 私自身ワインをたしなんでいますし、アルコールは絶対にダメとはいいません。ただ、ご自身の飲み方が依存症的になっていないか振り返っていただければと思います。----------和田 秀樹(わだ・ひでき)精神科医1960年、大阪府生まれ。東京大学医学部卒業。精神科医。東京大学医学部附属病院精神神経科助手、アメリカ・カール・メニンガー精神医学校国際フェローを経て、現在、和田秀樹こころと体のクリニック院長。国際医療福祉大学教授(医療福祉学研究科臨床心理学専攻)。一橋大学経済学部非常勤講師(医療経済学)。川崎幸病院精神科顧問。高齢者専門の精神科医として、30年以上にわたって高齢者医療の現場に携わっている。2022年総合ベストセラーに輝いた『80歳の壁』(幻冬舎新書)をはじめ、『70歳が老化の分かれ道』(詩想社新書)、『老いの品格』(PHP新書)、『老後は要領』(幻冬舎)、『不安に負けない気持ちの整理術』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『どうせ死ぬんだから 好きなことだけやって寿命を使いきる』(SBクリエイティブ)、『60歳を過ぎたらやめるが勝ち 年をとるほどに幸せになる「しなくていい」暮らし』(主婦と生活社)など著書多数。
----------
プレジデントオンライン
最終更新:8/7(木) 16:46