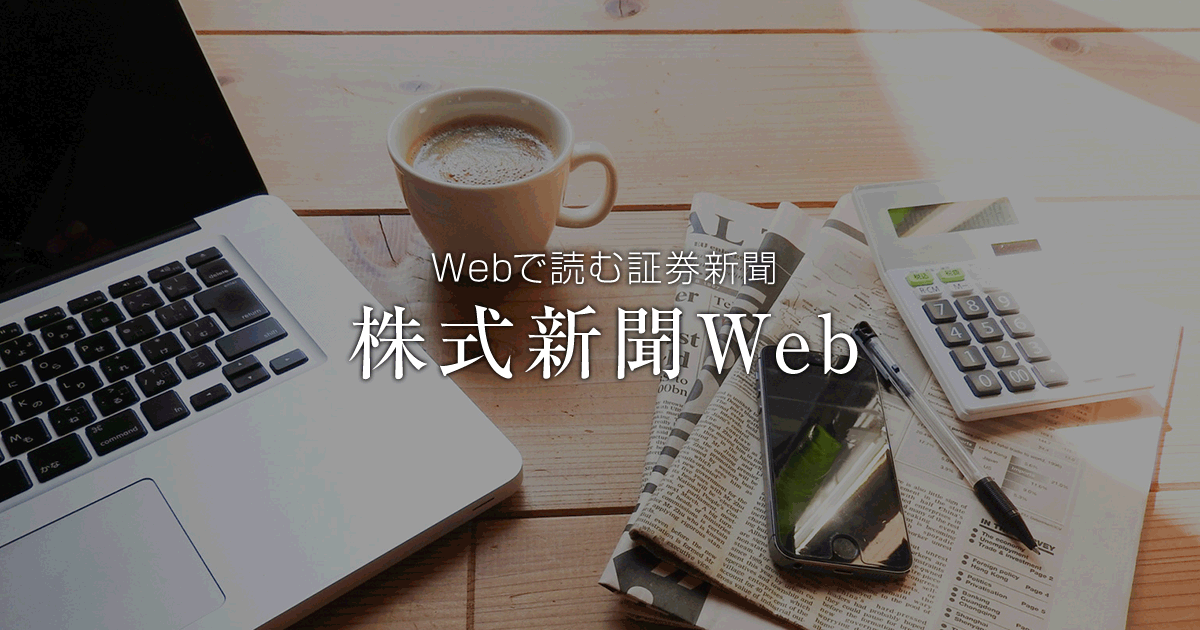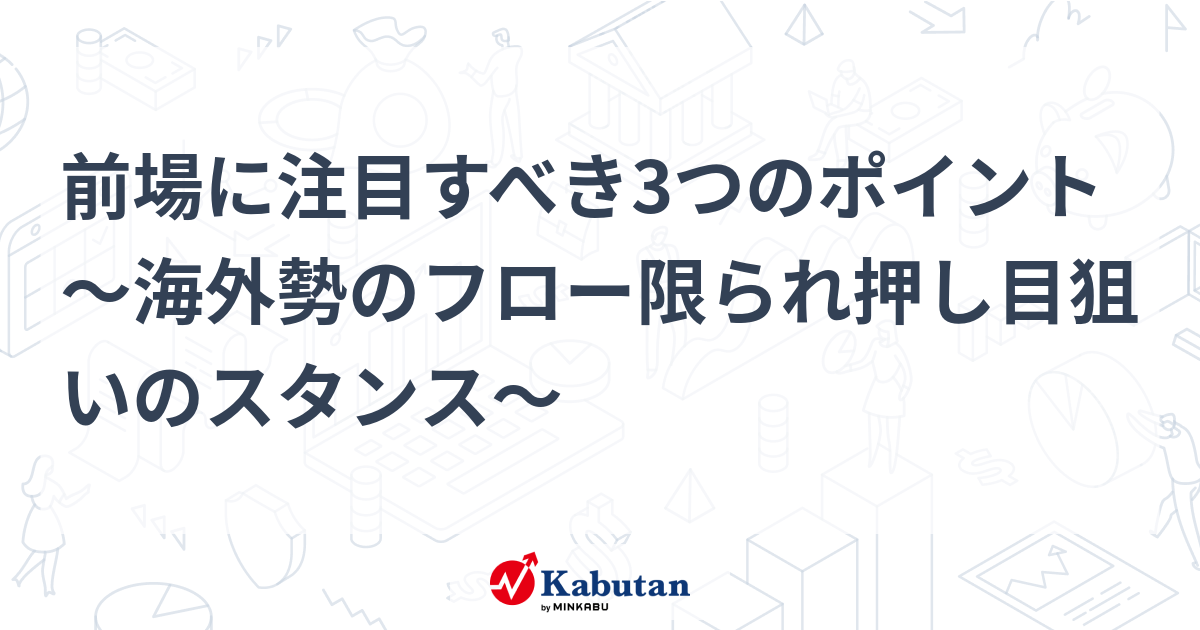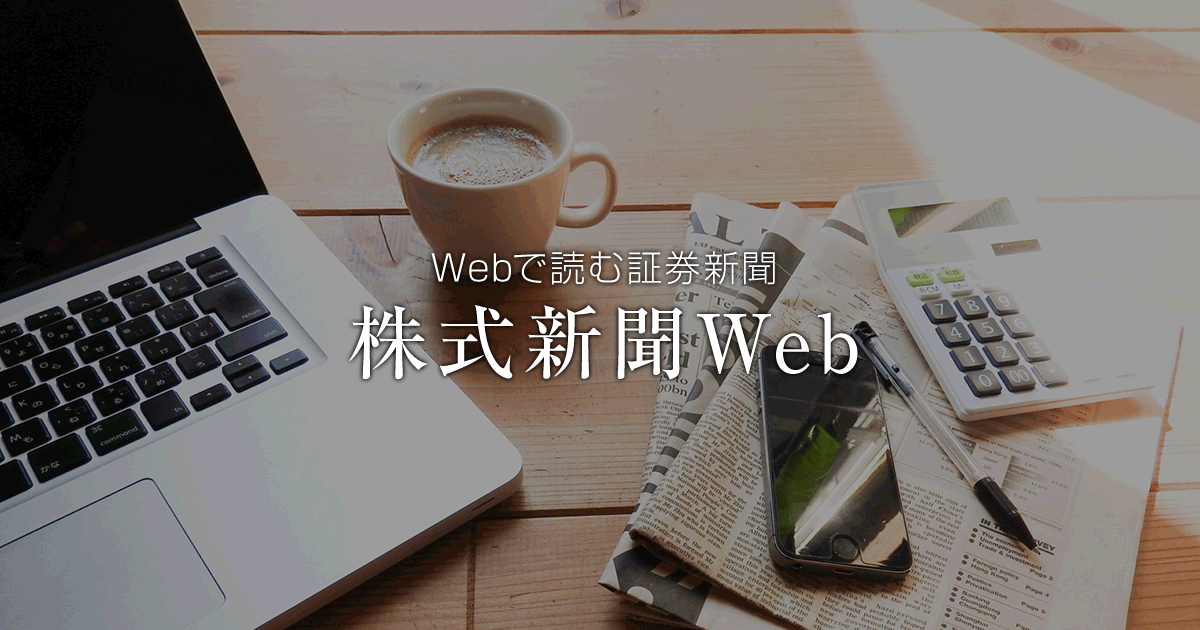【米国市況】主要株価指数が最高値、CPIで利下げへの環境整う

11日の米国株市場では主要指数がいずれも史上最高値を更新した。比較的穏やかなインフレ指標と、雇用の冷え込みを示す統計が重なったことで、米連邦公開市場委員会(FOMC)が今年初めて利下げに踏み切るとの思惑が高まり、買いが膨らんだ。
注目を集めた消費者物価指数(CPI)は、インフレ率が依然としてFOMCの2%目標を上回っているものの、制御不能な水準には至っていないことを示した。同時に発表された新規失業保険申請件数はほぼ4年ぶりの高水準となり、労働市場の急速な減速に対応する形で、FOMCが来週利下げに踏み切るとの見方を一段と強めた。
関連記事:米コアCPI、予想通りの上昇-来週のFOMC控え利下げ期待変わらず (4)
株式 終値 前営業日比 変化率 S&P500種株価指数 6587.47 55.43 0.85% ダウ工業株30種平均 46108.00 617.08 1.36% ナスダック総合指数 22043.07 157.01 0.72%リーガン・キャピタルのスカイラー・ウィナンド氏は「インフレが比較的落ち着いていることが明らかになった。これにより、連邦準備制度理事会(FRB)は労働市場の軟化を食い止めることに、より重点を置けるようになる。来週に0.25ポイントの利下げが行われ、その後さらに年内2回、0.25ポイントずつの利下げが実施されるだろう」と述べた。
モルガン・スタンレー・ウェルス・マネジメントのエレン・ゼントナー氏は「現時点でインフレは重要な副次的テーマではあるが、主役は依然として労働市場だ。この日発表されたCPIは、前日のPPIを相殺するように見えるかもしれないが、雇用情勢の軟化という状況からFRBの目をそらすほど強い数字ではなかった。これは来週の利下げにつながる。さらにその後も利下げは続く可能性が高い」と語った。
パシフィック・インベストメント・マネジメント(PIMCO)のティファニー・ワイルディング氏は「失業保険統計の方が、むしろ大きなニュースだった」と指摘。「FOMCは来週、25ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)の利下げを実施すると予想しているが、50bpの利下げも議論される可能性が高い。年内は合計75bpの利下げを引き続き見込んでいる」と語った。
プリンシパル・アセット・マネジメントのシーマ・シャー氏は「この日の米CPIは新規失業保険申請件数にかき消された。むしろ失業保険申請件数の急増がFRBの判断に一層の緊急性を与えるだろう。パウエル議長は連続利下げを示唆する公算が大きい」とした。
トレードステーションのデービッド・ラッセル氏は「労働市場が弱くなればなるほど、インフレの重要性は低下する」と指摘。「これはバランスの問題であり、物価安定よりも完全雇用のほうに軸足が傾きつつある。今週発表された年間雇用統計の大幅な下方修正や、先週の非農業部門雇用者数の弱い結果を踏まえれば、なおさらその傾向は強まっている」と話した。
国債
米国債相場は続伸。新規失業保険統計が労働市場の軟化を示し、今後数カ月間の利下げ観測が強まり、買いが続いた。
10年債利回りは一時、4月初旬以来初めて4%を割り込み、5年債利回りも今年の最低水準にほぼ並んだ。
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率 米30年債利回り 4.66% -4.0 -0.84% 米10年債利回り 4.02% -2.3 -0.57% 米2年債利回り 3.54% -0.2 -0.06% 米東部時間 16時51分今週実施された中長期債の入札3本のうち、30年債への需要はやや弱めだったが、全体としてはしっかりとした需要が確認され、米国債の上昇基調はおおむね維持された。
失業保険統計は、依然として目標を上回っているインフレに対する金融当局者の懸念を和らげ、来週の会合で今年初となる利下げに踏み切るとの見方を強めた。
一時は、年内の残り3回のFOMC会合すべてで、25bpの利下げが実施されるとの見方が完全に織り込まれた。来週の会合で50bpの大幅利下げが行われるとの観測は、依然としてごくわずかにとどまっている。
今回の経済指標は、来週の金融政策決定に対する市場の織り込みに大きな影響を与えなかったものの、その後の数カ月にわたるフェデラルファンド(FF)金利の下げ幅については、より急な軌道が織り込まれた。
FF金利の誘導目標レンジは、昨年秋以降に3回で計100bpの利下げが実施された後、現在は4.25~4.50%で据え置かれている。
来年前半に期限を迎える短期金利先物の利回りは約6bp低下し、2026年3月末までに25bpの利下げが4回実施されるとの見方が完全に織り込まれた。
PGIMフィクスト・インカムのチーフ投資ストラテジスト兼グローバル債券責任者、ロバート・ティップ氏は「市場全体の見方としては、FRBが雇用面により注目するとの認識が強まっている」と述べた。たとえ慎重な利下げ姿勢だったとしても、「今後1年で100bpの利下げという見通しと、ほぼ整合的に見える」と指摘した。
一方、BNPパリバの米国金利戦略責任者グニート・ディングラ氏は、今回の失業保険統計に対する市場の反応が限定的だった要因として、レーバーデーの祝日に伴うゆがみの可能性や、全体の申請件数が安定している点を挙げた。それでも「最近では、労働市場の弱さを示すあらゆる兆候が、大幅利下げへの道筋を意識させ、市場参加者を警戒させるようになっている」と述べた。
東部時間午後1時に締め切られた30年債入札は、落札利回りが4.651%と、入札前取引の水準と一致。需要がおおむね市場の予想通りだったことを示している。
今週実施された3年債と10年債の入札では、いずれも落札利回りが入札前取引の水準を下回り、利回りが今年最低水準にもかかわらず、強い需要が示された。30年債入札の落札利回りは、今年3月以来の低水準だった。
為替
外国為替市場では、ブルームバーグ・ドル指数が下落。CPIがおおむね予想通りの内容となったほか、失業保険申請件数が急増したことを受け、来週の利下げ観測が一段と強まり、ドル売りが優勢になった。
TDセキュリティーズの通貨ストラテジスト、ジャヤティ・バラドワジ氏は「CPIが上振れせず、失業保険申請件数が増加したため、強含んでいたドルは反転した」と述べた。
為替 直近値 前営業日比 変化率 ブルームバーグ・ドル指数 1197.58 -3.32 -0.28% ドル/円 ¥147.20 -¥0.26 -0.18% ユーロ/ドル $1.1737 $0.0042 0.36% 米東部時間 16時51分対ドルでの円相場はCPI発表直後に一時1ドル=148円17銭まで下げ幅を広げたが、すぐに買いが入り、上げに転じた。一時は146円99銭まで上昇した。
ユーロは上昇。欧州中央銀行(ECB)が政策金利の据え置きを決定し、追加利下げ観測が後退したため、ユーロが買われた。
関連記事:ECB、2会合連続で金利据え置き-リスクはより均衡したと総裁 (4)
原油
ニューヨーク原油相場は4日ぶりに下落。市場見通しの悪化が、地政学的混乱に伴う供給リスクへの懸念を打ち消した。
国際エネルギー機関(IEA)は、2026年に見込まれている記録的な供給過剰はさらに拡大するとの見通しを示した。石油輸出国機構(OPEC)と非加盟産油国で構成するOPECプラスが原油の供給拡大を続ける一方で、同グループ以外の産油国も生産を伸ばしていることが背景にある。この日はまた、米新規失業保険申請件数の増加を受け、米労働市場の減速懸念が強まった。
関連記事:来年の記録的な石油余剰、OPECプラスの増産でさらに拡大-IEA予測
市場では地政学的リスクと供給増加の両方が意識される状況が続いており、原油相場は8月初め以降、ほぼ1バレル=62-67ドルの範囲で推移している。
IEAの石油市場部門責任者、トリル・ボソニ氏はブルームバーグテレビジョンのインタビューで、「市場には余剰が生じつつある一方、供給リスクも存在する」と述べた。
米エネルギー情報局(EIA)は先に、供給過剰が既に進行しており、在庫は7-9月(第3四半期)に膨らむとの予想を示している。
ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物10月限は、前日比1.30ドル(2%)安の1バレル=62.37ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント11月限は1.7%下げて66.37ドル。
金
金スポット相場は下げを縮める展開。CPIと失業保険申請のデータを受け、FOMCが来週利下げに動くとの見方が強まった。
金は今年に入り40%近く上昇し、主要商品の中でも特に好調なパフォーマンスを見せている。米利下げ期待の高まりを背景に、金連動型の上場投資信託(ETF)への資金流入が増え、価格を押し上げている。
関連記事:信頼資産で金に存在感、価格は1980年のインフレ調整後ピーク超え
金スポット価格はニューヨーク時間午後2時25分現在、7.44ドル(0.2%)安の1オンス=3633.31ドル。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は、8.40ドル(0.2%)下げて3673.60ドルで引けた。
原題:Wall Street Rallies as Fed Gets All-Clear to Cut: Markets Wrap(抜粋)
Treasury Yields Near 2025 Lows as More Fed Easing Is Priced In
Dollar Slips After CPI, Claims; Euro Up Post-ECB: Inside G-10
Oil Falls as Weaker Outlook Undercuts Geopolitical Supply Risks