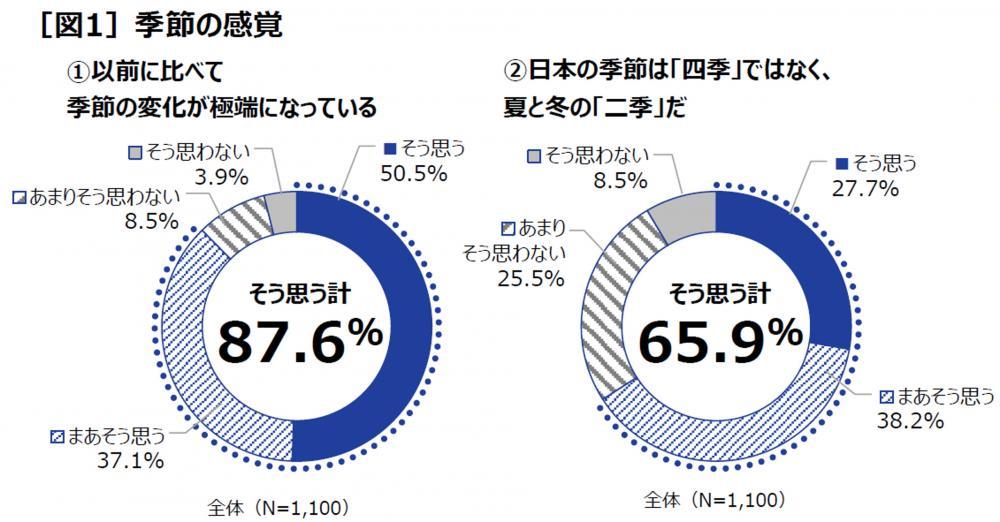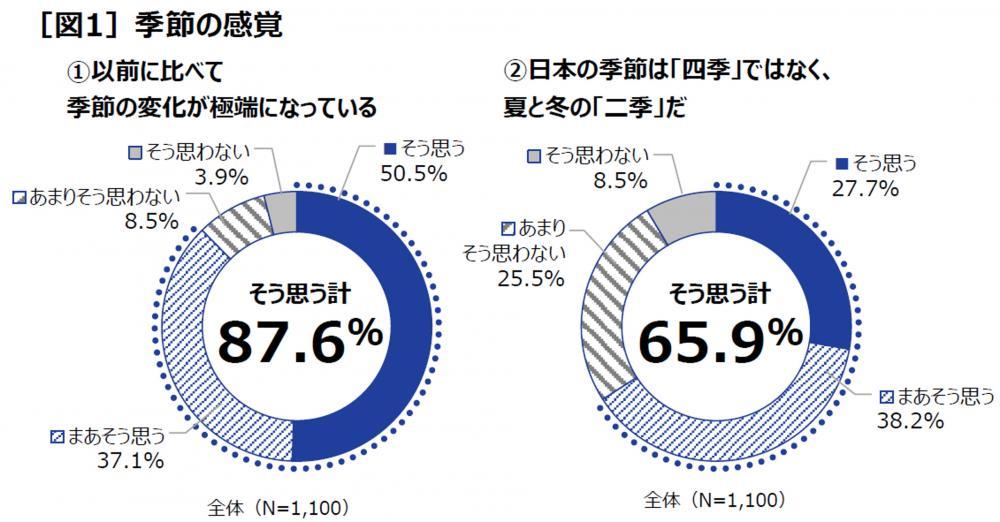9月特集のお知らせ(予告)

9月の特集記事や注目連載をご紹介! 「マイドクター会員」のご登録で、最新記事も過去の記事もすべて読み放題! 健康本のオンライン閲読や電話相談など、盛りだくさんのサービスもご利用できます。
マイドクター会員(有料)とは → ご案内はこちら
\健康長寿に役立つ記事が満載!/ (1カ月無料、まずはお試しください!)
【9月の特集】
背骨から若返る(9月前半公開予定)
60代の4割は「背骨の変形」が始まっている!――背中が丸くなり、腰が曲がってくる姿勢は、見た目の老化に直結し、将来の介護リスクも高くなります。たかが姿勢とあなどるなかれ。自分の立ち姿を見ながら、今からしっかり対策しましょう。
- 第1回 60代の4割に背骨の変形 老け見えの元凶「腰曲がり」のサインに注意
- 第2回 健康長寿のカギは背骨 「知らぬ間に老け見え」防ぐOK習慣、NG習慣
- 第3回 背骨から若返る!腰曲がりを撃退する4つの体操で「背すじがピン」
後悔しない「白内障手術」(9月後半公開予定)
誰もがなる白内障、そして一生に一度きりの白内障手術――手術によって快適な生活を送る人もいますが、知識不足や医師とのコミュニケーション不足から、手術で期待通りの効果を得られない人もいます。後悔しないための基礎知識をお伝えします。
- 第1回 白内障は誰もが通る道 3つの鉄則で進行を抑える
- 第2回 白内障手術は一生に一度きり 後悔しない眼科選びのポイント
- 第3回 白内障手術は若返り手術? レンズ次第で「40代の眼」に戻せる?
【テーマ別特集】
9月のテーマは「酸化ストレス」(9月前半公開予定)
【健康Q&A】
あなたの疑問に専門家が回答! 健康Q&A「足・足指・足の爪」のお悩みに高山かおる先生が答えます(9月後半公開予定)
【注目の連載】
「100年元気」を目指すアンチエイジング学(9月前半公開予定)
古武術式! 日常動作の極意(9月後半公開予定)
快眠の科学(9月前半公開予定)
Dr.ひらまつの「知っておきたい“老化”と“目”の話」(9月後半公開予定)
野口緑の「職場の健康」Q&A(9月後半公開予定)
名医が解説! 最新治療トレンド(9月後半公開予定)
【健康ブック】
9月1日から、以下の書籍をオンライン閲読できます。 健康ブックの詳細はこちら
スポーツ医学的に正しいエクササイズがわかる本
健康づくりのために運動に取り組むことはすばらしいこと。しかし、正しい知識に基づいて行うことが重要です。闇雲に行うと、体を痛めたりケガをしたり、思わぬ結果を招くこともあります。エクササイズを行う目的やその人の運動レベルによって、取り組むべき内容も異なります。
本書はメディカルフィットネス施設の亀田メディカルセンターが実践しているエクササイズの知識を1冊にまとめたものです。ぜひ参考にして、安心・安全なエクササイズに取り組んでください。
イラストでわかる せん妄・認知症ケア
大切な人の様子がおかしい……入院中や手術後など、突然態度が変わってしまうことがあります。あまりの豹変ぶりに驚くことも。その症状は、認知症やうつ病にも見えるし、せん妄とも考えられますが、症状が似ているため判別がとても難しく、対応に苦慮します。
高齢の患者さんでは、かなりの確率でせん妄症状が現れますが、認知症の始まりの場合もあります。本書は、認知症やせん妄についての正しい知識とその違い、ケアの方法、うつなどの症状が現れたときの対応のしかたなどを解説します。
最新版 アトピー性皮膚炎をしっかり治す本
アトピー性皮膚炎の寛解導入、寛解維持のための正しい治療法を専門医が詳しく分かりやすく解説します。患者さんが疑問に思うこと、迷うポイント、勘違いしやすい項目についてもしっかり説明します。
乳幼児から成人までアトピー性皮膚炎を発症してしまったとき、症状が長引いてなかなか治らないとき、再発してしまったとき、「この治療法でよいのかな?」と思ったときに、ぜひ読んでいただきたい一冊です。
*日経Goodayのコンテンツを許可なく複製、編集、翻訳、翻案、放送、出版、販売、貸与、公衆送信、送信可能化などに使用することはできません。日経Goodayで提供しているコンテンツの著作権についてはこちらをご覧ください。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 2
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 3
この記事では、今知っておきたい健康や医療の知識をQ&A形式で紹介します。ぜひ今日からのセルフケアにお役立てください!
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 4
この記事では、今知っておきたい健康や医療の知識をQ&A形式で紹介します。ぜひ今日からのセルフケアにお役立てください!
「熱帯夜における快眠法」に関する問題
【問題】熱帯夜が続く夏に気持ちよく眠るための方法として、以下のうち間違っているものはどれでしょう。
- (1)夏の冷房の推奨設定温度は、26~28℃くらいが妥当とされている
- (2)冷房を一晩中つけっぱなしにして寝るのはよくない
- (3)就寝30分~1時間前にシャワーだけでなく、ぬるめの風呂に入るとよい
- (4)夏は敷布団を少し硬めにすると眠りやすい
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 5
この記事では、今知っておきたい健康や医療の知識をQ&A形式で紹介します。ぜひ今日からのセルフケアにお役立てください!
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 6
この記事では、今知っておきたい健康や医療の知識をQ&A形式で紹介します。ぜひ今日からのセルフケアにお役立てください!
「脳の老化」に関する問題
【問題】脳の老化について、以下のうち正しいものはどれでしょう。
- (1)脳の老化スピードは、個人差が少ない
- (2)脳の老化は、50代から始まる
- (3)脳の機能は、何歳からでも高めることができる
- (4)脳の萎縮は、後ろの領域から前に進む
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 7
潜在患者数約600万人といわれる男性更年期障害(LOH症候群)。女性の更年期のように、あるとき男性ホルモンが急減することで心身にさまざまな不調が表れる。主要な男性ホルモンであるテストステロンはメンタルにも大きく影響するため、意欲の低下や抑うつなど精神的な症状が出ることも少なくない。もしかすると、最近感じている不調は男性更年期障害かもしれない――。第2回となる今回は、男性更年期障害のセルフチェック法、受診の目安、予防・改善の効果が期待できる食事や飲酒・行動習慣について紹介しよう。
(写真:PIXTA)
女性の更年期のように男性ホルモンが急減
女性だけではなく、男性にも更年期障害はある。すべての男性に起こるわけではないが、中には女性の更年期のようにテストステロン(主要な男性ホルモン)の分泌が急減する人がいて、そのため心身にさまざまな不調が表れるのだ。
女性の更年期は閉経前後の約5年間と言われているが、男性の場合は40~70代まで幅広い年代で起こり、医学的にはLOH症候群(加齢男性性腺機能低下症候群)と呼ばれている。国内の潜在患者数は約600万人。厚生労働省が2022年に行った「更年期症状・障害に関する意識調査」によると、40代男性の36.2%、50代男性の42.2%、60代男性の43.9%に男性更年期障害の症状が認められた。
テストステロンは筋肉や骨を強くし、体脂肪を減らす作用がある。そのためテストステロンの分泌が少なくなると、体脂肪が増え、メタボリックシンドロームになりやすい。動脈硬化が進んで脳卒中や心筋梗塞のリスクが高くなり、がんの発症率も高くなる。実際、血液中のテストステロン濃度が低い男性は寿命が短くなることが分かっている(*1)。
テストステロンは肉体や性機能だけでなく、メンタル面にも大きな影響を与えている。「社会性のホルモン」とも呼ばれており、テストステロンが高い男性は、冒険心やリーダーシップがあり、公正さを求め、社会に貢献しようとする気持ちが強くなる。テストステロンが低くなると意欲が衰え、うつ病にもなりやすい(*2)。
LOH症候群の診断基準は「血液中の総テストステロン値が250ng/dL未満、またはたんぱく質と結合していないフリーテストステロン値が7.5pg/mL未満で、かつ何らかの症状を訴える」というもの。診断の際にテストステロン値の計測は欠かせないが、これはあくまで目安であり、より重視されるのは症状のほうだ。
順天堂大学医学部附属浦安病院泌尿器科教授の辻村晃氏によると、「テストステロン値が基準を超えていても、男性更年期障害の症状が強ければ治療対象になる」という。逆に血液検査でテストステロン値が少し低くても、特に不調を感じていなければLOH症候群とは診断されない。
まずは「AMSスコア」でセルフチェック
では男性更年期障害(LOH症候群)になると、どのような不調が表れるのか。肉体的症状では、ほてり、発汗、頭痛、肥満など、精神的症状は不安、抑うつ、不眠、意欲の低下などがある。性機能の症状として、性欲の低下やED(勃起障害)なども挙げられる。最近、「やる気が出ない」「気分が沈む」「朝立ちがなくなった」という人は、テストステロンの分泌が減り、LOH症候群の可能性がある。
LOH症候群の診断で世界的に使われているのは「AMSスコア(男性更年期障害質問票)」だ。さて、あなたはどうだろうか? 次に示すAMSスコアで自分の状態をチェックしてみよう。
*1 Arch Intern Med. 2006 Aug;166(15):1660-1665. *2 Endocr J. 2012;59(12):1099-1105.
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 8
倦怠感や疲労感、気分の落ち込みを感じながらも、「少し体調が悪いだけ」と無理をして生活を送っている男性は、もしかすると更年期障害になっているかもしれない。「更年期障害は女性の病気」と捉えている人も少なくないが、実は男性にも更年期障害はあり、国内の潜在患者数は約600万人といわれている。そこで本特集では「男性更年期障害」とは何か、女性の更年期障害とは何が違い、どのような予防や改善法があるかを解説する。
辻村晃(つじむら あきら)氏 順天堂大学医学部附属浦安病院泌尿器科 教授
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 9
倦怠感や疲労感、気分の落ち込みを感じながらも、「少し体調が悪いだけ」と無理をして生活を送っている男性は、もしかすると更年期障害になっているかもしれない。「更年期障害は女性の病気」と捉えている人も少なくないが、実は男性にも更年期障害はあり、国内の潜在患者数は約600万人といわれている。そこで本特集では「男性更年期障害」とは何か、女性の更年期障害とは何が違い、どのような予防や改善法があるかを解説する。
辻村晃(つじむら あきら)氏 順天堂大学医学部附属浦安病院泌尿器科 教授
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 10
人生100年時代といわれる昨今、年齢を重ねても生涯現役で仕事をしたり、自立した生活を送ったりするためには、身体活動の基盤となる「筋肉」を維持することが欠かせない。特に、加齢によって衰えやすい筋肉は、意識的に鍛える必要がある。本特集では、「いくつになっても動けるカラダ」をつくるうえで必要な衰えやすい部位の筋力トレーニングを紹介する。
町田修一(まちだ しゅういち)氏 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科 教授
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 11
肝臓は生命維持に欠かせない“肝心要”の存在だが、少々機能が落ちたくらいでは自覚症状がない。日本人成人の4人に1人が該当する「脂肪肝」も、痛くもかゆくもないので放置しがちだ。だが、肝硬変や肝臓がんだけでなく、心血管疾患や他臓器がん、糖尿病などさまざまな病気のリスクを上げる元凶でもあることが、近年の研究から明らかになってきた。本特集では、ここ数年で刷新された脂肪肝に関する病気の枠組み変更や、検査値の最新の見方、今すぐ取り組むべき対策など、人生100年時代に知っておきたい「肝臓の新常識」を肝臓のエキスパート・大阪大学の鎌田佳宏氏に聞いていく。
鎌田佳宏(かまだ よしひろ)氏 大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻・生体物理工学講座 病態超音波医学研究室 教授
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 12
腎臓の働きは40歳を過ぎると年に1%ずつ低下していく。ただし、血圧高め、肥満、血糖が高め、といった人は腎臓の老化が速まる可能性も。慢性腎臓病(CKD)と診断されるようになると、心筋梗塞や脳卒中のリスクが上がり、さらに進行すれば人工透析や腎移植が必要になることもある。腎臓の健康を守るには、腎機能低下のサインに早めに気づき予防に努めることが大切だ。本特集では、腎臓を守るための生活改善の新エビデンスや次々と登場している治療薬など「腎臓寿命」を延ばす最新知識を解説する。
猪阪善隆(いさか よしたか)氏 大阪大学大学院医学系研究科 腎臓内科学 教授
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 13
日本の成人の5人に1人が発症する慢性腎臓病(CKD)は自覚症状がないまま進展、場合によっては「透析治療」や「腎移植」が必要になることもある深刻な病気だ。できるだけ早く発見し進展を抑えることが重要となる。ひと昔前には、生活改善が主で治療の選択肢は少なかったが、10年前から新たな治療薬が次々と登場し、「治りにくい病気」から「治る病気」へと認識が変わり始めた。そんなCKD医療の“今”、そして、病気の進展抑制のために実践したい生活改善を紹介する。
(写真:Thanawat/stock.adobe.com)
CKDの薬物治療に起きたルネサンス
「腎機能の働きが少し弱くなっていますね。もしかしたら慢性腎臓病(CKD)かもしれません。一度精密検査を受けてください」。健康診断や⼈間ドックで腎機能の働き方を示すeGFR(推算糸球体ろ過量)の値が低下してきたり、たんぱく尿が見られたりすると健診医はそう指摘するだろう。
「とにかくすぐにでもお医者さんに診てもらわなければ」と受診先探しをする人は多いだろう。だが、「特に自覚症状はないから」「忙しいから」「病院に行かなくても食事や運動など自分でやれることはいろいろあるから」「腎臓病は治らないと聞いたことがあるから」など様々な理由で、受診を先延ばしにする人も意外に多いのではないだろうか。
しかし、腎機能の指標となる「eGFR」が60を切ったら一度は医療機関を受診してほしい(受診先の選び方は後述する)。確かに、第2回で紹介したような「減塩」、今回触れるような「低たんぱく質」など、CKDの進展抑制に有効とされる「生活改善」はいくつかある。それらを実践することでeGFRの低下スピードを落とすことができれば、腎機能をある程度維持し、透析治療を避けることも可能だ。だが、CKDがある程度進むと、生活改善だけでは抑制できず薬による治療が必要になることもある。
実は、近年CKDの医療は大きく進歩している。大阪大学大学院医学系研究科腎臓内科学教授の猪阪善隆氏は「過去10年ほどでCKDの薬物治療にはルネサンスがもたらされました」と解説する。ルネサンスは「再発見」「再生」「復興」を意味する言葉だが、どういうことなのか。
猪阪氏は「CKDの発症と進展の背景には、高血圧、2型糖尿病などの生活習慣病があります。これまではこれらの疾患を治療することでCKDの発症や進展を抑えてきましたが、近年登場した治療薬の中には『腎臓を保護する力』があることが10年間で明らかになりました」と解説する。
例えば、SGLT2阻害薬と呼ばれる薬は2014年に糖尿病の治療薬として登場したが、臨床試験により糖尿病でないCKD患者でも腎機能の低下を防ぐことが「再発見」された。2021年にはCKDを治療目的として認められる薬も出てきており、専門家はこうした動きをCKD治療の「ルネサンス」と呼んでいる。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 14
腎臓の働きは40歳を過ぎると年に1%ずつ低下していく。ただし、血圧高め、肥満、血糖が高め、といった人は腎臓の老化が速まる可能性も。慢性腎臓病(CKD)と診断されるようになると、心筋梗塞や脳卒中のリスクが上がり、さらに進行すれば人工透析や腎移植が必要になることもある。腎臓の健康を守るには、腎機能低下のサインに早めに気づき予防に努めることが大切だ。本特集では、腎臓を守るための生活改善の新エビデンスや次々と登場している治療薬など「腎臓寿命」を延ばす最新知識を解説する。
猪阪善隆(いさか よしたか)氏 大阪大学大学院医学系研究科 腎臓内科学 教授
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 15
年齢とともに腎臓の機能は低下する。生活習慣などでその機能低下が早まった慢性腎臓病(CKD)は、今や5人に1人が発症する国民病になった。CKDと診断されると「自分もやがて透析治療が必要になるの?」と不安になるが、早期なら生活習慣を見直すことで進行を抑えられる。特集の第2回では、CKD対策として優先して行うべき生活改善は何か、最新研究で分かった「腎臓ケアの新常識」を紹介する。
慢性腎臓病の発症予防、進展抑制をしたければ、腎臓をもっといたわろう。(写真:SewcreamStudio/stock.adobe.com)
透析治療の患者数がピークを越えたワケ
「腎臓病が進んでいくと、やがて透析治療が必要になる」――そんなイメージを持っていないだろうか? しかし近年、透析治療を受ける患者の数は減少傾向にある。腎臓が血液をろ過する機能が大きく失われて「慢性腎不全」となり、透析治療にまで至る患者の数はこれまで増加を続けてきたが、2021年の約35万人をピークに減少に転じた。
大阪大学大学院医学系研究科腎臓内科学教授の猪阪善隆氏は「この10年間でCKDの治療が進歩してきたことが大きいといえます。CKD発症・進展の背景にある生活習慣の改善が進み、透析を受ける人がさらに減少すると期待したい」と解説する。
CKDの薬物治療については、発症原因でもある高血圧や糖尿病の治療薬のなかに腎臓の働きを保護する作用のあるものがあることが分かっていたが、近年、臨床研究が進み、現在ではCKDだけの場合でも治療に使える薬剤も出てきた(薬物治療については第3回で紹介する)。
CKD対策の基本は、食事・運動などの生活習慣の改善である。発症予防にも腎機能低下が進むのを防ぐためにも重要だ。
今年、日本腎臓学会と日本医療情報学会はCKDの発症・進展予防に関する世界中の臨床研究を徹底調査。生活改善のエビデンス(検証された科学的根拠)をまとめ、「積極的に予防する!CKD 発症・進展予防のためのマネージメントガイドブック」(以下、ガイドブック)として一般にも公開した。ガイドブック作成の代表研究者を務めた猪阪氏は「減塩、減量といったこれまで提案されてきた生活改善がどれぐらい有効なのか、科学的エビデンスに基づいた『推奨度』をガイドブックに示すことで、人々の生活改善の質を高められたらと思います。その結果として透析治療が必要となる人を大きく減らしたい」と話す。
「積極的に予防する!CKD 発症・進展予防のためのマネージメントガイドブック」 (2025年7月 日本腎臓学会、日本医療情報学会 発行:日本医療研究開発機構)
→日本医療研究開発機構のホームページ こちら からダウンロードできます。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 16
「自分の肝臓は大丈夫か」と心配になったとき、まずチェックするのは健康診断の肝機能の欄だろう。その中でも多くの人が気にするのが「γ-GTP」ではないだろうか。しかし、γ-GTPだけをチェックするのでは不十分。現在、日本肝臓学会は、検査項目の1つ「ALT」が30U/Lを超えたらかかりつけ医を受診するよう推奨している。そもそもALTとは何か? 30U/Lを超えるとどうなるのか? また、脂肪肝かどうかを正確に診断するには超音波による腹部エコー検査なども欠かせない。今回は肝機能値の見方や落とし穴、検査方法などを詳しく見ていこう。
γ-GTPだけで肝機能を判断してはならない
「沈黙の臓器」と呼ばれる肝臓は、辛抱強く、病気が進行してもなかなか症状が出てこない。前回はその理由や、日本人に多い「脂肪肝」の現状について解説した。脂肪肝は、肝臓の脂肪が5%以上になって“フォワグラ化”した状態のこと。近年、脂肪肝の枠組みや呼び名が改められ、肝臓を取り巻く状況は大きく変化している 前回参照 。
日本人は脂肪肝になりやすく、成人の4人に1人が脂肪肝を持つ。そのうち約2割は炎症を起こす「脂肪肝炎」に進み、さらにその1~2割は肝細胞が死んで線維化(詳しくは後述)が進み「肝硬変」へ、さらにその2割が「肝臓がん」を発症すると言われている。さらに脂肪肝があると心血管疾患や他臓器がん、糖尿病のリスクも高まる(詳細は前回を参照)。早く発見して治療や生活習慣改善につなげることが、これらのリスクを低減する上で欠かせない。
肝臓のことが気になったとき、多くの人が最初にチェックするのは健康診断の血液検査だろう(下図)。肝機能の欄には、γ-GTPやALT(*1)、AST(*1)などの項目が必ず記載されている。この中で、多くの人がまず見るのがγ-GTPではないだろうか。γ-GTPはお酒を飲むと上がることがよく知られているだけあって、昔から、「とりあえずγ-GTPだけは見ている」という人が多い。だが、それだけでは不足だ。
50代前半の男性の健診結果例
肝臓のエキスパート・大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻・生体物理工学講座教授の鎌田佳宏氏によると、γ-GTPのみに着目するのは必ずしも適切ではなく、現在、肝臓の専門家がまず見るべきと推奨しているのはALTなのだという。「他の基準値に比べて、ALTは肝障害の状態をストレートに反映するのです。日本肝臓学会では2023年に『奈良宣言2023』を発表しました。肝臓病の早期発見・早期治療を目的にしたもので、ALT値が基準値(30U/L)を超えたら受診することを勧めています」
一方、γ-GTPについて鎌田氏は次のように説明する。「γ-GTPの値は男女でかなり異なり、男性は70程度以下、女性は40程度以下が正常値です。性差が大きいこともあり、γ-GTPのみを肝臓病の指標に使うことはあまりありません。また、胆道の閉塞などにより上昇することがあるほか、γ-GTPが高くないのに肝障害を起こしているケースもあります」
では、ALTはどんな性質の検査項目で、どのくらいがボーダーなのか? 他のASTやγ-GTPはどう見ればいいのか。また近年では、肝臓の線維化の進行度合いを血液検査の複数の項目から推定する「FIB-4インデックス」という指標を取り入れる健診施設が増えている。健診結果で示される数値を使って計算できるので、ぜひ試してみてほしい。ただし、数値だけでは厳密には脂肪肝かどうかは分からない。腹部エコー(超音波)検査なども受ける必要がある。
今回は、肝機能の検査結果の意味や読み方、腹部エコー検査を受けるタイミングなどについて、鎌田氏に詳しく聞いていこう。脂肪肝を早期に見つけ適切な対応をとることは、さまざまな病気を生むリスクを抑える上で極めて重要だ。そのためにもまずこの記事を読んで、自らの状態を適切に把握してほしい。
*1 ALTはGPT、ASTはGOTともいう。健診結果などではALT(GPT)などと併記されていることがある。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 17
肝臓は生命維持に欠かせない“肝心要”の存在だが、少々機能が落ちたくらいでは自覚症状がない。日本人成人の4人に1人が該当する「脂肪肝」も、痛くもかゆくもないので放置しがちだ。だが、肝硬変や肝臓がんだけでなく、心血管疾患や他臓器がん、糖尿病などさまざまな病気のリスクを上げる元凶でもあることが、近年の研究から明らかになってきた。本特集では、ここ数年で刷新された脂肪肝に関する病気の枠組み変更や、検査値の最新の見方、今すぐ取り組むべき対策など、人生100年時代に知っておきたい「肝臓の新常識」を肝臓のエキスパート・大阪大学の鎌田佳宏氏に聞いていく。
鎌田佳宏(かまだ よしひろ)氏 大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻・生体物理工学講座 病態超音波医学研究室 教授
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 18
全身に酸素や栄養を届ける血管は、健康の要。老化すると全身の機能がうまく働かなくなり、心筋梗塞、腎臓病、認知症といった重い病へと突き進む「老化ドミノ」が起こってくる。人生100年時代を健康に生き抜くには、100年機能する若々しい血管を保つことが重要だ。本特集では、血管の老化を予防するために知っておきたい最新情報を、愛媛大学抗加齢医学講座教授の伊賀瀬道也氏に聞いていく。
伊賀瀬道也(いがせ みちや)氏 愛媛大学医学部附属病院 抗加齢・予防医療センター長/ 愛媛大学大学院医学系研究科 抗加齢医学(新田ゼラチン)講座 教授
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 19
血管の劣化がやがて心筋梗塞、脳梗塞などの重大な疾患へとつながっていく「老化ドミノ」。ただし、劣化した血管は生活習慣の改善で再生が可能だ。どうすれば劣化した血管を再生し、老化ドミノを食い止めることができるのか。第3回は、自宅などで簡単に取り組める4つの運動メニューについて、愛媛大学抗加齢医学講座教授の伊賀瀬道也氏に聞いていく。
血管を若返らせるために最も大切なのは運動
血管が劣化していく原因には、加齢、高血糖、高血圧、高脂質、喫煙などさまざまある。このうち加齢は誰もが避けられないが、それ以外の要因は、バランスのよい食事、適度な運動、禁煙などにコツコツと取り組むことで改善することが可能だ。これらの対策は、加齢による血管の劣化のスピードを抑えることにもつながり、「100年元気な血管」づくりにつながっていく。
中でも重要なのが運動だ。
運動をすると、全身の細胞でより多くの酸素や栄養が必要になるため、心臓は拍動回数を増やして、血流を増やす。また、筋肉が伸び縮みすると、筋肉の中にある血管も圧迫と緩みを繰り返し、血液が流れやすくなる。
血流が良くなると、働きが悪くなっていた毛細血管に血液が再び流れ込み、酸素や栄養が体の隅々にまで行き渡るようになる。さらに、血流が増えると血管内皮細胞が刺激を受けて、血管の若さを保つ一酸化窒素(NO)を多く産出する。するとNOの働きによって、硬くなった動脈が軟らかくなり、血管が若返る(血管内皮細胞の働きについては第2回参照)。
筋肉量の増加は、血管を元気にする
運動を習慣化すると筋肉量が増えるが、これも血管を再生するために効果的だ。
「血液中の糖は、筋肉内で最も多く消費されます。そのため筋肉量が減ると糖があまり使われなくなり、血糖値が上がりやすくなります。高血糖の状態が続くと血管が傷つき、動脈硬化のリスクが上がることは、すでにお話ししました(第2回参照)。つまり、運動をして筋肉量が増加すれば、血糖値が上がりにくくなり、血管が傷つきにくくなるわけです」と伊賀瀬氏は説明する。「私たちの研究では、太ももにある大腿四頭筋の断面積が小さいほど、動脈硬化が進行することが確かめられました。筋肉量が多いと血管の老化を抑える効果があることは確かです」(伊賀瀬氏)
運動をすれば、どんなに高齢であっても筋肉量の維持や増加が見込めることは、さまざまな研究で確かめられている。例えばデンマークの研究では、85歳から97歳の11人を対象に筋トレを12週間行った。すると、下半身の筋力が40%以上上がり、大腿四頭筋の断面積は約10%増えたという(*1)。
運動といっても、息が切れて苦しくなるようなハードな運動は必要ない。やや息が弾み、体が少し温まる程度の強度の運動で十分だ。「大切なのは、ケガをするリスクが少なく、継続しやすいものであるということです。そこで私どもの抗加齢ドックでは、年齢や運動経験を問わず取り組めて、日常生活に組み込みやすい以下のようなメニューを推奨しています」(伊賀瀬氏)
抗加齢ドックが推奨する「血管再生リハビリ」とは?
伊賀瀬氏らが「血管再生リハビリ」として推奨している運動メニューは、以下の4つだ。
愛媛大学抗加齢ドックが推奨する「血管再生リハビリ」
- (1)ニコニコ歩き … 笑って会話ができるくらいの早歩き
- (2)片足立ち … 片足を上げて1分間キープ
- (3)かかと上げ … かかとの上げ下げを繰り返す
- (4)ゆるジャンプ … 8秒ジャンプを繰り返す
(イラスト:内山弘隆)
それぞれの運動の実際については以下に説明していくが、中でも最も効果が高いのは「ゆるジャンプ」だと伊賀瀬氏は話す。「ゆるジャンプは、私自身が不摂生のために体重が増え、最高血圧が180mmHgになっていた時期に実行して、すごく効果がありました。朝・昼・晩に約10セット(100回)ずつ跳んで、途中からは歩く量を増やしたり、食事にも気をつけたりした結果、1年間で10kgの減量に成功し、血圧も薬なしで130mmHg未満に安定するようになりました」と伊賀瀬氏は言う。
「ただし、ゆるジャンプはこれら4つのメニューの中で一番運動強度が高いので、できないときは、くれぐれも無理をしないでください。大人になるとジャンプをする機会はほとんどありませんから、いきなりやろうとしてもなかなかできません。普段あまり体を動かしていない人は、ニコニコ歩きから始めてください」(伊賀瀬氏)
*1 Kryger AI, et al. Scand J Med Sci Sports. 2007 Aug;17(4):422-30.
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 20
全身に酸素や栄養を届ける血管は、健康の要。老化すると全身の機能がうまく働かなくなり、心筋梗塞、腎臓病、認知症といった重い病へと突き進む「老化ドミノ」が起こってくる。人生100年時代を健康に生き抜くには、100年機能する若々しい血管を保つことが重要だ。本特集では、血管の老化を予防するために知っておきたい最新情報を、愛媛大学抗加齢医学講座教授の伊賀瀬道也氏に聞いていく。
伊賀瀬道也(いがせ みちや)氏 愛媛大学医学部附属病院 抗加齢・予防医療センター長/ 愛媛大学大学院医学系研究科 抗加齢医学(新田ゼラチン)講座 教授
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 21
食の知識について「常識」だと思っていたものが、実は違っていたり誤解だったりすることがある。また新たな研究発表により、しばしば情報がアップデートされる。この連載では、生活に取り入れたい食の新常識について幅広く紹介する。
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 22
「畑の肉」と呼ばれる大豆は、死亡リスク低下や認知機能の維持、動脈硬化予防といった「健康長寿」に関わる様々な働きを持つことが、日本人を対象とした複数の研究で明らかになっている。日々の食事に大豆製品を取り入れることが、健康長寿の実現につながる。後編では、そんな大豆に期待される健康効果を詳しく紹介しよう。
>前編 「畑の肉」大豆の魅力はたんぱく質だけではない 発酵でより健康的に
(写真:PIXTA)
大豆は「畑の肉」と呼ばれるほど、植物性たんぱく質が豊富な食材だ。それだけでなくビタミンB群や食物繊維も多く含まれ、さらに、健康効果が期待される「機能性成分」も含まれる。そんな栄養豊富な大豆だが、実は、その力は「発酵」によってより強化される。「抗酸化作用アップ」や「栄養素の吸収率アップ」、「複数の栄養素の含有量アップ」といった効果が発酵にはあるのだ。
前編では、大豆やその発酵製品の栄養価や機能性成分、摂取を意識したいタイミング、食べる際のおすすめの組み合わせを紹介した。後編となる今回は、大豆に期待される健康効果や、過剰摂取リスクの有無などを紹介しよう。
死亡リスクが大幅減?研究で60%以上低下
まず注目したいのは、死亡リスクとの関連だ。大豆は、寿命と密接に関わる死亡リスク低減との関連が見られている。
豆類・大豆製品や、大豆に含まれるイソフラボンの健康効果を研究する徳島大学大学院医歯薬学研究部講師の中本真理子氏は「愛知県大府市・東浦町に住む中高年者2136人を対象にしたコホート研究(*1)では、大豆製品やイソフラボンの摂取はその後約20年の死亡リスクを大幅に減らす可能性が示唆されました」と話す。国立長寿医療研究センターが20年以上にわたって実施する日本人を対象とした疫学研究(NILS-LSA:国立長寿医療研究センター・老化に関する長期縦断疫学研究)の第1次調査参加時に中年(40歳以上60歳未満)だった人において、豆腐や油揚げ、納豆、味噌などの大豆製品やイソフラボンを積極的に摂取している人たちは、摂取量が最も少ない人に比べて、全死亡リスクが60%以上低下したのだ。
この集団では、特にがんや心血管疾患で亡くなる人が多かった。中本氏は「抗酸化作用を持つイソフラボンを含む大豆製品を摂取することが、がんや心血管疾患リスクを抑える可能性があると考えています」と話す。
研究では、年齢やBMI、性別、学歴、雇用状況、既往歴、喫煙、アルコール摂取量、総エネルギー摂取量といったデータも考慮して解析したが、これらを調整した後も、大豆製品の摂取と全死亡リスクの低下は関連していた。さらに、サブ解析では、野菜、果物、魚などの健康によいとされるほかの食品の摂取量を調整した場合でも、大豆製品の摂取は全死亡リスクの低下に寄与していた。
イソフラボンは大豆だけでなく、様々な食品に含まれる。興味深いことに、食事全体から算出したイソフラボン摂取量で見ると、摂取量が増えれば増えるほど全死亡リスクが低下するわけではなく、適度な摂取が最もリスクを低くし、最も多い場合ではリスクがわずかに上昇する傾向が見られた。
つまり、死亡リスクは、イソフラボンを多くとればとるほど低減するというわけではない、ということだ。
中本氏は「大豆製品にはイソフラボンだけでなく、食物繊維やビタミン、その他の栄養素や機能性成分が含まれています。それらが相乗的に働くことが、健康長寿と関連しているのかもしれません」と指摘する。
*1 Eur J Clin Nutr. 2021 Dec; 75(12): 1781-1791.
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 23
食の知識について「常識」だと思っていたものが、実は違っていたり誤解だったりすることがある。また新たな研究発表により、しばしば情報がアップデートされる。この連載では、生活に取り入れたい食の新常識について幅広く紹介する。
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 24
日経Goodayでは日々、新しい健康・医療情報をお届けしています。その中で、読者のみなさまが今、最も気になっているテーマ、例えば、「大腸がん」「脂肪肝」「痛風・尿酸値」「男性ホルモン」などに関する多数の記事の“エッセンス”をすばやく知りたい――。そんなニーズにお答えする新サービスを開始します。
それが「テーマ別特集」です。毎月、読者のみなさまの関心が高かったテーマをチョイスし、特に好評だった記事のポイントを編集部でピックアップしてお届けします。そのテーマ、ジャンルについて知っておくべきことが、この記事を読むだけですべて把握できます。さらに、そのテーマに関する記事一覧もご用意しました。ご活用ください。
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 25
全身に酸素や栄養を運ぶ血管は、健康維持の土台となる重要な存在だ。しかし、血管が老化すると体のさまざまな機能が低下し、心筋梗塞や腎臓病、認知症などの重篤な病気へと進行する「老化ドミノ」が引き起こされる。人生100年時代をすこやかに過ごすためには、若々しくしなやかな血管を長く保つことが不可欠だ。本記事では、血管の老化予防に役立つ最新の知見を、これまでの人気記事をもとに分かりやすく紹介する。
テーマ別特集「血管」 この記事の主な内容 血管の老化で一番怖いのは動脈が硬くなること 血管が傷む原因 高血糖と高血圧、どちらが危険? 血管を若返らせるために最も大切なのは… 熱すぎずぬるすぎず、10分間のゆったり入浴で血流アップ血管の若さが寿命を決める
人間の体には、脳、心臓、肺、肝臓、腎臓など、生命維持に不可欠な臓器が数多く存在する。これらの臓器へ酸素や栄養を送り届け、老廃物を回収する役割を担っているのが、全身に張り巡らされた血管である。
図1 全身に張り巡らされた血管
血管は全身の隅々まで酸素や栄養を届け、老廃物を回収する重要な役割を担っている。(イラスト:matis75/stock.adobe.com)
血管が劣化し、その機能が低下すると、全身の細胞に酸素や栄養が十分に行き届かなくなり、老廃物の回収も滞る。その結果、体全体の働きに支障をきたすことになる。また、血流が悪化し、血管の壁の内部にプラークと呼ばれる柔らかい塊(コレステロールなどが袋状になってたまったもの)が形成されると、やがて脳梗塞や心筋梗塞といった重篤な疾患につながる。年を重ねても健康を維持するためには、全身の臓器を支える血管を若々しく保つことが極めて重要である。
本記事では、血管の老化はどのように進むのかや、血管の老化を予防するための最新知見について、過去の人気記事をもとに紹介する。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 26
日経Goodayでは日々、新しい健康・医療情報をお届けしています。その中で、読者のみなさまが今、最も気になっているテーマ、例えば、「大腸がん」「脂肪肝」「痛風・尿酸値」「男性ホルモン」などに関する多数の記事の“エッセンス”をすばやく知りたい――。そんなニーズにお答えする新サービスを開始します。
それが「テーマ別特集」です。毎月、読者のみなさまの関心が高かったテーマをチョイスし、特に好評だった記事のポイントを編集部でピックアップしてお届けします。そのテーマ、ジャンルについて知っておくべきことが、この記事を読むだけですべて把握できます。さらに、そのテーマに関する記事一覧もご用意しました。ご活用ください。
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定