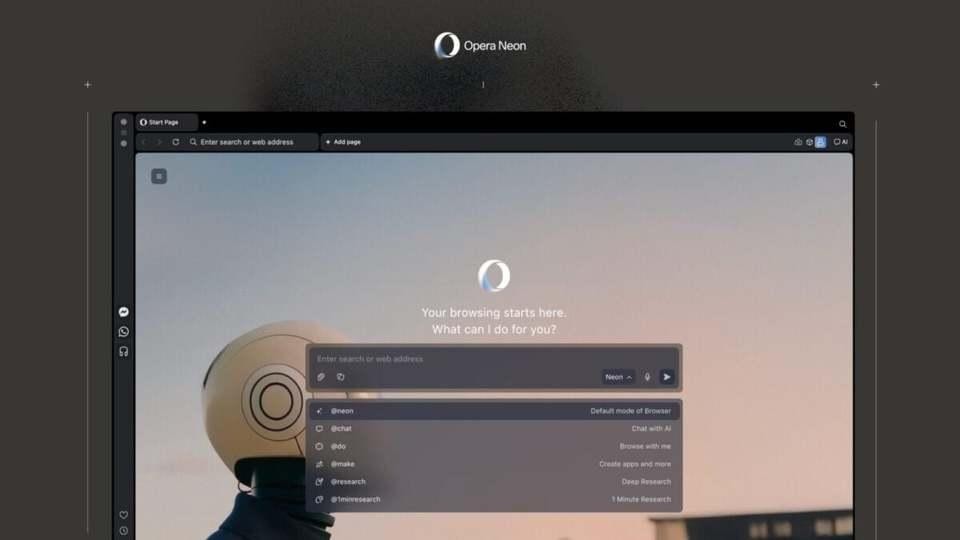“奇跡の村”に移住者270人 ベンチャー企業も続々 消滅可能性自治体から脱却のワケ

岡山県の北東端に位置し、鳥取県と兵庫県に隣接する西粟倉村は、のどかな自然が広がっている。およそ58平方キロメートルと、東京・世田谷区ほどの広さだが、村の95%を森林が占めている。 国定公園の特別保護地区に指定されている若杉原生林。中国地方でも有数の天然樹林で、およそ200種類の植物が生息する自然の宝庫は、1986年に森林浴の森百選に選定されている。 森の自然に囲まれながらの露天風呂は格別。 山間部にある西粟倉村は、コンビニは1つもなく、信号機も2基しかない。人口1300人ほどの小さな村だ。 明治時代から林業で栄えていた西粟倉村だが、昭和40年代を境に人口も減り、森は荒れ放題に。基幹産業である林業は廃れ、財政難に陥っていた村に浮上したのは市町村合併。しかし、住民の6割が反対し、村として独立の道を歩んできた。 そんな消滅寸前だった村が一転、移住者の数が274人にまで増加し、人口の20%を占めるほどに。 さらに去年は、消滅可能性自治体から脱し、若年女性人口の減少率が10ポイント以上も改善されたのだ。 なぜ移住者が増えたのか?そこには、森林が荒れ過疎にあえいでいた村に風穴を開けた、起業家の存在があった。
西粟倉村出身の、木の里工房 木薫・代表取締役の國里哲也さん(52)。案内された先には、間伐材で作られた自然な木の温もりがあふれるオーダーメイドの子ども用の椅子があった。 「これはヒノキの間伐材で作っています」 間伐材とは、森の成長を促すために木々を伐採し、間引いたことで出る木材。細い木や曲がっている木が多いため、建築資材として多くは売り物にならず、価値がほとんどなかったという。 「当時は全然。『間伐材で家具作っています』って言うと、逆に悪いように言われたこともあった。『お前ら、ごみでモノを作って売ってるのか』って…」 それでも、価値がほとんどなかった間伐材に目を付け、さまざまな家具の製造を始めた國里代表取締役。子どもが遊ぶ滑り台や巨大な遊具まで。 木の温かみが子どもに優しいと口コミが広がり、東京など全国およそ400の保育園などから注文が殺到。年間の売上が3億円にまで成長し、タダ同然だった間伐材に大きな価値が生まれたのだ。 「間伐して切った木をお金に換えて。うちがキッカケというか、ヒントになったのかもしれない」 國里さんが始めた間伐材の利用をヒントに、村は2008年、森の木を生かして財政難を解決する方針に舵を切ることにしたが、そこにはある問題が生じた。山には複数の所有者がいたため、森林整備が進められなかったのだ。 そこで村は、山林所有者に利益を還元する条件で山を預かり、森林整備を進められる仕組みを構築。そうすることで、価値を生み出す間伐材を大量に集めることに成功したのだ。 心身ともに疲れた身体を癒やす温泉。14℃という低い温度で湧き出ているため、これまで灯油を使って温めていたのを、間伐材を使った薪(まき)のボイラーに変更。 温泉の従業員 「(Q.薪ボイラーに替えて経費の節約になった?)10分の1ぐらいしか使っていないと思います」 西粟倉村役場・産業観光課 妹尾辰郎主事 「村にあるもので地域内で循環させて活用していく」 村営施設では、細かくチップ状にした間伐材を燃やした熱でお湯を作り、その熱を村内6カ所にある施設の空調に利用。そのうちの一つが8年前に間伐材を使って新設された保育園。子どもたちは心地よい風のとりこに。 園児 「ここ風出てる」 「あったかーい」 この保育園は、若い世代の移住者の増加に伴い新設され、園児のおよそ7割が移住者だという。
Page 2
274人もの移住者を呼び込んだ西粟倉村。間伐材を使ったビジネスに価値が見いだされ、県外からも次々とベンチャー企業が集まってきている。 9年前に神奈川から移住 (株)エーゼログループ 野木雄太さん(31) 「木のことを勉強したいと思って。西粟倉で林業で面白いことをしているというのを聞いて」 16年前に東京から移住して、西粟倉村で起業した(株)エーゼログループ・牧大介代表取締役CEOはこのように話す。 「(間伐材などの)木材加工をやっているので、木くずがたくさんの工場から出ますので、それを活用していくことができないかということを模索しているなかで、イチゴを作る」 広さ30アール=およそ900坪のハウスで、7種類のイチゴを栽培している。 (株)エーゼログループ 栽培担当 原田壮太朗さん(29) 「一見、イチゴと木材って関係ないように思われるんですけど、樹皮やおが粉を培土に使用しています」 間伐材の木材加工品を製造する過程で発生する、樹皮やおが粉を培土に使用。本来捨てていたものが有効活用され、空気をたっぷり含んだ土になるという。 今年は例年に比べて収穫量も多いというイチゴ。 兵庫・宍粟市から来たイチゴ狩り客 「うわ、また大きい。これ」 「うん、すごく甘くておいしいわ。甘くても優しい甘さ」 牧代表取締役CEO 「この村にあるもので、何か価値を生んでいけないかと試行錯誤を重ねていったなかで、森があって林業があって木材加工業があるからこその、イチゴに」
森を使って起業をした、別の移住者もいる。 5年前に東京から移住 Reml Behn代表 黄塚森さん(37) 「この山に自生している、元々生えている木に咲く花から集めてきた蜜がここに集まって、ハチミツになっていく」 5年前に東京から移住した、黄塚さん。養蜂場では、最大70の巣箱、150万匹以上のハチを飼育している。 黄塚さんは、前職は経営コンサルタント会社の執行役員をしながら、早稲田大学の非常勤講師をしていた。なぜ未経験の養蜂家として起業したのか? 「(前職では)ビジネスを伸ばすことをやっていたけど、経済活動をちゃんと回しながら自然を増やすことがやりたいと思って、移住してきました」 西粟倉村の森に咲く花の蜜から採れた自然の味そのままを閉じ込めた「純粋蜂蜜」。 ハチミツを焼き込んだグラノーラや、クラッカーとの相性は抜群。収益の一部を多様性の豊かな森づくりに還元しているという。 「ハチミツも本当に色んな味があって、その地域の自然の形を表しているというか、すごく面白い」