若者を狙う詐欺が増えている ― 犯罪心理学が明かす“だまされる心理”と実例
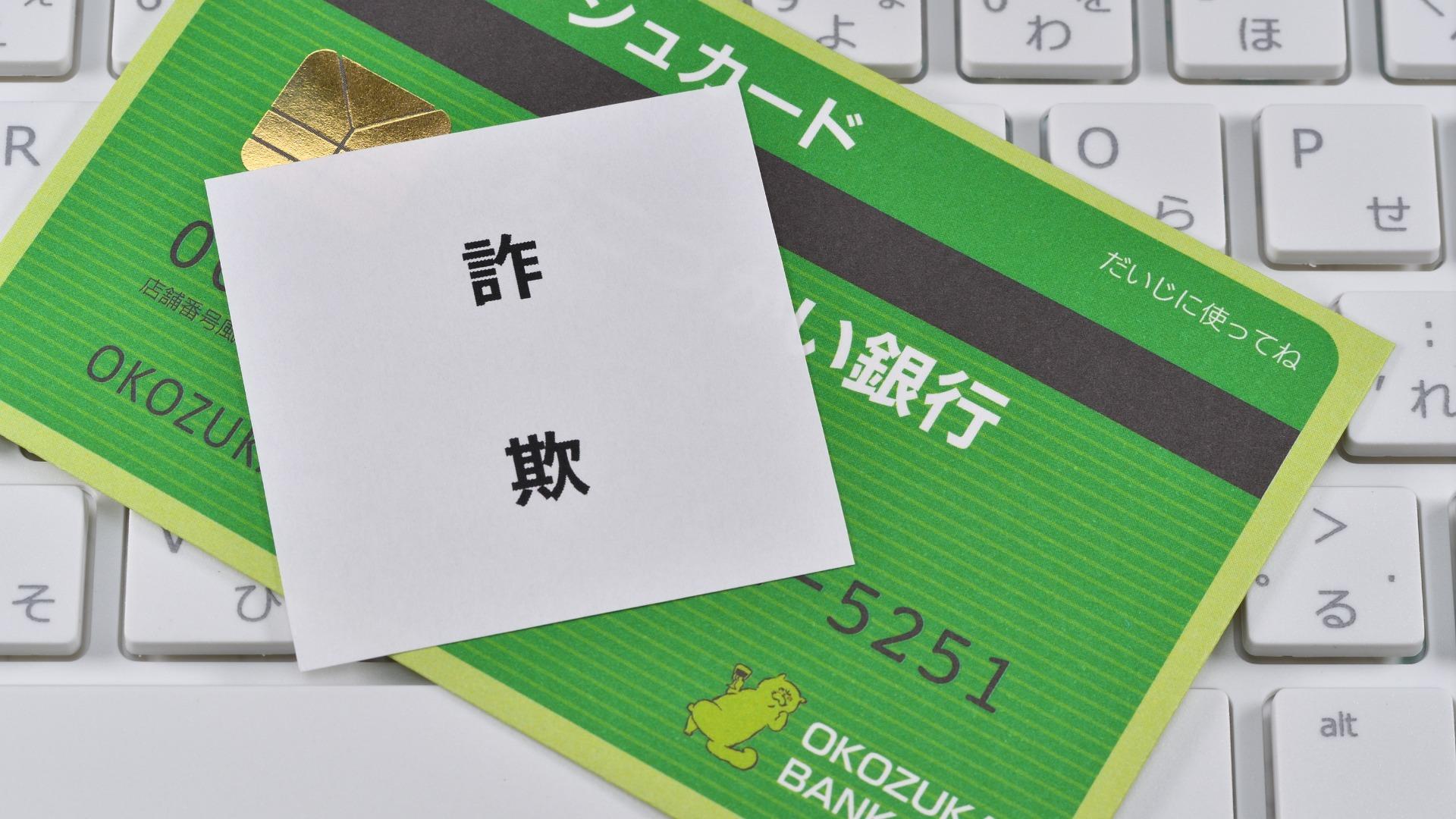
近年、日本における特殊詐欺(振り込め詐欺や警察官をかたる詐欺など)の被害は、かつて高齢者中心だったものが、次第に「若年層」にも拡大しています。警察庁や各地の調査でも、20代や30代の被害が増えていることが報告されており、SNSを介した投資詐欺や「警察官なりすまし」型の手口が広がっていることが背景にあります。
警察庁広報資料(2025)正常性バイアス ― 「自分は大丈夫」という思い込み
人は「自分には被害は及ばないだろう」と考える傾向があり、これを「正常性バイアス」と呼びます(Mileti & O’Brien, 1992)。若者はデジタル機器に慣れているため、「高齢者はだまされるが自分は大丈夫」という過信を持ちやすいといえます。
ところが詐欺師は、若者が油断するSNSや投資広告など、まさに身近な環境に罠を仕掛けてきます。
警察庁の「特殊詐欺及び SNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等」によれば、最近は詐欺の最初の接触が、電話ではなくYouTubeのバナーやSNS のダイレクトメッセージ、マッチングアプリなどが増えているとのことです。また、偽の権威証明書(警察手帳など)の提示による「偽警察官詐欺」も増えているとのことです。
このようなオンライン・デジタル技術を組み合わせた複雑な手口によって、普段からスマホ・SNSを使い慣れている若者が、むしろ狙われやすくなっていると考えられます。
実例1
SNSを通じて「投資すればすぐに儲かる」と持ちかけられ、兵庫県内の男子大学生が消費者金融で借りた資金を含む100万円を失ったと報じられています(朝日新聞, 2024年4月23日)。本人は「自分は被害に遭わない」と思っていたものの、短期的な利益への期待から冷静な判断を欠いてしまったのです。
権威バイアスと社会的証明
心理学の研究は、人は「権威ある者」に従いやすく、また「多くの人がやっている」という情報に安心感を覚えることを示しています(Cialdini, 2009)。詐欺師はこの傾向を利用し、警察官や銀行員を装ったり、投資詐欺ではSNSで多数の「成功者の声」を偽造したりします。
実例2
茨城県では、警察官をかたる詐欺が多発し、2024年1〜8月だけで16件、1.7億円超の被害が確認されました。被害者には20代の若者も含まれており、最も多かったのは30代(7件)でした。従来の「高齢者のみが狙われる」というイメージが覆されています。(茨城新聞, 2024年9月12日)。
即時報酬と遅延価値割引
人は将来の大きな利益(遅延大報酬)よりも、目先の小さな利益(即時小報酬)を重視する傾向があります。これを「遅延価値割引」と呼びます(Ainslie, 2001)。若者は経済的基盤が不安定な場合も多く、「短期間で大きな利益」という誘いに惹かれやすいのです。
実例3
茨城県の消費生活相談では、SNSで知り合った先輩から「USB教材を買えば誰でも儲かる」と勧誘され、20代男性が消費者金融から借金して契約金を支払った事例が報告されています。実態はマルチ商法であり、友人勧誘まで求められる典型的な被害でした(茨城県生活文化課, 2024年)。
承認欲求と孤立
SNS時代の若者は、つながりや承認を強く求めます。Twenge & Campbell (2018)が論じるように、承認欲求が強い環境では「特別扱い」や「限定性」に弱くなります。詐欺師は「あなたにだけ」「特別なメンバーに招待」といった文言を巧妙に使い、優越感と孤立感を同時に利用して判断力を鈍らせます。
防止策と心理教育
詐欺の防止には、単なる注意喚起では効果は期待できません。詐欺師は上に述べたようなさまざまな人間心理を巧みに悪用しているからです。
予防策の1つとして、疑似体験型の教育が有効であることが示されています。Modic & Lea (2013)は、詐欺のシナリオを体験することでリスク認知が高まると報告しています。実際、日本でも大学で生成AIを用いた「詐欺疑似体験授業」が導入され始めています(KBSニュース、2025年6月18日)。
また、若者が「自分もだまされ得る」と理解し、権威や多数派情報を無条件に信じない態度を養うことが重要です。そして、不審な誘いを断ることができるスキルを育てる必要があります。これも、ロールプレイングなどを用いて教育することが有効です。
詐欺被害の若年化は、単なる知識不足ではなく、人間が持つ心理的脆弱性と現代の社会環境が重なって起きています。正常性バイアス、権威バイアス、遅延価値割引、承認欲求――これらは誰もが持つ傾向です。上に挙げた例は、その現実を如実に物語っています。
誰もが詐欺の被害に遭わず、安心して生活できる社会をつくるためには、「だまされ得る自分」を理解させる体験型心理教育と、被害後に声を上げやすい相談体制の整備が不可欠です。
参考文献
- Ainslie G (2001). Breakdown of will. Cambridge University Press.
- Cialdini RB (2009). Influence: Science and practice (5th ed.). Pearson.
- Mileti DS & O’Brien PW (1992). Social Problems, 39(1), 40–57.
- Modic D & Lea SEG (2013). Journal of Economic Psychology, 34, 486–495.
- Twenge JM & Campbell WK (2018). The narcissism epidemic: Living in the age of entitlement. Atria Books.



