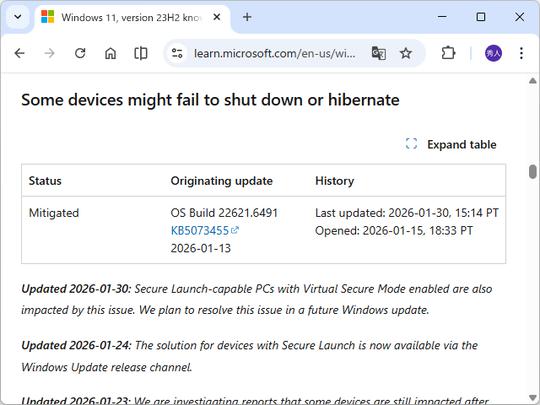「GPT-5は期待外れ、でも立ち止まれない…」AI開発の限界が囁かれる中、巨大IT企業たちが仕掛ける「最後の賭け」の行く末(小林 雅一) - 3ページ目

このOpenAI、ひいては同社と激しく競い合うグーグルやメタなどビッグテックはこれら桁外れの資金を投じて、いったい何をやろうとしているのだろうか?
当面の狙いは、(OpenAIの)ChatGPTや(グーグルの)Geminiなど既に商品化されているチャットボット用のAIインフラの拡充だ。現在の数億人から、いずれは十数億人、数十億人へと拡大する世界的なユーザー増加に対処するには、確かに単年で数千億ドル(数十兆円)もの巨額投資が必要になるかもしれない。
が、彼らアメリカの巨大IT企業が最終的に目指しているのは、我々人間の知能に匹敵する「AGI(汎用人工知能)」、あるいはそれを上回る「ASI(人工超知能)」などと呼ばれるスーパー・インテリジェンスの実現だ。
これに関する彼らの競争意識は常軌を逸している。一説によれば、グーグルの共同創業者で未だにその経営に隠然たる影響力を有するラリー・ページ氏は(将来のAGIを念頭に)「AIの開発競争で競合他社に負けるくらいなら、むしろ我が社を倒産させ(るくらいにお金を使っ)た方がマシだ」と社内で述べたとされる。
一方、メタの共同創業者・CEOのマーク・ザッカーバーグ氏は、(スーパー・インテリジェンスの実現に向けて)OpenAIやグーグルなどライバル企業のAI開発者らに総額数十億ドル(数千億円)の報酬パッケージを提示して、これらの人材を引き抜こうとするなど、なりふり構わぬ攻勢に出た。
https://gendai.media/articles/-/156720
Photo by gettyimages彼らはなぜ、そこまでしてAGI(あるいはASI)への一番乗りを果たしたいのだろうか?
ここからは想像に任せるしかないが、恐らくは「歴史に名を残したい」という功名心、あるいは「強大なパワーへの渇望」などが主な動機かもしれない。AGI(ASI)というスーパー・インテリジェンスの実現は、18~19世紀の蒸気機関など産業革命を遥かに凌ぐ経済的インパクトを持つと同時に、将来の国際政治を左右する点において核兵器に匹敵する地政学的な主要因子になると見られるからだ。
人工超知能はどのように実現されるのか?
しかし、これらAGIやASIの実現は一筋縄ではいきそうもない。そもそも「人工的に」再現されるはずの、私たち人間の知能すら現時点では厳密に解明されていないのだ。
たとえば過去の「ビネー式」や現在の「ウェクスラー式」など一般に知られている知能テストでは、人間の知能を「言語理解」「知覚推理」「ワーキングメモリ(短期・長期記憶)」さらには「処理速度」など、いくつかの知的要素に分け、それらの検査結果を総合して、いわゆるIQ(知能指数)を算出する。が、これらは所詮恣意的な分類に過ぎず、実際の知能がこれら知的要素の集積で実現されるという証拠は存在しない。
一方、OpenAIやグーグルなどAI開発の第一線で活躍する研究者・技術者らは、AGIやASIなどの人工的な超知能を実現する上で、(上記のような)「個々の知的要素を一つずつ実装して足し合わせる」というアプローチを採用していない。
むしろ「(脳の神経細胞を数学的に模倣した)ニューラルネットワーク」など数理的かつ統一的な枠組みの中で、人間の「知能」や「創造性」などの知性が半ば自然発生的に現れる「創発(emergence)」と呼ばれる現象に彼らは期待をかけているようだ。
その背後にあるのが一般に「スケール則(Scaling Law)」と呼ばれる考え方で、これは2010年代の後半にグーグルやOpenAIなどの研究チームによって発見・確立された経験則である。
スケール則に従えば、ChatGPTをはじめ生成AIのベースにある大規模言語モデル(LLM)は、その規模(パラメーター数)や機械学習に必要なデータ量、そこで必要とされる(GPUなど)コンピューティング資源の量を拡大していけば、その性能もどんどんアップしていく。
その過程で、当のAI開発者ですら予想できなかった「AIの推論能力」など、各種の知的能力が「創発」によって育まれていったのである。