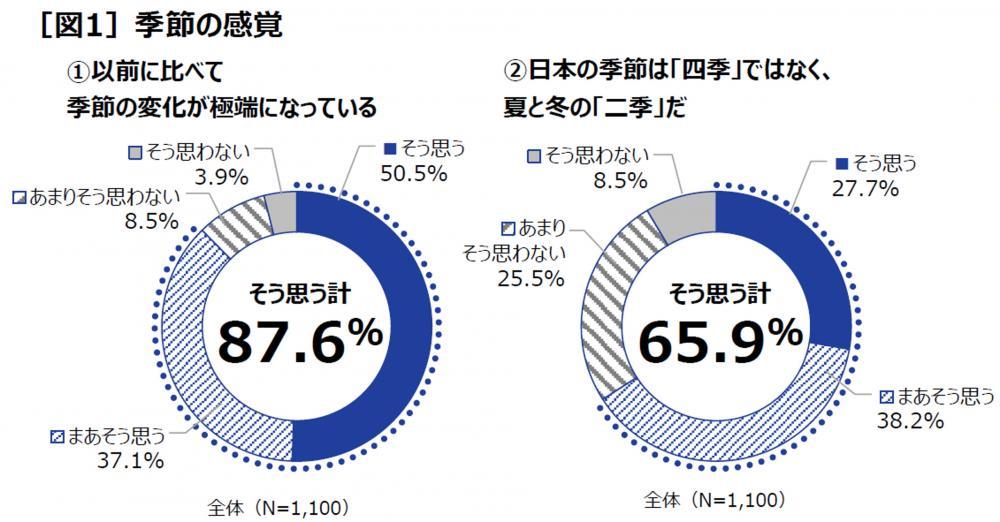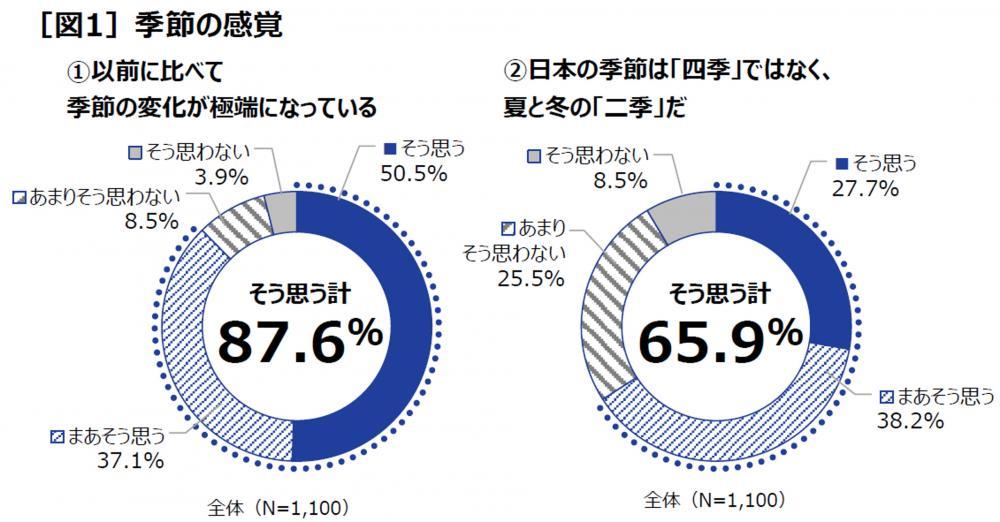研究進む「エピジェネティクス」~遺伝子制御で老化や疾患に対応~|トピックス|時事メディカル|時事通信の医療ニュースサイト

老化に伴うさまざまな身体的変化や疾患に対応するため、遺伝子の働きを制御して体に変化を起こす「エピジェネティクス」の研究が進んでいる。SAWAKO CLINIC x YSの日比野佐和子統括院長は「人それぞれに応じたオーダーメードの治療やライフスタイルの提案ができるようになる」と期待している。
日比野佐和子医師
◇遺伝子の働きを変える
エピジェネティクスとはDNAの配列を変えずに遺伝子の働きを変えることを指し、「DNAのメチル化」と「ヒストン修飾」という二つの仕組みがある。DNAのメチル化は、遺伝子に「メチル基」という小さな分子がくっつくことで起き、その領域の遺伝子は読まれにくくなり、働きがオフになる。
一方、DNAが巻き付いているヒストンというタンパク質が化学的な変化を受けるとDNAの巻き方も変化する。これがヒストン修飾で、その変化によって遺伝子が持つ機能をオンにしたりオフにしたりする。日比野統括院長は「さまざまな遺伝子のスイッチをオンにするかオフにするかは生活習慣で変わってくる」と話す。
バイオ企業のレリクサは、血液中のDNAメチル化パターンを解析して、加齢に伴う疾患リスクを反映した生物学的年齢や老化速度などを可視化する「エピクロックテスト」に取り組んでいる。日比野統括院長は「従来は皮膚年齢や血管年齢などバラバラだった老化指標に関し、遺伝子レベルで老化が進んでいる状態を見ることができる」と解説する。
このテストでは老化に関係する運動機能や腎臓機能、脂質代謝など15種類以上の健康指標の項目も検査。検査結果に基づいて老化の進行を遅らせるためのアクションプランを提案している。2025年5月上旬時点で全国100以上の医療機関で受診可能だ。
エピジェネティクスは再生医療とも密接に関連しており、細胞の状態を初期化して再構成する「エピジェネティック・リプログラミング」の研究が進んでいる。iPS細胞がその代表例と言える。
エピクロックテストの検査結果(イメージ図)=レリクサ提供
◇生活習慣に左右される老化
遺伝子の働きは、先天的な要因だけでなく、生活習慣など後天的な環境因子に大きく左右される。老化の3〜4割は遺伝的要因、残りの6〜7割は環境因子の影響とされている。例えば、同じ遺伝子配列を持つ一卵性双生児でも、喫煙の有無など生活習慣の違いによって老化の進行度が異なる。日比野統括院長は「遺伝子は親から受け継いだらそのまま発現すると思われがちだが、環境によって変わる」と強調する。
食生活の乱れやストレス、睡眠不足などが続くと、遺伝子のスイッチが誤ってオン・オフされる。その結果、細胞修復や抗炎症機能を持つ遺伝子が働かなくなり、逆に炎症を引き起こす遺伝子が過剰に活性化することで、病気や老化のリスクが高まる。
日比野統括院長は、遺伝子のスイッチをコントロールするために重要な要素として「食事、運動、睡眠、メンタル、環境」の五つを挙げる。栄養学の研究では、魚介類やオリーブオイルを用いる地中海食や、高血圧予防のDASH食が生物学的年齢を若く保つ効果があると報告されている。具体的にはタウリンやL-システイン、グルタチオン、ポリフェノールといった抗酸化作用がある成分を含む食品の摂取も有効だ。
◇睡眠は「長さ」より「質」
一般的に長寿の人は、1日平均7~8時間の睡眠を取るとされるが、日比野統括院長は「大切なのは睡眠時間より質」と指摘する。睡眠には、脳が活発に働くレム睡眠と、脳も休息するノンレム睡眠(深い睡眠)があり、「いかにノンレム睡眠が取れているかが重要」という。そのために①食事は就寝の3時間前までには終わらせる②夜間はカフェインの摂取を控える③ブルーライトが体内時計に影響を与えないよう、睡眠の2時間以上前にはスマートフォンやパソコンを見ないようにするといった生活習慣を推奨する。
また「寝ると決めたら(就寝の)2時間前からゆったりするのが一番いい」と日比野統括院長。入浴は就寝の1時間以上前に済ませ、朝はカーテンを開けて日光を浴び、睡眠ホルモンとして知られるメラトニンをリセットすることを勧める。自身も朝食に卵を食べ、メラトニン生成に必要なアミノ酸のトリプトファンを摂取しているそうだ。
最後に、日比野統括院長は「再生医療が進めば臓器再生も可能になる時代が来るが、生活習慣が乱れていれば意味がない」とし、健康的なライフスタイルの重要性を改めて強調した。(江川剛正)
(2025/09/25 05:01)
【関連記事】