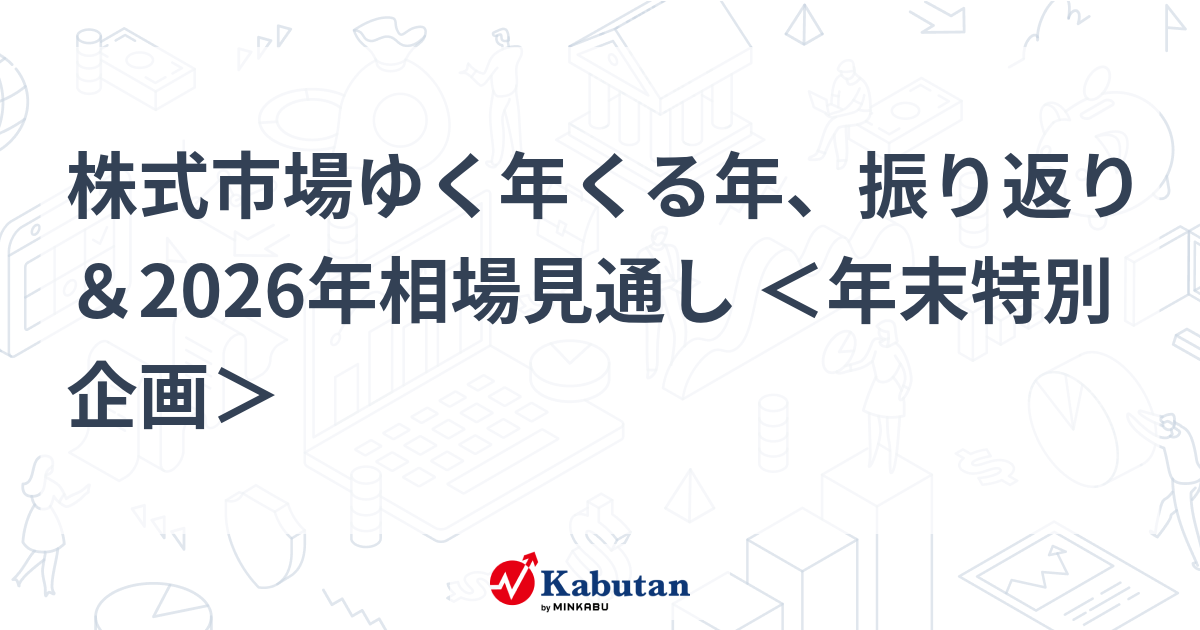生きたネズミ混入、盗難 雨被害…多発する「置き配」トラブル 配送業者の責任どこまで

玄関先や宅配ボックスに荷物を届ける「置き配」。ドライバー不足やネット通販の広がりに伴い需要が高まっており、国土交通省も宅配便の標準サービスとして普及させるべく検討に入っている。利用者にとっても便利な半面、気になるのが、盗難や誤配達などのトラブルだ。置き配の盗難被害では荷物が戻ってくることはめったにないとされる。置き配を巡るトラブルが生じた場合、配送業者の責任はどこまであるのか。
「商品がない」
《荷物が雨でぬれていた》《指定していないのに置き配で届けられた》
交流サイト(SNS)には置き配に関する批判を書き込む投稿が相次ぐ。国民生活センターには「配達完了メールが届いたが、商品が届いていない」といった相談も寄せられているという。
実際、玄関先での置き配のリスクは高い。兵庫県姫路市では6月18日、男性(30)宅の玄関前に置き配されていた荷物が盗まれる事件が発生。防犯カメラの捜査などから今月1日に窃盗容疑で女子中学生が逮捕された。中学生は「目に留まって中に何が入っているか気になった」と供述したという。
3月にはフードデリバリー大手の出前館(東京)で、玄関先に置き配された商品の袋に生きたクマネズミ(体長約5センチ)が混入していた事案があった。混入経路は特定できなかったが、同社は購入者に謝罪、配達員に商品の確認を徹底するよう対応を強化した。
苦情経験30%
宅配大手のヤマト運輸(東京)の調査では、置き配を利用したことのある人は8割近く。利用経験のない人のうち、54・4%が「盗難リスクが心配」と回答した。
不安を抱くのは購入者だけではない。
宅配ボックス販売も手掛けるハウスメーカーのナスタ(東京)が令和5年、宅配ドライバー400人に調査したところ、置き配の場所として最も多かったのは玄関先で66・5%。ただ、玄関先に荷物を届けることに75・3%のドライバーが「不安」と回答した。
実際に「荷物がない」「荷物がぬれた」などのクレームを受けた経験があると答えたのは、30・2%にも上った。
業者側もトラブルを見越した対策を進める。
通販大手では購入者が置き配を指定した場合、決められた配達場所に荷物を届けた写真を送るケースが多い。また、日本郵便(東京)では「置き配保険」を設けており、盗難に際し、警察への届け出など手続きを済ませた上で、支払い限度額1万円で、保険金を請求できるとしている。ヤマト運輸も、盗難や紛失などがあった場合、会員であれば個別の状況を確認して対応するという。
玄関先対策を
ただ、盗難などのトラブルによる配送業者の責任は極めて限定的だ。ベリーベスト法律事務所の斉田貴士弁護士は、「置き配は現状、買い主側もリスクを承知の上で選択する配達方法」と指摘。その上で、配送業者側に明確な落ち度がない限り責任を問うことは難しいとする。
例えば、大雨の中、あえて雨にぬれる場所に放置したり、乱暴な配達で荷物の中身を破損させたりした場合などは、業者側が「リスクを明確に予測できた」として責任を問われる可能性もある。しかし、盗難や地震などの自然災害といった「不可抗力」では責任を問うことはできないという。
斉田氏は、盗難被害を防ぐため、置き配された荷物をなるべく早く回収するほか、玄関先ではなく、宅配ボックスやロッカー、防犯カメラを設置するといった対策が必要だとしている。
◇
国土交通省は置き配を、宅配便の基本ルールを定めた「標準運送約款」に盛り込み、普及させたい意向だ。物流業界関係者も交えた検討会で今秋までに方向性をまとめる。
背景には、物流業界の輸送力低下への懸念がある。時間外労働の上限を年960時間とする規制が6年4月から始まったことやドライバー不足の深刻化が要因とされる。
国交省によると今年4月の宅配大手事業者6社の再配達率は8・4%。近年は減少傾向にあるものの、令和6年度までに6%まで引き下げる目標は達成できなかった。
物流ドライバーの負担軽減のためにも再配達率削減に向けた取り組みは急務といえる。(藤木祥平)