【プレビュー】「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」 東京上野・国立科学博物館で11月1日から 科博の叡智を結集!地球史の大事件”大量絶滅”の謎に迫る
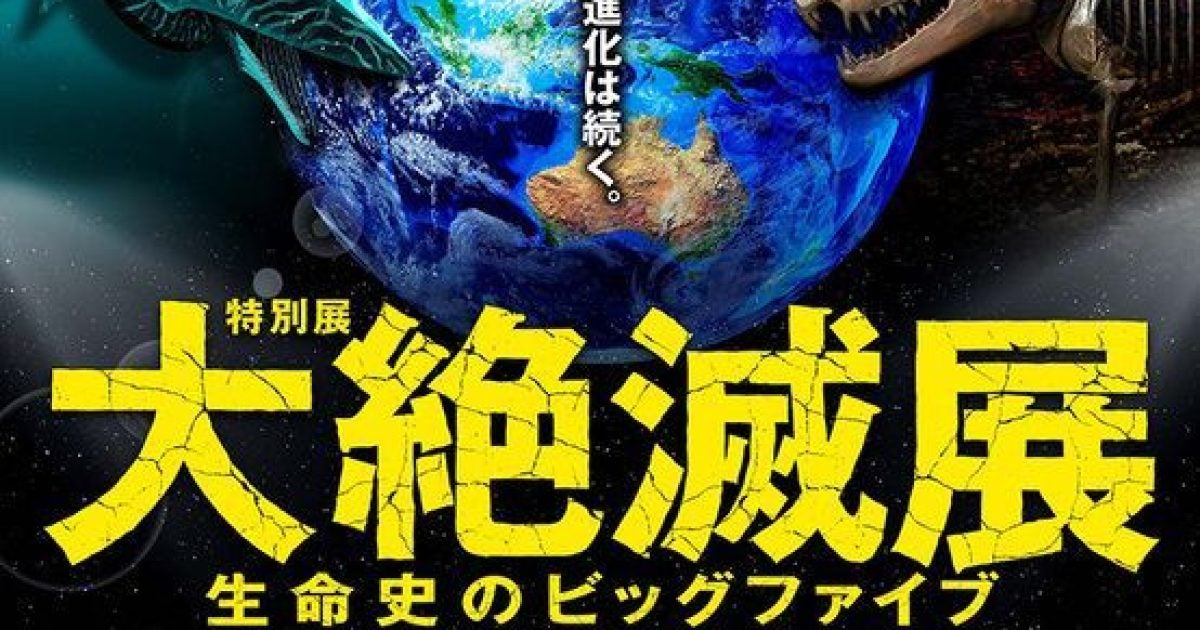
国立科学博物館(東京・上野公園)で特別展「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」が11月1日から開催されます。
生命が誕生してから40億年、地球上では幾度も生命の危機が訪れました。それは主に地球外からやってきた小天体の衝突や火山などの地球内部の活動によりもたらされましたが、ときに生命活動そのものが引き金になったこともあります。しかし生命は、その都度、したたかにそれらの危機を乗り越え、絶滅したグループに代わるグループが新たに繁栄することを繰り返すことで、多様に進化を遂げてきました。言わば、大量絶滅は生命の繁栄を促した現象だと捉えることもできるのです。
本展では、その中でも規模の大きかった5回の「大量絶滅」事変(通称「ビッグファイブ」)を、化石や岩石に残された様々な証拠から紐解き、「生き物たち」の生存をかけた進化の歴史を辿ります。「ビッグファイブ」をテーマとする特別展は、国立科学博物館では初めてとなります。各種の古生物や火山、古気候・古海洋などを専門とする国立科学博物館の研究者10名による監修で、様々な角度から5回の大量絶滅の謎に迫ります。
2月16日(月)、2月23日(月・祝)は開館
観覧料:当日券:一般・大学生2,300円 / 小・中・高校生600円 ※未就学児無料※障がい者手帳をお持ちの方と介護者1名は無料※同日に限り常設展示(地球館・日本館)も観覧可
問い合わせ:ハローダイヤル 050-5541-8600 アクセス:JR「上野駅」公園口から徒歩5分/東京メトロ銀座線・日比谷線「上野駅」から徒歩10分/京成線「京成上野駅」から徒歩10分 公式SNS:X(旧Twitter) Instagram 展覧会詳細は、公式サイトまで。本展の見どころ
Point1 国立科学博物館では初!「ビッグファイブ」をテーマとする特別展
国立科学博物館では「ビッグファイブ」から生命進化の歴史をたどる特別展は初めての開催となります。生命史全体をテーマとする特別展も実に10年ぶり。国立科学博物館の古生物研究者全員と火山の研究者が協力して、「ビッグファイブ」の最新研究をご紹介します。
★ビッグファイブとは★
生命の歴史の中で「進化」と「絶滅」は隣り合わせにある現象です。通常、100万年ごとに10%程度の種が絶滅すると考えられていますが、通常の絶滅とは異なって、短期間に75%以上もの分類群が絶滅したとされる現象(=大量絶滅)が過去に何度も起こっています。そのうち最も大きな5回の絶滅現象が「ビッグファイブ」です。「ビッグファイブ」を境としてそれ以前と以降の生命の世界が大きく変わったため、それが次の新しい世界へと繋がる大きな原動力になったという考え方があります。
1 . オルドビス紀末約4億4400万年前 2 . デボン紀後期約3億8000万年前~約3億6000万年前 3 . ペルム紀末約2億5200万年前 4 . 三畳紀末約2億100万年前
5 . 白亜紀末約6600万年前
Point2 迫力の展示演出!
会場では大きな地球儀「大絶滅スフィア」が皆様をお出迎えします。「大絶滅スフィア」は球形の映像展示で、地球史における「ビッグファイブ」をご紹介します。また、史上最大の絶滅の要因でもある火山活動を体感できる模型も展示いたします。
「大絶滅スフィア」のイメージパース 画像提供 ©アフロ 火山活動模型のイメージパース ※画像はイメージですPoint3 デンバー自然科学博物館から日本初公開の標本が来日!
全米有数の自然史博物館の一つであるデンバー自然科学博物館の貴重な標本の数々をご紹介します。日本からは全長約6mのステラーダイカイギュウの全身化石を世界初公開するなど「ビッグファイブ」や生命史を紐解く貴重な標本が多数紹介されます。
デンバー自然科学博物館は、アメリカのコロラド州にある、全米有数の自然史博物館の一つ。特に脊椎動物と植物の化石は、その規模、範囲、科学的価値において世界有数のコレクションです。
Point4 モロッコでの発掘調査の成果を紹介!
本展のために大量絶滅と関連の深いモロッコにおいて発掘調査を実施。オルドビス紀の世界を垣間見ることができるフェゾウアタ化石群や、三葉虫などの採集標本のほか、三畳紀末の絶滅に関わる火山活動の調査結果などを世界初公開いたします。
モロッコでの調査の様子 カンブロパラス展示構成
EPISODE 1 O-S境界 海の環境の多様化
海の生物に大きく影響した最初の大量絶滅事変です。オルドビス紀化石の世界有数の産地があるモロッコの最新研究から絶滅事変の詳細に迫ります。
アノマロカリス復元画 アノマロカリス(レプリカ) エーギロカシス/オルドビス紀前期に生息していた巨大な節足動物に近い生物で、体長は2mに達し、櫛状の器官でプランクトンをこし取って食べていたと考えられている エーギロカシス復元画EPISODE 2 F-F境界 陸上生態系の発展
火山活動に起因した寒冷化による複数回の絶滅事変です。海ではダンクルオステウスなどの板皮類や多くの三葉虫が絶滅し、陸では巨大な森を中心とした生態系が始まりました。
ダンクルオステウス(レプリカ)/デボン紀後期に生息していた大型の板皮類。強力な顎がある頑丈な頭骨を持ち、当時の海洋で最強の捕食者の一つとされている タリーモンスター/石炭紀の海に生息していた謎多き古代生物で、細長い体と特徴的な吻(ふん)を持っている タリーモンスター復元画 ワッティエザ(※レプリカ。実物の化石は展示されません)/高さ8mにもなった最古の高木植物。日本初公開となるEPISODE 3 P-T境界 史上最大の絶滅
シベリアで起こった大規模火山活動に起因した、古生代の終わりを告げる史上最大規模の絶滅です。海陸で多くの生物が絶滅しましたが、恐竜や魚竜、私たち哺乳類に繋がる仲間が生き残りました。
ウタツサウルス(レプリカ)/宮城県に分布する三畳紀前期約2億5000万年前の地層から発見された、世界最古級の魚鰭類。陸上にいた祖先から水中での生活へと進出する初期の段階を示す重要な種である ディメトロドン(レプリカ)/約2億8000万年前に生息していた大型の捕食者で、背中の帆が特徴的。恐竜ではなく、哺乳類に近い仲間だったEPISODE 4 T-J境界 恐竜の時代への大変革
大西洋をつくった超大陸パンゲアの分裂。この時の火山活動が原因とされる絶滅事変は、“爬虫類”の世界を大きく変え、恐竜が主役に躍り出るきっかけになりました。歴史的に有名な北米の化石産地の研究も紹介します。
クリオロフォサウルス(レプリカ) レドンダサウルス(レプリカ)/約2億500万年前の三畳紀後期に北アメリカ大陸に生息していた大型の肉食性爬虫類。恐竜類ではなくフィトサウルス類と呼ばれる分類群に属し、体全体はワニ類に似ていたEPISODE 5 K-Pg境界 中生代の終焉
小天体の衝突により恐竜などの中生代型生物が絶滅しました。原因となった隕石や、この時代の変化が詳しく研究されている北米西部の化石を紹介します。恐竜絶滅後の哺乳類の変化に注目です。特に本章では、アメリカ・デンバー自然科学博物館から来日した貴重な標本が多数展示されます。
ティラノサウルス(レプリカ)/白亜紀末期に北アメリカ大陸に生息していた大型の肉食性恐竜で、体長は最大約13mに達した。強力な顎と鋭い歯で、他の恐竜の骨を噛み砕くことができたと考えられている トリケラトプス(レプリカ) エクトコヌス ワナガノスクスの一種 マメ科の一種(さや) エオコノドン ロクソロフスの一種EPISODE 6 新生代に起きた生物の多様化
大量大量絶滅のなかった新生代ですが、寒冷化や乾燥化など激しい気候変化が原因で生物の世界に大きな変化がありました。生き物の多様な世界がどうやって形づくられてきたか、化石で辿ります。世界初公開となる、全長約6mを誇るステラーダイカイギュウ全身の実物化石にも要注目です。
ステラーダイカイギュウ ステラーダイカイギュウ復元画 メリキップス(レプリカ) メソヒップス(レプリカ) シフルヒップス(レプリカ)本展では、科博の古生物研究者全員と火山の研究者が協力して、地球史において発生した5回の大量絶滅「ビッグファイブ」の最新研究にフォーカスをあてます。デンバー自然科学博物館から初来日する貴重な標本群をはじめ、本展のために行われたモロッコでの発掘調査での数々の成果報告では、世界初公開となる標本・情報も登場。約40億年にわたる地球の生命史において最大の謎である「ビッグファイブ」を最新のビジュアルと知見で読み解く、この秋最大の注目点の一つとして今から開幕が楽しみです。(美術展ナビ)
- NEW
- NEW
- NEW
- SPECIAL
- NEW
- NEW
- NEW
- NEW
- NEW
- NEW
- SPECIAL
- NEW
- NEW
- NEW
- NEW
- SPECIAL
- SPECIAL



