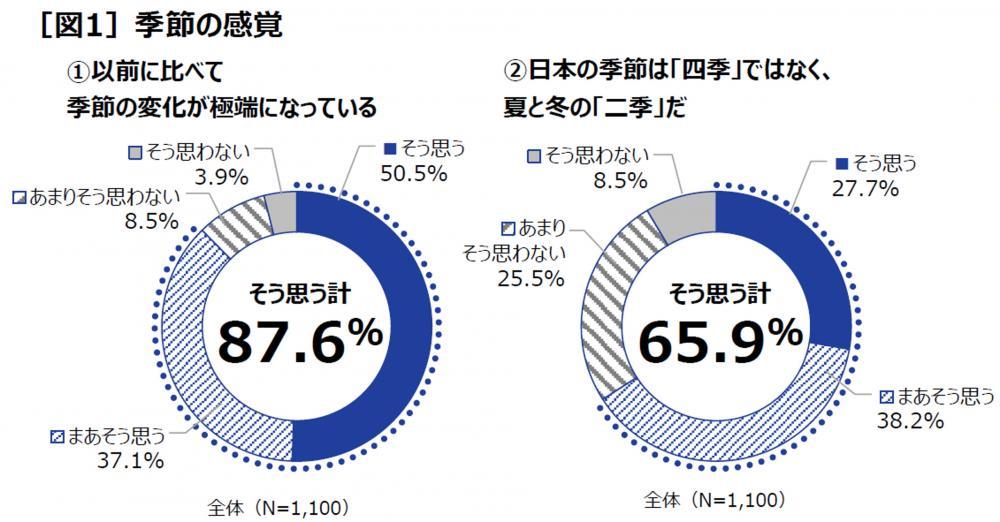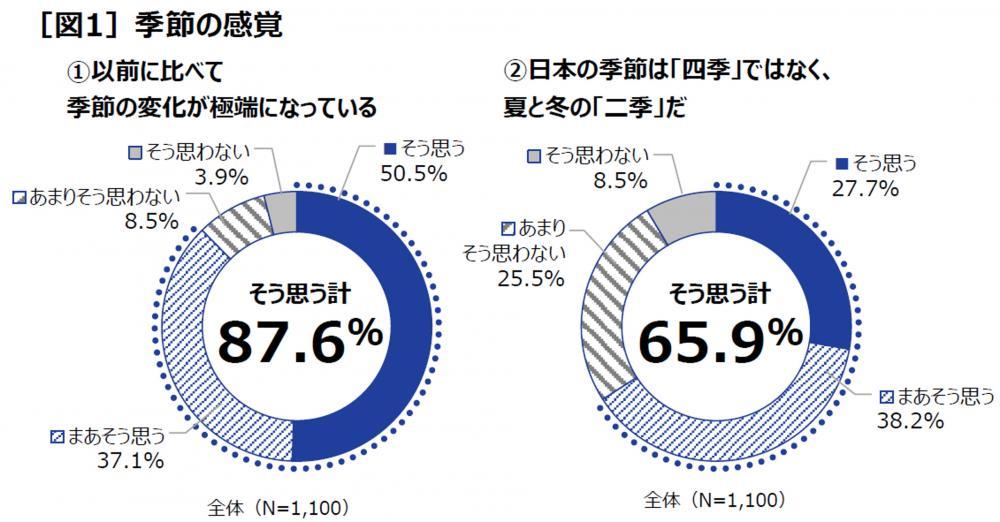CKD例の尿アルブミン測定率は半数止まり

慢性腎臓病(CKD)の進行や合併症に対してはガイドラインに基づく予防戦略が存在するが、臨床現場でどの程度実施されているかは明らかでない。オーストラリア・The George Institute for Global HealthのDaniel B. Ketema氏らは、この点を明らかにするためシステマチックレビューとメタ解析を実施。その結果、CKD患者における血圧や推算糸球体濾過量(eGFR)の測定率は高い一方、尿アルブミン測定の実施率は約半数にとどまるなど、診療の質には大きなばらつきがあることが分かったとBMJ Open(2025; 15: e102044)に報告した。(関連記事「CKD患者の家族歴聴取、10のコツを伝授」)
24カ国59研究・300万例超のデータを解析
Ketema氏らは、MEDLINE、EMBASE、CINAHLを用いて、2025年7月18日までに収載され、成人CKD患者を対象に診療の質を検討した観察研究の文献を検索。最終的に24カ国59研究・約300万3,641例を解析対象とした。
CKD診療の質指標に関するデータを、患者モニタリング(eGFR、尿アルブミン、血圧など)、薬物療法〔ACE阻害薬、アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)、スタチン〕、治療目標(血圧、HbA1c)に関連する領域ごとに評価。各指標を達成した患者の割合について、ランダム効果モデルを用いて統合推定値(95%CI)を算出した。
解析の結果、eGFRは81.3%(95%CI 75.0〜87.6%)、血圧は90.0%(同84.3〜95.9%)と高頻度で測定されていたのに対し、尿アルブミン測定率は47.4%(同40.0〜54.7%)にとどまることが明らかになった。糖尿病を合併する患者では尿アルブミン測定率が52.2%とやや高かったものの、依然として半数近くが未実施であった。
薬物療法については、ACE阻害薬またはARBの処方率は56.7%(95%CI 51.5〜62.0%)、スタチンの処方率も56.6%(同48.9〜64.3%)といずれも6割に満たなかった。非ステロイド抗炎症薬(NSAID)の回避率は82.1%(同74.4〜89.8%)と比較的高かったが、徹底には至っていなかった。
血圧値130/80mmHg以下の達成率も35%程度と低い
治療目標は、血圧140/90mmHg以下を達成したのは56.5%(95%CI 48.5〜64.6%)にとどまり、より厳格な130/80mmHg以下の達成率は35.2%(同25.1〜45.4%)にすぎなかった。糖尿病を合併する患者においては、HbA1c 7%未満を達成した割合は43.5%(同39.4〜47.6%)と低調であった。
以上から、Ketema氏らは「CKD診療の質には世界的に大きなばらつきがあり、特に尿アルブミン測定の実施率が低い状況が浮き彫りとなった」と結論。その上で、尿アルブミン測定はCKDの進行度評価やリスク層別化に不可欠であり、推奨薬の導入判断にも直結する重要な検査であると、意義を強調している。
なお、2024年版Kidney Disease Improving Global Outcomes(KDIGO)ガイドラインでは、2型糖尿病患者には年1回以上、リスクの高い群にはより頻回の尿アルブミン測定を推奨している(Kidney Int 2024; 105: S117-S314)。同氏らは「CKD診療の改善には尿アルブミン測定を中心とした検査体制の強化と、診療の質を体系的にモニタリングする仕組みの整備が不可欠である」と付言している。
(編集部)