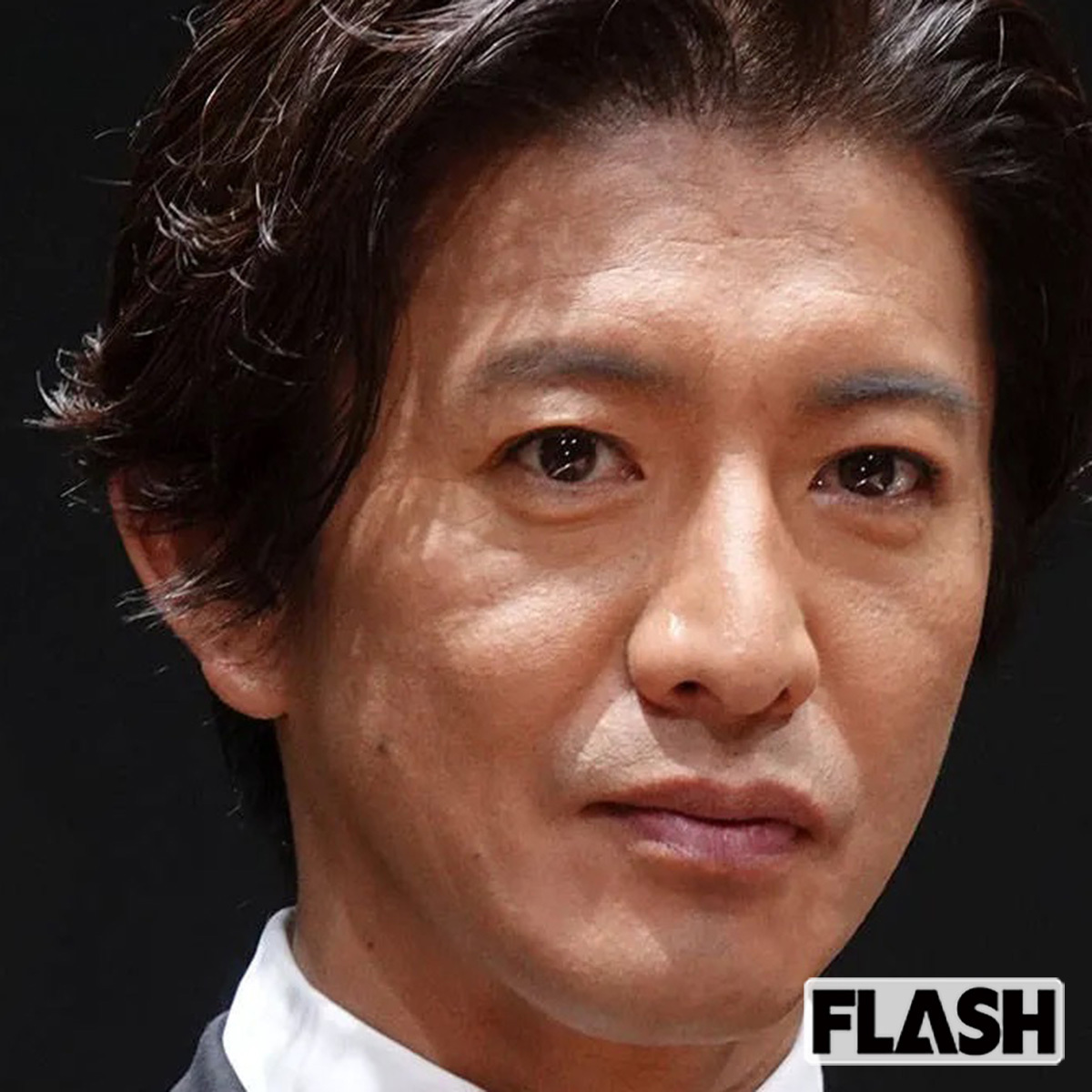『7月5日に大災難』は「科学的根拠なし」 トカラ列島で地震多発 南海トラフ地震の危険性は?【専門家が解説】
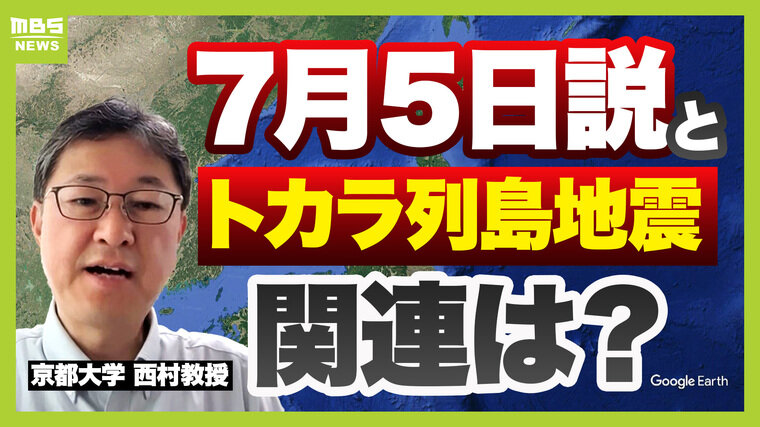
地震が頻発している鹿児島・トカラ列島。体に揺れを感じる震度1以上の地震の回数は、地震活動が始まった6月21日午前8時から7月4日午前11時までに、なんと「1180回」にのぼります。
SNSで話題となっている「7月5日説」の真偽や、南海トラフ地震の危険性も非常に気になるところ。京都大学防災研究所・西村卓也教授の見解も交えてお伝えします。
トカラ列島周辺の地震 他の地域への影響は?
そもそも地震は大きく分けると、「本震-余震型」と「群発地震型」の2種類があります。
まず本震-余震型について。地球の表面には、プレートがいくつかのブロックにわかれて存在しています。プレートは1年間で数cm~10cm程度ずつゆっくり移動していて、プレート同士の境界では、一方のプレートがもう一方の下に沈みこむなどしています。そのうえで、本震-余震型には大きく「海溝型地震」と「直下型地震」があります。
例えば日本の周辺では、フィリピン海プレートとユーラシアプレートが接しています。フィリピン海プレートが下へもぐり込むと、ユーラシアプレートもぐぐっと引っ張られ、その引っ張られる状態が限界に達すると、ユーラシアプレートが反発して跳ね上がります。こうして起こるのが「海溝型地震」です。
もう1つのパターンとして、押される陸側のプレートでひずみが生じて限界に達すると、プレート内部の強度の弱い場所で破壊が起き(=断層運動)、地震が発生することがあります。これが「直下型地震(内陸型地震)」です。
そして今、トカラ列島で起きているのは「本震-余震型」ではなく「群発地震型」。これは、本震-余震型の地震とは発生メカニズムが全く異なります。
群発地震型は、プレートの動きに加えて、マグマの移動や地下水の動き、スロースリップ(プレートの境界で片方のプレートが引っ張られたときに、急激に反発するのではなくゆっくりと戻る動き)などによって発生します。
トカラ列島や伊豆諸島の群発地震はマグマの移動、和歌山市周辺や京都府南部(亀岡周辺)の群発地震は地下水の動きが要因とみられていますが、まだ厳密なメカニズムは解明されていないということです。
トカラ列島近海で頻発している地震が、他の地震に関係するのでは?と心配する声も聞かれますが、西村卓也教授によると、今回の群発地震の影響は広く見ても半径100kmほど。他の地震への影響は、基本的には考えられないということです。
7月5日説は「科学的根拠なし」
また、SNSなどでは「トカラ地震が増えると大きな災害が起こる」、いわゆる“トカラの法則”という言葉が飛び交っています。トカラ列島周辺での地震回数が多い年やその翌年に大きな地震が起きていることから流れている風説ですが、西村教授は「別の災害との関係はない」といいます。
トカラ列島で年間の地震の数に、年によって差が出ている傾向については、マグマがたまるまでの期間などによる法則性は考えられるとしつつも、他の地震の前兆などではないため、過剰に恐れる必要ないと訴えています。
さらに、マンガをきっかけにSNSなどで噂されている「7月5日に何かが起こるのではないか」という説についても、西村教授に見解を聞きました。
西村教授は「科学的根拠はありません」と断言。マンガには、ある地点が盛り上がり大きな津波が起こるとして図が描かれていますが、その地点に言及し「ここはプレートの真ん中なのでメカニズム的には地震が起こるとは考え難い」と指摘します。一方で、現時点で地震の予知はできないため、「絶対ないとは言い切れない」ということです。
地震の発生確率はどう算出?
マグニチュード8~9クラスの超巨大地震で、最悪の場合死者が約30万人とされている南海トラフ巨大地震。発生確率は「30年以内80%程度」とされていますが、この数字はどのようにして出されているのでしょうか。
まず、地震の発生確率を計算するうえで、大きく「時間的にランダム」と「周期的」の2種類の考え方があるといいます。
「時間的にランダム」の考え方は、地震の発生理由などが判然としていない場所の予測で用いられます。「周期的」の考え方は、プレートの運動で起きる地震の予測で用いられます。
南海トラフ地震の発生確率の計算「前回地震の規模」も重要な要素に
しかし、南海トラフ地震の発生確率の算出は少し特殊です。基本的には「周期的」の考え方を用いていますが、それに加え「時間予測モデル」を適用しているのです。
これは、地震の「周期」だけではなく、「前回の地震の規模」も考慮に入れるものです。たとえば前回の地震の規模が小さめであれば、まだエネルギーが発散しきれておらず蓄積された状態なので、周期より早めに来るのではないか、という考え方です。南海トラフ地震については、史料などで過去の地震に関する“データ”も豊富であるため、こうした計算が可能になっています。
南海トラフ地震の周期は平均すると「約120年」ですが、直近3回の南海トラフ地震は以下のように発生しています。
【1707年 宝永地震】地震の規模をはかる高知県室津港の隆起量:1.8m(大) 【1854年 安政地震】高知県室津港の隆起量:1.2m(中)
【1944年・46年 昭和東南海地震 昭和南海地震】高知県室津港の隆起量:1.15m(小)
前回の1944年・46年の地震規模が比較的「小」で、安政地震からの間隔も比較的短い点(90年)などを踏まえ、次の南海トラフ地震は「大規模」で「まもなく」発生する危険性が高いと予想されているのです。
一方で、南海トラフ地震についてのみ“特殊な計算モデル”を適用していることに、疑義を呈する声もあります。
南海トラフだけじゃない…活断層にも警戒を
当然、過去に繰り返し活動し、将来も活動すると考えられる断層である「活断層」にも注意が必要です。活断層が起こす地震の規模は、仮に南海トラフ地震ほど大きくなくても、都市などの「直下」で起きるため、被害が大きくなりやすいと西村教授は警鐘を鳴らします。
大地震の発生確率が30年以内で3%以上の「Sランク断層」が、近畿にも3か所あります。
【近畿のSランク断層】 滋賀県 琵琶湖西岸断層帯(北部) 大阪府 上町断層帯
京都府・奈良県 奈良盆地東縁断層帯
決して油断することなく、改めて地震への備えの徹底をお願いします。