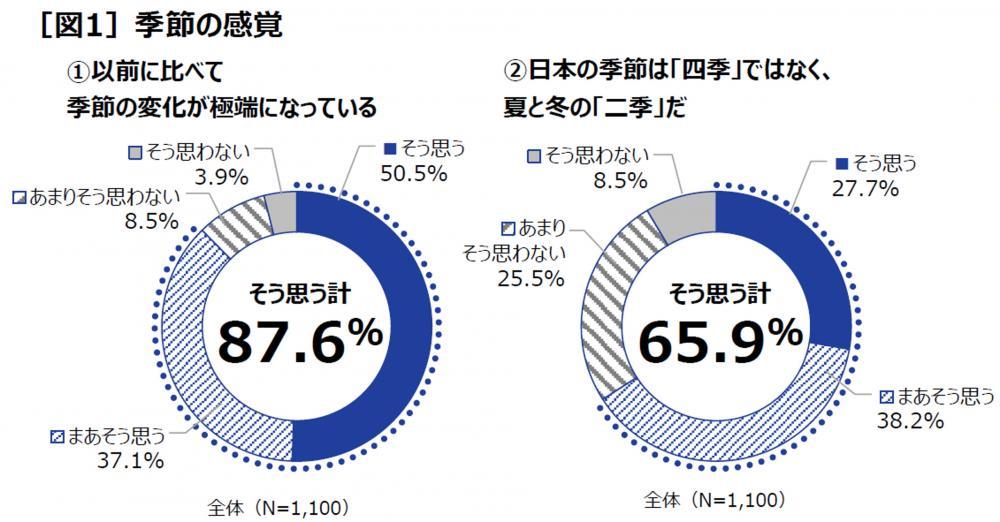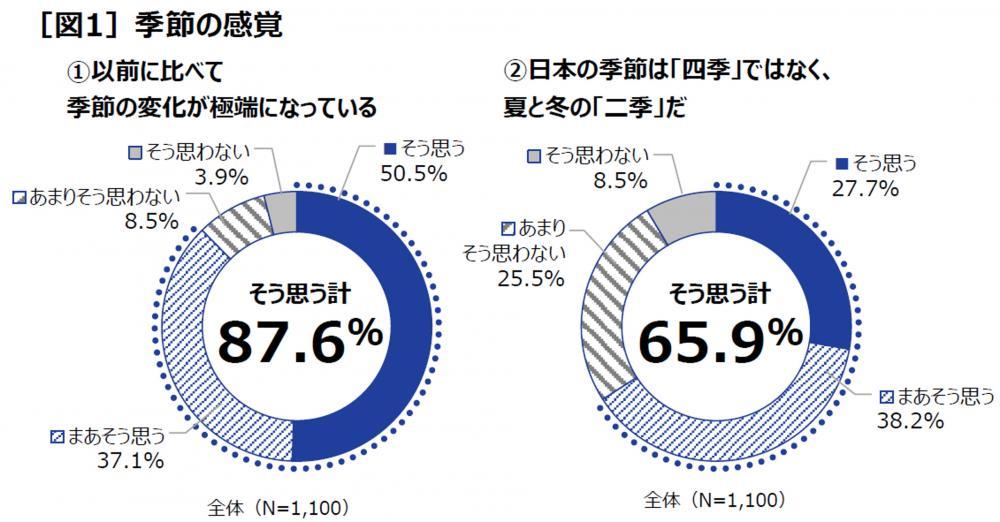家族が認知症になりまして(6) 「人は長生きすれば、ほぼ100%認知症になる」―内門大丈医師に聞く、40代から始める“脳の備え”

家族が認知症になったらどうしよう……そんな漠然とした不安が現実に。軽度の認知症の人に対する情報が乏しい中、少しずつ調べていくうちに、私が持っていた認知症のイメージは古いことを知りました。この連載では“認知症の解像度”を上げてくれる場所や人を訪ねて、認知症の現実に向き合います。
父が認知症になり、認知症について深く知りたいと本屋に行った時に、たくさんの本が並んでいるのに読むべき本がないことに愕然としました。どれも重度の認知症の方を対象としたものやお金についての話ばかり。診断されたばかりで、まだ症状があまりない状態の人がどうすれば穏やかに過ごせるのか、重度までの時間をどうやったら伸ばせるのかを知る術はほとんどありませんでした。
そんな中で見つけたのが内門大丈先生の「家族で「軽度の認知症」の進行を少しでも遅らせる本: 正しい理解と向き合い方」(大和出版)です。「軽度の認知症」が対象で、ショッキングな重度のことは書かれていない(当事者に読ませやすい)。しかも実際に認知症を診ている先生の体温のある言葉や対処法なので、心からありがたい本だと感じました。
今回は、そんな内門大丈先生に医者の立場から見た認知症について、わかりやすくお話していただきます。
PROFILE:内門大丈医師
「メモリーケアクリニック湘南」院長。横浜市立大学医学部臨床教授。平塚市医師会副会長。横浜市立大学大学院博士課程(精神医学専攻)修了。レビー小体型認知症を発見した小阪憲司先生との出会いをきっかけに認知症の診療現場に身を投じるようになる。レビー小体型認知症研究会(世話人、事務局長)、N-Pネットワーク研究会(代表世話人)、湘南健康大学(代表)、日本認知症予防学会神奈川県支部(支部長)などの取り組みを通じて、認知症に関する啓発活動・地域コミュニティの活性化に取り組んでいる。監修本に「家族で「軽度の認知症」の進行を少しでも遅らせる本: 正しい理解と向き合い方」(大和出版)、「家族が認知症になった時の 接し方・介護・頼れるサービス」(ナツメ社)など。
■人は長生きしたらほぼ100%認知症になる!? 治る認知症(MCI)とは
――この連載では“初期”の認知症にスポットを当ててお話を聞いてきたのですが、そもそも初期の定義自体が難しいと感じています。
認知症の進行度を表すFASTステージというものがあって、それは正常のステージ1から重度まで7つの段階に分けられています。
また最近では「アルツハイマー病連続体」という考え方が主流になっています。認知症の原因疾患は70種類ぐらいあると言われていて、その中で一番多いのがアルツハイマー型認知症です。アルツハイマー病の原因であるアミロイドβなどのタンパクが脳内に溜まってくると最終的には神経細胞が減っていき、やがて認知症になります。それは40代ぐらいから始まっているんです。脳の変性が進んでいくことでだんだんと生活機能障害が出たりするわけで、ある時から突然認知症になるわけではない。プレクリニカル期(無症候期)から認知症期まではグラデーションになっているという考え方です。
-
FASTステージはアルツハイマー型認知症の進行度を7段階で表す評価法。軽度の物忘れから始まり、日常生活に支障をきたす重度の認知症までの進行状況を把握できる
――2023年にレカネマブ(アミロイドβを減少させてアルツハイマー病による認知症の進行を遅らせる薬)が日本で承認されて話題になりました。その治療対象となるのが「軽度認知症障害(MCI)」と「軽度の認知症」とあって、その違いが明確にあるのかも気になります。MCIは認知症予備軍で、認知症にならない人もいるとか。
レカネマブの対象になるということでMCIにフォーカスが当たるようになりましたね。MCIの人が1年後に認知症に移行するリスクは5〜15%で、16~41%の人は健常な状態に戻ると言われています。ただ、MCIの人は1年後も同じリスクがある。先ほどの話でいうと、MCIの人も「アルツハイマー病連続体」の中にいるので、僕からすれば、長生きすればみんな認知症になると思っています。
ただ、「ナン・スタディ」というアメリカの修道女たちを対象にした研究があって、亡くなったあとの脳にはアルツハイマー病理変化があったのに、生前に認知症の症状がなかった人が約8%いたと報告されています。なので、みんなが「アルツハイマー病連続体」の中にいるけれども、症状が出ない人もいるかもしれない。
――では「MCIは治る認知症」という言い方は違うんですね。
もちろんMCIの中には、甲状腺機能低下症や特発性正常圧水頭症などの治る認知症も含まれますが、ちょっと違いますね。人は長生きしたらほぼ100%認知症になります。ならないとしたら、体のフレイル(虚弱)が脳のフレイルより先に来ただけ。必ず人は老化するじゃないですか。どの臓器が最初に老化するかによって、体の病気で死ぬのか、脳の障害である認知症で死ぬのかの違いがあるだけという気がします。
――なるほど、たしかに。では、認知症の進行を約7ヶ月半遅らせるというレカネマブのような薬に意義はあると思いますか。今はまだ治療が高価なので治療を受けるか迷う方もいると思います。
僕が医学部を卒業した1996年には、認知症の薬はなかったんですよ。当時、僕が勤めていた痴呆疾患医療センター(現在は、認知症疾患医療センター)でも、薬がない中で認知症の人を見ていた。その後、アリセプト(1999年発売)という薬が出たんですが、薬の登場によって認知症の進行は全般的に遅くなっていると感じます。レカネマブの対象となるMCIは、髄液検査もしくはアミロイドPET検査で脳の中にアミロイドβが溜まっているのは分かっているけれど,認知症と診断される前、もしくは初期の人たちです。その状態を7〜8か月長引かせることができるというのは、意外と長く遅らせることができるなというのが僕の感覚です。
■認知機能低下の原因は他の病気や薬のせいかもしれない?
――最初の話に戻りますが、“初期”を定義づけるのは難しいということですよね。
認知症の症状そのものは個人差が大きくあります。我々はアルツハイマー病連続体の中にいて、1人暮らしができなくなったら認知症と呼びましょうという考えです。生活機能障害が起きているかどうかということですね。
――私の父の場合、診断された直後は知り合いの顔がわからない状態になって、その数カ月後、忘れていた人の顔がわかるようになったんです。すべてにおいて一進一退で、進行スピードが測りづらいと感じています。
進行度合いは0、1じゃないと思いますし、本人自身が自己効力感、自信がない時だと、パフォーマンスを発揮できない。精神的に安定してくるとパフォーマンスが発揮できるというのはあると思います。MCI軽度の時のほうが、認知機能の低下に対する自覚が比較的保たれているため、不安症状が強く現れることが多いとされています。それは想像してみるとそうですよね。できていたことができなくなることへの戸惑いや、それに伴うストレス反応が背景にあるでしょう。また、病状が進行し自覚が薄れると、不安症状が軽減する場合もあります。
――先生が監修された『家族で「軽度の認知症」の進行を少しでも遅らせる本 正しい知識と向き合い方』(大和出版)は、どのような方を対象としているんですか。
-
『家族で「軽度の認知症」の進行を少しでも遅らせる本 正しい知識と向き合い方』(大和出版)/軽度認知症に向けた情報提供が少ない中、内門先生は「家族で「軽度の認知症」の進行を少しでも遅らせる本: 正しい理解と向き合い方」などを監修。軽度の認知症への向き合い方や、早期からの認知症リスクを提言している。
認知症ご本人やご家族の方を対象にしているのはもちろんですが、まだ若いご家族自身のためにも、40代からの認知症リスクの低減というコンセプトを知ってもらいたいという狙いもありました。ランセット委員会の報告というのが2020年に出されて、高血圧や過剰な飲酒、喫煙、糖尿病など12の因子を改善することで認知症のリスクを減らすことが可能だと発表されています。2024年の最新報告では、従来の12項目に加え「視力障害」と「高LDLコレステロール値(悪玉コレステロール)」の2つが新たに追加され、合計14項目となりました。これら14のリスク要因を全て適切に管理・改善できれば、認知症の最大45%を予防または発症を遅らせることが可能とされています。高血圧や糖尿病が脳梗塞や心筋梗塞に関係あるのはイメージできても、認知症になるリスクはあまり知られていない。そういう脳の老化をできるだけ食い止めるために大事な情報を伝えるために書いた本です。
僕は睡眠時無呼吸症候群にも注目しているんですが、認知症と睡眠時無呼吸症候群の合併率が高いことが報告されています。睡眠時無呼吸症候群の人にCPAPという治療を導入するだけで認知機能が改善することもあるんです。認知症の疑いで病院に来た50代の女性が、実は糖尿病と重症の睡眠時無呼吸症候群があって、それをすべて治療したら認知機能が戻ってきたという例もあります。
-
世界的な医学誌「ランセット」が設立した専門家チームによる報告。最新版には「視力低下(特に高齢期)」と「高LDLコレステロール値の上昇(特に中年期)」が追加され、14のリスク要因に対処することで認知症の約45%を予防または遅らせることができるとされている
――薬の併用についても注意したほうがいいと書かれていますね。
多くの薬を飲んでいると有害事象が起こりやすくなる。例えば胃薬のH2ブロッカー、抗ヒスタミン薬というアレルギーの薬、頻尿などで使われる抗コリン薬など、副作用として認知機能を下げる場合の薬があります。抗ヒスタミン薬は風邪薬にも入っている場合があって、高齢者が飲むと具合が悪くなったりする。高齢者によくある過活動性膀胱に抗コリン薬が出されて認知機能がさらに低下する場合があるわけです。
――私の父は認知症以外でかかっている複数の病院から薬をもらっていますが、薬によって認知機能が下がることはすべてのお医者さんが把握しているものですか?
必ずしも全ての医師が十分に意識しているとは限りません。薬剤による認知機能低下の影響は、教科書やガイドラインには明記されていますが、実際の診療では見落とされることもあります。医師は日々さまざまな領域の情報を扱っており、薬剤の影響についても常にアップデートが求められるため、知識や意識に差が出ることもあります。特に、高齢の患者さんが複数の診療科を受診している場合、薬の処方が分散されてしまい、全体のバランスを見ている医師がいないという状況も起こりえます。
とはいえ、認知機能に影響する薬を避けるという視点は、認知症予防や進行抑制において非常に重要です。たとえば抗コリン薬のように、記憶や注意力に影響を与える薬は、高齢者や認知機能に不安のある方にとっては慎重に扱うべきです。医師がそのことを理解していれば、同等の効果が期待できる別の薬を選択することも可能です。そうした薬の見直しの積み重ねが、認知機能の維持に大きく寄与すると考えられます。
――本の中で「周辺症状は薬剤より“人薬(ひとぐすり)”で改善していく」と書かれていますが、どのような“人薬”が有効的だと考えていますか。
いろいろなところにコミュニティがあるのがいいと思います。近くに気軽に入れる喫茶店があったり、散歩中にあいさつできる人がいたり、少しずつ人との繋がりがあることを感じられるのがいい。もちろん親密な人間関係があってもいいと思うんですけど、親密な人間関係は少しストレスになることもあるじゃないですか。だから訪問看護師さんが週1回来るというのも僕としては有効だと思っていて、大勢の人が善意で関わってくれている状況が人薬的になるんじゃないかなと思います。
――親密な人間関係があったほうがいいと思っていたので、意外です。
イタリアにサルディーニャ島という”長寿の島”があるんですけど、長寿ということは脳の機能も体の機能も衰えが少ないわけじゃないですか。その長寿の理由を調べた研究があって、2位が親密な人間関係があることで、1位はsocial integration(社会的統合)、要するに“社会の中に所属している”という感覚なんです。親密な人間関係より気軽な人間関係のほうが上なんですね。もちろん、これは「親密な関係が重要でない」という意味ではなく、両者が相互に作用しながら、特に社会的統合が全体の健康や長寿に強い影響を与えるということです。
――家族としては頑張って何かをやってもらいたいと思ってしまうのですが、それはストレスですか?
アルツハイマー型認知症において、意欲低下が一番の主症状だと言われたりもする。だから頑張って何かをやろうとしてもなかなかできないんですよね。でも、一緒にやるんだったら、もしかしたらできるかもしれない。
――認知症がわかってやめてしまった畑仕事をまたやってくれたらと思うんですが、一緒にやれば忘れていたことを思い出す可能性はある?
あると思います。平塚に僕も関わっているSHIGETAハウスというのがあって、認知症の当事者とスタッフと家族とで畑をやったことがあります。やっているうちに昔の知識が戻ってきて、しかも自尊心も持てるので、いい状態になると思いますよ。
■認知症をしっかり診てくれる病院の探し方がある!?
――認知症かもと思った時に病院選びも大切だと思いますが、どのように選ぶのがいいのでしょうか。
ある一定年齢になったら“かかりつけ医”がいて、高齢者の認知機能を低下させないように考えられるといいですよね。うちの場合はかかりつけ医機能と認知症の診療機能(診断機能及びフォローアップ機能)を備えているから、そういう意味ではよりいいのかもしれない。名前は「メモリーケアクリニック湘南」ですが、基本理念としては、「その人が大切にしてきた人生と、これからの暮らしの質の両方を支える」という意味です。僕以外の常勤4人は、いずれも“かかりつけ医”というスタンスですが、もともとの専門は、2人が外科医で、もう1人は内科医、もう1人は麻酔科医です。僕は精神科が専門ですが、健康全体を総合的に診る“かかりつけ医”という立場です。訪問診療もやっていて、最後まで面倒を見ようというスタンスでいます。
――理想的な病院です。でも日本全体を見ると、そういう病院は少ない印象です。
現在、「認知症診療」を前面に掲げている医療機関は決して多くはありません。その背景には、認知症が“治りにくい病気”という印象や、診療の難しさ、時間的・心理的負担の大きさなどがあるのかもしれません。しかし今後、高齢者人口の増加とともに、認知症の患者さんが地域医療の中心的な存在になっていくことは確実です。
実際に、かつては認知症をほとんど診ていなかった医療機関でも、いまでは認知症の患者さんが多くを占めているという例も少なくありません。 時代の変化とともに「医療のボリュームゾーン」は変わっていきます。 これからの地域医療は、認知症を避けるのではなく、真正面から向き合い、支えていく医療へと進化していくことが求められています。
――現状、認知症をしっかり診てくれる病院の探し方はありますか?
日本認知症学会というのが認知症関連で一番権威がある学会とされていて、日本認知症学会のHPから近くの専門医がいる病院を検索することができますよ。あとは、老年精神医学会、私が理事をつとめる日本認知症予防学会でも各学会の専門医を探すことができます。
■老後は認知症があったほうが幸せかもしれない!?
――認知症は家族のことも忘れてしまう怖い病気だというイメージがまだまだ強いと思います。数多くの認知症の方を診てきた先生から見て、認知症は怖いものですか?
施設に入って何も分からなくなった人たちを突然見させられるから「こんな風になっちゃうの!?」と思うんでしょうけど、認知症の変化はゆっくりです。それに、人によって認知症があっても幸せな人と、認知症がなくても不幸せな人がいるから、認知症だから怖いというものではない。認知症であっても、穏やかで幸せに暮らしてる人は多くいらっしゃいます。
――漠然としたイメージだけで、「認知症にだけは絶対なりたくない」と思っている人は多いですよね。
それは「絶対、死にたくない」というのに近い気がします。僕は在宅医療を約14年間やってきているので、少なくとも百人以上は看取ってきました。ですから“人は死ぬ”ということが当たり前の事実としてあるんですけど、老化したり、死を迎えることを自分とは関係ないと認識している人も多いんでしょうね。
――認知症は人間が死ぬまでの間に自然に起こりうることなんですよね。でも普段の生活が死からあまりにも遠いから、それを受け入れることが難しい。
そうですね。ただ一方で、もし頭がずっと明晰なままだと、かえって不安や死への恐れが強くなることもあると思います。認知機能が少しずつゆるやかに変化していくことが、ある意味で心を守る作用を持つこともあるのではないでしょうか。実際、身体の衰えが先に来て、意識がはっきりしているほうが、むしろつらそうにされているケースも見てきました。そう考えると、認知機能の変化もまた、自然な老いの一部として、穏やかに受け入れていく視点があってもよいのかもしれません。
――本人が幸せで穏やかな余生を生きてくれることが、家族としては一番なんですけどね。
これから認知症への偏見は減ると思いますよ。認知症かそうじゃないか分断するような話じゃない。今すでに、アミロイドβがどれだけ溜まっているか採血すれば分かる時代なので、そのうち「そろそろアミロイドβを消す治療をしたほうがいいかな」という会話を友だち同士で気軽に話す時代が来ると思うんです。
今でもアポリポ蛋白E(ApoE)遺伝子検査を受けると、認知症になりやすいかどうかが分かります。うちの病院でもできますけど、受けたいと思いますか。
――それは……受けたくないですね。なりやすいという結果が出るのが怖い。
いつ死ぬか分かっていて生きるのもしんどくないですか。でも、明日死ぬかもしれない可能性はみんなに残っているわけです。だからこそ、今日という一日を、自分なりにきちんと生きてみようって、自然とそういうところに行き着くのかなと思います。不安があっても、その人の歩幅に合わせて一緒に考えてくれる。そんな医療があれば、少し先のことも、怖くなくなるかもしれません。
先生の話を伺ってまず感じたのは、「認知症」という点だけを見ているとつらく感じることも、長い人生を俯瞰で見た時、認知機能が低下することは、いたって自然だということ。そう思うと、これまで「認知症」に抗おうと力が入りすぎていたなと気づきました。そして、「アルツハイマー病連続体」が40代から始まっているということは、自分自身もすでにその中にいるということ。親の話だけでなく、遠い未来でもなく、今現在の自分ごとなんだと背筋が伸びます。
その時、自分がどうしたいのかを考えると、内門先生のような「かかりつけ医」と出会うことの大切さを思います。現在放送中のドラマ「続・続・最後から二番目の恋」に、還暦を前にした主人公がかかりつけ医を探す回があって、すべてはつながっているなと思ったり。この連載が、ナチュラルに「認知症」と付き合える一歩となれると幸いです。
加治屋 真美
この著者の記事一覧はこちらPage 2
ビジネスパーソンの心とからだの健康についての様々なコンテンツをお届け。医師監修のもと、ストレスから心と体を守る方法などの心身の健康に関する情報を提供します。