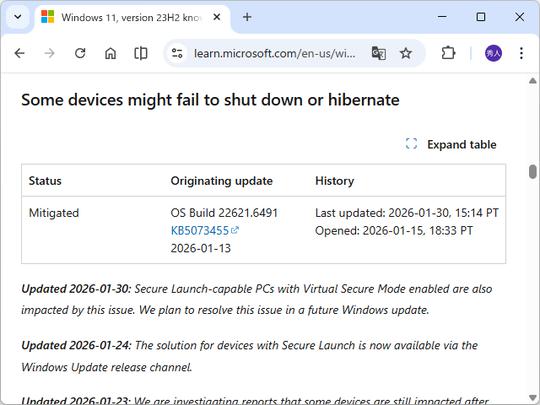IBMのMCAバスに対抗してAT互換機メーカー9社が共同で開発したEISA 消え去ったI/F史
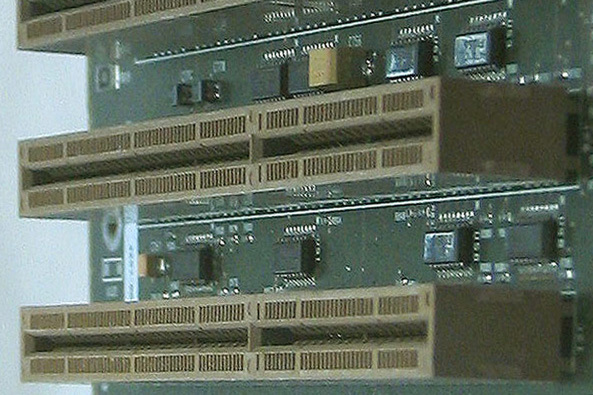
久々の「消え去ったI/F史」となる今回は、ISAの後継バスの話をしたい。連載490回と連載491回で、IBM-PC/ATが生まれてから消えるまでの話をした。端的に言えば、IBM-PCは大ヒットした(これが連載490回)が、そのIBMをはるかに上回る勢いでIBM-PC互換機メーカーの売上が伸びることになった(これが連載491回)ということだ。
連載491回の最後でも触れたが、1988年末にIBM-PCとその互換機は1190万台出荷され、その内IBMが出荷したのは122万9000台とされるので、市場シェアは10%弱といったあたり。
もともとIBMが切り開いた市場にもかかわらず、そのIBMが10%程度しかシェアが取れない、ということが当時ESD(Entry System Division)のトップだったBill Lowe氏にとっては我慢できなかったのだろう。このあたりは、もしDon Estridge氏が生きていたらどういう判断を下したのか興味あるところだ。
そもそもEstridge氏は市場を広げないと成功は覚束なく、そして市場を広げるためにはオープンスタンダード的に構築するのが一番であるという信念に基づいて開発の指揮を執ったからこそ、回路図からBIOSまで全部公開するという荒業に出て、その結果が市場の爆発的な拡大である。したがって、マーケットシェアよりも自社の出荷台数を重視する方向に舵を切った気がするが、これはタラレバの話なのであまり意味がない。
次世代バスとして設計されたMCA ライセンス料が高額なため市場が拒絶
では互換機を封じ込めるためにどんな手が打てるか? 実はあんまり打てる手がなかった。CPUや周辺チップ、メモリー類はいずれもインテル製の汎用品で、これを独占することは不可能だった。周辺機器類も同じであり、いずれも汎用品がすでにたくさんあるので、IBMでなにかを独占するのは無理である。
例えばセキュリティチップを搭載し、それがないと起動しない対策を取っても、それが効果的なのはIBMから提供されるPC-DOSを利用した場合であって、マイクロソフトから提供されるMS-DOSにそんな対応を求めても拒否されるのは目に見えている。
BIOSの著作権による保護は、クリーンルーム方式で互換BIOSを製造されると無効というのはCOMPAQやPhoenix BIOSですでに実証済みである。マザーボードの回路にしても、実際完全にコピーした互換機は存在しないし、そもそもがインテルのリファレンスデザインにのっとる形で製造されていたら、そこに著作権云々を言い出すのは無理がある。
同様にXT-BusやISAはIntel 8088/80286のバスプロトコルそのものなので、これに著作権云々を言い立てても勝ち目がない。だからXT-BusやISAを捨てて、独自のI/O Busに変更するしか互換機を締め出す方法がなかった、というのが正確なところかもしれない。
とはいえ、それを正直に言うわけにもいかない。だからこそ、「XT-Bus/ISAのままではI/Oがボトルネックになって性能が出ないので、互換性を捨てて高速かつ高効率なバスを用意した」という言い訳が必要になるし、実際技術的にもそうだった。
最大の問題は、CPU BusをそのままI/O Busに転用した関係で、周辺回路とメモリーの両方がISA Busにぶら下がり、CPU性能が上がってもISA Busのままではメモリーアクセスがボトルネックになって性能が上がらないことは事実だった。
そこでIBMはMCA(MicroChannel Architecture)をPCに持ち込むことにした。MCAをデザインしたのはChet "Wild duck" Heath氏だが、氏がいつMCAのデザインを始めたのかを示す明確な資料は見つからなかった。ただ後述するようにMCAは当時のPC向けのバスとしては明らかにオーバーキルであって、実際このあとRS/6000やAS/400、IBM 9370などのシステムにも利用されている。
おそらくはこうした、より強力なシステム向けの次世代バスとして設計をスタートし、その最初の実装がPS/2向けになった、という格好だったのだろう。1987年4月に発表されたPS/2でMCAは初デビューを果たす。
MCAの仕様を簡単にまとめると、16ないし32bit幅のパラレルバスで、バスクロックは10MHzでということで、16bit幅の基本的なモードでも20MB/秒、32bit幅のもので40MB/秒になった。のちにはバスクロックを20MHzに引き上げた上で、オプションとして用意されたAddress Busを利用してデータを送る(この場合64bit幅になる)Data Multiplexing Modeを併用すると転送速度は160MB/秒に達するとしている。