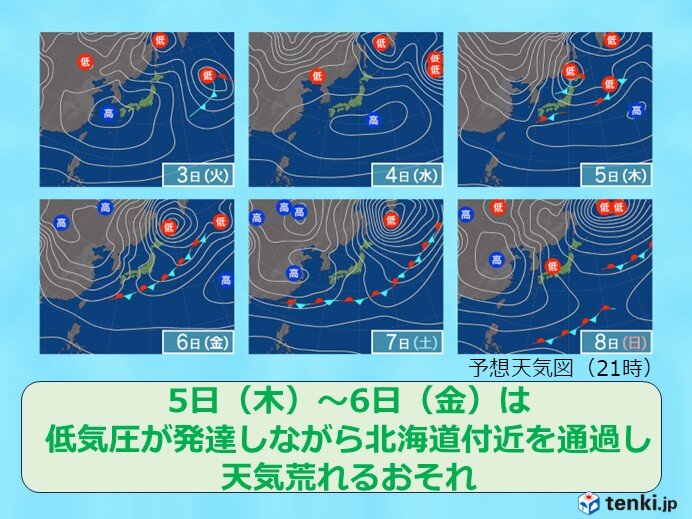寝屋川ショックで公立の統廃合加速か 定員割れ3年ルールと吉村知事の「選ばれる公教育」

少子化時代に公立高校の存在意義が問われている。21日に令和7年度入試一般選抜の合格発表を控えた大阪府では、全日制128校のうち半数以上で志願者数が定員に達しない事態に。少子化に加え、先行導入した私立高授業料の無償化による私学志向の高まりが背景にあるとみられ、今後、府条例に基づく公立高の統廃合など再編が加速する可能性もある。無償化は国も進める方針で、大阪の動向が全国に波及するか注目される。
寝屋川ショック-。大阪府内の公立高入試の出願結果がもたらした衝撃は関係者にそう呼ばれている。倍率が1倍を下回った65校に、難関大への進学実績もある寝屋川、八尾、鳳など伝統校が含まれていたためだ。
府教育庁の担当者は「想定より志願者が集まらず、予測を見誤った部分がある」と明かす。
寝屋川と八尾は5年度入試までの高倍率を踏まえ、6年度入試で定員をそれぞれ1クラス分(40人)増やした結果、倍率は1倍近くまで下がった。7年度入試も同じ定員を維持したが、裏目に出た。
背景には、府内で6年度から段階的に導入が始まった高校授業料完全無償化によって私立を希望する生徒が増えていることがあるとみられる。
府公立中学校長会が昨年11月下旬に行った調査では、私立を第1希望とする専願率が現行制度で過去最高の26・22%となり、公立の第1希望者が初めて7割を下回った。
一方、寝屋川や鳳が立地する各地域でそれぞれトップ校とされる四條畷や三国丘をはじめ、府内随一の進学校である北野など公立10校は、寝屋川などのような普通科の代わりに文理学科を設けている。難関大に進む学力のある生徒を育てる学科で、人気が高い。
無償化された私立が受け皿の選択肢になり、「文理学科(のある公立)に挑戦しやすい環境ができた」(受験関係者)ことが、普通科の公立離れに拍車をかけているとの声もある。
公立高関係者は危機感を募らせている。念頭にあるのが、3年連続で定員割れした公立高を再編の検討対象とする府立学校条例だ。地域政党「大阪維新の会」設立後の平成24年に制定された同条例は、公立と私立の間に競争原理を導入。再編に伴い、平成28年度から令和7年度にかけて府内の公立高は11校減る計算だ。
今回倍率が0・94倍だった鳳は2年連続の定員割れで「崖っぷち」。ただ、1学年当たり7クラス編成で、府教育庁が活力ある学校の運営目安とする規模が「6~8クラス」であることを考えると、クラスを減らし、定員を少なくする余地はまだある。
定員を減らし6クラスを下回ると、部活動の展開といった点で学校の魅力が下がりかねない。近畿圏などで学習塾を展開する開成教育グループの藤山正彦上席専門研究員は「1学年600人規模の私立に比べて見劣りしてしまう」と語る。
一方、府立高等学校教職員組合の志摩毅執行委員長は再編の必要性を認めつつ、条例について「定員割れを統廃合の基準に結び付けており、(学びを保証するべき)公教育とは相いれない」と批判。「定員に近い生徒数を確保している学校は存続させるべきだ」と訴える。
吉村洋文知事は「3年連続定員割れだからといって即、再編整備の対象とするのではない。定員を満たす見込みなど、さまざまな状況を考えて再編していく」と断った上で「選ばれる公教育、質の高い公教育はどういうものかを追求していく必要がある」と強調した。(藤谷茂樹、木ノ下めぐみ)