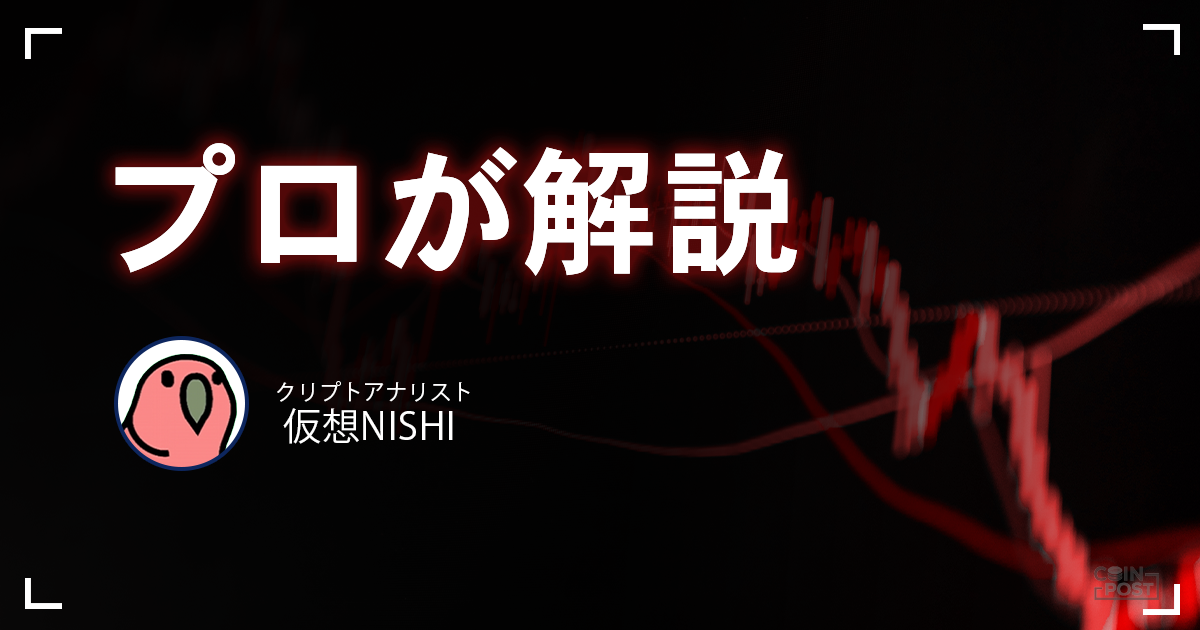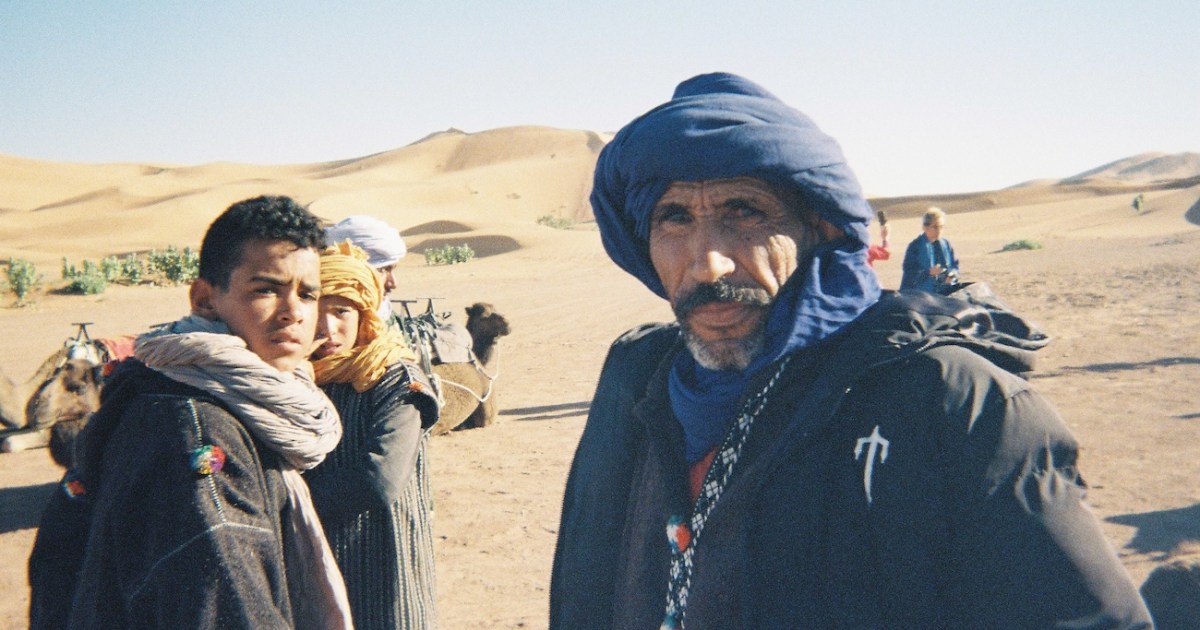日銀の金融機関への付利負担が急増、年内利上げ観測で財務悪化に注目

日本銀行の金融政策運営で政策金利を操作する役割を担う付利制度。日米関税交渉の合意などを受けて年内利上げ観測が広がる中、金融機関への支払利息の急増で日銀財務が悪化する副作用に注目が集まる可能性がある。
白川方明総裁時代の2008年に導入した付利制度では、日銀が金融機関から預かった当座預金のうち、法定預金準備額を超える超過準備に利息を支払う。金融機関には余剰資金を当座預金に置くか、市場に放出するかの選択肢があり、金利差を利用した裁定取引によって市場金利は付利金利に近い水準に誘導される。
日銀は昨年3月、マイナス金利解除や長短金利操作の廃止で大規模緩和に終止符を打った。その後2度の利上げで政策金利である無担保コール翌日物の誘導水準は0.5%程度、付利金利は0.5%となっている。
この結果、24年度の付利負担は1.3兆円と前年度の6.6倍に急増。保有長期国債の運用利回り(0.353%)が付利金利を下回る逆ざやも初めて生じた。
13年4月に黒田東彦前総裁が始めた量的・質的緩和に伴い、付利適用残高は507兆円に上る。単純計算では、付利の負担は0.75%への利上げなら年間3.8兆円。1%まで利上げが進めば5兆円超に増え、赤字決算も現実味を帯びてくる。
ブルームバーグによる1日のエコノミスト調査では、利上げ時期の予想の前倒しが進み、最多の4割超が次の利上げを10月の金融政策決定会合と見込んでいる。5割超は年内とみている。政策正常化路線の継続に伴う財務悪化が鮮明になれば、日銀は付利制度の副作用についてより丁寧な説明が必要となりそうだ。
米連邦準備制度理事会(FRB)や欧州中央銀行(ECB)など多くの中央銀行が量的緩和の際に付利制度を導入している。購入する国債の利回りは通常、付利金利を上回るため、保有国債が増えれば中央銀行の収益は拡大する。一方、利上げ局面では金融機関への支払利息が増えて収益を圧迫する。
日銀が昨年12月に公表した試算では、政策金利2%など厳しい仮定を置いた場合、一時的に赤字が発生する可能性はあるが、債務超過にはならない。植田和男総裁は5月の国会答弁で、利上げ過程で赤字が発生する可能性に言及。長期的には保有国債が金利の高いものに入れ替わるため「収益が戻ってくる」と説明した。
内田真一副総裁も6月の金融学会での講演で、FRBやECBを含む多くの中央銀行が現在赤字を計上し、その一部は債務超過になっていると指摘。その上で、「業務や政策の運営に支障は生じていない」と語った。
こうした日銀の見解について、ピクテ・ジャパンの市川真一シニア・フェローは、日銀のバランスシートは極端に大きく、1%を超える水準に利上げすれば赤字が急速に膨らむ可能性を指摘。「下手をすると日本国債売りとかにつながるリスクがある」とした上で、日銀の金融政策運営上の「大きなネックになってくる」とみる。
銀行への「補助金」
利上げで先行した欧米の事例からも、日銀当座預金への付利はリスクのない運用先として銀行への補助金批判の対象になりやすい。欧米では銀行収益が拡大する中、銀行への超過利潤税導入や中央銀行による利払い停止などが議論になった。
国内銀行も金利上昇による利ざや拡大で好業績が続いている。三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)など3メガバンクが4日までに発表した26年3月期の連結純利益予想はそろって1兆円を超えた。実現すればいずれも過去最高となる。
MUFGの亀澤宏規社長は1日のブルームバーグとのインタビューで、日銀が9月か10月の金融政策決定会合で次の利上げを決める可能性が「十分にある」との見解を示した。銀行には収益を利用者や社会に適切に還元することが求められそうだ。
内田副総裁は6月の講演で、バランスシートの縮小を進めている各国の中央銀行の「多くは伝統的な金融調節方法に戻ることはないだろう」と指摘。市場の求める流動性に見合ったバランスシートを維持しながら、「当座預金への付利によって短期金利操作を行うことになる」と述べた。
第一生命経済研究所の熊野英生首席エコノミストは、利上げで生じる日銀の逆ざやを解消するには国債保有残高を削減していく必要があると指摘。そう簡単に解消しないことは量的・質的緩和が始まった時から分かりきっていたとし、黒田緩和による「負の遺産に植田日銀がチャレンジしている」との見方を示した。
国庫納付金
日銀の収益悪化の影響は財政運営にも及ぶ。日銀は法人税や住民税などを納めているほか、当期剰余金から法定準備金と配当を除いた額を国に納付している。24年度も過去最高の23年度に続き2兆円台だった国庫納付金は、赤字決算ならゼロになる。
24年度の日銀決算では、経常利益は4.6兆円と過去最高の23年度の5.1兆円に次ぐ高水準を維持した。保有国債の利息収入や上場投資信託(ETF)の配当金収入が、付利支払額の増加分の大半を打ち消した形だ。
英国では中央銀行の損失を政府が補てんしている。イングランド銀行は09年以来、資産買い入れの子会社を通じて量的緩和を実施。出口局面で子会社に損失が発生した場合には政府による補てんを取り決めており、22年10月以降に実際に行われた。
ピクテ・ジャパンの市川氏は、これまでは政府の日銀保有国債に対する利払い額よりも、日銀から国庫納付金と法人所得税で受け取る額の方が大きかったと説明。日銀が赤字決算になれば政府の歳入は数兆円単位で減ることになり、「金融政策の決定に影響を与えていく可能性はある」との見方を示した。