埼玉・行田のマンホール転落事故はなぜ起きたのか?事故経緯や専門家を取材 8/4放送

8月2日、埼玉県行田市で、作業員4人がマンホールの中に次々に転落して死亡した事故が発生しました。事故はなぜ起きたのか、これまでの取材や事故経緯、専門家への取材などをまとめました。(記事内容は8月4日放送のものです)
8月2日、埼玉県行田市で作業員4人がマンホールの中に次々に転落して死亡した事故で、4人は硫化水素のガスを吸ったことによる中毒と窒息が原因で死亡したとみられることが分かりました。警察は作業の安全管理に問題がなかったか詳しく調べています。8月2日、行田市長野で下水道管の点検作業をしていた50代の作業員4人がマンホールの中に転落して死亡した事故では、警察ははじめに1人が転落し、助けようとした3人も次々に転落したとみて調べています。
現場では、8月4日、労働基準監督署の担当者も訪れ、調査を行っていました。
死因は硫化水素中毒と窒息か
この事故で警察が、4人の遺体を詳しく調べたところ▼最初に転落した作業員ともう1人は硫化水素のガスを吸ったことによる中毒が原因で、▼残る2人も硫化水素の中毒になったうえ、窒息したことが原因で死亡したとみられることが分かりました。
当時の事故の状況は
現場で作業を行っていた会社の説明によりますと、最初に作業員がマンホールに入る際は硫化水素の濃度を測定する検知器の警報は鳴っていませんでしたが、4人が転落した直後には、安全に作業を行うため、法律で定められた基準の15倍を超える150ppm以上の濃度が、検知されたということです。また、当時、4人はいずれも落下を防止するための器具や地上から空気を取り入れるマスクを着けていない状態だったということです。
警察は硫化水素のガスが発生した状況や、作業の安全管理に問題がなかったか詳しく調べています。
「三栄管理興業」のコメント(3日)「亡くなられた方のご冥福を心よりお祈り申し上げるとともに、ご遺族の皆さまには深くおわび申し上げます。事故の原因究明に全面的に協力し、今回の事態を厳粛に受け止め、再発防止に向けた対策を速やかに講じてまいる所存です」
八潮の大規模陥没受け作業中に発生
八潮市で発生した道路陥没事故2025年1月、埼玉県八潮市で起きた大規模な道路陥没を受けて、2か月後の3月に国土交通省は下水道管を対象とした点検を全国の自治体に要請しています。今回の事故は、この一環で行われている点検で起きたもので行田市によりますと、現場の下水道管は、河川の下を潜る形で設置されている伏越管路(ふせこしかんろ)と呼ばれる形状で、汚物などがたまりやすく、硫化水素などが発生しやすいということです。そのため、市は事故現場周辺のおよそ180メートルの下水道管を最優先で調査するため、指名競争入札でさいたま市の会社に発注を行ったということです。
市側は、入札前に転落防止や硫化水素などの対策を行うよう入札業者側に求めていて、落札したこの会社からは、調査を開始する際に▼落下防止器具を使用することや▼酸素や硫化水素の濃度を測定して安全を確認してから調査を行うことなどと伝えられていたとしています。
行田市下水道課(コメント)「亡くなられた方のご冥福とご家族にお悔やみ申し上げます。捜査状況を踏まえて、今後の対応を検討したい」
事故の経緯(詳報)現場では何が?
点検作業を行っていたさいたま市の会社や埼玉県行田市によりますと、事故があった下水道管は、河川の下を潜る形で設置されている伏越管路と呼ばれる形状で、マンホールの穴が、直径がおよそ60センチ底までの深さはおよそ12メートルありました。汚物などがたまりやすく、硫化水素などが発生しやすいということです。
7月16日と17日に下水道管に入り目視で点検したところ、腐食などの異常が確認され、詳しく調べるため、8月2日は下水を抜く作業が進められる予定でした。
死亡事故の経緯は?
【事故発生前まで】事故があった8月2日は、午前8時から作業員あわせて12人で作業が開始されました。下流のマンホール内では、酸素濃度に問題はなく、硫化水素の濃度も基準を下回る10ppm未満だったことから作業員がマンホールに入って、排水ポンプを設置する作業を始めました。硫化水素の濃度の計測は、作業員がマンホールの中にいるときは常に行い、異常を知らせる際には警報が鳴る仕組みとなっていました。午前9時ごろから、排水ポンプで水を抜く作業を始めたところ、硫化水素濃度が30ppmから上がり続けていたため中にいた作業員を避難させて、ポンプを停止したということです。排水作業によって、管内の下水がかき回されたことで硫化水素の濃度が上がったとみられます。
【1人目の落下】その後、午前9時10分から20分ごろ内部の状況を確認するために、作業員1人が通常は使わない下水道管に直接つながるマンホールからはしごを使って地上からおよそ9メートルの深さまで入りました。このとき、ふだんは必ず装着する落下防止の器具をつけていませんでした。硫化水素を計測するガス検知器からの警報は鳴っていなかったということです。地上にいた別の作業員はマンホールの中から大きな声がしたため、作業の指示だと思い、その場を離れましたが、その後、マンホールの中から作業員が落下するような音を聞いたため、現場責任者に報告しました。
【2人目の落下】報告を受けた現場責任者は、すぐにもともと使われる予定だった踊り場につながるマンホールから中に入りましたが落下防止の器具をつけておらず、濃度はわからないものの、ガス検知器の警報が鳴っていたということです。その後、別の作業員2人がロープをマンホールの中に垂らしてつかまるよう叫びましたが、反応がなかったということです。
【3人目の落下】警報器は鳴っていたものの、ロープを垂らした作業員のうち1人も、踊り場につながるマンホールから入りましたが、この作業員も落下防止器具をつけていなかったということです。その後、地上にいた作業員が午前9時25分に119番通報をしました。
【4人目の落下】さらに、別の作業で一時現場を離れていた作業員が、3人が落下したという報告を受けたあと姿が見えなくなりました。この作業員は、踊り場につながるマンホールから穴に入っていて、落下防止器具をつけていなかったということです。その後、姿が見えなくなった4人目の作業員を探すために別の作業員がマンホールの中に入ったところ4人が中で倒れているのを確認しました。この際、ガス検知器の警報が鳴っていて、硫化水素の濃度は基準の15倍を超える150ppm以上でした。事故が起きた日は、7月の点検で硫化水素の濃度に問題がなかったことから、「エアラインマスク」と呼ばれる地上から空気を取り入れるタイプのマスクを現場に持ってきていなかったということです。
専門家“安全意識不十分”
下水道に詳しい東京大学大学院の加藤裕之特任准教授は、現場で作業を行っていた会社の安全対策について、「意識が十分でなかったと言わざるを得ない」と指摘しました。加藤特任准教授は長年、国土交通省などで下水道政策などを担当し、2025年3月に秋田県男鹿市で起きたマンホールの中で作業員3人が死亡した事故では、再発防止に向けた県の委員会で委員長を務めました。加藤特任准教授は、事故の原因について、硫化水素を発生させる菌は▼下水のような酸素濃度の低いところで繁殖しやすく、▼30度以上になると活動が活発になる特徴があるため、下水道のような狭い空間では硫化水素が充満しやすいとして、「作業を始めるときに濃度が低かったとしても下水を触ったりすることで水中の硫化水素が空気中に出てくる可能性もある」と指摘しました。また、会社が7月に行った作業時に現場の硫化水素の濃度に問題がなかったため、今回、「エアラインマスク」と呼ばれる地上から空気を取り入れるマスクを用意していなかったとしていることについて、「7月の作業時とは水温など現場の状況が全然違うおそれがあるので、『前回大丈夫だったから』というのは、安全に対する意識が十分でなかったと言わざるを得ない」と指摘しました。そのうえで、加藤特任准教授は、埼玉県八潮市で発生した陥没事故を受け、全国で下水道管の点検が進む中、点検を急ぐことで作業員の安全対策がおろそかになるおそれがあるとして、事故の教訓を全国で共有することの重要性を訴えました。
加藤 特任准教授「ドローンによる点検など人が中に入らずに済む技術開発も進んでいるが、見た目だけでは下水道管の腐食の度合いが分からないこともあり、現状では一定の限界がある。インフラの老朽化により、地下での作業はこれからますます増えていくので、国と自治体、そして作業を受注する企業が『地下の作業は危険』という意識を常に持ち、作業員の安全を最優先にコミュニケーションをとっていくことが必要だ」
全国で相次ぐ下水道事故
下水道での作業中に作業員が死亡する事故は全国で相次いでいます。
相次ぐ下水道事故
2020年10月 茨城県土浦市 汚泥を取り除く作業中に転落し2人死亡 2023年11月 静岡県伊東市 清掃作業中に意識を失い男性死亡 2025年3月 秋田県男鹿市 マンホールの中で作業員3人死亡2020年10月には、茨城県土浦市で下水管の汚泥を取り除く作業にあたっていた作業員2人が相次いでマンホールの底に転落し、死亡しました。警察の調べによりますと、2人の死因はいずれも、十分な換気が行われず酸素が欠乏したことによる窒息死だったということです。
また、2023年11月には、静岡県伊東市でマンホールの中で下水道の清掃作業にあたっていた作業員の男性が意識を失って倒れ、死亡しました。
そして、ことし3月には、秋田県男鹿市の下水道工事の現場で、作業員3人がマンホールの中で倒れているのが見つかり、死亡しました。秋田県が設置した委員会は、事故の原因について長期にわたって送水を止めていた「圧送管」と呼ばれる管に水を通したことで、管の中にたまっていた硫化水素ガスや酸素濃度の低い空気などが漏れ出した可能性が高いことを明らかにしていて、警察や労働基準監督署による調べが続いています。
対策は?ドローン活用も
人のかわりに機械で下水道管を点検できるようにしようと、千葉市の会社では下水道管の内部で使える小型のドローンの開発を進めています。千葉市の会社が開発した縦と横の長さがおよそ20センチの「超狭小空間点検ドローン」は、直径50センチの狭さでも使うことができ、2025年1月に埼玉県八潮市で発生した大規模な道路陥没では、下水道管の中を飛行して転落したトラックの運転席部分を見つけました。
2025年3月に秋田県男鹿市の下水道工事の現場で作業員3人が死亡した事故を受けて、7月にはこのドローンで下水道管の内部を点検する調査を秋田市で行いました。
ドローンは、管の内部をLEDライトで照らしながら点検し、地上のモニターでリアルタイムで異常がないか確認することができます。下水道管の中には水位や硫化水素の濃度が高く作業員の立ち入りが難しい場所もあり、そうした場所での活用が期待されているということです。
一方、▼映像だけでは管の腐食の程度がわからないことや▼水没すると動かなくなることなどが課題で、会社は今後、▼超音波で腐食の程度を確認できるようにしたり、▼防水機能を高めたりして対応していくとしています。
ドローンを開発した会社 閔弘圭 代表取締役「人が下水道の中に入って直接点検するのは危険を伴いますが、ドローンを活用すれば安全に作業できます。インフラの老朽化は社会課題になっているので、解決のためにこれからも活動していきたいです」
国土交通省 安全対策徹底の通知
国土交通省は、8月4日、下水道管で作業をする際の安全対策を徹底するよう全国の自治体に通知しました。具体的には、▼下水道管内の硫化水素や酸素濃度の測定や換気を行うほか、▼転落を防止する器具の使用、▼緊急時用の酸素マスクを準備するなど、自治体が委託事業者に対して適切に指導・監督することなどを求めています。
今回の事故は2025年1月に埼玉県八潮市で発生した大規模な道路陥没を受けて国土交通省が2025年3月、全国の関係自治体に要請した下水道の特別調査の中で起きていて、調査に当たっては何よりも安全確保を最優先するよう自治体や事業者に求めています。
下水道の特別調査とは今回の事故は、2025年3月に国が自治体に要請した下水道管の特別調査に基づく点検作業の最中に起きました。この「全国特別重点調査」は、2025年1月に埼玉県八潮市で発生した大規模な道路陥没を受けて、国土交通省が2025年3月18日付けで全国の関係自治体に要請しました。調査の対象は、▼1994年以前に設置され、▼直径が2メートル以上と大きい下水道管で、総延長は47都道府県のおよそ500の自治体にある5000キロメートルに上ります。
このうち、下水道管の構造や地盤の条件が八潮市の現場と類似する1000キロメートルについては特に緊急性が高いとして優先的に調査を行うよう求めていて、国土交通省によりますと、今回の行田市での点検は、優先的な調査の一環だったということです。
国土交通省は▼優先的な調査については8月8日まで、▼それ以外については2026年2月末までに結果を報告するよう要請していますが、調査に当たっては何よりも安全確保を最優先するよう自治体や事業者に求めています。
また、今回の事故を踏まえた再発防止策をまとめて、改めて知らせるとしています。
Page 2
「防災・減災」に関する記事、最新情報から話題のニュース。「防災・減災」がわかるデータや今起きていることをお届けします。
Page 3
「防災・減災」に関する記事、最新情報から話題のニュース。「防災・減災」がわかるデータや今起きていることをお届けします。
Page 4
北関東の注目ニュースや暮らしに関する「もっと」知りたい情報を、詳しく掘り下げてお届けします。
Page 5
Page 6
甲信越の注目ニュースや暮らしに関する「もっと」知りたい情報を、詳しく掘り下げてお届けします。
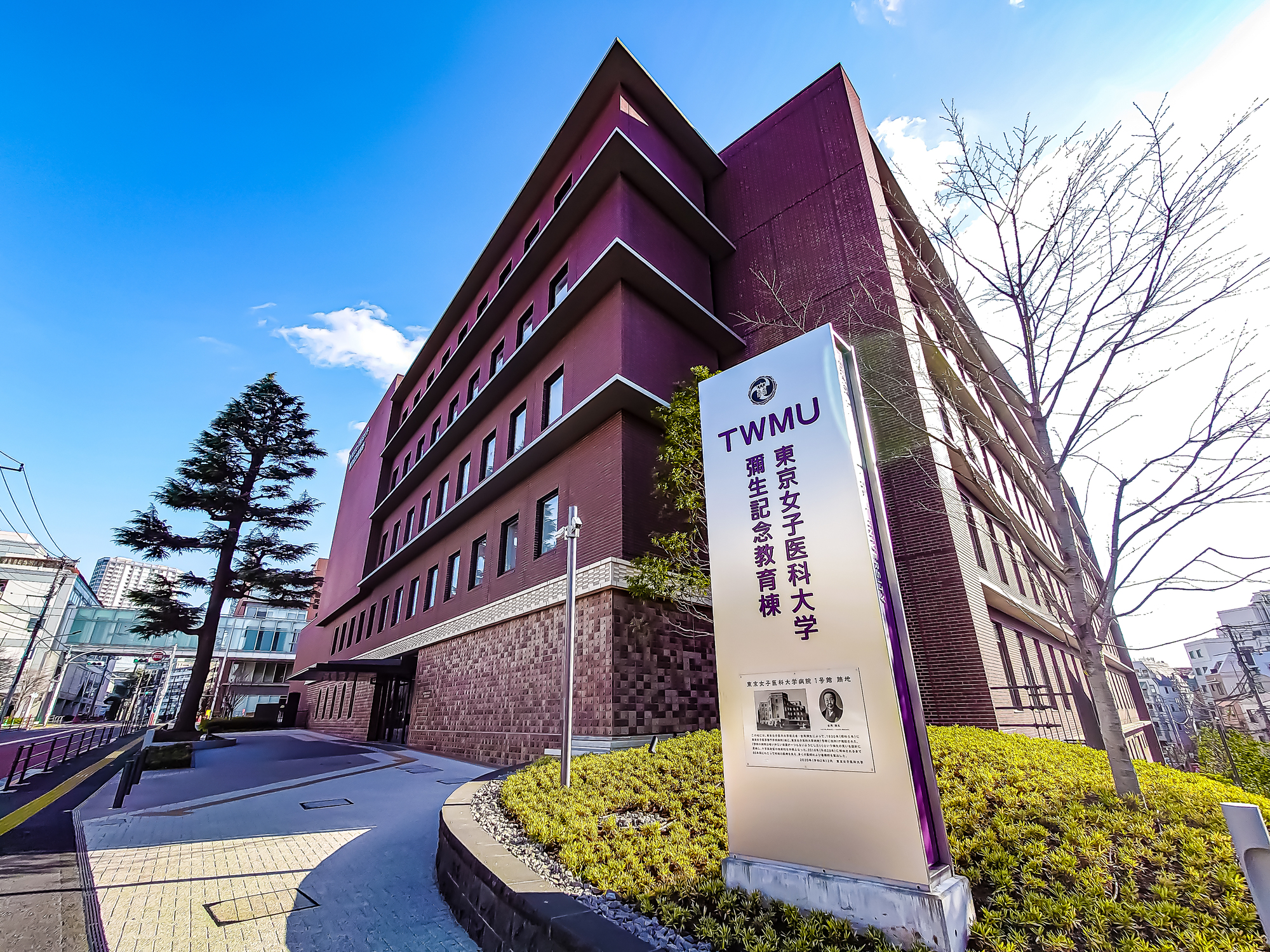


![農水省の元職員が自死、「セクハラ被害、対策せず」国に賠償求め提訴 [福岡県]:朝日新聞](https://image.trecome.info/uploads/article/image/5c6399cf-edc2-499e-928f-540eab4b07d8)