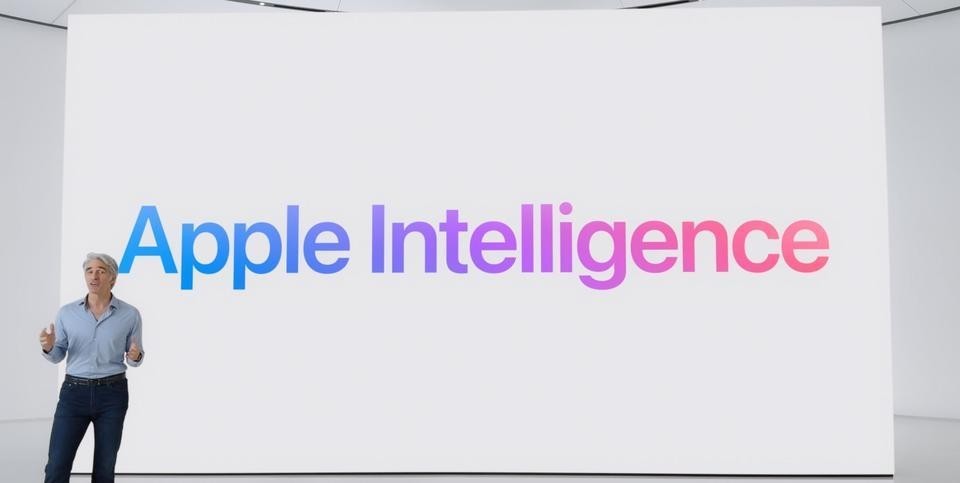【2028年終了】なぜ、ドコモの衛星電話「ワイドスターII」は日本のStarlinkになれなかったのか?(スマホライフPLUS)

一方で、Starlinkが選んだ低軌道(LEO)は、そのアイデア自体は1990年代から存在しましたが、技術的・コスト的な課題から大規模な商用化は困難とされてきました。いまでも「ケスラーシンドローム」のリスクなど、低軌道衛星に対する懸念の声は多いです。 Starlinkの革新性は、低軌道(LEO)の大規模な商用化にあることは間違いありません。すなわち「高遅延で低速」という根本的な問題を解決し、地上系の光ファイバーや5Gに匹敵する大容量かつ高速なユーザー体験の提供を実現したことは大きな功績でもあるでしょう。 ■【理由2】「B2B特化」と「グローバル」 第二に、両者はターゲットとする市場とビジネスモデルの射程が全く異なっていました。 ワイドスターIIは、前述の通り、その誕生の経緯から一貫してB2B(Business to Business)およびB2G(Business to Government)市場に特化してきました。災害対策や事業継続計画(BCP)のために、高価であっても確実な通信手段を確保したいという、支払意欲の高いニッチな顧客層がターゲットでした。その市場規模は本質的に限定的であり、一般消費者へと爆発的に普及するモデルではありません。
対照的に、Starlinkは創業当初から法人需要に加えて「グローバルなB2C(Business to Consumer)」市場を明確に視野に入れていました。全世界でインターネットにアクセスできない、あるいは不満を抱えている数十億人という巨大な潜在市場も潜在的なターゲットに据えたのです。 このビジネスモデルは、衛星通信を一部の専門家や大企業のものではなく、一般家庭の選択肢へと変貌させました。その成長スピードは従来の通信事業者の常識を遥かに超えています。このグローバルなフォーカスが、圧倒的な普及率とブランド認知度をもたらしました。 ■コスト構造の違い ビジネスモデルの違いは、コスト構造と価格戦略に直結します。 ワイドスターIIの価格が高価なのは、その「高信頼性」を担保するためのコストが反映されているからです。2局の地上設備や冗長化されたシステムなど、万が一の事態にもサービスを継続するための投資は莫大です。これらのコストは、限られた数の法人ユーザーで回収する必要があるため、必然的に単価は高くなります。 たとえば2025年4月から実施された通話料の大幅な値上げ(例:携帯電話発→衛星電話着が30秒55円から177.1円)は、サービス維持コストの厳しさを物語っていると言えるでしょう。 一方、Starlinkの最大の強みは、その革命的なコスト構造にあります。親会社であるSpaceXが、ロケットの開発、製造、打ち上げ、そして再利用までを自社で一貫して行う「垂直統合モデル」を確立していることです。こうしたコスト削減により個人でも手の届く月額料金(日本では月額6,600円から)という形でユーザーに還元され、普及の最大の原動力となっています。