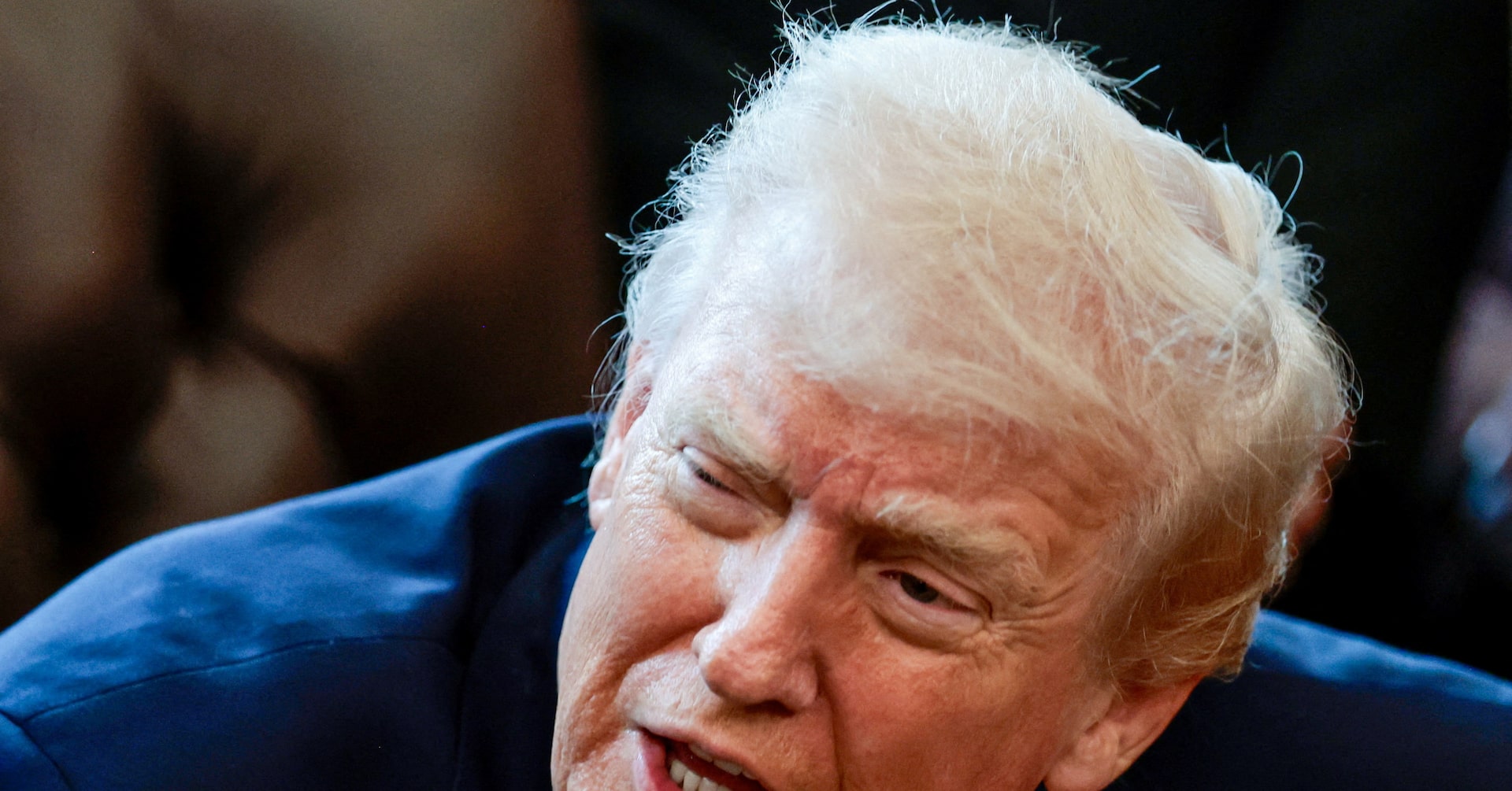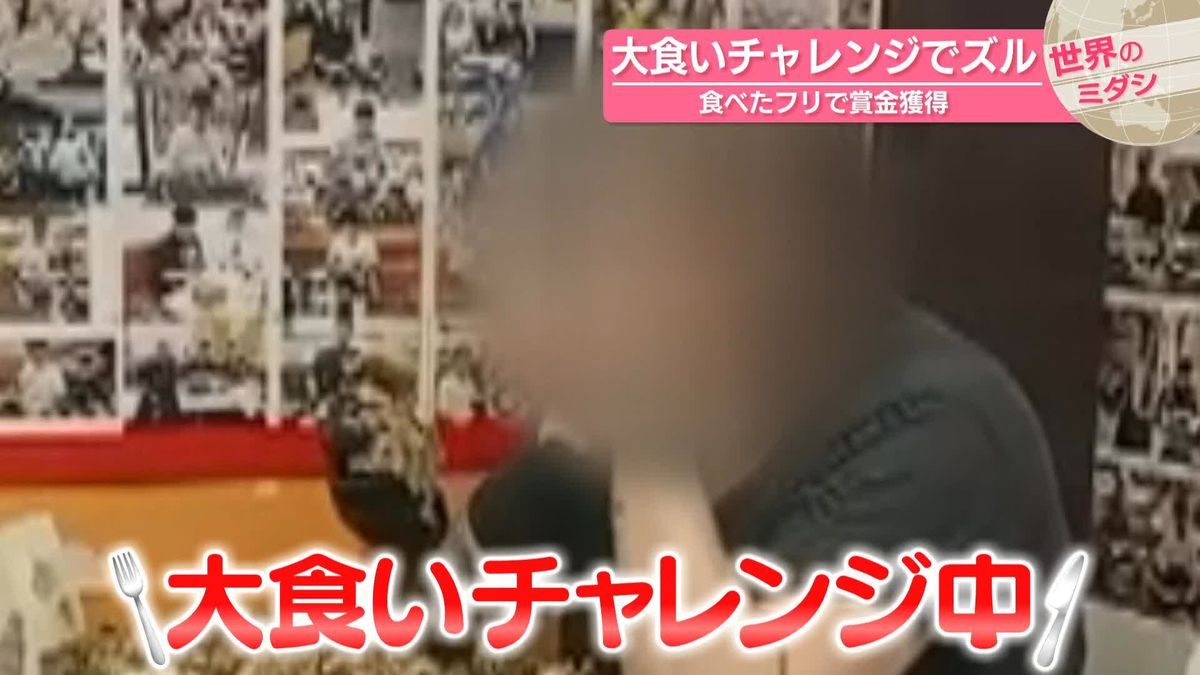2年間続けたヒゲ脱毛 男らしさの行方は?

男性のヒゲ脱毛への関心が高まり続けている。頭髪以外のあらゆる毛が「むだ毛」とされ、無毛社会とも言える風潮には、男らしさの象徴の一つであるヒゲもあらがえない。その喪失は現代社会で何を意味するのか。自らもヒゲ脱毛を2年間続けた記者(46)が探った。(デジタル編集部 斎藤健二)
男だってきれいになりたい?
記者は2年間で16回、ヒゲ脱毛を行った。写真は5回目の施術時で、この頃には頬からはほとんど生えなくなっていたそもそもヒゲはなぜ生えるのだろう? 細菌や風、寒さから肌を守る、性的なアピールなどの生物学的な役割があげられる。ただ、衛生的で保温にも優れた現代社会ではそうした役割は不要となり、そることが推奨されて久しい。ヒゲはむしろ社会的な役割を担わされてきたと言える。「ヒゲの日本近現代史」(講談社現代新書、2013年)を著した共立女子大の阿部恒久名誉教授は「明治期や戦争時には権力や権威、学生運動時はヒゲが反体制の象徴とされ、高度経済成長のサラリーマン拡大期にはヒゲなしが従順の証しとして機能した」と解説する。では、昨今流行するヒゲ脱毛は何を意味するのだろうか。阿部名誉教授は「社会進出が進んだ女性との関わりが増え、基本的には『男だってきれいになりたい』という話。一方、それに対する意識的な反発もあり、ヒゲを生やす男性も少なくないが、あくまで女性に嫌われないよう、威張らずおしゃれな無精ヒゲ風を選んでいる」。
阿部名誉教授はヒゲを巡る状況の変化要因として、①権力側のはたらきかけ②欧米文化の影響③女性の目線④カミソリなど器具の発達、の4点をあげる面倒なヒゲそり
記者がヒゲ脱毛に乗り出したのも、変化を続ける社会の美意識の影響を知らず知らずに受けたからかもしれない。コロナ禍のマスク生活が続いていた2021年5月。10年ぶりに会った友人がマスクを取ると、見た目が一変していた。若い頃に特徴的だったそり残しの青ヒゲは面影もなく、むきたての卵のように肌はツルツルだった。「毎日のヒゲそりもなくなったし、ヒゲ脱毛おすすめだよ」
それから2年――。新型コロナウイルスが感染症法上の「5類」に移行した2023年5月以降、マスクを外す機会が増えたものの、記者はヒゲそりがすっかり面倒になっていた。「将来、生やしたいと思うこともないだろう」。同月中にヒゲ脱毛を決断した。
蓄熱式のイスラエル製医療用レーザー脱毛機。アルマレーザーズ社は20年以上、世界の脱毛市場をけん引している医療用レーザー脱毛機の進化
都内の自宅近くにちょうどその頃開業した皮膚科医院に通い始めた。同院は蓄熱式のイスラエル製医療用レーザー脱毛機を使っている。別の医療機関で勤務しているときに、ヒゲ脱毛の需要の高さを肌で感じたという光谷純郁院長は「医療用レーザー脱毛機の進化で痛みが少なく、スピーディーに施術できるようになったことが大きい。ヒゲ全体の脱毛は1回につき15~20分ほどで終わる」と話す。
ヒゲにレーザーを照射する時の痛みに耐えるため、施術時に記者はボールを握りしめていた照射時の痛み、大きなハードル
医療脱毛は、医師または医師の監督・指示の下、看護師が行い、毛の黒い要素であるメラニンにレーザー光を反応させて、毛を作り出す細胞などを破壊する。これが医療行為に該当するわけだ。一方、エステやサロンは医療資格のないエステティシャンが施術するため、医療用のレーザー脱毛機は使用できない。出力の弱さなどから、厳密には脱毛とは呼べない。
ヒゲ脱毛には大きく分けると、蓄熱式とショット式がある。記者が続けたのは蓄熱式。低出力のレーザーを2~7秒間、繰り返し照射することで皮下に熱を蓄積して毛に関連する領域を破壊する。ショット式に比べ、痛みややけど、ムラが生じるリスクが低いとされる。とはいえ、照射時に生じる痛みが、ヒゲ脱毛の大きなハードルだ。
前より若く見られるように
「ヒゲ脱毛は回数がかかるため、通いやすさも大事」と話す光谷院長一般的に脱毛の完了には10~15回かかる。施術は1か月に1回ペース。記者はまずヒゲ全体を脱毛する6回コースを選んだ。回数を経るごとに毛量が減り、照射時の痛みを感じることが少なくなった。半年後には大部分のヒゲがなくなり、毎日の処理が楽になった。めざましい効果を実感した。だが、口周りにはまだ多く残っていたため、さらに10回追加。日焼けをした夏から秋はやけどのリスクがあることから通院を避けた。施術後に患部が少し赤くなることがあった程度でトラブルはなかった。男らしさの象徴を一つ喪失したとの思いも全くない。2025年5月現在、唇下にヒゲが少し残るが、他部位にはほぼ生えてこない。ちなみに白髪には照射効果がない。
同院へのヒゲ脱毛の来院者は徐々に増え、1か月に12人訪れたこともあったという。光谷院長は「ヒゲ脱毛後は、前より若く見られるようになったという声をよく聞く。日々のお手入れの時短から仕事上の身だしなみ、美の追求など男性の意識が変化し、ニーズも多様化している」と話す。
コロナ禍で時間 体毛を意識
東京未来大の鈴木公啓准教授(社会心理学)らが2023年2月に男性約1500人に行った調査では、医療機関やエステでの脱毛経験は20代が16%、30代、40代も1割を超えた。「興味関心あり」は20代34%、30代31%、40代25%だった。特に20代はコロナ禍での脱毛経験が1割近かった。
鈴木准教授は、ヒゲ脱毛への関心の高まりについて「コロナ禍で時間に余裕ができたことが大きい」と話す鈴木准教授は「コロナ禍で時間に余裕ができ、自分の顔や体に向き合う時間が増えたことも大きい。特に若者はソーシャルメディアなどを通じて、体毛処理の広告や韓流アイドルらのツルツルした外見などが、日常的に目に入る。そのことによって、自分の体毛を意識するようになることもある」と話す。現代社会の底流としてあるのは男女平等や清潔、健康志向だ。男性の場合、パートナーの女性から勧められることもあるという。「若い男性は、今はまだ、ヒゲ脱毛をしたい人はするぐらいの段階。『皆するのが当たり前』となると息苦しい世の中になる」と鈴木准教授は指摘する。
脱毛トラブルも増加傾向
男性脱毛の料金は、女性より高く設定される傾向がある。毛が濃く、量が多いため、施術回数も増える。美容産業は、女性市場が飽和状態のため、当然男性もターゲットに入れている。電車内やインターネットの広告で「脱毛」を目にしないことはない。ただ、脱毛とは言え、費用は高額で身体に危害が及ぶリスクも伴う。国民生活センターによると、ヒゲなどを含む脱毛エステの男性からの契約・解約を巡る相談件数が増えている。2014年度には112件だったのが、24年度には約10倍の1016件。やけどなど身体被害の相談も寄せられている。
たかが毛、されど毛 薄毛と脱毛に資本主義の構図
著者の藤田さんは薄毛をテーマに幅広い対象を取材し、美容・健康分野のコンプレックスビジネス全盛の時代を照射したかつてコンプレックスを刺激する大量のテレビCMや広告で集客するのは、育毛・カツラ産業が有名だった。薄毛をテーマにしたテレビディレクターの多角的な取材によって、コンプレックスをお金に換える資本主義社会の構図を描き出したのがルポ「ぼくらはみんなハゲている」(太田出版、2005年)だ。薄毛に悩み、男らしい自分を求めて植毛手術に踏み切って失敗した人たちにも話を聞いている。著者の藤田慎一さんは現状について、「たかが毛、されど毛。毛に罪はないけど、どこに生えるかで喜ばれたり、悲しまれたりする。人間自らが一つ一つの毛に価値を付け、 翻弄(ほんろう) されもする。基本的に老いによる喪失である頭の薄毛は選択ができないし、歴史上格好いいとされたこともない。それに対し、脱毛はファッションと同様に、お金を回していくために資本主義のシステムが作り出す流行の一つとも考えられる」と話す。
完璧な人間はいない「完全勝利目指すな」
同書の出版から20年たつが、美容産業が時代の一つ先を読み、『脱毛はマナーです』などと、人々の心に踏み込む広告を打ち出してくる点は変わらないという。ヒゲ脱毛が進むと、記者には思わぬ副作用があった。ヒゲのそり残しによって覆い隠されていたシミやそばかすが気になるようになったのだ。看護師にも勧められ、「脱毛の次はレーザーでシミ取りかも」と考え始めていた。藤田さんは言う。「コンプレックスや美意識との闘いに完全勝利を目指してはいけない。効果ゼロだとしても許せる範囲で資金を投入した方がいい。少しだけ闘うとか、上手な付き合い方を学んだ方が有益。完璧な人間などいないのだから」