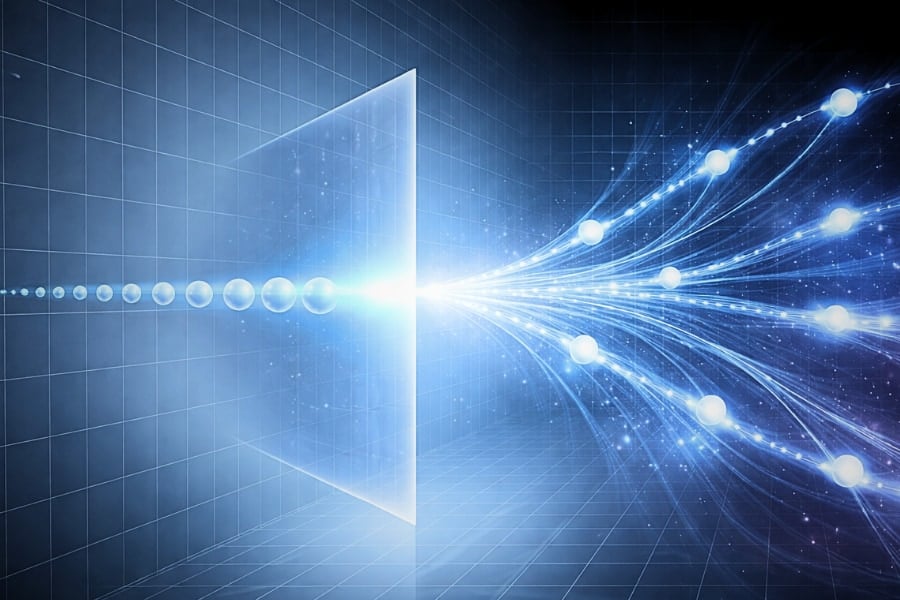【中国ウオッチ】頼総統拘束で台湾併合?◇統一問題で中国研究機関幹部:時事ドットコム

台湾の併合による「祖国統一」という中国共産党の悲願達成のため、中国の有力シンクタンク幹部が、台湾で何者かが頼清徳総統を拘束し、中国側に治安要員派遣を求める事態を期待すると公言して、物議を醸している。総統拘束は冗談のような話だが、中国が軍事作戦ではなく「治安行動」として台湾を制圧する案は目新しい。背景には、平和統一も武力統一も見通しが立たず、手詰まり状態にあるという認識の広がりがあるとみられる。(時事通信解説委員 西村哲也)
中国のニュースサイト・観察者網は7月10日、シンクタンク「中国・グローバル化センター(CCG)」の高志凱副主任が同4日に行った講演を映像で報じた。高氏は往年の最高実力者、鄧小平氏(故人)の英語通訳。国営中央テレビ英語チャンネルの評論員を務め、蘇州大学の教壇にも立つ。CCGは、顧問や諮問委員のリストに多くの元高官が名を連ねており、習近平政権と密接な関係にある。
7月10日は、台湾が中国の侵攻を想定した過去最大規模の軍事演習「漢光41号」を開始した翌日だった。
高氏は講演で次のように語った。
一、平和統一は見通しが立たない。武力統一はコストや代償が大き過ぎる。そこで、第2の西安事件(1936年の蒋介石拘束)発生に期待する。
一、国民党政権の指導者だった蒋介石を捕まえて抗日を迫った張学良のような人物が台湾に現れ、頼総統を拘束。台湾内部の混乱を理由に、治安要員派遣を中国側に求める。中国は台湾の「地方政府」から要請を受けて、大量の治安要員を台湾に上陸させ、占領する。
台湾メディアによると、台湾の識者からは「中国の台湾併呑(へいどん)手段は武力行使か降伏要求かという単純なものではなく、さまざまな強制手段があるということだ」「中国共産党の代理人が騒ぎを起こす可能性は確かにある」と警戒の声が出る一方で、「高氏は台湾や両岸(中台)の情勢について、よく分かっていない」と相手にしない人もいる。
中国のインターネット世論は総じて好意的ながら、「考えが甘い」との批判意見もある。この件を巡る議論は言論規制の対象になっていないようだ。
高氏が名前を挙げた張学良は、日本軍が爆殺した旧満州(中国東北地方)の軍閥、張作霖の息子。蒋介石の共産党討伐に不満を持ち、督戦のため西安に来た蒋を拘束して、内戦停止と抗日断行を迫った。蒋は解放されたが、この事件がきっかけで、後に第2次国共合作による抗日民族統一戦線が成立した。共産党にとっては、九死に一生を得た重要な出来事だった。
日米台での世論工作が重要
興味深いのは、タカ派の高氏が平和統一、武力統一の両方について、実現は難しいと判断していることだ。確かに、中国より経済的に豊かで政治的自由もある台湾が、一党独裁の中国との統一に積極的に応じる事態は考えにくい。また、大部隊で海を渡る中国の台湾侵攻は、ロシアのウクライナ侵攻よりはるかに難度が高く、失敗した場合のリスクも極めて大きい。
そもそも、習近平国家主席に台湾侵攻を決断・実行する政治力があるかどうかも、はっきりしない。最近の中国軍は、習派要人が次々と失脚して政治的混乱が続いているので、なおさらだ。
もちろん、「平和統一を目指すが、場合によっては武力を使う」という中国共産党の基本方針は変わっていないし、今後も変わらないだろう。
ただ、平和統一と武力統一の中間的方策は、中国の学術論文にも見られる。例えば、蘇州大学マルクス主義学院で中台関係を研究する王鶴亭教授は最近公表した「非平和的方式による祖国完全統一」に関する論文で、中国側の言う「台独(台湾独立)政権」「台独勢力」に対する手段として、軍事手段による殲滅(せんめつ)のほか、軍事的威嚇による統一強制や強度の低い軍事行動による統一促進を挙げた。また、海上封鎖についても、平時封鎖と戦時封鎖があると指摘した。平時でも、統一政策の一環として封鎖を実行する選択肢があるわけだ。
もっとも、台独の殲滅だけで統一は実現できず、治安行動による占領など多くの方策はいずれも、台湾で統一を支持もしくは許容する考えが広がるのが前提となる。中国が台湾問題に介入する恐れがあると見る日米両国についても同様だ。
したがって、中国としては、台湾と日米で(1)軍事力・経済力に関して、中国を過大評価させ、日米台を過小評価させる(2)それにより、台湾併合は阻止不可能であり、統一した方が日米台にも有利と思わせる─ことを狙った浸透・世論工作が必須となる。「習1強」の盤石アピールも必要だろう。
頼総統が3月に中国を「域外敵対勢力」と規定した際、中国によるスパイ活動や統一戦線工作の強化に警鐘を鳴らし、その後の定例軍事演習を侵攻前段階の「グレーゾーン事態」対処も含む過去最大規模で実施したのは、中国側のこのような事情を踏まえた対応だとみられる。
(2025年7月23日)