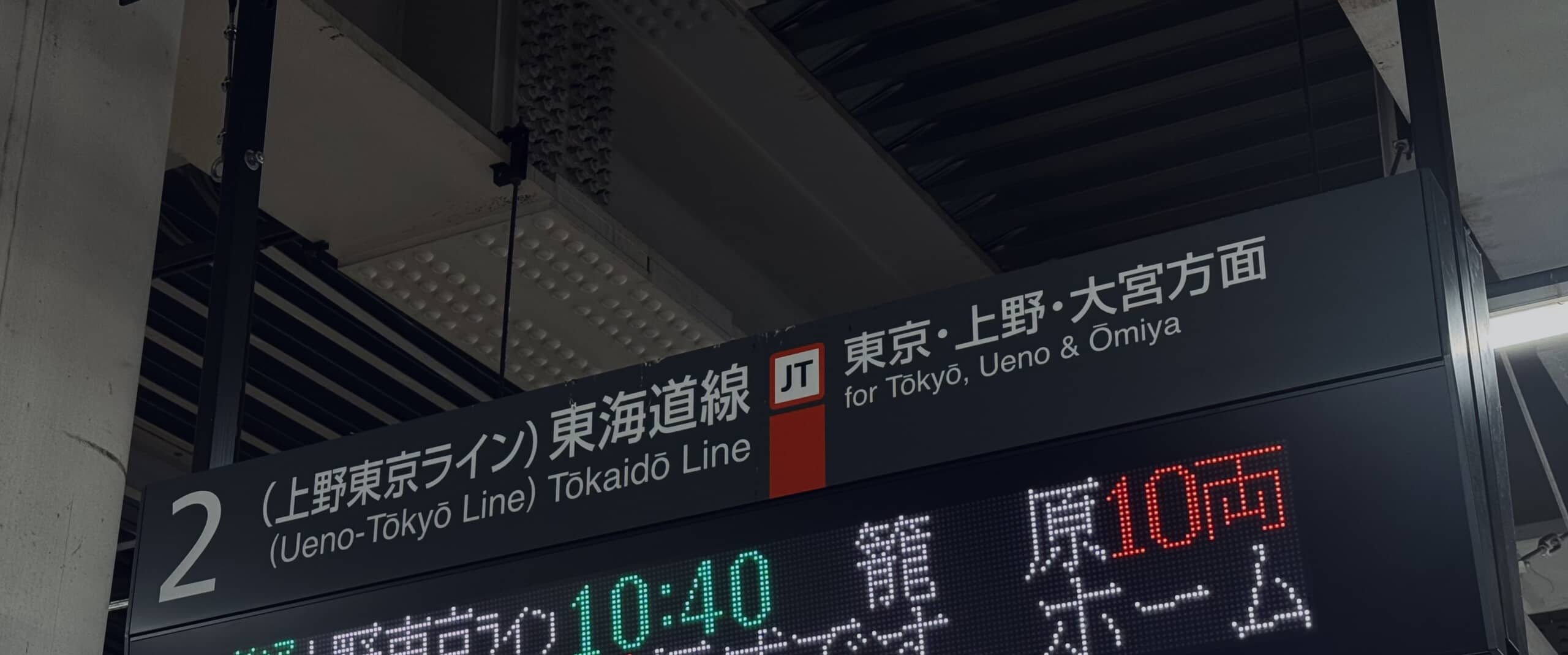「フィジカルAI」の新たなる地平、10倍株を探す旅「特選5銘柄」<株探トップ特集>
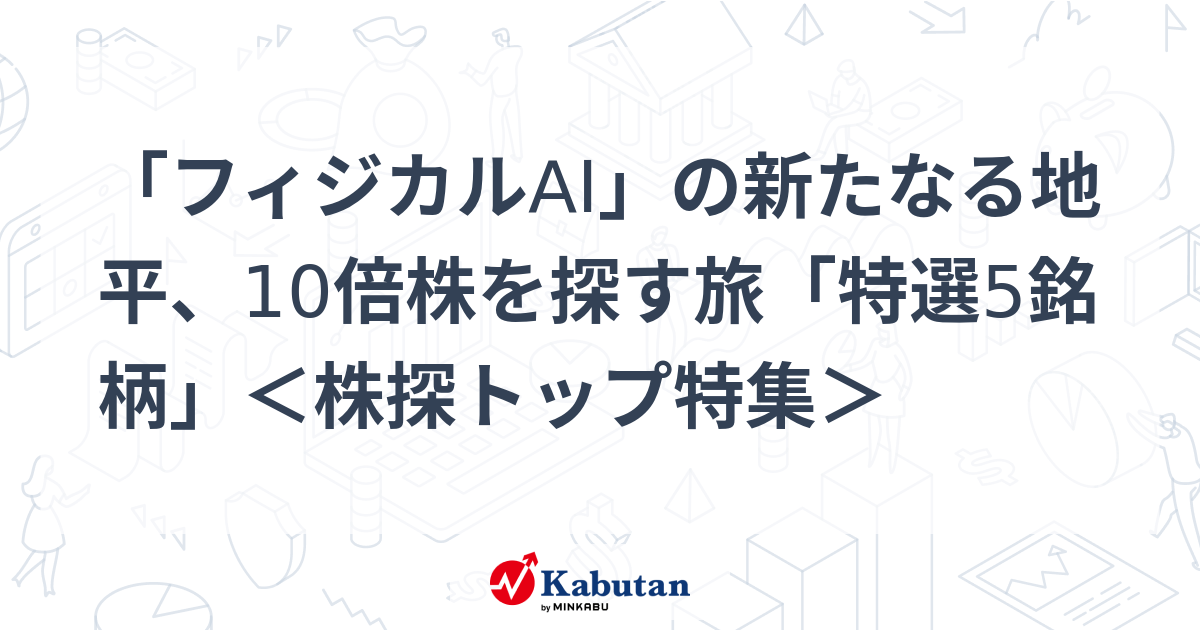
人工知能(AI)はあらゆる産業分野でその存在感を際立たせてきた。我々の日常において静かに水のように浸透し、業界を問わず技術革新の担い手となり、同時に企業のダイナミズムの源泉となってきた。しかし、生成AIの登場から現在までの進化プロセスは、これまでAIが辿(たど)ってきた歴史とは比べ物にならないくらいにスピードが速い。既にかなり以前からAIは演算能力や知識・情報処理能力で人間をはるかに凌駕する存在となっていた。しかし活躍のフィールドは3次元の空間には及ばず、我々にとって賢い“チャット相手”までで止まっていた現実がある。だが、いよいよAIが平たい画面から抜け出し、3次元で“行動する存在”へと変貌を遂げる時代が迫っている。 生成AIの進化系である「フィジカルAI 」の概念が歩き出した東京市場において、これから革命的な相場が訪れる可能性が出てきたのである。
●ソフトバンクGとアドテスト大躍進最近の東京市場で時価総額を爆発的に増やした2銘柄といえばソフトバンクグループ <9984> [東証P]とアドバンテスト <6857> [東証P]が挙げられる。また、いずれも株価水準が急速に切り上がったことで日経平均株価への寄与度が高まり、かつてなく日経平均の値動きを左右する存在となっていることも周知の通りだ。この2銘柄はいずれも米国株市場でエヌビディア<NVDA>を筆頭とするAI関連相場の大波が東京市場に波及したことによって、株価の居どころを大きく変えることとなった。
生成AI市場の拡大スピードとソフトバンクG、アドテストの株価変貌は時間軸的にも符合する。東京市場という狭い空間だけでみると、この2銘柄の値動きは行き過ぎに買われている印象は拭えないが、米国というAI先進国の大舞台で見た場合は、水準訂正の一コマにすぎないということが分かる。 米新興AI企業で「チャットGPT」の生みの親でもあるオープンAIのIPOに向けた動きが報じられているが、同社の企業価値は1兆ドル、日本円にして約154兆円に及ぶと試算されている。他方、ソフトバンクGの時価総額は大膨張したとはいえ未だ40兆円未満にとどまっている。もし、オープンAIが“1兆ドル上場”を果たしたとしたら、大規模インフラプロジェクトの「スターゲート」を主導する同士であるソフトバンクGの時価総額が今のままであるはずがない。このロジックこそが、世界の投資マネーが先を競ってソフトバンクG株式を抱え込む最大の背景となっている。●「次のフロンティアはフィジカルAI 」
このソフトバンクGが直近、耳目を驚かす経営戦略を打ち出した。10月8日、同社はスイスの重電大手ABBのロボット事業を約8000億円で買収することを発表し、同時にAIとロボティクスを融合させた分野における技術開発に本格的に乗り出す方針を表明したのだ。この時、孫正義会長兼社長は「次のフロンティアは『フィジカルAI』である」と言い放った。孫氏いわく、ASI(人工超知能)とロボティクスを組み合わせ、画期的進化を実現するというもので、今回の買収はその歩みを進めるための重要なM&Aとなる。このフィジカルAIに関してはジェンスン・ファン率いる米エヌビディアも日本を代表するメカトロニクス大手の安川電機 <6506> [東証P]とタッグを組んで事業機会を虎視眈々と狙っている。このフィジカルAIの定義としては、「物理環境と直接相互作用しながら業務を遂行するAI技術」ということになるが、具体的にはヒト型ロボットや自動運転などの次世代分野を生成AIの次なる応用領域とすることである。いわば現実空間での実動をAIが担う。世界経済フォーラムの報告書では「産業の自動化で新時代を切り開く原動力になる」とも指摘されている。
その際カギを握るのが、AIが自律的にタスクを遂行する「AIエージェント 」だ。AIエージェントは現在、世界のビッグテックが開発に鎬(しのぎ)を削っており、さまざまな分野で革命的な業務効率化をもたらすシナリオが描かれている。例えばフィジカルAIの中でもヒト型ロボットは代名詞的な位置付けとなるが、人間に近い形状と動作を持つことで既存環境との親和性が高く、ここにAIが自律的に判断してタスクを行えば、人間同士によるシチュエーションと近い形でサービスを完結することができる。
●日本がイニシアチブをとれるロボティクス日本はAI分野の研究開発や社会実装で米国や中国の後塵を拝していることは確かだが、産業ロボット 分野などでは明らかに上位に位置しているといってよい。そうしたなか、AIとロボティクス分野の融合は、日本の強みを発揮できる新たな舞台でイニシアチブをとることも可能となる。前述のエヌビディアと安川電の協業もその可能性を肯定する一つの事例ともいえる。ソフトバンクGの孫会長がいみじくも述べたように、生成AI時代の“次のフロンティア”がフィジカルAIであるならば、それをいち早く織り込みにいくのが株式市場である。生成AIの市場拡大は、第1幕ではAI半導体やAIデータセンター、それに付随する光ファイバーや光関連部品、電力設備といったインフラ領域の銘柄に怒涛の勢いで投資マネーが流れ込んだ。フィジカルAIは、その次に用意された生成AIが躍動するステージとしてテーマ性を存分に発揮しそうだ。
そして、このテーマにおいては、既に出来上がった大手企業ではなく時価総額の小さい銘柄の中から、中長期で大化け株が輩出されることへの楽しみがある。今回のトップ特集ではロボティクス分野における独自の展開材料を持っている中小型株に着目した。時価総額が3000億円の銘柄が3兆円に育つためには、それは「選ばれし企業」ということでもあり、かなりの時間と運が必要となる。しかし、収益基盤の安定した時価総額200億~300億円の企業が数千億円のレベルに成長するのは、それほど稀有なケースではない。その観点に立って、フィジカルAI関連で近い将来テンバガーの可能性を秘める5銘柄を選出した。 ●中長期で株価変身のシナリオが描ける5銘柄 【CIJは日立が主要顧客、AYUDAで業界先導】CIJ <4826> [東証P]は独立系システム開発会社で基盤システムからシステムインテグレーションに至るまで豊富な実績を有し、NTTデータグループや日立製作所 <6501> [東証P]向け受託開発が収益の主柱を担っており、高い技術力をベースとした強固な収益基盤が強みだ。ロボティクス分野にも早くから取り組み、AIサービスロボット「AYUDA(アユダ)」は業界でも先駆的なポジションで耳目を集めている。昨年11月オープンのロボット企業交流拠点「ロボリンク」にも設置されているが、自律移動型のコミュニケーションロボットとしてインフォメーション関連を中心に多方面で活躍しており、中期的にはバージョンアップによるサービスの高度化が期待できる。
業績面でも増収増益路線をひた走っており、直近発表された26年6月期第1四半期(25年7~9月)決算は営業利益が前年同期比41%増の6億3100万円と大幅な伸びを達成した。通期の営業利益は前期比4%増の22億5000万円と連続ピーク益更新を見込むが、一段の上振れも視野に入りそうだ。 株価は400円台後半での上下動を約1カ月続けているが、このもみ合い局面は絶好の買い場と捉えたい。いったん動き出せば足は速い。2024年に年初からジリ高を続け、3月下旬に上げ足を強め一気に株価を倍化させた経緯がある。目先は調整一巡でリバウンド期待が募るところで75日移動平均線ブレークから500円台での活躍が有力視される。 【豆蔵はAIロボの社会実装でカギを握る存在に】豆蔵 <202A> [東証G]は企業のDX支援ビジネスを展開する。クラウドコンサルティングやAIコンサルティング、AIロボティクス・エンジニアリングのほか自動運転及び先端カーエレクトロニクス分野を深耕するモビリティ・オートメーションサービスが主戦場だ。同社が将来的に目指すタスクはヒューマノイドロボットと生成AIの融合によって実現される新たな自律型システムの世界、言い換えればAIエージェントとフィジカルAIをリンクさせることで可能となる高度なサービスである。AIロボットの社会実装に向けて現在も積極的な取り組みを続けており、今後の動向が注目される。
業績も成長トレンドが鮮明。25年3月期は売上高が前の期比10%増の105億5100万円と初の100億円台乗せを果たし、営業利益は同15%増の20億7000万円と2ケタ成長で過去最高を更新した。26年3月期の業績見通しについて会社側は未開示だが、増収増益路線は確保される公算が大きい。そして27年3月期は開発に傾注するAIロボットなどの業績貢献が具現化し、収益の伸び率が加速する可能性が高い。 4月上旬の底値形成時からは株価の居どころが大きく変わっており、10月31日に2325円の上場来高値をつけたばかり。これは4月7日の年初来安値1090円と比較して既に株価を倍化させた状況にあるが、上値を出し切った感は全くない。直近は大勢2段上げの様相で、中期的に2000円台後半から3000円台活躍を視野に入れそうだ。 【セックはリアルタイム技術をロボット分野で発揮】セック <3741> [東証P]はシステム開発会社で、時間とともに変化する情報やデータを扱うリアルタイムソフトウェア技術に特長がある。防衛や宇宙先端システムなどの分野で高評価を得ているほか、ロボット分野も20年以上前から研究開発に取り組み実績を重ねている。屋内自律移動ロボットソフトウェア「Rtino(アルティノ)」や自律移動型ロボット協働パッケージ「RTakt(アールタクト)」などを手掛ける。また、今年7月には国際宇宙ステーション上の宇宙ロボット協働実証実験に技術協力するなど活躍が続いている。
売上高は過去最高更新が続くなか25年3月期に初の100億円台乗せを果たし、26年3月期は前期比4%増の107億円を見込んでいる。また、今期の営業利益も同3%増の18億4000万円予想とピーク利益更新基調に陰りがない。なお、今上期(25年4~9月)については期初予想を上方修正、営業利益段階で従来予想の7億7000万円から8億2700万円(前年同期比8%増)に増額した。 9月末に株式2分割を実施したが、株価はその後上下動を繰り返しながらも下値を切り上げ、10月28日には分割後高値である2640円をつけた。高値形成後はひと押し入れていたが、目先再浮上に転じた。日足一目均衡表で雲抜けを果たしたが、2600円台から上は滞留出来高も希薄で上げ足が速まる可能性も。中勢3000円台活躍をにらむ。 【ジーデップはAIロボット開発支援で新境地開拓】ジーデップ・アドバンス <5885> [東証S]はAI領域のハードウェア及びソフトウェアの開発・販売を主力展開するが、米半導体大手エヌビディア<NVDA>のエリートパートナーに認定されており、今年8月下旬にはエヌビディア製最先端GPUを搭載したサーバーの提供を開始。10月には東京工科大学の大規模AIシステム導入プロジェクトへの参画を発表した。
また、同社はマクニカホールディングス <3132> [東証P]と連携してAIロボットの開発支援パッケージ「ROBODEV(ロボデブ)」の提供も行っており、フィジカルAI開発向けなどで需要獲得が期待されている。業績は文字通りの高成長路線をまい進中で、トップライン、利益ともに過去最高更新基調が続いている。26年5月期売上高は前期比10%増の73億800万円、営業利益は同11%増の9億3400万円といずれも2ケタ伸長を見込む。また、27年5月期についても大幅増収増益が有力視されている。
株価は7月11日に3670円の年初来高値を形成後に軟化し3000円台前半でもみ合っていたが、9月下旬以降は更に水準を切り下げ、75日移動平均線が抵抗ラインとなって上値の重い展開が続いていた。しかし、時価3000円を割り込んだ水準は売り物もこなれており、仕切り直しの機が熟しつつある。当面は3000円台後半を指向する展開が期待され、中期的には23年7月の上場来高値4650円(分割修正後株価)の奪回も視野。 【TホライゾンはFA向けロボティクスで実績高い】テクノホライゾン <6629> [東証S]は映像・IT分野に特化した製品やサービスを手掛け、教育向けなどで先駆しているほか、ロボティクス分野ではFA関連を中心に実績を重ねており、将来に楽しみが多い。生産現場に向けてAI技術による高速検査機能を搭載したX線装置の提供なども行っており、半導体パッケージなどの製造プロセスで活躍が期待される。このほか、経営面ではM&Aを駆使した業容拡大戦略で優位性を発揮している。
足もとの業績は利益の伸びが際立つ。26年3月期上期(25年4~9月)の営業利益は前年同期比6倍となる8億9100万円と変貌した。4~6月期時点で営業利益は2100万円であっただけに、7~9月期の実績はインパクトが極めて大きい。通期の営業利益予想12億円(前期比3.2倍)は進捗率から一段の上振れも視野に入る。指標面ではPBRが0.7倍と割安感が顕著で、バリュエーション的にも株価の水準訂正が濃厚だ。 株価は好決算発表を材料に10月27日に一本値で513円のストップ高に買われ、翌28日にはザラ場564円まで上値を伸ばし年初来高値を形成したが、その後は利食い急ぎの動きが出て値を下げた。ただ、信用買い残など株式需給面から上値を重くする要素に乏しく、5日移動平均線との上方カイ離解消に伴い再浮上のタイミングが近い。当面は28日の564円の高値奪回を通過点に600円台活躍を目指す強調展開を期待。 株探ニュース