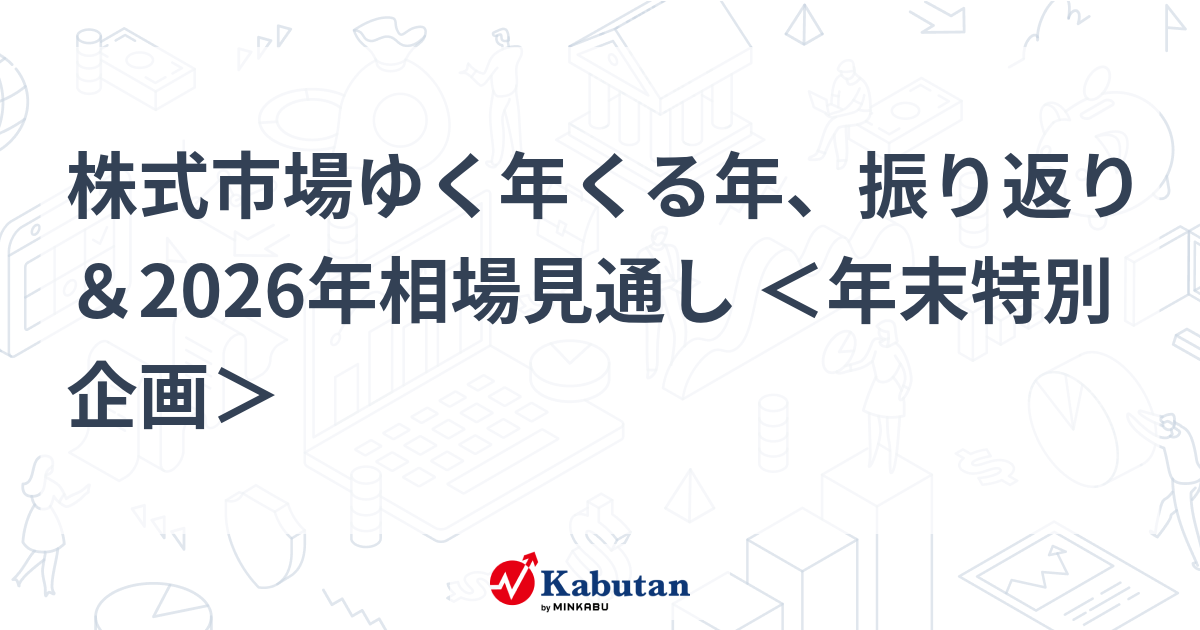【焦点】米インフレ、関税転嫁で再加速の兆し-物価・小売り統計注目

米国では数カ月にわたりインフレが落ち着いていたが、企業が輸入品にかかる関税をコスト増として販売価格に転嫁し始めたことで、消費者がやや速いペースでの物価上昇を感じている可能性が大きい。
15日に発表される6月の米消費者物価指数(CPI)統計では、変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアCPIは前月比0.3%上昇と、5カ月ぶりの大きな伸びになるとブルームバーグがまとめたエコノミスト予想は示している。5月は0.1%上昇だった。
基調インフレの指標であるコアCPIは前年同月比でも1月以来の加速になるとみられ、2.9%上昇と予想されている。
6月のCPI統計には、米輸入関税の影響が物価にわずかに反映される程度と想定されているが、多くのエコノミストは今後、年内を通じて徐々にインフレが進むと予測している。
一方で、労働市場の冷え込みを背景に米国の消費者が支出を抑える姿勢を強める中で、小売企業の多くは価格転嫁に慎重な姿勢を保っている。このバランスの見極めが難しい局面だ。
17日に発表される6月の米小売売上高は、2カ月連続の減少を経て小幅な増加に転じる見通し。モノへの支出を反映するこのデータは、4-6月(第2四半期)の経済成長率予想の精度を高め得る手がかりとなる。
消費需要と労働市場がいずれも減速する中でも、米連邦公開市場委員会(FOMC)は利下げを見送っている。高関税が最終的にインフレを加速させるという懸念がその背景だ。次のFOMC会合は29、30日両日。
ブルームバーグ・エコノミクス(BE)によれば、「価格上昇の構図は5月と似た形になり、財のカテゴリーでの関税転嫁は限定的にとどまる一方で、サービス分野の軟調さが続くとみている。一部の価格データでは、家電や家具など一部のカテゴリーで価格の上昇が見られる一方で、航空運賃や中古車の価格は下落している」という。
BEエコノミストのエステル・オウ、スチュアート・ポール、イライザ・ウィンガー、クリス・コリンズの4氏がコメントした。
今週は連邦準備制度理事会(FRB)が地区経済報告「ベージュブック」を16日に公表するほか、ウォラー、クーグラー、クック各FRB理事らの発言も予定されている。
また南アフリカ共和国で20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議が開かれ、アジアでは日本と中国から相次いで発表されるデータに注目が集まる。
日本と中国
6月の中国貿易統計が14日に公表され、米国の関税の影響や輸出前倒しの動きが浮き彫りになるとみられる。
中国は15日、4-6月(第2四半期)の国内総生産(GDP)に加え、6月の工業生産と新築住宅販売、小売売上高、失業率を発表する。GDPは成長ペースが鈍化したもよう。工業生産も経済全体の健全性を映す指標として注視される。
日本では5月の機械受注と鉱工業生産確報値が14日に発表され、景気減速の兆候が強まる可能性がある。17日に公表される6月の貿易統計も弱いとみられている。18日には6月の全国CPIが発表され、総合インフレ率は3.3%に低下する見通しだ。
G20財務相・中銀総裁会議は、南アフリカがブラジルから議長国を引き継いで以来2度目となるが、米関税政策への懸念やベッセント米財務長官の欠席が影を落とす。米国は南アフリカが掲げる「連帯、公平、持続可能性」というテーマや同国の一部外交政策に不満を示している。
原題:US Inflation to Pick Up on More Tariff Pass-Through: Eco Week (抜粋)