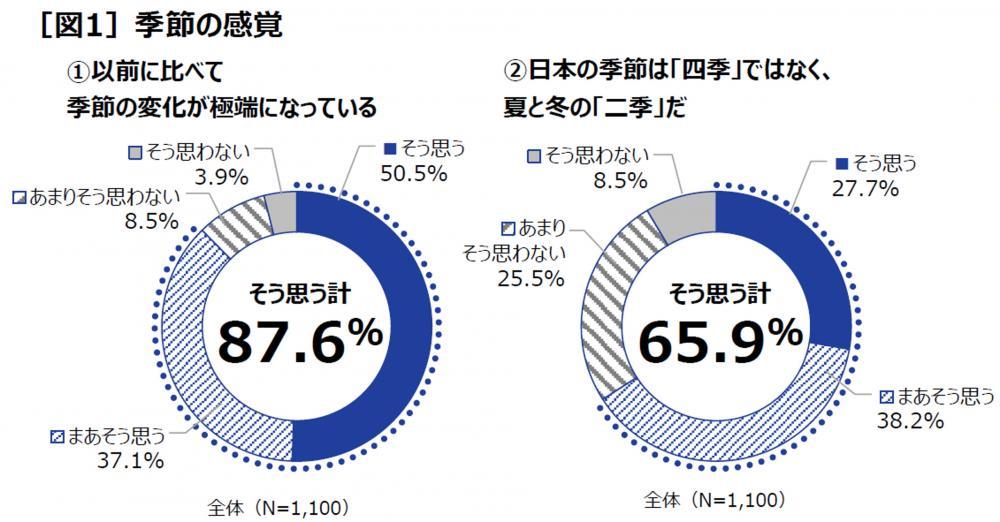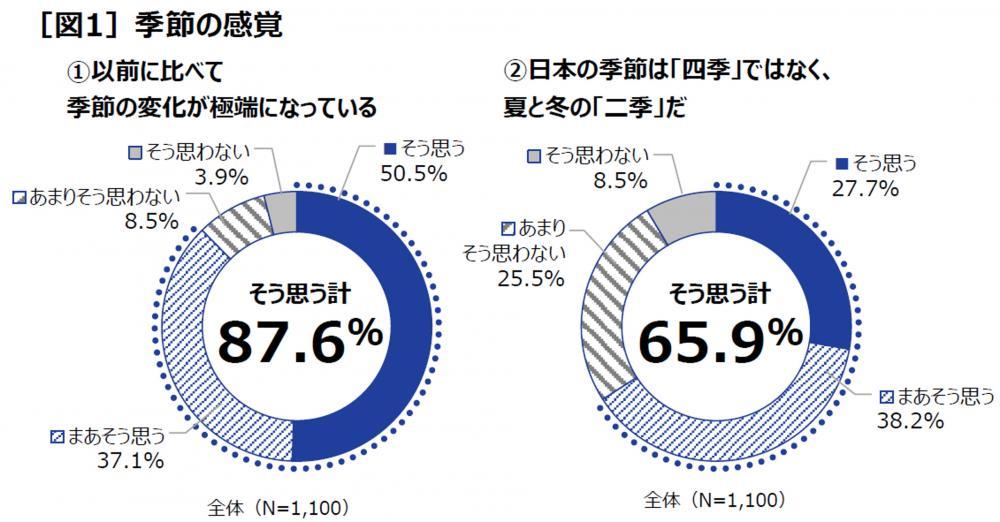”遺伝ガチャ”はうそ!? 科学的に考察すると…

他者のメッセージが持つ強い影響力は"呪い"だ。私たちはみな、無意識のうちに他者の意見や価値観を取り込み、それによって人生に絶望を覚えたり、言葉にできない生きづらさを感じてしまうことがある。サイエンスジャーナリスト・鈴木祐の新著『社会は、静かにあなたを「呪う」』を一部抜粋。6回目。【その他の記事はこちら】
※写真はイメージ。unsplash「遺伝子が人生を支配する」といったい”呪い”をよく見かける。
「人生の成功は、親から受け継いだ遺伝で決まる」「生まれつき遺伝に恵まれないと、努力しても無駄」
「人生は生まれで決まってしまう"遺伝ガチャ"だ」
他にも、「才能の半分は遺伝」「性格の大半は遺伝」「頭のよさは遺伝」などの主張も、半ば常識のように語られることが多い。
たいていの場合、これらのフレーズの後には、「人生は残酷なのだから、その事実を受け入れるしかない」や「遺伝という不平等を前提にして現実を諦めろ」という主張が続く。それとは逆に、「遺伝の影響は半分だから、残りは努力でどうにかなる」と、あいまいな希望が提示されるケースもよく見かける。
遺伝が私たちの能力や資質に影響するのは事実で、ある大規模な双生児研究によれば、知能の遺伝率は約66%にもおよぶ。この数字は高齢者ほど大きくなる傾向があり、私たちの学習能力や問題解決能力は、人生の後半になるほど遺伝の支配力が増すのだと考えられる。
次に遺伝率が高いのは"性格”で、多くの研究では、私たちの性格は約50%が遺伝の影響を受けるとしている。「不安になりやすいかどうか」や「人づきあいがよいかどうか」といった生まれつきのパーソナリティにも、遺伝が大きく関わるわけだ。
他に遺伝率が判明している特性としては、芸術的な才能が約40%、政治的な立場が約30~60%、運動の習慣が約30~50%だと言われる。遺伝が人生のあらゆる側面に影響をおよぼすのは確実だ。
これらの数字に気持ちが沈んだ人もいるだろう。「あなたの未来は遺伝で決まる」という言葉は、裏を返せば「努力などしても無意味だ」や「頑張っても人生は変えられない」と言っているに等しい。これが事実なら、私たちに自由意志は存在しないことになってしまう。
ケンブリッジ大学の分子神経科学者ハンナ・クリッチローも、こんな発言をしている。
「現代の遺伝学は、私たちが意識する以上に、遺伝が人生に影響を与えている事実を示した。このことは、『私たちは自分の人生を本当にコントロールできるのか?』という古くからの疑問を改めて提起している」
なんとも気が滅入るような問題だが、果たして私たちの運命は本当に遺伝で決まり、努力は意味をなさないのだろうか。
問題の答えを得るために、まずは「遺伝率とは何か」を考えてみよう。
多くのメディアでは「学校の成績は遺伝が70%」や「青年期のIQは半分が遺伝」といった数字だけが独り歩きしがちだが、"遺伝率”がどのような考え方なのかを掘り下げたものは多くない。巷間に語られる「遺伝が影響している」とは、具体的にはどのような現象を指すのだろう。
そこで、第一問。次の問題の答えを考えてみてほしい。
問1. IQの遺伝率は約70%だと考えられている。この数値は、次の三つのうち、どのような状態を意味するだろうか?
1 親のIQが高いときは、その子供も70%の確率でIQが高くなる。つまり、親のIQが低ければ子供のIQも低くなることが多い。2 自分のIQの70%は遺伝で決まるため、努力は30%しか意味がない。または、自分のIQが100だった場合、そのうち70点分は遺伝で決まり、残り30点分は環境で決まる。
3 IQの70%は生まれつきで決まり、その数値は何をしても変わらない。
正解は、すべて間違いだ。この三つは遺伝率に関する定番の誤解であり、世の中に"呪い"が広まる原因になっている。これらの考え方が誤りなのは、そもそも遺伝率が、以下の内容を表現した数値だからだ。
「ある集団内で観察されるばらつきのうち、どのくらいの割合を遺伝で説明できるか」
ここで大事なのは、”ばらつき"の部分だ。遺伝率は特定グループの個人差の原因を示す数値であり、あなたの「能力や資質が、どれだけ遺伝に由来するか」を表すわけではない。
「カフェオレ」を例に説明しよう。ある日、あなたが1杯のカフェオレを作ったところ、友人がこんなことを訊ねてきたとする。
「そのカフェオレの味の濃さには、コーヒーとミルクのどちらの影響が大きい?」
どうやらこの友人は、カフェオレの濃さに影響を与えている原因を特定したいようだが、そもそもこの質問が無意味であることは言うまでもないだろう。当たり前だが、コーヒーを増やせばコーヒーの味は濃くなるし、ミルクを増やせばミルクの味が濃くなる。カフェオレの濃さは「コーヒー+ミルク」のバランスで決まり、どちらか片方だけで味が定まるわけではない。
それでは次に、あなたが一度に10杯のカフェオレを作り、このときコーヒーとミルクを以下のように配分したとしよう。
1 10杯のカフェオレすべて、コーヒーの量を50mLにそろえる。2 ミルクの量は適当で、あるグラスには150m、別のグラスには250mlといった具合にばらばらに注ぐ。
すると、10杯のカフェオレを見た友人が、再び訊ねてきた。
「カフェオレの濃さがそれぞれ違うのは、コーヒーの量が原因?それともミルクの量が原因?」
相変わらず奇妙な質問ではあるが、この聞き方なら意味は通る。友人はカフェオレの濃さに"ばらつき”がある原因を聞いているので、「どのカフェオレもコーヒーの量は同じなので、ミルクが原因です」と答えられるからだ。これを遺伝率のように表現すると、カフェオレの濃さは100%ミルクの量で決まっているため「ミルク率100%」となる。
逆に、あなたが10杯のカフェオレを作る際に、ミルクの量をすべて200mLにそろえ、コーヒーを適当に注いだらどうなるだろう。この場合、カフェオレの濃さのばらつきは、100%が「コーヒーの量」の違いによってのみ決まる。そのため、こちらは「コーヒー率100%」と表現できる。
さらに、数字を少し複雑にしてみよう。もしコーヒーの量を40mLから60mL、ミルクの量を150mlから250mLの範囲で10杯のカフェオレを作った場合、それぞれのコーヒー率とミルク率はどうなるだろうか。この問題における「コーヒー率」と「ミルク率」は、それぞれのカフェオレの濃さのばらつき幅にもとづいて計算できる。つまり、「コーヒーのばらつき幅=20mL」「ミルクのばらつき幅=100mL」なので、「コーヒー率」は約17%で「ミルク率」は約83%が答えであり、濃さのばらつきの大部分はミルクの量によるものだと判断できる。
もうおわかりのとおり、遺伝率”の考え方は、この「カフェオレの濃さのばらつき」に似ている。私たちはみな異なる遺伝子を持って生まれるが、それと同時に誰もが異なる環境で育ち、その独自の組み合わせによってユニークな個性ができあがる。これは、コーヒーとミルクの配分によって、複数の濃さのカフェオレができあがるのと同じだ。そして、そんな個性のばらつきのうち、遺伝と環境がそれぞれどれくらい影響しているのかを、割合で示したのが遺伝率というわけだ。
「知能は親の遺伝で決まる」という”呪い"についても考えてみよう。「IQの遺伝率は約70%なので、IQが高い親からはIQが高い子供が生まれる確率が高い」という考え方のことだ。
しかし、ここまでの説明を読めば、もうおわかりだろう。遺伝率は集団内の”ばらつき"を説明したものなので、この数字を見たところで、頭のよい親から頭のよい子供が生まれるかどうかは何もわからない。先の例で言えば、「コーヒー率70%のカフェオレ」を見ても、そのカフェオレがコーヒーが濃いとは限らないのと同じだ。
それでは、IQが高い親からは、本当にIQの高い子供が生まれるのだろうか? ある研究によれば、2202組の親子のIQを分析したところ、親子間のIQの相関係数は0.3~0.4だったという。簡単に言えば、両親の知能をいくら調べてみても、子供のIQが高いかどうかは9~16%程度でしか予測できないという意味だ。これでは「知能は親の遺伝で決まる」とは、とても言えない。
同じような現象は、"身長"の遺伝率でも確認できる。身長の遺伝率はだいたい80%だが、こちらもやはり「親の身長が高いと、子供も80%の確率で背が高くなる」といった意味になるわけではない。8~9歳の児童419人を調べた研究によれば、両親と子供の身長の相関は0.47であり、この数字をパーセンテージに直すと、背の高い親から背の高い子供が生まれるかどうかは”22%”の確率でしか予測できないことになる。
一般的には、「頭のよさ」や「背の高さ」といった要素は、どちらも親に似やすいイメージがあるだろう。しかし、実際に調べてみると、その確率は意外なほど低く、親の能力や特徴を見ても子供がどのような人間になるかは予測できない。
それもそのはずで、「親子の遺伝率」と「親子が似る確率」は、まったく異なる現象を表した尺度だ。「遺伝率」が「ある特徴をどれくらい遺伝で説明できるか?」を集団のなかで見る数字なのに対して、「親子が似る確率」はあくまで「親と子」という個人の間での話を扱っている。
たしかに、子供は両親から半分ずつ遺伝子をもらうが、どの遺伝子を受け継ぐかはほぼランダムに決まるし、特にIQのような特性には複数の遺伝子の組み合わせが影響する。こんな複雑な現象を遺伝率だけで判断するのは、全国の平均気温を見て「今日の自分の家の温度は何度だろう?」と推測するようなものだ。
言い換えれば、遺伝率は「私のIQには遺伝と環境のどちらが影響しているのか?」という問いにはまったく答えてくれない。遺伝率は「集団全体のばらつきの話」であって、あなた個人とは関係がない数字だからだ。
以上のような誤解について、ピッツァー大学の心理学者デビッド・ムーアは、2016年の総説でこう述べている。
「遺伝率』という用語は、現代のヒト行動遺伝学において、科学史上"最も誤解を招きやすい概念"のひとつである。我々はすでに、遺伝的な要因があらゆる人間の特性の発現に重要な影響を与えていることを知っているため、ほとんどの場合において遺伝率は価値がない」
遺伝率という言葉は、人間の行動や能力を説明する際に誤解を招きやすいし、ごくまれなケースを除いて使う価値がない。遺伝率を測っても大きな意味はないし、むしろそれを使い続けることで、私たちは自分の能力を伸ばす方法を誤って理解してしまう。そんな批判だ。
ムーアが言う「ごくまれなケース」とは、たとえば特定の農作物の収穫量を遺伝子改良で増やしたり、特定の遺伝子変異による病気のリスクを評価したりといった状況を指す。たしかに、遺伝率が役に立つ場面は非常に限られており、これを私たちの「特性」や「能力」を判断するために使ったところで、人間の可能性を無駄に縛るだけにしかならないだろう。ムーアの指摘には反論の余地もあるが、少なくとも遺伝率を人間の能力にまで当てはめて、「人生の残酷さの証明」のように語っても意味がないのは確かだ。
『社会は、静かにあなたを「呪う」』経済や幸福、働き方、遺伝や才能――私たちが「正しい」と信じてきた常識は、果たして真実なのか。人気サイエンスジャーナリスト・鈴木祐氏が、膨大な科学的エビデンスをもとに現代社会の“呪い”を解き明かす。思考と行動を縛る思い込みから抜け出し、真に自由になるための一冊。¥1,980/鈴木祐著/小学館クリエイティブ2025年10月号
NEVER DIE 完全無欠の復活メソッド
仕事に遊びに一切妥協できない男たちが、人生を謳歌するためのライフスタイル誌『ゲーテ10月号』が2025年8月25日に発売となる。今回の特集は、トップリーダーの健康と美をかなえる“NEVER DIE 完全無欠の復活メソッド”。表紙には大沢たかおが登場。
最新号を購入する
電子版も発売中!
忙しい日々の中で、心を満たす特別な体験を。GOETHE LOUNGEは、上質な時間を求めるあなたのための登録無料の会員制サービス。限定イベント、優待特典、そして選りすぐりの情報を通じて、GOETHEだからこそできる特別なひとときをお届けします。