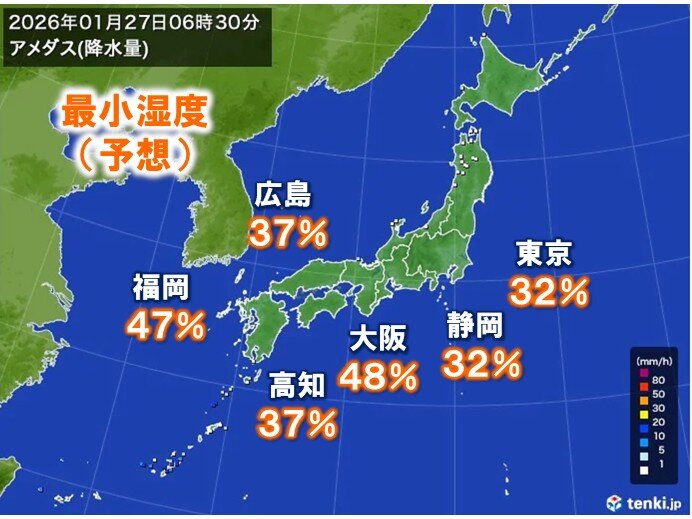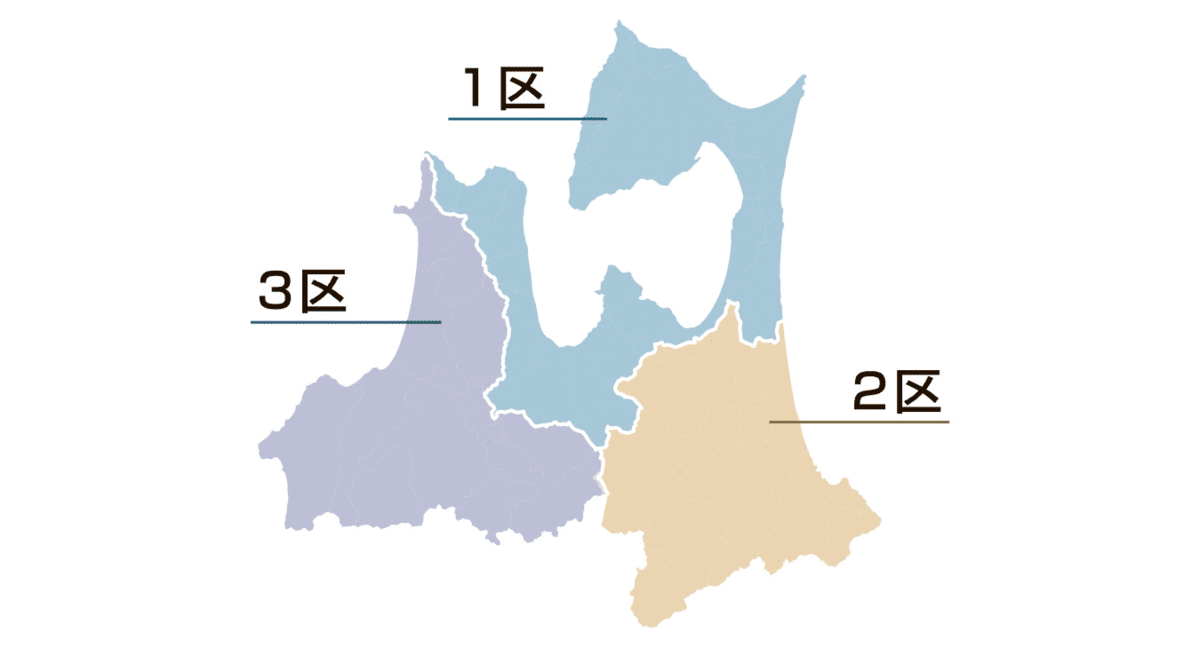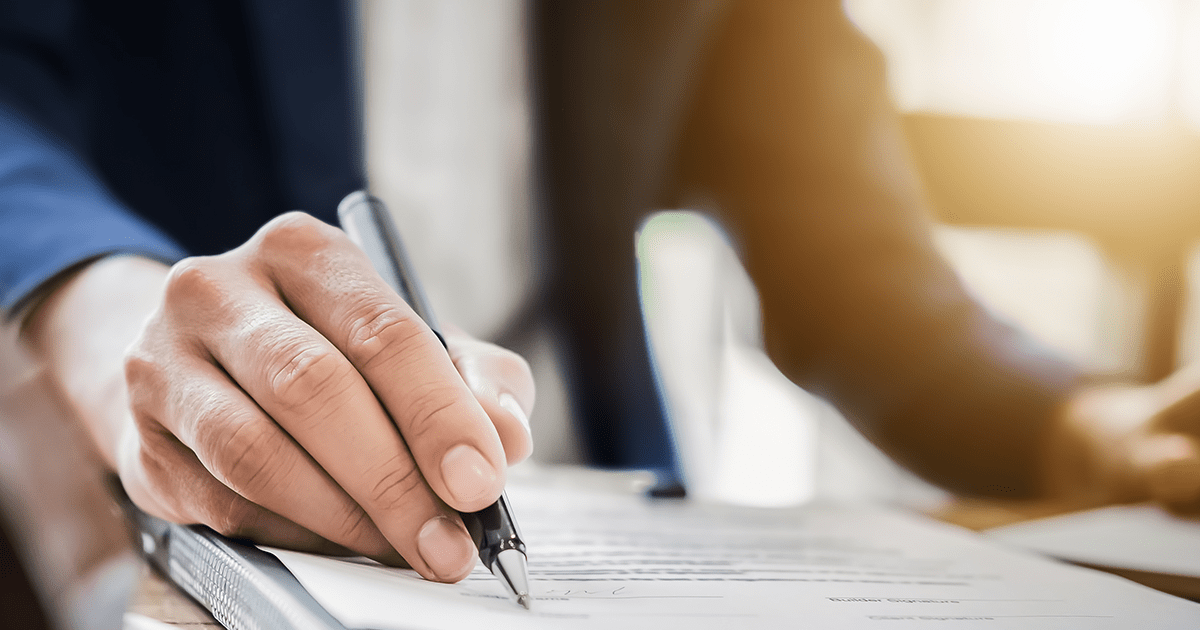GW明け「学校へ行きたくない」 特にストレスが大きい学年は?

楽しくのびのび過ごしたゴールデンウイーク(GW)も、明けると憂鬱な日常が待っている。もし、わが子が「学校へ行きたくない」と言い出したら、どうすればいいのか? 不登校や発達障害を持つ子どもらの学びを専門とする学習塾「キズキ共育塾」(本部・東京都新宿区)の不登校相談員、伊藤真依(まい)さん(26)に、心構えと対処法を聞いた。
ストレスが大きい中学1年生
「GWは、新学期が始まって疲れがたまった頃に迎えるので、途端に緊張の糸が切れて、そこから学校へ行けなくなるということはよくあります」
Advertisement連休明けの不登校を自ら経験したことがあり、これまで多くの塾生らの相談に乗ってきた伊藤さんはそう話す。
特に注意が必要なのは、中学1年生だ。というのも、中学は複数の小学校から生徒が集まることが多い。新しい同級生との出会いは、友達が増えるチャンスでもある半面、ストレスを伴うものでもある。人間関係や環境の変化に加えて、勉強の負担も増し、小学校までは問題なく過ごしてきた子どもでも、この時期に突然、登校できなくなることがあるという。
「あなたの絶対的な味方」と表明を
不登校の兆候は「学校へ行きたくない」という言葉が出る前から表れる。「疲れた」などのネガティブな言葉の増加、体調不良の訴え、昼夜逆転の生活、これまで興味を持っていたことへの関心の低下などだ。
だが、この段階で「サボっている」「仮病だ」などと疑ったり叱ったりしてはいけない。「SOSを受け止めてもらえないと感じると、子どもは親に相談できなくなってしまいます。そうすると、親側も何が問題で、どう対処すればいいのか見通せなくなります」と伊藤さん。
不登校になる理由は、学習面の不安や友人関係の悩みが多い傾向があるものの、子ども自身が言語化できないことも多い。伊藤さんは、親は学校へ行きたくない理由を無理に問い詰めてはだめで、まずは「あなたの絶対的な味方ですよ」とはっきり表明することが大切という。その上で「話せる時に、いつでも相談してね」というメッセージを伝えるといいとアドバイスする。
学校へ相談する前に、子どもの了解を
学校へ相談する際には、まず子ども本人の了解を得ることが不可欠という。「子どもでも、先生に知られたくないことがあります。親子の信頼関係を保つためにも、子どもの意思を尊重することが大切です」
また、登校を渋る背景には、発達障害が潜んでいる場合もあるという。
「ただ、学校の教員は必ずしも発達の専門家とは限りません。医師や発達障害を専門とする塾など第三者機関に支援を求めるのも有効な方法です。学校とうまく連携を取りながら対応していく進め方についてアドバイスをもらえることもあります」と伊藤さん。
そして、学校に相談する前には、まず親側が「どんなことに困っているのか」「どうしてほしいのか」を明確にしておくことが、その後、学校とスムーズに連携を進めていくコツという。
そもそも学校へ行かないことが問題なのではない、と伊藤さんは強調する。不登校を一概にだめと捉えるのではなく、学校へ行けば得られるはずの知識や社会性を身に付ける機会を、どう補っていけばいいのかの方法を見いだすことが重要という。
「学校へ行くための助走じゃない」
では、GWはどう過ごせばいいのか?
「思い切り遊ぶのも、ゆっくり過ごすのもリフレッシュになります。早寝早起きで生活のリズムを整えるのもいいでしょう。でも、それらは連休明けに学校へ行くための助走ではありません」と伊藤さん。「『連休明けには学校へ行ける』と親子とも期待し過ぎると、かえってプレッシャーになるので逆効果です」
不登校には、前兆期から進行期、混乱期を経て、回復期まで四つの段階があるという。「子どもの心の状態は行きつ戻りつ、揺れ動きます。どんな場合もこうすれば効くという万能な対処法はありません。親御さん自身、子どもと一定の距離を保ちながらよく観察し、焦らずじっくり、わが子に合わせたアプローチを探していくといいでしょう」と呼びかける。【山崎明子】