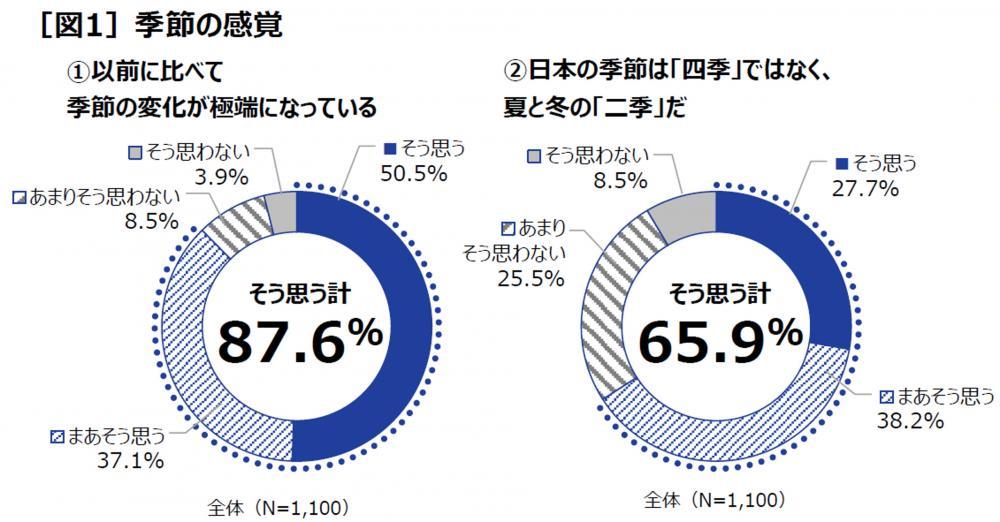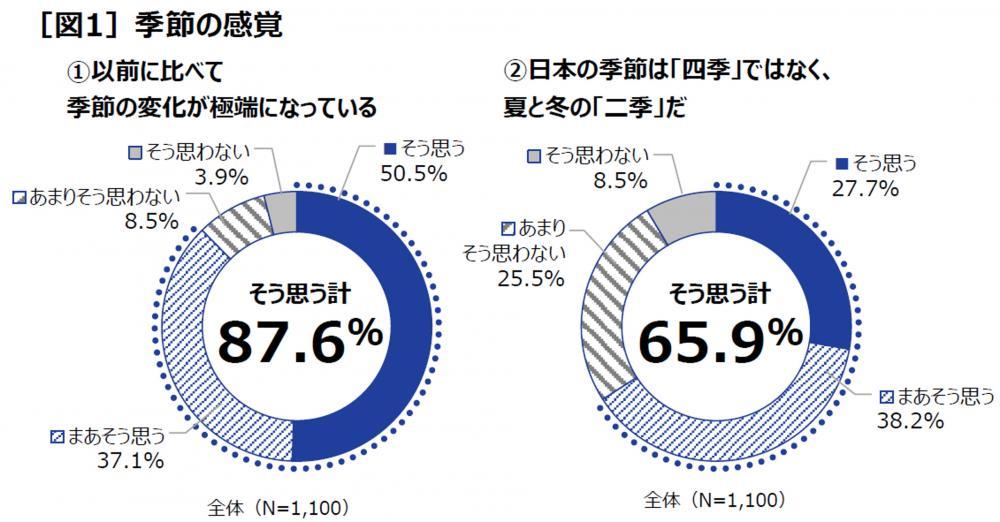よだれが止まらない「慢性流涎」~生活に支障、社会的孤立も~|トピックス|時事メディカル|時事通信の医療ニュースサイト
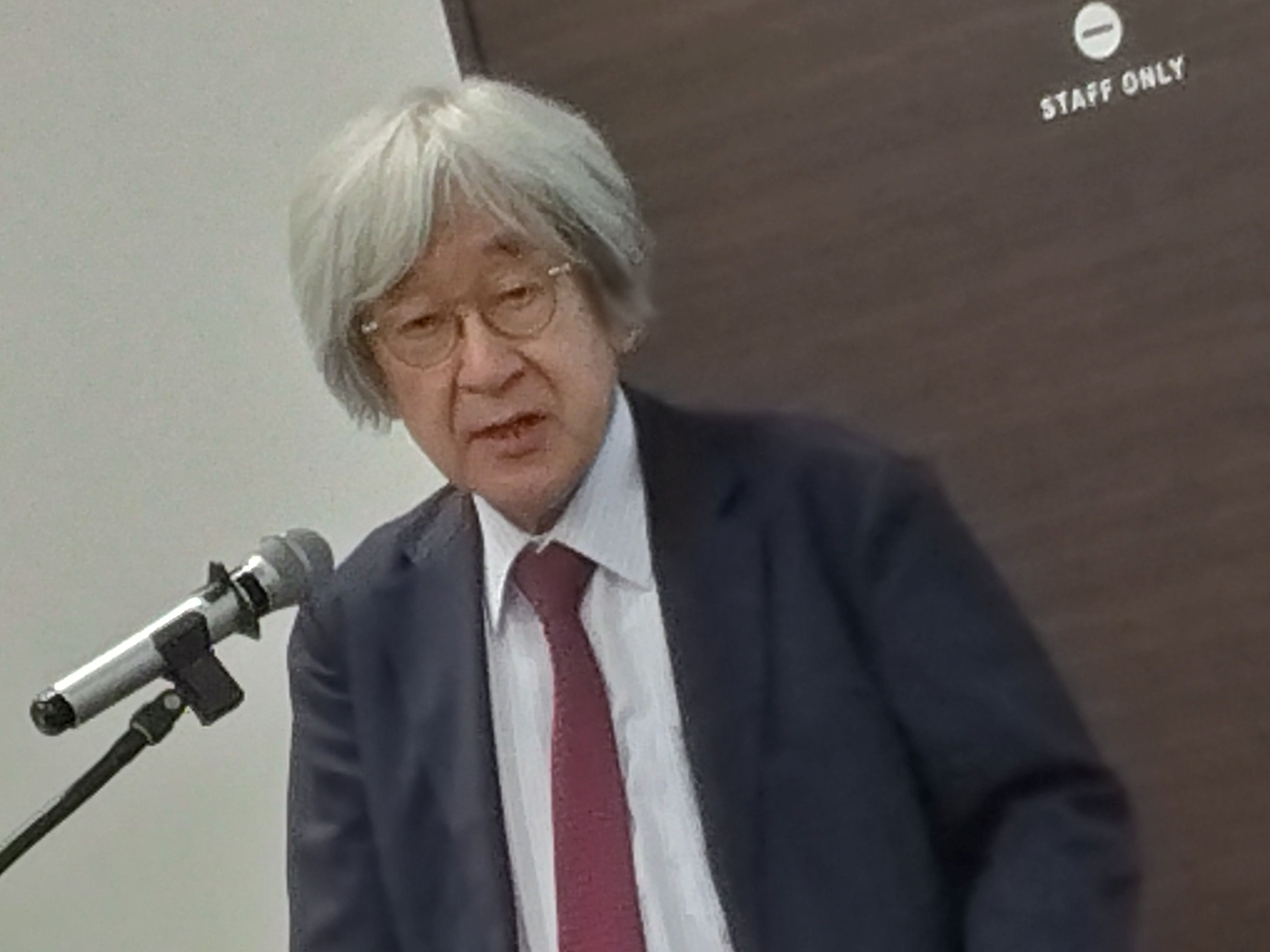
よだれが止まらず、困っている大人がいる。慢性流涎(りゅうぜん)という病気で、会話や食事がしづらくなったり衣服が頻繁に汚れたりし、日常生活に支障が出る。他人との接触をためらい、社会から孤立するケースもある。治療法はリハビリテーションなどが中心だが、このほど唾液の量を減らす薬が国内で初めて承認され、新たな選択肢が加わった。
順天堂大学の服部信孝学長補佐
◇パーキンソン病患者らに多く
順天堂大学の服部信孝学長補佐(特任教授)によると、人が1日に分泌する唾液は1~1.5リットルで、通常は就寝中を含め無意識のうち飲み込んでいる。飲み込む量が減って分泌量を下回るようになると、口からあふれ出る。こうした状態が続くのが慢性流涎だ。
国内の患者数は推定18万~38万人。脳や筋肉、神経の機能に異常が生じる「パーキンソン病、脳卒中、脳性まひ、筋委縮性側索硬化症(ALS)が原因で発症する例が多い」という。
パーキンソン病の患者を例に取ると、進行期に発症するケースが目立つ。唾液を飲み込む回数が減少したり、姿勢を保てずに体が前に傾いたりし、よだれが出やすくなるとみられる。
◇家族にも重い負担
この病気が患者や家族に及ぼす影響は軽視できない。患者自身に関しては、誤嚥(ごえん)性肺炎、声をうまく出せない構音障害、嫌な臭いといった身体的問題のほか、恥ずかしさや自尊心の低下など心理的・社会的な悪影響が見られる。家族も衣類や寝具の交換・洗濯が大変なのに加え、当事者に不潔感を抱いて温かく接することができなくなったり、不安や気分の落ち込みを感じたりする。
パーキンソン病を患い、2年前に流涎の症状が出始めた66歳の男性は「話しているときに口角がぬれ、文字を書くときに頭を下に傾けるとよだれが出る」といい、ティッシュで拭き取ったり、マスクを着用したりといった対応を余儀なくされている。パーキンソン病の夫がいる63歳の女性は「着替えをしている最中によだれで新しい服が汚れたり、食事をしているときにだらだらと出て衣服が汚れたりすることがすごく大変だった」と、介護の苦労を語る。
◇相談に二の足、医師も関心薄か
一方で、当事者や家族の切迫感が強いとは言えない側面もある。
欧米のパーキンソン病患者・介護者を対象とした調査では、9割近くが流涎を経験していたが、そのうちの半数弱は医療従事者側に相談していなかった。また、慢性流涎に対する医療従事者の関心度を患者・介護者が5点満点で評価したところ、治療・ケアの中心となる脳神経内科をはじめ、理学療法士、看護師、言語聴覚士、介護職など全てが1点台にとどまった。命の危険がある疾患ではないことが意識の低さにつながっているのかもしれない。
帝人ファーマが作成した啓発ポスター
◇治療はリハビリ中心
嚥下障害の恐れがある場合や、日常生活に支障が出て患者らが困っているときは治療を受けることになる。方法としては、まず薬物療法と非薬物療法があり、前者では原因となる疾患の治療薬の量を増やして改善を目指す手法などが採られる。自由診療で抗コリン剤を投与する手法もあるものの、「幻覚と精神症状が出る人がいるため、使いにくい」(服部氏)とされる。
非薬物療法にはリハビリ、姿勢調整、歯列矯正などがある。リハビリは嚥下・呼吸・構音訓練や顔・口・舌の運動、また飲み込む動作と関連する首や肩、体幹の運動・マッサージなどが行われる。臨床現場ではリハビリが主体となっているが、「長期的な効果についてはまだ分かっていない」(同)。これらの手法で改善しない、あるいは副作用で治療を続けられない場合は外科手術や放射線療法が検討される。
◇初の承認薬
そうした中で今年6月、帝人ファーマが取り扱うボツリヌス毒素製剤「インコボツリヌストキシンA(商品名ゼオマイン)」が国内初の治療薬として承認された。同製剤は肘や手首、指が不自然に曲がったままになる上肢痙縮(けいしゅく)などの薬としてすでに使われており、慢性流涎についても効果が認められ、対象疾患に追加された。
使用に際しては、唾液分泌の主要な部位である顔の耳下腺、顎下線に医師が直接、注射する。脳からのシグナルを伝える自律神経のうち、副交感神経を介して分泌を促すメカニズムを阻害し、唾液量を減らすという。1回の投与で効果はおよそ4カ月持続する。服部氏は「ボツリヌス毒素製剤の投与で患者のQOL(生活の質)を上げられる。社会的孤立を防ぐ意味でも積極的に治療を行っていきたい」と期待を示す。(平満)
(2025/09/17 05:01)
【関連記事】