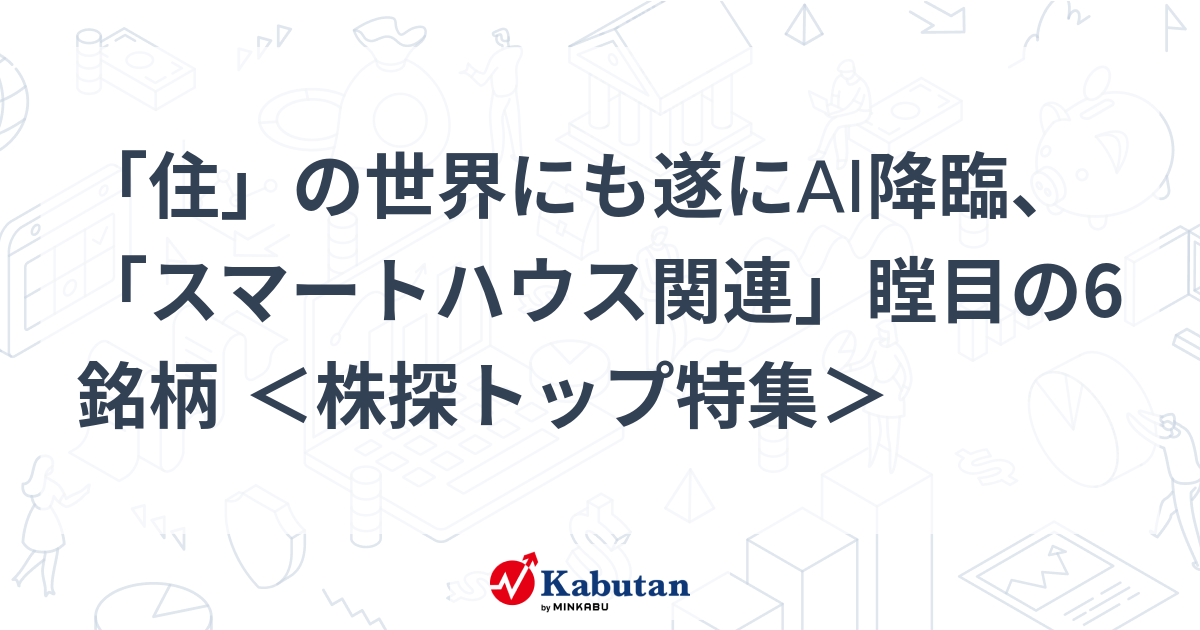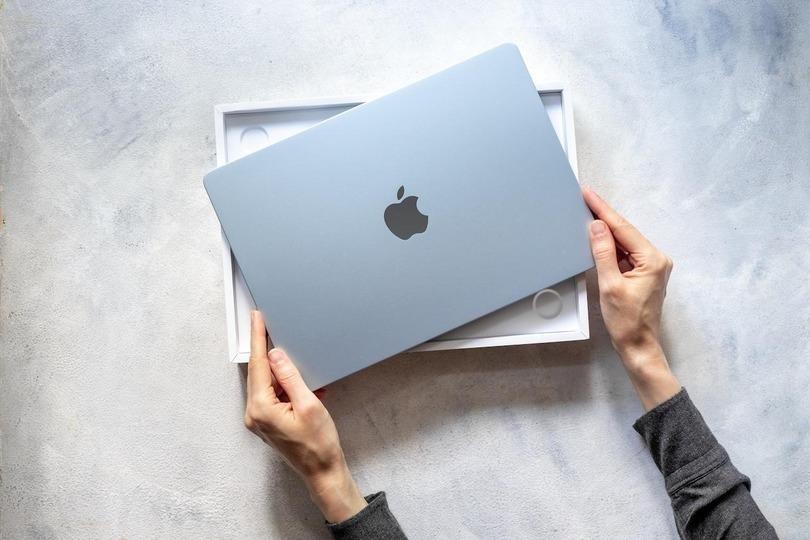中古で人気の「iPhone 13」は今でも“使える”のか? 性能面で不満はないが、注意点も

まず、スマートフォンを使う上で重要な「処理性能」はどうだろうか。iPhone 13に搭載されているSoC「A15 Bionic」は5nmプロセス、6コアのCPUを採用しており、当時としては高効率と高性能を両立したチップだった。 近年のApple製品の中でもこのチップを採用した機種は多く、今回のiPhone 13シリーズに限らず、2022年発売のiPhone 14やiPhone SE(第3世代)、iPad mini(第6世代)などと多岐にわたる。 今回、iPhone 13を2週間ほど使ってみたところ、多くの場面で性能的に困ることはなかった。もちろん、最新の機種の方がより機敏に動作するが、4年落ちとはいえブラウジング、SNS、CapCutでの動画編集はもちろん、3Dゲーム(原神など)も画質を落とせば問題なく動作する。 アプリの起動速度やUI(ユーザーインタフェース)の滑らかさは最新のiPhoneには劣るものの、今でも5万円以下で購入できるAndroidスマートフォンよりは機敏に動作する。4年前のスマホというカテゴリーで評価しても「快適」な部類に入る。 iOSの最適化もあって、iPhone 13は2025年現在でもミドル~ハイレンジ帯のAndroidスマートフォンと同等かそれ以上のパフォーマンスを有している。ベンチマークの結果はiPhone 16 Pro(Apple A18 Pro)と比較すると劣るものの、iPhone 15(Apple A16)との比較ならその差は思ったほど大きくない。 iPhone 13はシングルコアで2152点、マルチコアで5125点に対し、iPhone 15はシングルコア2644、マルチコア6558点。世代差はあるが、思ったほど大きな差は開いていない。 不満があるとするなら、高負荷なゲームを遊ぶシーンだ。iPhone 13はこのような場面でも“そこそここなせる”性能を備えているものの、やはり発熱や処理落ちが気になる。このような場面でも画質を落とす、冷却ファンを使うなどの対応をすれば、今でも問題なく遊べる。性能的には決して低いスマホではないのだ。 カメラ性能は1200万画素の広角カメラ、1200万画素の超広角カメラを備える。インカメラも1200万画素と十分なスペックを持つ。メインカメラにはセンサーシフト式の手ブレ補正を備えており、静止画はもちろん、動画撮影でもブレを抑えて撮影できる構成だ。