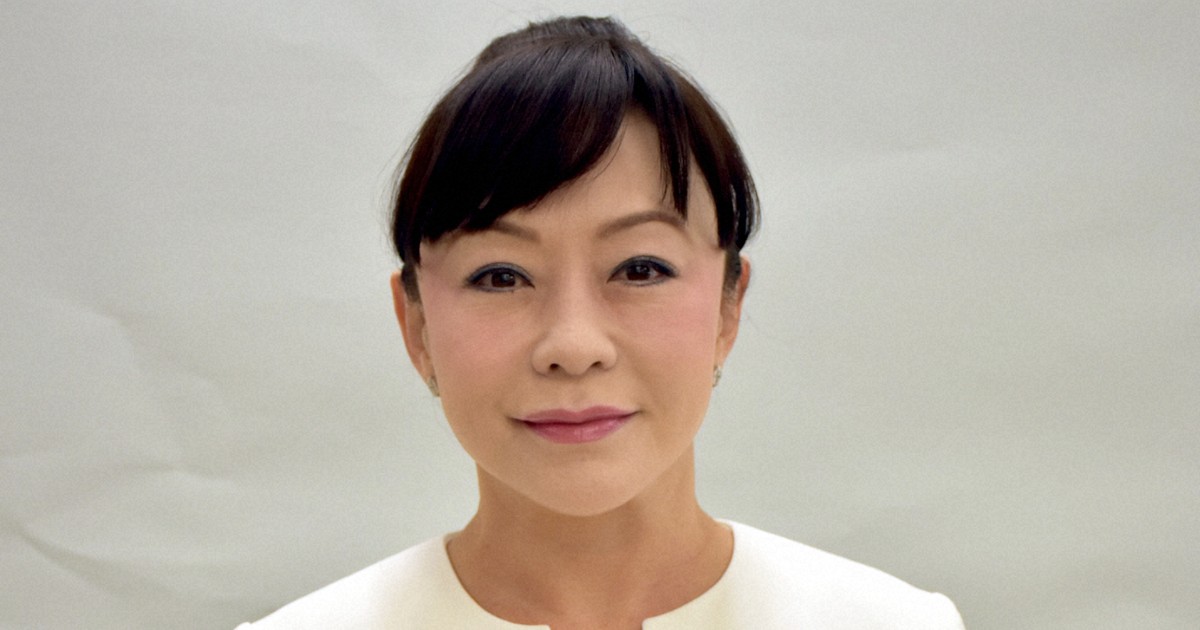「日帰り観光」が不満に拍車、美瑛町ではオーバーツーリズム対策

オーバーツーリズムが大都市だけでなく、地方都市でも深刻化している。経済効果が限定的な「日帰り観光」が多い地域では不満に拍車がかかっており、対策に乗り出す自治体も現れ始めた。
人口約9000人の北海道・美瑛町は、年間で町民の210倍もの観光客を受け入れている。1月、撮影スポットとして人気だった「シラカバ並木」の約40本が住民の希望で伐採された。シラカバの陰が農作物の生育に影響を及ぼしていたほか、観光協会によると、写真を撮ろうと農地へ侵入する観光客に悩まされてきた地元の農家は、我慢の限界に達していたという。
「なかなか町にお金が落ちず、町民も観光客がたくさん来ることの恩恵を感じにくい」。美瑛町の商工観光交流課の成瀬弘記課長補佐はこう話す。2023年には238万人が訪れたが、多くが旭川市などに泊まる日帰り客で、美瑛町に滞在する人は1割にも満たないという。
町は混雑対策として、観光客が多く集まるエリアに人工知能(AI)搭載のカメラを設置し、混雑状況を可視化。さらに私有地への侵入を検知すると、多言語で注意を促す音声を流す仕組みを導入した。6月には観光客を対象とした駐車場税の導入が町議会で可決され、この税収をオーバーツーリズム対策にも充てる計画だ。
政府は30年までに訪日客を6000万人に増やす目標を掲げ、地方都市への誘客も進めている。東京など大都市の混雑緩和につながる可能性はあるものの、地域経済の活性化に直結するとは限らない。
持続可能な観光について研究する九州大学の田中俊徳准教授は、「日本には無料の観光地が多い」と指摘する。観光客が集まっても収益が上がらず、投資余力も生まれない。田中氏によれば、観光客増加に伴って行政の負担も膨らむが、日帰り客が多い場所では宿泊税を活用できず、混雑緩和の財源確保も難しい。
地方自治体が抱える構造的な課題もある。現在、地方交付税交付金の算定に用いられる各地の需要額は、基本的に住民数と面積で配分が決まり、観光客数は考慮されない。「観光需要の高まりに対して地方自治体は耐えきれない」として、田中氏は政府が検討する国際観光旅客税(出国税)の引き上げ分を、観光客を多く受け入れる地方に再配分すべきだと提案する。
世界遺産・白川郷の合掌造り集落で知られる岐阜県白川村では、これまで観光客による交通渋滞やポイ捨てなど、マナー違反が村の悩みとなってきた。観光客数は、過去最高だった19年の約215万人に迫る水準まで回復しているが、観光振興課の小関弘翔係長は「必ずしも事業者や村民が望む数字ではない」と話す。
24年に訪れた観光客のうち約96%は日帰り客で、「どうお金を落とす仕組みを作っていくかが観光課の課題」と小関係長は話す。一方で、村の宿泊施設では受け入れ人数も限られるため、発酵食品を使った商品開発などに力を入れて付加価値を高めようとしている。
美瑛町では、シラカバ並木が伐採された後も、ほかの撮影スポットに観光客が集まる状況が続いている。美瑛町観光協会の理事で写真家の中西敏貴氏は、これまではおもてなしの精神で観光客を迎えてきたが、観光を「マネジメントする方向にかじを切らないと、シラカバの木がなくなってもまた別の場所で同じことがきっと起こる」と話した。