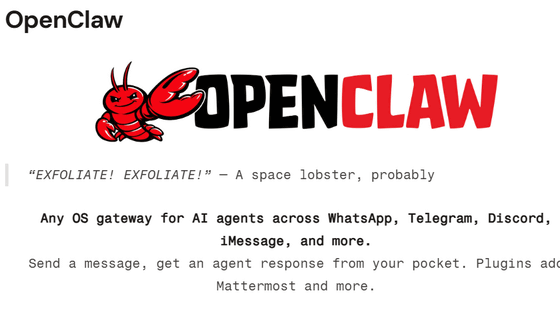独自プロセッサ搭載スマホ「Xiaomi 15S Pro」の実力検証 なぜHuaweiほど米国の規制を受けずに開発できたのか

ここで気になるのが、Xiaomiは中国メーカーながら、なぜXRING O1という自社開発のプロセッサを世に送り出せたのかという点だ。 中国では独自プロセッサを自社のスマートフォンに採用していたHuaweiは制裁対象となり、TSMCからのチップ供給が断たれた。一方で、Xiaomiは同じ中国メーカーでありながら、最先端の3ナノメートルプロセスを用いたプロセッサを製品化できている。 端的にいえば、米国が両社に対して抱く「脅威度」の差が大きく影響していると考えられる。Huaweiは“全面的な技術封鎖が必要”と判断されるほどのハイリスク企業と見なされたのに対し、現在のXiaomiはそこまでの戦略的脅威とは見なされていない。 Huaweiが米国の標的となった理由は、プロセッサに関して高い技術開発力があるためだと考える。 スマートフォン向けに限っても、2017年に発表されたKirin 970は世界初のNPU(AI演算処理ユニット)を搭載し、2019年のKirin 990では世界初の5Gモデム統合型SoCを実現。微細化にも積極的に取り組むなど、業界の最先端を走っていた。 さらに、2023年には、設計から製造までを完全に中国国内で完結させた「Kirin 9000S」を採用したMate 60シリーズをひっそりと投入。厳しい制裁下にあってもその開発力の高さを見せつけた。 こうした背景を受け、米国は2019年にHuaweiをエンティティリストに追加。以降、米国由来の技術の使用に対する規制を段階的に強化し、製造装置などを用いる企業は、Huawei向けのチップ製造を行えなくなった。もちろん、TSMCやサムスン電子もその対象となっている。 それでは、Xiaomiはなぜ3ナノメートルチップを製造できたのだろうか? Xiaomiは、確かに中国メーカーではあるが、XRING O1プロセッサの設計にARMのCortexアーキテクチャとARMのGPU「Immortalis」を使用しており、基幹技術は依然として欧米の知的財産に依存している。 このため、ARMのライセンスを断てば製造は困難になることもあり、米国としても直ちに規制対象とすべき戦略的リスクとは見なしていないと考えられる。 また、XRING O1は「第2世代3ナノメートルプロセス」で製造したとされるが、現時点で中国国内にはこのプロセスに対応可能なファウンドリ(製造メーカー)は存在しない。公表されている「第2世代3ナノメートルプロセス」は、台湾TSMCによるものとみられている。 もっとも、TSMCは既に中国向けの先端チップ製造には消極的な姿勢を見せており、2025年以降では、14ナノメートル未満のチップ製造には米国の商務省・産業安全保障局(BIS)によるライセンス取得が必要になる。 しかし、BISが2025年1月に更新した輸出管理規則では、AI向け、高性能演算向けチップに対する規制が中心となっており、以下の条件を満たす民生用途の製品はライセンス対象外となる。 ・トランジスタ数:300億個未満(2029年以降は400億個) ・高帯域幅メモリ(HBM)非搭載 ・搭載機器が民生向けであること XRING O1は190億個のトランジスタを使用していることを公表しており、HBMは搭載していない。現時点では民生機器のスマートフォン向けにのみ供給されているため、輸出管理の規制対象には該当しない。このため、TSMCはXiaomi向けにライセンス不要でチップ製造を行っているとみられる。 また、XRING O1はセルラー通信機能を内蔵しておらず、スマートフォンとして使用するにはMediaTekやQualcommのモデムチップを組み合わせる必要がある。これはモデムを統合したSoCと比較すると、消費電力で不利なことを意味する。 この点も5Gの特許を多く保有し、中核技術にアクセスできるHuaweiとは異なり、携帯電話として利用するためには他社のモデムが必要なことから、Xiaomiの技術的独立性が限定的であることを示している。米国が「脅威度が低い」と判断する理由の1つと考える。