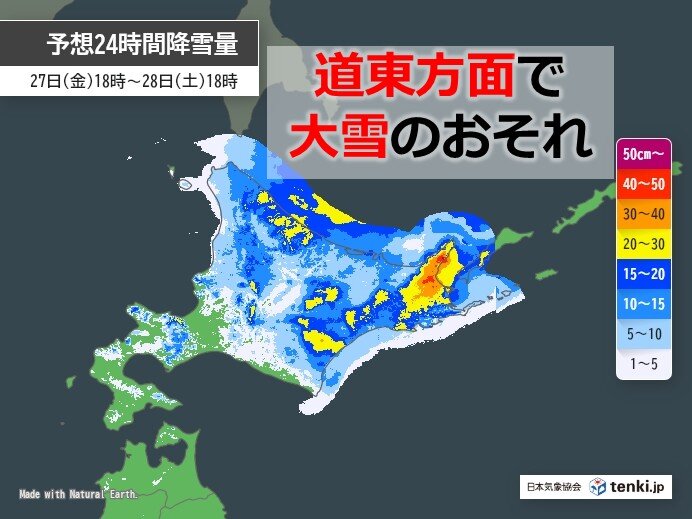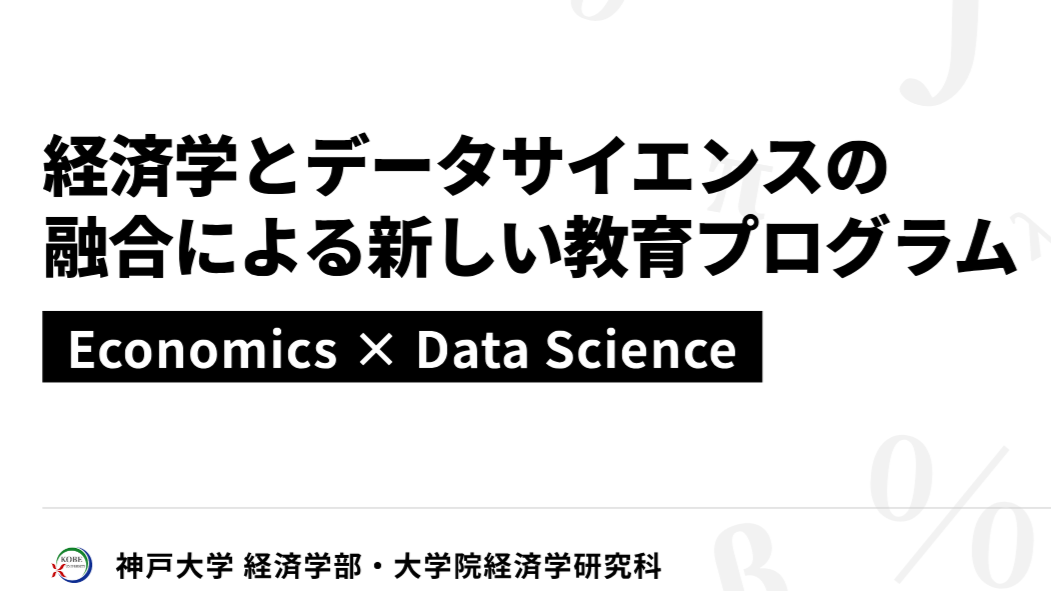インタビュー:「石破おろし」の動き限定的か、党内派閥の解消で=ピクテ・ジャパン 市川氏

[東京 22日 ロイター] - 参議院選挙での与党大敗を受けて、今後の政局や経済政策運営などへの影響を識者に聞いた。
<ピクテ・ジャパン シニア・フェロー 市川眞一氏>
与党の苦戦が事前に伝えられていた中で、実際には思ったほど得票数が減らなかった印象だ。野党が減税を主張していたこともあり、選挙期間中に長期金利が上昇する場面が見られた。それで有権者の中には、(与党の一方的な敗北を)懸念した人もいたのかもしれない。結果として、自民党は過去最低の獲得議席数は免れた。
石破茂首相の続投を阻止しようとする動きは、党内でそれほど広がらないのではないか。理由はいくつかある。まず、今回の参院選で石破首相に批判的だった保守系議員が落選した。さらに、党内派閥が解消されたことで、反対勢力が以前ほど結集しにくくなっている。となると、今後の注目点は連立拡大の行方だ。立憲民主党との連立については、自民党内の右派の反発もあり、個人的にはハードルが高いと見ている。連立の可能性として最も現実的なのは日本維新の会だろう。ただし、維新は党内が分裂しており、自民側からすると「誰と交渉すればよいのか」が分かりにくい状況かもしれない。
国内政治に不安定さが増したとはいえ、株式市場へのマイナス影響は限られる。これまで外国人投資家が日本株を大きく買い越す局面では、アベノミクス相場をはじめ、日本政治の変化への期待感が背景にあった。しかし現在は様相が異なり、日本企業のコーポレートガバナンス(企業統治)改革が主な買い要因となっている。
日米間の関税交渉については、今回の選挙が、災い転じて福となすかもしれない。どういうことかと言うと、高関税政策については米国側も大きな課題を抱えている。輸出企業の値引きだけでは関税コストを吸収できず、米国内の消費者に価格が転嫁される。消費者物価が大幅に上昇するため、米経済がそれに耐えられるかどうかは不透明だ。自らの首を絞める形となり、いずれ政策の見直しを迫られるのではないか。
日本としては安易な妥協を避け、米国が自らつまずくのを待つ方が得策だと考える。選挙で敗北した石破首相が今後、強いリーダーシップを発揮して交渉を矢継ぎ早に進展させるとは考えにくいが、むしろその方が日本にとって好都合の可能性もある。
(聞き手・小川悠介)
Reporting by Yusuke Ogawa
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab