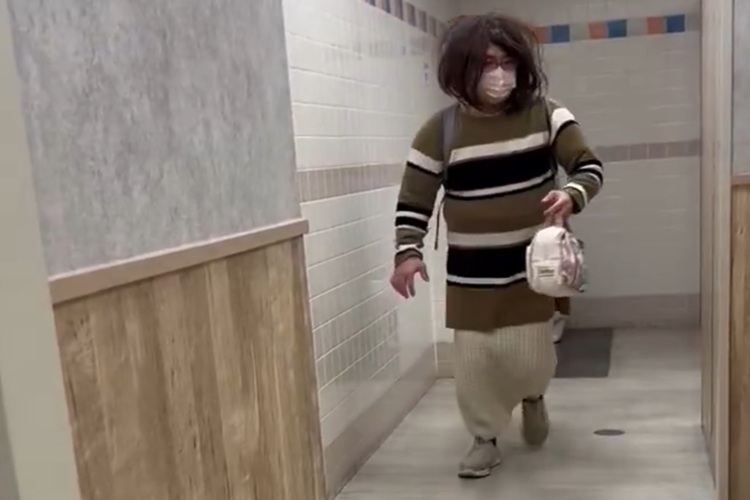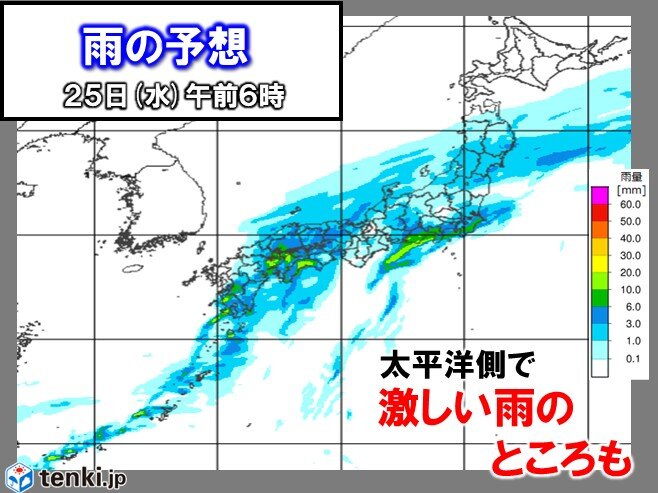仏像盗んだ男、無人の寺社狙い被害190点…ネットで下調べし電話番号の有無で「無住寺」判別

寺から仏像などを多数盗んだとして窃盗罪などに問われた福島県田村市、解体業の被告の男(48)の判決が1日、福島地裁郡山支部であり、下山洋司裁判官は懲役2年6月(求刑・懲役3年6月)を言い渡した。被告は、住職など管理者がいない「無住寺」に狙いを定めて仏像盗を繰り返していた。(山口翔平、内間木蓮)
県警が押収した被害品とみられる仏像判決によると、被告は昨年9~11月、三春町や須賀川市などの9か所の寺社に侵入し、仏像47点などを盗むなどした。県警は、被告が福島だけでなく、宮城県の寺社にも侵入し、両県で約60件の窃盗を行い、被害点数は約190点に上ると明らかにしている。
盗品は、被告によって県内の古物商に売却され、さらに別の業者を介してオークションにかけられていた。県警は盗品の多くを回収したが、行方がわからなくなっているものもある。
公判では検察側が、被告が侵入する寺社を選んだ方法を指摘した。「インターネットで侵入する寺の下調べをし、電話番号の記載があれば管理者が近くにいるので避けた。無人で人目につかない寺社を標的とした」。侵入した約60件のうち、ほとんどが「無住寺」だった。
仏像の盗難被害に遭った郡山市のある寺では、住職はいるものの、市内の他の複数の寺も一人で管理している。防犯カメラなどの対策もできておらず、住職は「防犯まで手が回らないし、対策をしてもまた盗まれるかもしれない」と戸惑いを口にした。今後は 檀家(だんか) に管理を手伝ってもらうことも検討するという。
須賀川市横田の護真寺でも今年3月、県重要文化財「木造宝冠釈迦如来坐像」がなくなり、これも被告が盗んでいた。寺の管理に携わる近くの男性(74)によると、盗難被害を受け、檀家が定期的に施設の見回りをする活動を4月から始めたほか、各施設には鍵をつけた。像は返還されたが、男性は「このような被害は二度と起こしたくない」と話す。
盗難対策のポイント地域の寺社に伝わる仏像などを、どう守ればいいのか。過去に仏像の大量盗難被害があった和歌山県では、県教育委員会が2023年に「わかやま文化財盗難対策ガイドブック」を作成した。2か所以上の施錠や防犯カメラの設置などが有効だとしている。
所有権の証明に写真、寸法記録を
一連の盗難事件では、捜査当局が保管している仏像のうち、所有者がわからないものが複数あることが問題になっている。文化財に指定されていない仏像の中には、写真が残されていない場合があり、所有権を証明できないためだ。
和歌山県立博物館の学芸員、島田和さんは「文化財の写真を撮影したり、寸法を測ったりして記録に残すことが極めて重要だ」と指摘する。同県であった盗難事件でも、警察が盗品を回収したものの、所有者がわからず博物館で保管している仏像があるという。
島田さんは「秘仏を撮影することに抵抗があるケースもあるだろうが、一枚でも写真があれば盗まれても返還されやすくなったり、市場に流れるのを防いだりする効果がある」と話す。
福島地検によると、こうした所有者不明の盗品は判決確定後、公告にリストを載せる措置が取られる。それでも持ち主が現れなければ、仏像のような文化的な価値がある物品は、地元の博物館などと保管について協議することがある。