人間の脳と同じ電圧で動作、「脳のような」ニューロンを科学者らが作製(Forbes JAPAN)
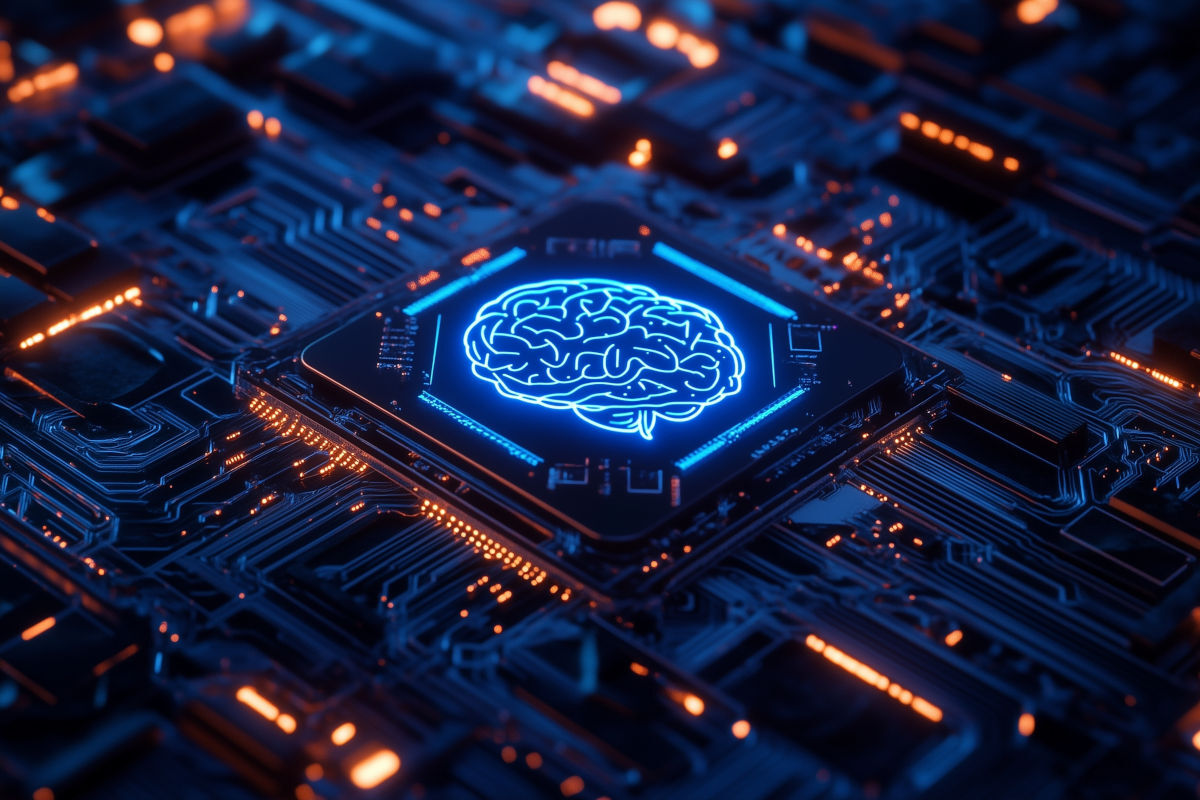
数十年にわたり、科学者たちは脳のように振る舞う電子回路を作ろうとしてきた。この発想はニューロモーフィック・コンピューティング(neuromorphic computing)と呼ばれ、現在主流のプロセッサーに頼るのではなく、脳内のニューロンが発火し結合する仕組みを模倣するようチップを設計するものである。期待は大きい。人間により近い「考え方」をしながら、消費電力ははるかに小さいコンピューターなのだ。しかし問題は、人工ニューロンが実際のニューロンと同じ電圧レベルでやり取りしないことであり、これが能力の限界となっている。 マサチューセッツ大学アマースト校(UMass)のチームが、このギャップを埋めたかもしれない。同チームの人工ニューロンは、生体細胞と同じ電圧範囲で発火し、1回のスパイク当たりピコジュール単位のエネルギーしか用いない。この成果はNature Communicationsに掲載され、シリコンと生物がついに同じ「電気の言語」で会話できることを示した。 ■微生物ナノワイヤ vs. シリコン UMassのデバイスの中核はメムリスタ(memristor。メモリーとレジスターを組み合わせた造語)である。メムリスタとは、電気的状態を「記憶する」素子のことだ。チームはシリコンの代わりに、ジオバクター・スルフレデュセンス(Geobacter sulfurreducens)という細菌から得たタンパク質ナノワイヤ(タンパク質繊維)を用いてこれを作製した。これらのナノワイヤは、低電圧で自然に電荷を移動させる。 UMassのアプローチは、テック大手が取り組むものとは大きく異なる。インテルのロイヒ(Loihi)チップやIBMのトゥルーノース(TrueNorth)は、完全にシリコンで構築されたニューロモーフィック・プラットフォームだ。数千個のトランジスターでニューロンを模擬するが、発火電圧は依然として生体よりはるかに高い。これに対し、UMassは生物学的特性を使った近道を採用した。 足りなかったピースがはまったのは2年前である。大学院生のシュアイ・フーが、ナノワイヤ・メムリスタを、実際のニューロンの充放電の仕方を模倣する単純なRC回路(抵抗とコンデンサを使った回路)に接続したときだ。 「当時は、それを人工ニューロンの構築にどう使えるのか、あまり手がかりがありませんでした」と、UMass応用生命科学研究所/電気・コンピュータ工学科の研究者で准教授のジュン・ヤオは振り返る。 この取り組みの成果は、1度きりのバーストではなく、再現性のある電圧スパイクだ。実務上、これは脳と同様に、ある人工ニューロンを次のニューロンの引き金にできることを意味する。 この設計は、チップ工場で用いられる標準的なCMOSプロセスで製造可能である。その点で、特別な設備を要する量子デバイスやフォトニクス・デバイスとは異なる。ただしスケール化は依然として難しい。タンパク質ナノワイヤは、細菌によって生産し、精製し、チップ上に配置しなければならない。ヤオのグループはエネルギーハーベスティング・デバイス(環境中のエネルギーを電力に変換する装置)でこれを実施してきたが、産業規模での一貫性は未証明だ。 これに比べ、インテルやIBMはシリコン製のニューロンを数百万単位で容易に製造できるが、生体の電圧レンジにはまだ到達していない。UMassは電圧とエネルギーの面で生物学的忠実度を実現することでこの関係を逆転させたが、その代わりに材料面の課題が厳しい。



