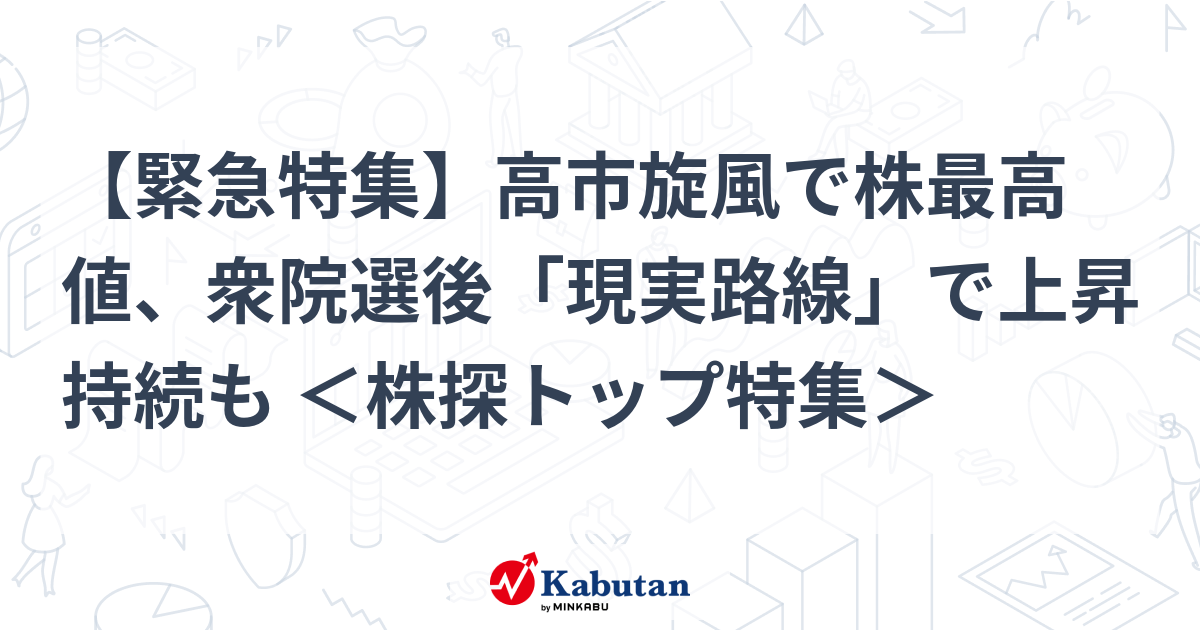時代遅れの日本の現金社会がようやく終わる

黒坂岳央です。
長年ガラパゴス化を維持していた我が国の「現金社会」、その終焉が少しずつ見えてきた。
これまでの日本が長く「現金社会」を維持してきた背景には、日本円の偽造が極めて困難であるという高い信頼性や、他国に比べて急速に高齢化が進んだという社会的特殊性があった。
特に高齢者は年金生活者が多く、IT機器の利用に不慣れなため、地域社会のメイン顧客である彼らに配慮し、地方の店舗や交通機関が現金払いを継続せざるを得なかった構造は根深い。
この「美徳」が今、経済成長と生産性向上の足枷となっていたが、それが終わりつつあるのだ。
travelism/iStock
国も社会もキャッシュレスを望んでいる
ここまで読んでいただいた方の中には「筆者は個人的に現金払いを毛嫌いしているだけでは?」と感じたかもしれない。もちろん、利便性の面から現金とキャッシュレスなら後者を取る。だが、これは個人的な願望に留まらない、国家と社会による願望といえる。
近年、右肩上がりにキャッシュレスは普及しており、日本の公共交通機関において「現金お断り」の波が急速に広がりつつある。相鉄バスの一部路線における完全キャッシュレス化への実証実験導入の発表は、その象徴的な事例だ。
これは単なる「利便性向上」といったレベルで語られるべきではない。国土交通省の試算によれば、全国のバス事業者が完全キャッシュレス化すれば、年間で約86.3億円ものコスト削減効果が見込まれるという。この莫大な原資を、深刻化する運転者不足対策や処遇改善に再投資し、路線網の維持に繋げるという、まさに「バス会社の生存戦略」であり、日本経済が長年抱えてきた構造問題への抜本的なメス入れを意味する。
また、国も積極的にキャッシュレスを推進している。経済産業省は、キャッシュレス決済比率を2025年までに4割程度にするという政府目標の達成に向け、関係省庁と連携しつつ、キャッシュレス決済の推進に取り組んでいる。同庁による2025年3月の発表によると、2024年のキャッシュレス決済比率は、42.8%と政府目標である4割を達成した。将来的にはグローバル基準であるキャッシュレス決済比率80%を目指すといっている。
現金決済はもう完全に「時代遅れ」の選択肢となりつつあると言える。
現金払いを終わらせる黒船の正体
これまでいかなる施策も効果が薄かったキャッシュレス推進だが、ここで最大のインパクトが現れた格好となる。インバウンド顧客である。
キャッシュレス化は、訪日外国人観光客にとっては待望の朗報である。多くの国で公共交通の標準となっているクレジットカードのタッチ決済が利用可能となれば、慣れない現金や小銭のやり取りは不要となる。
日本は観光業を第2位の外貨獲得輸出産業にまで成長させたが、その成長を阻害している要因の一つが「現金社会」だ。様々な意識調査で「現金払いのみだったので旅先で水を買えなかった」「お金を引き出す場所に困る」「大量の現金を持ち運ぶのが不安」というエピソードが示している。
特に地方は、未だ現金払いのみの店舗が非常に多く、インバウンド利用者にとっては「現金を引き出す場所がない」「大金を持ち歩く不安」に直結し、地方観光を敬遠する一つの理由にもなっている。
インバウンド利用者の消費を現金払いの維持という非効率によって削ることは、日本経済全体で「機会費用」という負担を負うことに他ならない。だが、インバウンド顧客がメインプレーヤーになりつつある今、逆に現金払いが利益を減らすことになる。
手数料をペイできるほどの売上増加に加え、キャッシュレス化は現金管理の手間、両替の手間、レジ締め時間の短縮といったオペレーションコスト削減効果も生む。店舗側にとっては、高額な手数料コストと、煩雑な現金管理コストの比較考量が、もはやインバウンド売上機会の損失という形でインバウンドに傾きつつあるのだ。
キャッシュレスは高齢者の切り捨てか?
一方で、デジタル機器に不慣れな高齢者にとっては、キャッシュレス化は新たな「壁」となる。
「スマホの電池切れ」や「家族に端末を持たせていない」といった技術的な不安に加え、日常の生活様式そのものの変革を強いるという点で、「高齢者を切り捨てるな」といった強い反発を生む可能性が高い。
キャッシュレス化は、誰もがアクセス可能であるべき公共交通サービスにおいて、一部の利用者を排除する「冷たい選別」ではないかという批判も噴出するだろう。だがもうこれからはその維持も厳しくなっており、本格的なキャッシュレス社会の到来は不回避だ。
第一に、高齢者中心社会の維持は、もはや公共交通サービスの存続自体を危うくしている。 バス路線の維持すら困難な状況で、現金扱いの非効率を継続することは、結果として路線網の縮小や運賃の高騰を招き、最も移動手段の選択肢が限られている地方の高齢者自身を追い詰めることになる。
第二に、高齢者は「赤ん坊」のように無力ではないという前提だ。 新しい決済方法を学ぶ能力は、年齢に関わらず存在する。頑なに固定電話を手放さないお年寄りも、孫との通話を望むなら必死にスマホ教室に通ってLine電話を覚える。これは能力ではなく意欲の問題だ。
仮にクレジットカードやQRコード決済に抵抗があるとしても、預金残高の範囲内で利用できるデビットカードなど、比較的導入ハードルが低い決済手段は存在する。
むしろじゃらじゃらと大量の硬貨を扱う現金支払いよりも、タッチ決済やデビットカードは操作が簡単で、防犯上も有利であるというメリットを認識させる啓発が必要である。
◇
<キャッシュレス化は、高齢者を切り捨てる冷たい選別ではなく、むしろ将来にわたり全ての人のための利便性の高い社会を守るための、避けて通れない選択である。
■最新刊絶賛発売中!